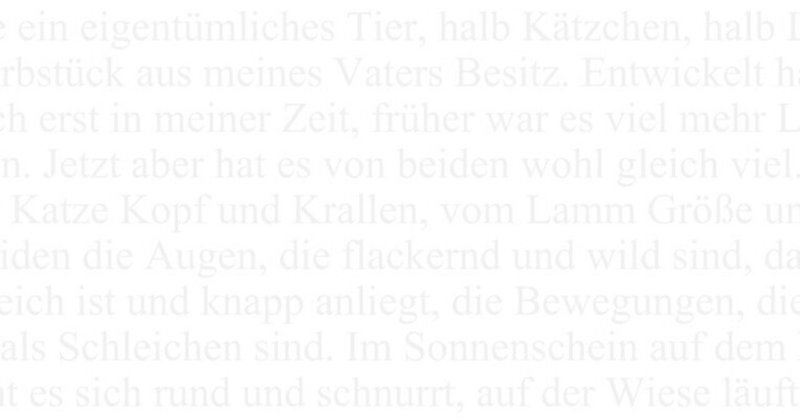
5歳まで人間ではなかった私へ
「よるさんって、悩みとか無さそうだよね」とよく言われる。
まあ、確かに、(悩みは)無い。ただ、これは「解けるまで考えるから、悩みはない」だけなので、ただ楽観的な奴だと思われるのも実のところかなり癪なのだけれど、大凡「悩みがない」のはその通りなので、私は私の優先順位に従って「そうだね」と応えることが大半だ。
ただ先日、知人から「傷付いたこともあんまりなさそう」と嘯かれ、あまりにも人を見る目のなさに思わず笑ってしまった。冗談だとしても、あまりにもなあまりにもだ。
そのおかげで、数日間珍しく全く思考が働かず、いつもなら「全てぶん投げて海に行きたい!」が最上限の「限界モード」なのがうっかり「死にたい」になってしまっていた。
だから――というわけではないけれど。
死にたい自分から逃げるために、少し、自分のことを書こうと思う。
見出しにした一文(表題?)だけれども、かつて「私」は、生みの親ふたりから、あまりよろしくない扱いを受けていた。
平たくいえば虐待、なのだろうけれど、いまでも酷く受け入れ難い過去だ。
なので、少しばかり他人事のように書く。
母は「私」を産むより以前、身籠った子供をひとり流してしまったと聞いている。女の子だったらしい。
母も父もふたりとも、その子の名前を決めて、この世にきちんと生まれ落ちてきてくれることを、ちゃんと祝福を込めて願っていた(と思う)。
だからこそ、その子が胎からいなくなってしまったことを悔やんでも悔やみきれず、自責の末に病んでしまったらしかった。(全て後から聞いた話だから、らしいらしいばかりなのは許されたい。どこが事実にせよ、私がされてきたことに変わりはないのだし。)
幸か不幸か、その後に彼らは「私」を授かって産むことになった。
祝福されていたのかどうかは、もはや私の預かり知るところではないのだけれど。ただ、「私」の名前には、以前流してしまった「生まれるはずだった子」の名前をつけることを決めていたらしい。
彼らにとってやはり幸か不幸か、「(今回も)女の子」のはずだったからだった。
ところが実際「私」を産んでしまってから、どうやら「正しい女児」ではなかったことが判明してしまう。ぱっと見は女性型であっても、そのデキは中途半端。
それが「私」の身体だった。(いまだとDSDと云うらしいが、私が知った頃にはまだまだISの名称だったなと思うという余談。)
最初の子を産めなかったこと。その子が戻ってきたと期待を込めて産んだものが、いろんな希みに反していたこと。
結果、最初に壊れてしまったのは母だったようだ。父は母の手を離さないひとだったがために、引き摺られてしまったんだろう。
それでも彼らは「私」が産まれて数年、育ててくれた。
それどころか、恐らくは愛そうと努力してくれていたことを、私はほんの少しだけ察している。(話しかけてもらったのだろう記憶。絵本の記憶。たくさん本を読み聞かせてくれたのだろうと思う。そうでなければ私のこの言語能力の高さは説明がつかないというところもある。ただの天才だったと自惚れても良いけれど。)
何歳のことだったかなどというのは流石に微塵も記憶にないが、「私」に残っている最初の痛烈な記憶は、母の涙だ。
喃語で、母のことを呼んだのだと思う。そのときのこと。
私……ではなく、「あの子」のものならば、それがどんな呼称であれ、母は受け入れられたのかもしれないのだが、そのとき「私」が選んでしまった呼称は、母のなかでの「あの子が選ぶはずの呼称」ではなかったようだった。
彼女が、母が、なんと言って泣いたのかは覚えていない。
それでも、そのときにぶつけられた憎悪と嫌悪感、「違う」という拒絶だけは、育っていた感受性が拾ってしまったようで、我ながら驚く程度には、いまでも鮮やかに覚えている。怖かったんだと思う。
……逆に、あの馬鹿みたいにデカい負の感情を抱えたまま、数年、よく頑張ってくれたものだとも思う。なりたい親の、なりたかった家族の偶像もあっただろうに。
あったからこそ、の地獄だったのかもしれないが。
ともあれ、最初に「私」が何かを間違えてしまってから、両親の間には、特に母の中には「私」と「産まれるはずだったあの子」の線引きがしっかりできたように思う。存在した身体は、確かに私のもの、ひとつだけなのだけれど。
両親はふたりとも、「あの子がやること(或いはやりそうなこと)」は諸手をあげて喜んでくれたが、「私」のすることは、全て嫌悪と拒絶の対象になった。
左を使うこと。大きな音を怖がること。甘いものが嫌いなこと。
同じ絵本を繰り返し読みたがること。おもちゃを並べること。
よく眠ること。何かを指差すこと。泣かないこと。泣くこと。
(矛盾はあるがそんなものだ。他にもたくさんあった。)
幼児期というものは、驚くほど吸収が良いもので。
「私」に備わっているものは、だいたい彼らにとって不正解なのだと、私はだいたい齢3歳にして学んでいた。私が「私」でいると、両親が苦しんでいることが伝わってきたから、それも酷く悲しかったし、だからこそ自分の存在を申し訳なくも思っていた。「あの子」として正解を選んでいる分には彼らは優しくよく笑い、理想的な両親だった。笑えることに(いまの私の皮肉がうっかり漏れ出た)、それは私自身のひたむきな協力もあり、表向きにもそう見えていただろうと思う。
「あの子」として外にいるときは、耳元で詰られも、抓られもしないので、本来の私は恐らく結構なインドアなのだけれど、外出は好きだった。
その頃には、両親の顔色を伺う癖がついていた。外を往く間、自分と同じくらいの子供がどういうことをして親の笑顔をもらっているのかを観察する癖もついたが、いくら自分と比較しても、特別な芸をして喜んでもらっているようには見えず、困惑したのを覚えている。
「あの子」の正解から外れると、自宅に戻ってから、「私」はよく罰を受けた。本気で殺そうとしていたのではなかろうかと思う罰も、一度や二度ではない。
怖いし、痛いし、苦しいのは嫌なので、必死に考えて答えを探そうとするのだけれど、さっき正解だった筈のことでも、明日は、どころか2時間後に不正解になるなんて反則でしかないわけだが。
運良く「あの子」を遂げられたときこそ両親の間に肌触りの良いタオルケットをかけて眠らせてもらえるのだが、「私」の部屋は主に風呂場やベランダだった。最初の頃こそ、訳もわからず泣き叫んで謝ったが、それが彼らの怒りをさらに燃やす燃料になると気付いてからは、ただ静かにしていることこそが「そこそこ正解」なのだと悟った。
たまに、母ほど壊れていなかったらしい父が、恐らく彼なりの謝罪なのだろう言葉を呟きながら、慰みに置いていってくれる絵本が救いだった。
「あの子」のために読んでくれた音をあたまのなかで拾い上げながら文字をなぞるのはたまらなく惨めだったが、だからこそ読みの能力を得たのは、もしかしたら他の同年代の子供たちより随分早かったのではなかろうかと、いまでは思う。
どんなに我慢しようとしても涙は出るのだけれど、泣いたとき、目を擦るのもダメなことを私は知っていた。
それより以前に目が腫れていることを見咎められたとき、珍しく「私」に晩ごはんが与えられることになり、最初はこれが正解だったのかと驚いたものだけれど。
眼前に水道水の入ったコップを置かれ、その中にさらさらと生米を入れられて、「はい、どうぞ」と笑顔で渡されたときの言いようのない絶望感で、これが正解かもしれないという感覚は、当たり前のように消し飛んだ。
当然のようにそれを食べて(飲んで?)腹は壊したが、嘔吐に喘ぐ「私」の腹を撫でながら、「そういえばお前の身体、女の子じゃないのに男の子でもないんだって! 気持ち悪いね!」と、母が厭な笑顔を浮かべていたのを覚えている。この頃にはもう、私は「私」を半ば諦めていたと思うのだけれど、このとき「あの子」ではなく「私の身体」を侮蔑されたが故に、「あの子」ではなく「私」は私でどうやらきちんと存在するのだと、(この頃は明確に言語化できておらずとも)理解できたのだろうとも感じている。
(余談として、成長してからもサラリと、「私」の性自認は「男女どちらでもない」と迷わず言えるのは、このときの体験も関わっているのだろうと考えたりする。)
そういう、(他にもいろいろあったけれど割愛する)人間以下の扱いを受けてきた「私」の心が一度砕けたのが、逆算すると(たぶん)4歳、5歳のころだ。
両親たちは私以外にもハムスターを飼っていて、私は幼いながら、このフワフワしたいきものが愛らしくてとても好きだった。好奇心旺盛な個体だったのか、私のことも嫌がっているようには見えなかったから。
とはいえ「私」としてハムスターに触れていると良くないことになるだろうことは、もうこの頃には把握していたから、気を付けていた――つもりだった。
あの日はたまたま、何かのはずみで両親が部屋にいなかったのだと思う。
だから気を抜いていたというには、あまりにもお粗末だけれど。
遊んでいたところをうっかり見つかったのだろう。気がついたら私はひたすら叫ぶように謝っていたから、そこに至るまでのことは、あまりよく覚えていない。
私の手には可愛いフワフワがゆるく握らされており、その私の手は、母が包んでいた。
母によりゆっくり高く上げさせられた私の手のなかで、フワフワもただならぬ気配を感じているのか、必死に暴れていた。はじめて噛まれたような記憶もあるけれど、そんなことは最早どうでもよかった。
何をさせられるのか具体的なことはわからずとも、「とても厭なこと」だというのだけは理解できて、私も、「私」としての抵抗を殆ど諦めていたこの頃にしては珍しく、必死で謝っていた。なにひとつ許してもらえなかった程に、大人の力は強かったけれど。
結果私は、母に指を開かされてから、フワフワを床に叩きつけさせられた。
ほんの小さな「ギッ」という断末魔が聞こえて、あまりのことに自分がどの感情を抱いているのか把握できないなかで、一度では絶命しきれなかったフワフワを、固まっている身体を誘導され、拾い上げられ、私はもう何度か、それを繰り返させられた。
ごめんなさいも、いやだと、やめてと叫ぶのも、そのとき枯れた。
私が殺したわけではない――筈、だけれども。いまでも、私がもう少し抗えていればああはならなかっただろうかと、ふとしたときに考える。
ふっつりと感情の糸が切れてしまった「私」は、それから「あの子」にもなれず、ただ、息をしているだけのものとしてしばらく過ごした。「あの子」にもなれなくなったが、何も反応しない、反射として薄ら笑うことができるものは、あの人達にとっても、意外にも都合が良かったのかもしれない。ギリギリのところで、私は生かされていた。
抜け殻になってしまった子供の身体を流石に不憫に思ったのか、父親が一度だけひとりで私の手を引いて本屋に連れて行ってくれたのも、母親が家に不在がちになったのも、このときだったと思う。
父親が、何をずっと謝っているのか、この頃の私にはもう理解できなかったけれど、「どれでも良いから好きな本を一冊選んでいい」と言われたのは、素直に嬉しかったように思う。
図鑑や辞書は、「あの子」らしくないようで怒られるだろうからと、このときですら私は少しだけ考え、だから結局「どれでも良く」はなかったのだけれど――
《表紙はあかがね色の絹で、動かすとほのかに光った。パラパラとページをくってみると、なかは二色刷りになっていた。さし絵はないようだが、各章の始めにきれいな大きい飾り文字があった。》
物語のなかでそう語られる装丁そのままを現実にもってきたような、ミヒャエル・エンデの「はてしない物語」。私はこのとき、それを選んだ。
読めない文字(漢字)は多かったから、何故か許されるようになった知らない大人との散歩の時間に、少しずつ訊きながら読み進めた。
このときに触れたあの世界(ファンタージエン)に感じた風や木々の深さが、その場に存在しない景色のなかに生きていた彼らが信じられないくらい美しいものだと感じられたからこそ、私はいまも生きていられると言っても過言ではない。
物語の魔法により瞬きを思い出したころになって、父親がいない時間に母親が帰ってきたのを覚えている。
彼女は「私」がいることに気付くと、無感情に風呂場で水をかぶせ、それからベランダにしばらく置いた。抵抗する気は微塵もなかったのだが、帰ってきた父親に部屋に入れてもらえたときにはもう、寒くて寒くて、呼吸がうまくできなかったことしか覚えていない。どうしても息ができなくて、往生際悪くそれを伝えようとしたのだけれど、母と父はお互い泣き喚くことに必死だったのか、結局、このとき私は、エンデの物語を抱えてふらふらとひとり外に出た。
それが「私」がヒトになる転期になった。
気管支炎を起こしかけていた私は、外で気を失ったことによりたまたま善意の人に保護(?)され、そこからは本人の知らないところで色々なことがあった、のだと思う(どうしても他人事のようになる)。
いま、他人事のように、などと書きながら、涙もべしょべしょで、冷汗も止まらないのだから、トラウマ極まるといったところという感覚でもあるのだけれど。生きてるから大したことがないんだったなと、同時に本心から笑えるようになってきた。
母の日や、父の日の近くになると、胸の奥のほうが、いまだにぎゅうぎゅうと苦しくなる。(そんな最中に知人から投げかけられた言葉で、普段保っている均等が崩れたのだろうなと思いつつ。)
いまどうしているかなんて知りたくもないと思いながらも、それでも少しでも心穏やかでいてくれたらいいと、ずっと願っている。私のこの来歴を知る人からはお人好しとも言われるのだけど、性分なのだと思う。バスチアンだって、たくさん、たくさん間違えたから。それでも、誰でも、遍くひとが、自分なりの幸福を得る権利がある。
壊れそうなところでギリギリ壊れていない(と思いたい)私ですらこんなにも痛いのだから、壊れてしまった彼らはもっと痛かったのだと思う。飽くまでも、私のせい、ではないけれど。それでもほんの些細な衝撃で、堰き止めていた狂気を招いてしまったのは、他でもない私だったんだろうと思う。
伝えられたらよかったと思う気持ちはずっとあるのだけれど、きっと一生伝える機会など来ないだろうから、ここに記しておく。
母よ、父よ。
あなたたちの「あの子」になれなくて、ごめんなさい。
……どうして、冒頭で「死にたい自分から逃げるために、」なんて書いたかというのは単純な話、「コレを乗り越えてきたから、まだまだいける!」というのを思い出すためでもある。
苦しいときは笑えとも言うけれど、今回はゼロ地点からプラスを生み出すことは敵わず、マイナスからの反発を使わなければならなかった。
乗り越えたから、なんてのも実際には、入った施設で名前を訊ねられ、「私の」名前を応えられなかった私に対して「夜」の音をくれた人の多大すぎる助けを得たりして、私は私というヒトに成ってきたのだけれど。(いまでも「よる」以外の名前で呼んでくるニンゲンさんはほんのわずかにいるが、毎回本当に逃げ出してしまいたくなる。)
いまとなってはその人も偶発的な事故で死んでいるため、比較するものではないにせよ、どちらかといえばその人に纏わる傷のほうが、愛したが故に苦しい離別だったので、なんとも「私の人生心を折りにくるイベントシーン多すぎないか……????」とべしょべしょ泣くしかなかったりもするわけだけれども。
他様にもそれぞれ大切なニンゲンさんたちがいて、それぞれに抱えられる大事なものには限りがあるから、私は私自身で私のことを救わなくちゃいけない。
見て見ぬふりをされるのは経験上、心にくるほうなのだけれど、喚き散らすのが見苦しいのも当然のことなので、それも、できるかぎり減らしていきたい。(どうして減らさなきゃならないんだと叫びたいどうしようもなさもあるので苦笑いしつつ。)
誰に聞かせる話にしても、あまりにも無様な話だ。
だから、せめてひとりで語れるように文字にしてゆく。気まぐれに、読んでくれる余裕がある誰かが、私という炉端の石を知ってくれたら、触れてくれたら、それでもやっぱり嬉しいと、そう思ってしまうけれど。
人並み以上に恥はあるのに、コントロールが泣き笑ってしまうほど難しいのも、PTSDが関わっているのだろうと、知識としては知っている。……が、私は、これを理由にしたくない。
私は「救われたほう」なのも本当のことなのだから。
ひとまず――
5歳まで人間ではなかった私に、5歳から人間になった私自身が伝えておく。
大丈夫だ、きみはまだ生きていける。
2021.06.13.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
