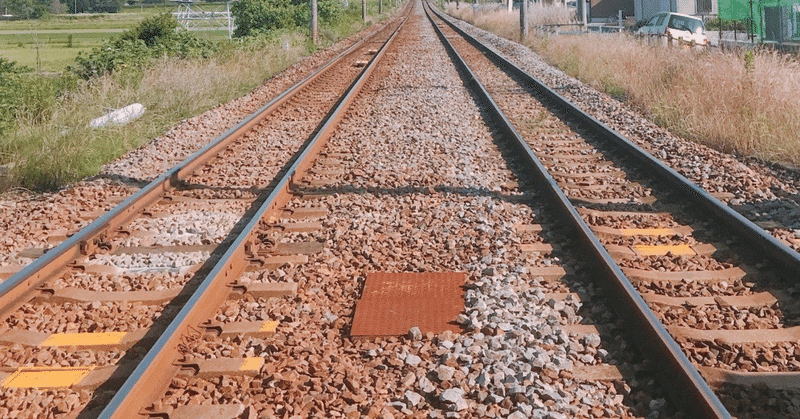
短編小説:無人駅のホームにて
7年ぶりに訪れたその駅は、無人駅になっていた。
用事があって出掛けた先と、その駅がそれほど遠くないと知り、久しぶりに寄ってみようと思い付いた。友人の車に乗せてもらう予定だったが、帰りは断ってタクシーで駅に向かい、電車で帰ろうと考えたのだ。
7年ぶりだが、外観はさほど変わりない。駅舎の外に佇む赤い自動販売機。こぢんまりとした待合室にある、古い木製のベンチ。壁に貼られた、近くの特別支援学校の子どもたちが描いた絵。さすがに7年前とは違う作品だが、相変わらず色とりどりで可愛らしい。
ただ、7年前にはいたはずの駅員さんの姿はない。空っぽの窓口の外に、「御用の方は、通話ボタンを押して話しかけてください」と書かれたタブレットが置いてあるだけ。
県内では、利用者の少ない駅は次々に無人駅になったのだが、ここも該当したようだ。
寂しいけれど、それが時代の流れというもの。仕方あるまい。
改札にICカードをタッチし、短いホームの中央にある小さなベンチに腰をおろした。
暑い。セミがうるさい。
前にここに訪れたときは、確か秋だった。私はぼんやり、その時のことを思い出す。
7年前、大学院の2年生だった私は、2歳年下の恋人と共にこの駅に訪れた。特に深い意味はない。たまたま見ていたテレビ番組の企画を真似て、サイコロをふって出た目の数だけ電車に乗ってみよう、という私の思い付きに彼女が付いてきてくれただけだ。
あんまり近くだとつまらないから、ふたりともふって足すことにした。私のサイコロは4で、彼女は5だった。
路線図を見ながら、全然知らない駅だね、なんてはしゃぎながら電車に揺られたのを覚えている。
最寄り駅から9つ先の駅は、小さな古い駅だった。そこに降りたのは、私と彼女のふたりだけ。何かあるかな、喫茶店とかありそうだね、なんて話しながら、切符を白髪の駅員さんに手渡した。
「残念やけど、駅の近くには何もないよ」
私たちの話が聞こえていたのか、駅員さんは笑って言った。
「えー、そうなんですか?」
彼女はがっかりしたような声を出す。
「車やったら、海とか植物園とか行けるんやけど、歩きやとなあ」
「それって遠いんですか?」
「歩いたら一時間はかかるで。このへんはバスも通っちょらんし。歩いて行けるんは、近くの神社くらいやわ」
「神社は近いんですか?」
「近い近い。歩いて10分くらい。この道をずーっと真っ直ぐ行けば良い」
私は彼女にどうする?と目で尋ねた。
「んー、じゃあ、神社行ってみようかな」
よかった。歩いて海まで行きたい、と言われたら正直辛かった。
「まあ、そん神社も何もねえけどな」
笑う駅員さんにお礼を行って、私たちは神社に向かった。さすがに神社以外も何かあるだろう、と思っていたが、本当に何もなかった。小さなたこ焼き屋とコンビニがあるくらいで、あとは国道と田んぼがあるだけ。
神社も想像以上に小さくて、誰もいなかった。
それでも、きちんと参拝して、おみくじをひいて、少しだけ近くを散歩して、ついでにたこ焼きを買って食べて…、それだけのことが楽しかった。
結局、「本当に何もなかった!」とげらげら笑いながらすぐに戻ってきた私たちを見て、駅員さんはまた笑う。
「今度は電車やねえで、車でおいで!ここの海は綺麗やけんな!」
はい、また来ます!次は海行きます!と答えて電車に乗り込んだ。乗り込んだのは、私と彼女のふたりだけだった。
結局、彼女と一緒にもう一度そこへ行くことはなかった。
あれから、大学を卒業した彼女は地元で働くことを選び、私は学び続けることを選んだ。
彼女の地元は特急と新幹線を乗り継いで3時間ほどの場所。私たちは離れてしまった。
そして、私も彼女も、物理的な距離と一緒に、心の距離も離れていった。
ただ、それだけ。
もう一度あの駅に行こう、という約束は果たされることなく消えた。
電車のブレーキ音でふと我に帰る。2両の短い電車の扉が開いていた。
私はあわてて電車に乗り込む。乗り込んだのは、私だけだった。
16時過ぎの下りの電車はガラガラだった。そういえば彼女と乗った電車も、このくらいの時間帯だったなんて、余計なことを思い出してしまう。
電車は、ゆっくりと動き出す。
車窓からの景色が流れ始める。
景色は7年前とそんなに変わっていない気がする。
でも正直、景色のことはあまり覚えていない。あの日の帰り道、私はきっと景色なんて見ていなかった。
7年が経ったのだ。
変わらないように見えた駅だって、無人駅になっていた。
私だって7年も経てば変わる。彼女だって変わっているはず。思い出は鮮明だけれど、今の彼女がどうなっているかなんて、何も知らない。
別に、引きずっているわけじゃない。
綺麗な思い出として、ずっと持っているだけ。
今はただ、彼女が幸せであれば良いと思う。7年も経てば、そう思える。
降りる駅まで、あと9駅。
まだずいぶんある。
退屈な時間。これ以上余計なことを思い出さないように、私は静かに目を閉じた。
※フィクションです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
