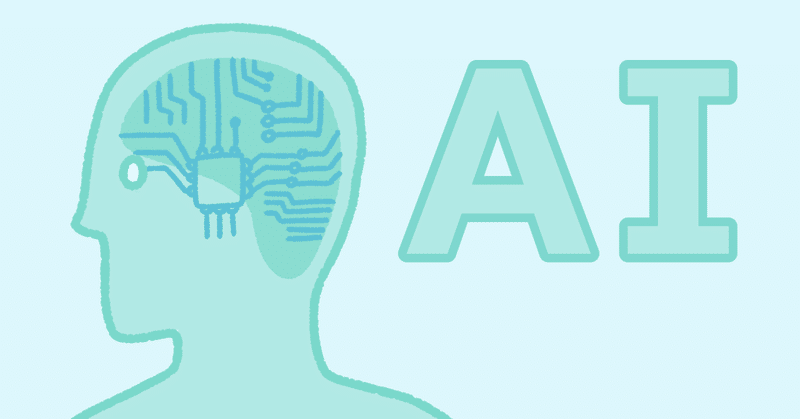
【中学生でも分かるニュース解説!2023/7/21(金)】安保理で中国とロシアの主張が割れる”異例の事態”って?
今日のニュース
アスパラガスtのニュース速報。
今日は、国連の安保理で開かれたAIテーマの世界初の会合で、
ロシアと中国の主張が割れる
”異例の事態”
になったニュースを解説します。
AIというテーマも大切なのですが、今回は
「なぜ、この状態が”異例の事態”なのか?」
について解説をしていきます。
今回の記事で活用する主な中学生が社会科授業で学んだ知識は以下の通り。
公民・・・安全保障理事会、拒否権
歴史・・・冷戦
安全保障理事会と拒否権
安全保障理事会は、
・アメリカ(米)
・イギリス(英)
・フランス(仏)
・ロシア(露)
・中華人民共和国(中)
の5か国の常任理事国と、10ヶ国の非常任理事国
から成り立っています。
そして、常任理事国には”拒否権”という強い権力が与えられ、
ある議案について、他の14か国が全て賛成していても、
常任理事国の1か国でも反対していれば、
その議案は否決されてしまいます。
こんなすごい権力を持っている常任理事国が
なぜこの5か国かというと、
とてもおおざっぱに言えば、
第2次世界大戦の戦勝国の中心だった国だからです。
冷戦
第2次世界大戦後、平和な世界はそう長続きしませんでした。
資本主義と社会主義の対立である冷戦が勃発します。
資本主義のリーダー国はアメリカ。
社会主義のリーダー国はソ連です。
ベルリンの壁はその対立を象徴する建造物として今も大切にされています。
この対立は世界中に影響します。
「お前の国はどっちなんだ? 資本主義?社会主義?」
といった感じで、それぞれの国に選択を迫っていく感じですね。
それぞれの国内事情も抱えながら、
世界中の対立へと発展していきます。
実際に世界大戦のように大きな戦争には発展しなかったため、
”冷たい戦争”と呼ばれるようになりました。
常任理事国と冷戦体制
さて、ここからが本題となりますが、
常任理事国の5か国は、先ほどもお伝えしたように
1⃣アメリカ
2⃣イギリス
3⃣フランス
4⃣ロシア
5⃣中国
です。この5か国を2グループに分けるとしたらどう分けますか?
【グループA】1⃣アメリカ 2⃣イギリス 3⃣フランス
【グループB】4⃣ロシア 5⃣中国
中学校レベルで考えると、こう分けるのが妥当だと思います。
なぜか、もう分かりますよね?
”冷戦の対立軸”です。
【グループA】資本主義よりの考え方の国
【グループB】社会主義よりの考え方の国
安全保障理事会においては、
冷戦時も冷戦が終わったと言われる現代でも、
ずっと冷戦状態が色濃く残っています。
アメリカを中心とした資本主義諸国が提案している案を
ロシアや中国が賛成すると思いますか?
当たり前ですが、答えは「No!」です。
安全保障理事会の機能は半分停止状態だと言われています。
なぜなら、
ここで議論されていることのほとんどは、
ロシアと中国が反対をして、拒否権が発動されます。
つまり、
いくらそれ以外の国が賛成をしていても、
この2か国が反対すれば、
そこで議論は終了になるんですね。
中国とロシアの意見が分かれる”異例の体制”
さて、ここまでくればなぜ”異例の体制”なのか分かりますね。
これまで、ロシアと中国はアメリカを中心とした資本主義大国
の案を拒否し続けてきました。
ですが、このAIに関しては、一致団結とはいかなかったようです。
中国はAIはこれからの自国の経済成長に欠かせないと考えているようですね。貿易のことなどを考えると様々な国と協調していく姿勢が必要だったのでしょうか。
一方ロシアは、自由に自分の国が思うとおりにAIを使用していきたいと考えているのかもしれません。AIは軍事利用をすると、とてつもない効果を発揮するとも考えられていますので。恐ろしい話ですが…。
こういったAIに関する立場の違いから、中国とロシアの意見が異なるという”異例の事態”に陥ったということです。
まとめ
国際関係というものは、こういった一つのほころびで大きく変わっていきます。中国とロシアの関係はこれからも注目していかないといけません。
そして、
そのほころびを理解するための必要な知識は中学生で学んでいるということですね。
公民・・・安全保障理事会、拒否権
歴史・・・冷戦
みんなが学んでいることは、現実の社会とつながっています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
