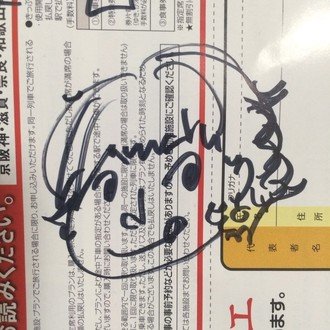小説を「古典」にするもの/スコット・フィッツジェラルド「温かく冷たい血」全訳
小説を「古典」にするもの
今年、物書きとして食っていかねばならないという焦りがいよいよ深刻なものに思われ、どうにか仕事を得ようといろいろやってみた。その結果、「大滝瓶太」としての仕事だけではまだ食べていくには程遠いものの、いくつかの幸運に恵まれ、少しずつではあるけれど小説に関わる文章を書かせてもらう機会が増えた。とてもありがたく、月並みだけど声をかけてくださった方々の期待にこたえられるようがんばっていきたい気持ちが強まった。
その一方でやはり悩みもある。最たるものはじぶんの小説を世に出せていないということで、そもそも書きあげた小説の数が少ない。振り返れば、ぼく自身の小説のために割いた時間というものがほとんどなかった。また、書いたところでだれがいったい読んでくれるのだろうかという不安も大きく、無意識的な領域で小説でお金を稼ぐ難しさを、小説を書くことの無意味さにすり替えてしまっていたのかもしれない。そもそも生活のために小説を書こうとおもったわけではなかったはずなのにどうしてこんなことになってしまったのだろうか。いうまでもないが、この疑問じたいが致命的な無意味をはらんでいる。
そうした疑問を払拭する唯一にしてもっともシンプルな方法は小説を書くことにほかならない。そこで毎月1本、たとえ下手でもいいから50枚程度の短編をとりあえず書き上げるというノルマをじぶんに課すことにした。7月に1本書き、8月に1本書いた。そして今月も1本着手していて、たぶん来月も書くだろう。どのように公開するかはまだ決めていないけれど、とにかくいまは小説を書くことによって、いまのぼくが小説を書くことでなにを考えられるのかをまずは見つけたい。
小説について、じぶんのなかで違和感が大きくなってきたことがある。それは固有名詞として圧縮された大量の情報を扱い、構造化させるという手法の是非であり、この方法によって書かれた小説がはたして現在ではない時間で読みうるものになりえるかということだ。普遍性、などといえば聞こえはいいけれど、インターネットを基礎においた一種の筆記用具が浸透した現在において、その環境への過度な依存についていまはどこか不自由を感じる。この詳細についてはまた別のところで書きたいのだが、現代的筆記用具への過度な信頼が、いわば「古典」と呼びうる作品が持ち合わせていたものを損なわせてしまっているのかもしれない──そうした気持ちが日々ぼくのなかで大きくなっている。
そういう経緯を経て、発表から長い時間が経ったいまでも「古典」として広く読まれている小説を、できるだけ時間をかけて読み返すことをはじめてみた。それがドストエフスキーやサリンジャー、千夜一夜物語などにあたるわけだけれども、そのどれもが小説の構成や文体、細かな表現とはまたちがった次元で、野生的とでもいいたくなるような力を宿している。それはたぶん決して情報化されえない「物語」が持つものだ。古典化が可能な──つまり時間に依存せず「古典」として読みうる──小説は、情報の群れによって構造化されるのとはちがい、わずかな情報のなかに潜むものを的確にとらえる。それにかたちの有無とは無関係に質感が得られたとき、ぼくら読者はメタファなるものをテクストの表面に見る。そしてそれが真実かパラノイアであるかの精査がその次のフェーズにある。
*
以下はスコット・フィッツジェラルドによる短編集“All the Sad Young Men(若者はみな悲しい)”に収録された短編”Hot and Cold Blood”の拙訳である。
本文のまえに少しだけフィッツジェラルドの短編について。
よく言われる話ではあるけれど、フィッツジェラルドにとって長編小説が真に創作的な意味を持ち、短編小説とは「食うための手段」という位置付けだったらしい。そしてそれゆえにフィッツジェラルドの短編とは「クオリティにムラがある」らしく、複数の短編集から良いものを選出したかたちで日本に紹介されているそうだ。
かといって、オリジナル版の短編集が無意味だというわけではない。特に”Hot and Cold Blood”を収録した「若者はみな悲しい」は、フィッツジェラルドが代表作「グレート・ギャツビー」を書くための調整の要素も含んでおり、かれの文脈において極めて重要な作品集だった。
フィッツジェラルドの短編を読んでいておもうのは──まさに“Hot and Cold Blood”もそうであるが──多くの作品で対立する二項が用意されているということだ。男と女、大人と子ども、豊かさと貧しさ、アメリカ南部と北部……など、登場人物たちの土壌にそれらは根ざしているゆえに、物語内での激しい衝突はさけられない。
しかし、重要なのは二項対立を分離可能な二項としてとらえることではない。ここに今回、“Hot and Cold Blood”を先行する翻訳「温血と冷血」とはちがい、「温かく冷たい血」と訳した意図がある。たとえば「グレート・ギャツビー」では「裕福であること」が「満たされていること」や「豊かであること」をかならずしも保証してくれるわけではないことがわかる。そしてそれは事物に対してどこに光を当て、どの角度からまなざしを向けるかという問題でもない。「Aであるもの」と「Aでないもの」が同時に、そして同一の場所に共存し、ないまぜになったかたちでぼくらの前に姿を表してる。「温かく冷たい血」は所帯染みた小話だといってしまえばそれまでだが、しかしこの物語で主張され、実行される善や悪は、常に分離がむずかしい両義的なかたちで現れている。
小ささゆえのシンプルさだが、起こっている現象は決して単純ではない。フィッツジェラルドの詩情はこの単純でなさが時間から切り離されているところにあるようにおもえる。小説の複雑さはみかけの情報量や構造によるものではないのだろう。素朴さのなかに広さが垣間見えたとき、ぼくは未だ自信を持って定義できずにいる「古典」なるものをたしかに読んだのだという感触を得る。そしてそれは、同時代に書かれる多くの物語を現在進行形で「古典」として読む方法を見出すために不可欠なものなのではないか──などということを最近は考えている。
温かく冷たい血(スコット・フィッツジェラルド)
1
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。