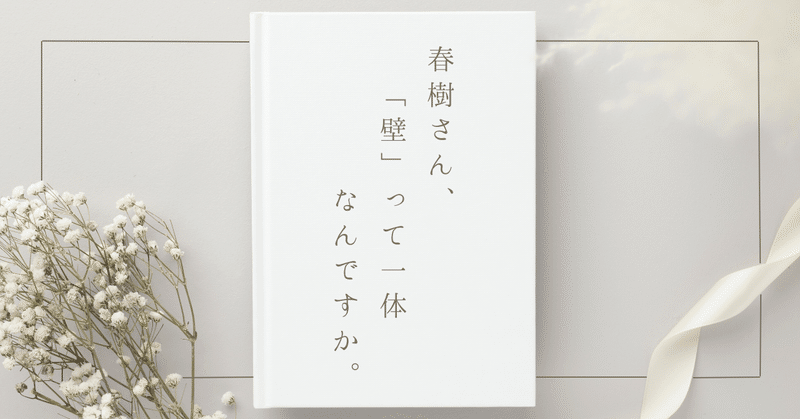
春樹さん、「壁」って一体なんですか。(システムとしての「強固な壁」と、意識の境界線としての「不確かな壁」)
わたしは普段、小説を分析したり検証したりすることは、どちらかというとあまり好きじゃない。
細切れに分断すると、物語の生命力のようなものが損なわれてしまうような気がするから。
蛍の体を分解して「なぜ光るのか」を知っても、生きた蛍が光るさまを見る感動を知ることはできないのと同じように、優れた物語は蛍のように生きて光を放っているし、その美しさを味わい愛でるときに分析や説明は不要だ。
蛍も物語も、わたしは丸ごと味わいたい。
それが放つ光ごと、それが持つ魔法ごと。
だから、「村上春樹にとっての壁とは何か」
ということを分析することは、春樹さんの作品を味わう上で、もちろんまったく必要じゃない。
だけど。
「街とその不確かな壁」を読み終わった後、その余韻の中でぼーっとするうちに、ふと思った。
「そういえば、春樹さんにとって『壁』って一体、何なんだろう。」
春樹さん周辺にたびたび登場するモチーフ、
「壁」。
それが意味するところを掘り下げてみるのが、なんだか面白そうに思えた。
蛍を見て感動した少年が、「どうやって光ってるんだろう?」と蛍のことについて知りたくなるみたいに。
夏休みに、特に誰にも求められない研究を「ただ知りたいから」という理由でノートに書きつけていくみたいに。
* * * *
そんなわけで、春樹さん好きの一人として、
春樹さんの過去作からエルサレム賞受賞スピーチ『壁と卵』、そして新刊『街とその不確かな壁』を振り返りながら、「村上春樹にとっての壁ってなんだろう?」を、考えてみました。
(※考察する中で、『街とその不確かな壁』の内容に触れる箇所があります。未読の方で「内容を知りたくない」という方は、ご注意ください。)
1.システムとしての「強固な壁」
◇ 1985年:『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』

1985年に発行された、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』。
「世界の終り」という名のついた幻想的な世界と、「ハードボイルド・ワンダーランド」と称される現実世界とが平行して進んでいく物語だ。
「あちらの世界」と「こちらの世界」、パラレル・ワールドの物語。
「世界の終り」の世界線では、人々は高い「壁」に囲まれた街に暮らしている。
その壁は恐ろしく強固で、どれほど鋭いナイフで引っ搔こうと傷一つつけることができない。
唯一の出入り口とされる門は頑強な門番に守られ、一度ここに足を踏み入れた者は二度と出ることができない。
街の人々は、そのことに不満も疑問も抱かない。
「この街は完璧だ」と信じ、壁の内側で静かにひっそりと暮らしている。
物語の終盤、主人公はこの街からの脱出を図ることになるのだけれど、「壁を越える」という脱出手段は、早い段階で選択肢から外されることになる。
不可能だからだ。
その壁は「世界の果て」を意味するものであり、どこまでも強固で冷ややかでシステマティックな「不可侵なもの」だ。
つまり、この物語において「壁」は、
「壊すことのできない絶対的なもの」
として描かれている。
◇ 2009年:エルサレム賞受賞スピーチ『壁と卵』
2009年、村上春樹はイスラエルの最高文学賞、エルサレム賞を受賞する。
当時イスラエルは、ガザ地区への武力行使を行っていたため、国際的な批判を受けていた。
そのため春樹さんがこの賞を受けることについても賛否両論あったのだけれど、結果的に彼はエルサレムまで出向き、賞を受けることを選んだ。
そのとき春樹さんが行った受賞スピーチが、『壁と卵』だ。
これがもうとても素晴らしかったので、ぜひ全文を読んでみていただきたいのだけれど、このスピーチの中でも春樹さんは「壁」というメタファーを使っている。
(スピーチの全文はこちら。シンプルでわかりやすい言葉の中に、春樹さんの確固とした意思表明が込められている。素晴らしいので、ぜひ。)
このスピーチの中から、「壁」について言及している部分を抜き出してみる。
もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます。
そう、どれほど壁が正しく、卵が間違っていたとしても、それでもなお私は卵の側に立ちます。正しい正しくないは、ほかの誰かが決定することです。あるいは時間や歴史が決定することです。もし小説家がいかなる理由があれ、壁の側に立って作品を書いたとしたら、いったいその作家にどれほどの値打ちがあるでしょう?
さて、このメタファーはいったい何を意味するのか?ある場合には単純明快です。爆撃機や戦車やロケット弾や白燐弾や機関銃は、硬く大きな壁です。それらに潰され、焼かれ、貫かれる非武装市民は卵です。それがこのメタファーのひとつの意味です。
しかしそれだけではありません。そこにはより深い意味もあります。
こう考えてみて下さい。我々はみんな多かれ少なかれ、それぞれにひとつの卵なのだと。かけがえのないひとつの魂と、それをくるむ脆い殻を持った卵なのだと。私もそうだし、あなた方もそうです。そして我々はみんな多かれ少なかれ、それぞれにとっての硬い大きな壁に直面しているのです。その壁は名前を持っています。それは「システム」と呼ばれています。そのシステムは本来は我々を護るべきはずのものです。しかしあるときにはそれが独り立ちして我々を殺し、我々に人を殺させるのです。冷たく、効率よく、そしてシステマティックに。
このスピーチにおいて春樹さんは、「壁」についてこう表現している。
「もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立ちます。」
さて、この「壁と卵」というメタファーは何を意味するのだろう?
春樹さんによると、その意味は2つある。
一つは「兵器と非武装市民」、そしてもう一つは「システムと個人」だ。
つまりここで言う「壁」とは「兵器」及び「システム」のことであり、どちらも「個人としての生身の人間」を抹殺し得る「硬く大きな壁」を意味している。
* * * *
1985年の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』、そして2009年のエルサレム賞受賞スピーチ。
このどちらにおいても、春樹さんにとっての「壁」とは、
個人の外側にある強大なもの
として表現されている。
それは個人の外部にあって個人を潰し得る、圧倒的な力を持った硬くて冷たいもの、「マクロな組織」や「システム」だ。
2.意識の境界線としての「不確かな壁」
◇ 1988年:『ダンス・ダンス・ダンス』

1988年に発行された、『ダンス・ダンス・ダンス』。
この物語のクライマックスで、主人公の「僕」が壁を抜ける場面がある。
その「壁抜け」の場面は、こんなふうに表現されている。
不透明な空気の層。ざらりとした硬質な感触。水のような冷やかさ。時間が揺らぎ、連続性がねじ曲げられ、重力が震えた。太古の記憶が時の深淵の中から蒸気のように立ちあがっているのが感じられた。それは僕の遺伝子なのだ。僕は自分の肉の中に進化のたかぶりを感じた。僕はその複雑に絡み合った自分自身のDNAを超えた。地球が膨らみ、そして冷えて縮んだ。
ここでは「壁」は、ざらりとした硬質で不透明な空気の層として主人公に知覚される。
そこにあるのは兵器やシステムの強固さではなく、空気のように掴みどころのないものだ。
夢と現実のあわいの中で、主人公はその壁を抜ける。
そして、過去や夢といったいわば意識の中にしか存在しない領域から、「今ここ」の現実に帰ってくる。
ここに描かれている「壁」が意味するものは、「夢や記憶の中で超え得るもの」としての、時間や意識だ。
◇ 2023年:『街とその不確かな壁』
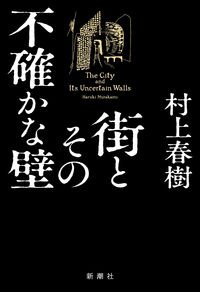
そして2023年、『街とその不確かな壁』。
この物語の中には、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の「世界の終り」と酷似した場所が登場する。
高い壁に囲まれた街だ。
第一部の終盤までは、この街の描写も物語の筋も、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と『街とその不確かな壁』の2つの物語の間には大きな違いはない。
けれど第一部の終盤、主人公が街から脱出するくだりで、とても大きな(と、わたしには思える)変化がやってくる。
主人公が、壁を抜けるのだ。
壁は言った。おまえたちに壁を抜けることなどできはしない。たとえひとつ壁を抜けられても、その先には別の壁が待ち受けている。何をしたところで結局は同じだ。
「耳を貸さないで」と影が言った。「恐れてはいけません。前に向けて走るんです。疑いを捨て、自分の心を信じて」
ああ、走ればいい、と壁は言った。そして大きな声で笑った。好きなだけ遠くまで走るといい。私はいつもそこにいる。
壁の笑い声を聞きながら、私は顔を上げずにまっすぐ前に走り続け、そこにあるはずの壁に突進した。今となっては影の言うことを信じるしかない。恐れてはならない。私は力を振り絞って疑念を捨て、自分の心を信じた。そして私と影は、硬い煉瓦でできているはずの分厚い壁を半ば泳ぐような格好で通り抜けた。まるで柔らかなゼリーの層をくぐり抜けるみたいに。そこにあったのは喩えようもなく奇妙な感触だった。その層は物質と非物質の間にある何かでできているらしかった。そこには時間も距離もなく、不揃いな粒が混じったような特殊な抵抗感があるだけだ。私は目を閉じたままそのぐにゃりとした障害の層を突っ切った。
主人公が街の壁を抜けたこと、それはわたしにはとても大きな驚きだった。
だってあの街の壁は、いわば世界の果てだったから。
それは、超えられないものであるはずだったから。
* * * *
『街とその不確かな壁』の中には、「壁とは何か」についてはっきりと言及される場面が2つ(細かく見ればもっとあるけれど、大きな柱としては2つ)ある。
1.意識としての「壁」
この街を囲む壁について、脳外科及び精神医学を志す医学生が、主人公に対してこう話す場面がある。
「僕は思うのですが、街を囲む壁とはおそらく、あなたという人間を作り上げている意識のことです。だからこそその壁はあなたの意思とは無縁に、自由にその姿かたちを変化させることができるのです。人の意識は氷山と同じで、水面に顔を出しているのはごく一部に過ぎません。大部分は目には見えないくらいところに沈んで隠されています」
ここでは壁についての定義が、ひとつの仮説として提示される。
定義1:「壁とは、あなたの意識である」。
2.現実と非現実を隔てるものとしての「壁」
そしてさらに、主人公が「現実とは何か」を内省するこんな場面がある。
何が現実であり、何が現実ではないのか?いや、そもそも現実と非現実を隔てる壁のようなものは、この世界に実際に存在しているのだろうか?
壁は存在しているかもしれない、と私は思う。いや、間違いなく存在しているはずだ。でもそれはどこまでも不確かな壁なのだ。場合に応じて硬さを変え、形状を変えていく。まるで生き物のように。
ここでは壁は、「現実と非現実を隔てる不確かなもの」として表現される。
定義2:「壁とは、現実と非現実を隔てるものである」。
* * * *
1988年の『ダンス・ダンス・ダンス』、
そして2023年の『街とその不確かな壁』。
このどちらにおいても、春樹さんにとっての「壁」とは、
個人の内側にあるもの
として表現されている。
それは個人の内部にあって、顕在意識と潜在意識、あるいは現実と非現実を隔てるものだ。
その手触りは異質な空気のごとく不確かで、必要とあらば通り抜けて「向こう側」に行くことさえできる。
そこでは「壁」は硬く不可侵なものではなく、自由自在に変形する不確かなものなのだ。
3. 物語の成熟 ー 内在化された「壁」
ここまで見てきた通り、
春樹さんのいう「壁」が象徴するものは、
少なくとも2つある。
ひとつは、自分の外側にある「システム」としての壁。
国家、大企業、政治、戦争、兵器。
とても硬く強大で、個人が単体でぶつかりにいけば簡単に潰されてしまう種類の壁だ。
もうひとつは、自分の内側にある「意識」の壁。
顕在意識と潜在意識を隔てる壁、リアルと非リアルを隔てる壁。
そこには確かに境界線があるのだけれど、必要性に迫られ、あるいはふとしたはずみでその壁を越えて「向こう側」に行くことがある、そんな種類の壁。
(わたしたちが毎晩眠りに就き夢を見るときも、きっとこの壁を越えている。)
このふたつは混じり合うことなく、いわば並走する形で、春樹さんの作品の中に混在してきた。
けれど今回の新刊『街とその不確かな壁』においては、この2つの壁が融合したという感触があった。
外側にあった壁が、内在化したのだ。
外側にあると思っていた「壁」が実は自分自身の内側にあったのだと気づくこと。
外側にあると思っていたものを自分自身の内に発見すること。
それは「成熟」だ。
* * * *
今回の新刊はいろいろな意味で「成熟」がテーマになっている、とわたしは思う。
書き直された物語の成熟、主人公の成熟、そして春樹さん自身の、作家としての成熟。
10代後半から現在に至るまで、同時代に生きる読者として春樹さんの作品を読んでこられたことは、わたしにとってはとても幸運なことだった。
わたし自身の成熟やライフステージの変化、時代の変化、そういったものと並行して、いわば生きたものとして春樹さんの作品を吸収できたこと。
ライブ感のようなものが、そこにはあった。
それは何にも代えがたい財産として、わたしの中できらきらと光を放つ。
* * * *
村上春樹さん。
同じ時代を生きてくださって、
ほんとうに、ありがとう!
* * * *
最後までお読みいただきありがとうございました。
どうぞ素晴らしい読書体験を!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
