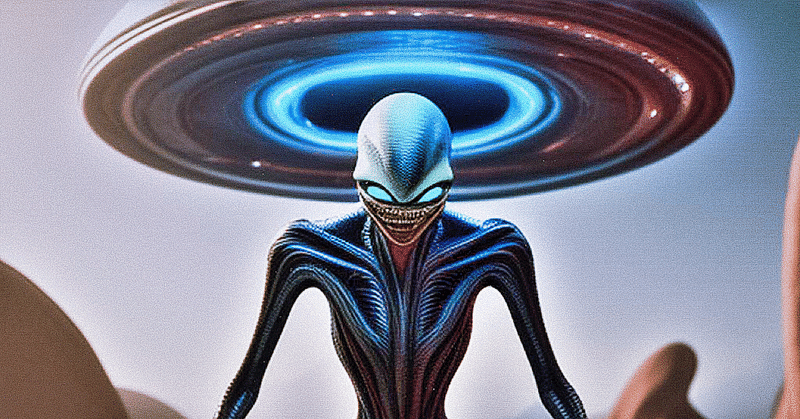#読書の秋2020
山岸俊男『安心社会から信頼社会へ』はまあまあイケナイ本だった
高名な社会心理学社である山岸俊男氏の『安心社会から信頼社会へ』ようやっと読んだ。
この本は、私が敬愛してやまない白饅頭ことテラケイ氏がおすすめされていたので購入したのだが、これまた4ヶ月以上も放置していたのだった。。。
本書は信頼に関する様々な研究を紹介していくものだが、テラケイ氏が言うようにそれ以上いけないことがたくさん書いてあって口角が上がりっぱなしであった。
例えば、他人を信じやすい人
石弘之『感染症の世界史』とても勉強になった
英検や国連英検のスピーキング、ライティング対策として感染症の歴史をざっくりと捉えておく必要があるなあと前から思っていて、たまたまどなたかが紹介されているのが目についたのが本書である。
名著『鉄条網の世界史』と同じ著者ということで購入したんだけど、いまAmazonの履歴をみるともう半年も前のことだった。でもやっと読んだのでKONAMI感想を書いてみる。
総論がまずけっこう面白くて、感染症と人類の
フィリップ・K・ディック『高い城の男』やっと読んだ
SF熱が再燃したので『三体』の次に読むSF小説を探していたのだ。
そうすると早川書房から『サイバー・ショーグン・レボリューション』とかいうものの邦訳が発売されるというではないか。
どうもこれは『メカ・サムライ・エンパイア』というものの続編らしい。
メカ・サムライ・エンパイア、サイバー・ショーグン・レボリューション、なんと少年の心をかきたてるタイトルであることか。
これは読むしかないと思った。