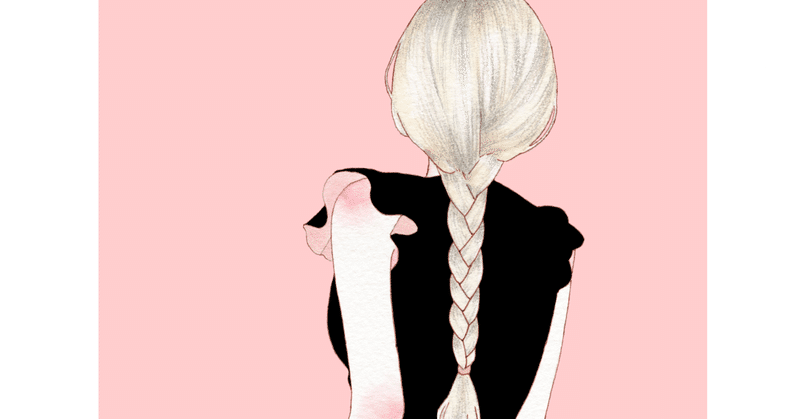
『階段を下りる女』 ベルンハルト・シュリンク
美しい女性の登場するラブストーリーと思いきや、消化不良になりそうな難易度の高い内容だった。ストーリー自体はシンプルなのだが。
語り手の「ぼく」は、フランクフルトで駆け出しの弁護士だった頃、忘れられない恋をした。
発端は奇妙な依頼だった。
依頼主はシュヴィントという画家。彼はグントラッハという金持ちの注文で、グントラッハの妻イレーネをモデルにした絵を描いたのだが、その後イレーネと恋仲になり駆け落ちした。
そのことに腹を立てたグントラッハが、イレーネの絵を故意に傷つけている、というのだ。
シュヴィントは画家として自分の作品に思い入れがあり、そもそも売らなければいけないことにすら耐えられない。
修復しても繰り返される損傷行為に業を煮やしたシュヴィントは、絵とイレーネを交換するという契約書を作ってほしいと「ぼく」に依頼する。
恋人を交換条件にするなんてと驚愕する「ぼく」。
この時すでに自分がイレーネに恋していることに気づいていた「ぼく」は、イレーネと共に逃げることを考えつき、イレーネもそれに同意する。
ぼくにはほんとうに、何の不安もなかった。自分が事件に関わってしまったこと、もし捕まったら弁護士としてのキャリアは終わりだということは、わかっていた。でもそんなことはどうでもいい。イレーネとぼくはもっと別の、もっといい人生を見つけることができるだろう。
計画は、契約が交わされて絵が積み込まれるマイクロバスを盗んで逃走し、どさくさに紛れて逃げ出してきたイレーネと合流するというものだった。
しかし、「ぼく」が思い描いた逃避行は実現されない。合流後、イレーネが「ぼく」を残して絵を積んだマイクロバスと共に消えてしまったからだ、、、。
そして時が経った40年後、弁護士として成功している彼は、出張先のシドニーで偶然立ち寄ったアートギャラリーで、その絵と再会する。
「階段を下りる女」。全裸で階段を下りてくるイレーネを描いた、シュヴィントの絵である。
「ぼく」はフランクフルトへ帰る予定を遅らせ、探偵を雇ってイレーネの居場所を突き止める。彼女は、長期にわたってオーストラリアに不法滞在していた。
彼女と再会して自分が何をしたいのか、彼自身よく分からないままに、「ぼく」は吸い寄せられるように彼女を訪ねて行く。
なぜあの時自分を利用して傷つけたのか。なぜ今になって絵をアートギャラリーに寄贈したのか。
彼の問いに対してイレーネは言う。
グントラッハにとって自分は若くて美しい戦利品に過ぎなかった。シュヴィントにとってはただのインスピレーションの源という意味しかなかった。そしてあなたにとっては王子が救い出すお姫様という役割でしかなかった。男たちこそ、自分を利用していただけだと。
さらには、ただの「上品な社会の一員」であると「ぼく」のことを批判する。
企業の買収や合併など無意味なことにかまけて、国を相手取ったり、政治犯を弁護するような危険な仕事に身を賭けない、正義に命を賭けようとしない、と。
イレーネの言動は図々しかった。別人でなくちゃいけないだって?搾取された人や辱められた人たちのための正義を夢見て、しかも夢見るだけではなく、そのために生きるべきだって?
「ぼく」も反発しているように、イレーネの主張は正直なところ青臭い独りよがりにしか感じない。彼女の主張には真実の一面、理想の一つはあるものの、あまりにも独善的だ。
イレーネがアートギャラリーに絵を寄贈した目的も、よく理解できない。
それはグントラッハとシュヴィントをおびき寄せるためだったと彼女は言う。
結局何が残ったのか、知りたかったの。そしてあのころ••••••わたしは彼らにとって、ほんとうにただの戦利品やミューズに過ぎなかったのかどうか?
イレーネの言葉にはことごとく引っかかるものを感じるが、とにかくその目論見通り、絵におびき寄せられてグントラッハもシュヴィントも間もなく彼女の元へやってくる。
しかし2人とも彼女を求めているのではなく、絵を求めてやってきたというのが皮肉だ。
「時間の流れを止めるために、絵があるんだな。あの当時、きみが若くあり続け、自分もきみとともに若くいられるように、あの絵を描かせたんだ。絵のなかのきみを見て、わたしはふたたび若返った気がしたよ」グントラッハは前屈みになり、イレーネの手を取った。「わたしはあのころ、すべて間違っていた。だから、きみはわたしと一緒には生きられなかったんだな。だが、あの絵だけは返してくれ」
「・・・俺はアートギャラリーとも話し合ったんだ。お前が一言言えば、あの絵はニューヨークに運ばれる。回顧展にも間に合うはずだ。俺たちが夢見てたのを覚えているか?MoMaでの展覧会を?」
数十年ぶりの再会というのに、2人そろって気にするのは絵のことばかりだ。
さらには彼らはイレーネそっちのけで、各々自分の世界観で朗々と論をぶちはじめる。
集まった元夫、妻、恋人達が各論を投げ合う箇所は、やや読みにくいが、それぞれの価値観と人間性がぶつかり合うのが面白い。
資本主義がルールとなった世界の仕組みについて長広舌をふるうグントラッハに対し、イレーネは革命運動の挫折と世界が滅ぶという終末観を語る。そんな2人に対してシュヴィントはイライラし、そんなことより俺の絵を返してもらいたいね、と発言してグントラッハをかっとさせる。
その会話から、イレーネが逃走後、東ドイツに住んでいたこと、そこで革命運動に参加し、テロリストとして指名手配されていることが分かってくる。
彼女が具体的に指名手配されるような何をしたのか、なぜオーストラリアに来ることになり、この地に何を求めたのか、そのようなことは明らかにされないが、うっすらと見える人生から、その青臭く感じられる思想を醸造した彼女の人間というものが想像できる。
言うだけ言って身勝手な男2人が去っていき、再び「ぼく」と2人きりになると、イレーネは「ぼく」に心を開くようになる。
実は彼女は末期の病に冒されていており、彼がやってきてからも度々、一人で歩けなくなるなど弱り切った様子を見せていたのだ。
今まではぐらかしていた自分の状態をイレーネは素直に話し、「ぼく」の介護に身を任せる。
ベッドに寝たイレーネに請われ、「ぼく」は話を聞かせる。
それは2人の、そうだったかもしれない運命、送ったかもしれない人生についての物語、若い「ぼく」が夢見ていた「もっと別の、もっといい人生」の物語だ。
もしあの後2人でアメリカに逃げていたら、もし2人が学生時代に出会っていたら、もし2人が同じ小学校に通っていたら。「ぼく」が語って聞かせる夢物語は甘く優しい。
しかし、そんな甘い想像に遊びつつも、「ぼく」の目線はあくまで現実的であり、イレーネの老いやつれた姿の描写は生々しい。また、彼女の言動に毎回細かく腹を立て、そうやって腹立ちつつも、介護の際に頼り切って首に腕を回されるたびに幸せを感じるなど、「ぼく」自身の心の反応にも現実感がある。
過去に関わった男女が老境に入って再び出会う。いくらでも甘い感傷で着色できそうな舞台設定だが、ここに描かれるのはそんな目を喜ばす絵ではない。
男たちと再会したことでイレーネはどんな答えを得たのか、イレーネの人生について、その最期について、読んだ自分は何を感じるのか。考えてもはっきりした言葉で表現できない。この言葉にできなさこそが、人生というものなのかもしれない。
人間とはこれ以上のものではない、ということを思い知らせる、ある種のリアリズムを感じる小説だった。
