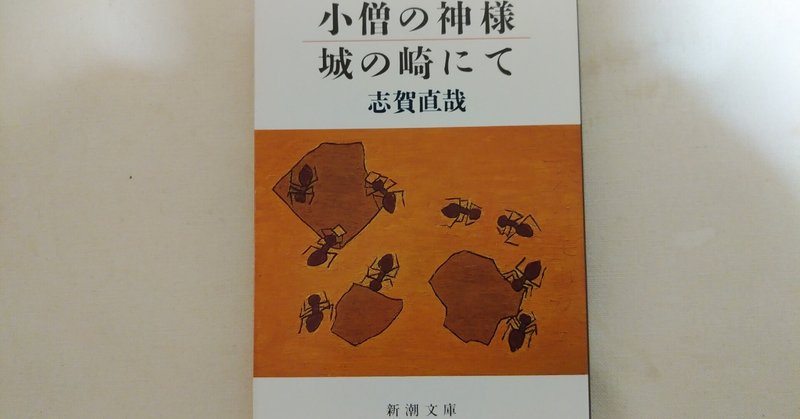
志賀直哉『小僧の神様・城の崎にて』(新潮文庫)
短編集。収録作は「佐々木の場合」「城の崎にて」「好人物の夫婦」「赤西蠣太」「十一月三日の午後の事」「流行感冒」「小僧の神様」「雪の日」「焚火」「真鶴」「雨蛙」「転生」「濠端の住まい」「冬の往来」「瑣事」「山科の記憶」「痴情」「晩秋」
私が小説を読むのに慣れてきたのか、これらが志賀の後期の作品群で円熟してきたのか、無理なく読む事ができるようになってきた。なぜこんなに小説を読むのが苦痛なのかも疑問だが。二十代ぐらいまでは読書と言えば小説しかなかったのだが。
「佐々木の場合」、面白かった。志賀は、人から聞いた話という体裁を取る場合があるが、志賀自身の話も入っているかもしれない。これを読んで私は、近代のある階層以上の家庭における「女中」という存在が、近代社会、ひいては近代小説において持っている影響力を改めて考えた。漱石の「坊ちゃん」も太宰の「津軽」も女中(あるいは下女)無しでは存在し得ない。(これは以前どこかで書いたな。どこだったか。一度きちんとまとめておかないと。)
作者は佐々木をエゴイストだと言っているし、もちろん佐々木自身は自分を誠実この上ない人物と思っているだろうが、読者としては作者の思惑通り佐々木を本当にエゴイストだと思うのだ。気になるのは、作者は佐々木をエゴイストと言いながら、そのエゴイストの心境を、まるで自分の心境ででもあるかのように、実に真に迫って書いている。この種のエゴイストは近代だから、ではない。現代にももちろん大勢いる。
「城の崎にて」、これは押しも押されもせぬ名作。教科書で一部を読んでいたが、今回実にしみじみと読んだ。教科書で読む高校生はこれに共感できるのだろうか。死ぬかも、と思ったことの無い場合は難しいのではないか。頭で読むだけになりそうだ。
「赤西蠣太」「転生」、お話っぽくて良い。
「小僧の神様」、あんまり良くない。小僧の描き方が何か違う感じがする。
「瑣事」「山科の記憶」「痴情」「晩秋」、うんざり。いわゆる私小説。でも曝している私生活がこれでOKだった時代はもう終わってると思う。今なら許されないタイプのモラハラ夫。こんな思いをさせられた上に、それを小説の材料にされる家族はたまったもんではない。
〈私は不愉快だった。如何にも自分が暴君らしかった。ーそれより皆から暴君にされたような気がして不愉快だった。〉〈気がとがめている急所を妻が遠慮なくつッ突き出した。私は少しむかむかとした。「今頃そんな事いったったて仕方がない。今だって俺は石(女中の名)のいう事を本統とは思っていない。お前まで愚図々々いうと又癇癪を起すぞ」私は形勢不穏を現す眼つきをして嚇かした。「お父様のは何かお云い出しになると、執拗いんですもの、自家(うち)の者ならそれでいいかも知れないけど……」「黙れ」〉「流行感冒」より
大体こんな調子。もちろん、志賀や彼の描く人物だけがこんなプチ暴君だったわけではなく、珍しくない存在だったのだろう。そうでなければ彼の小説が読まれるわけはない。
〈「総てに馬鹿さの感じが、漲っているじゃないか。家中が馬鹿さの埃で一杯だ。眼も口も開いてられやしない」こんな風に見得も振りもなく怒鳴り散らした。「又、出家遁世ですか」「本統に俺は旅行するから、直ぐ支度してくれ」「お株が始まりましたネ」「直ぐ支度してくれ」「何をそんなに怒っていらっしゃるの?何もそれ程お怒りになる事ないじゃありませんか。何がいけないの?」「一から十までいけないんだ。十から百までいけないんだ」子供から寝起きの悪い良人は朝飯の食卓でよくこういう癇癪を起した。空腹だと一層それが烈しかった。〉〈「つまり貴方があんまりお利口過ぎるのね」或朝良人が珍しく機嫌のいい時、細君は笑いながらこんな事をいった。「お前が馬鹿過ぎるんだよ」「そう?そんなら私も今度は出来るだけ利口に生れて来ますからね、貴方ももう少し馬鹿に生れてきて頂戴よ。釣合いがとれないからね」「人間に生れて来たんじゃあ、いつまで経っても同じ事だよ。女の馬鹿は昔から通り相場だ」「人間でなく、何がいいの?」「豚かね?」「貴方さえおつき合い下さるなら……」細君は笑った。「豚は御免蒙ろう」〉「転生」より
こういう男はいなくなったわけではないが、こういう女はいなくなった。こんな出来た女というか、物分かりの良過ぎる、度量の広い女はもういない。現代の全ての女性には「旅行したかったら自分で支度しろ!二度と帰って来るな!」と叫ぶ権利があるはずだ。この女はこの夫と生まれ変わっても一緒になろうとしているのだから驚く。しかしこの結末は——二重になっているのだが—―笑える。この短編集の中で一番お話らしいお話と言えるかもしれない。
新潮文庫 1968.7. 本体520円(税別)
