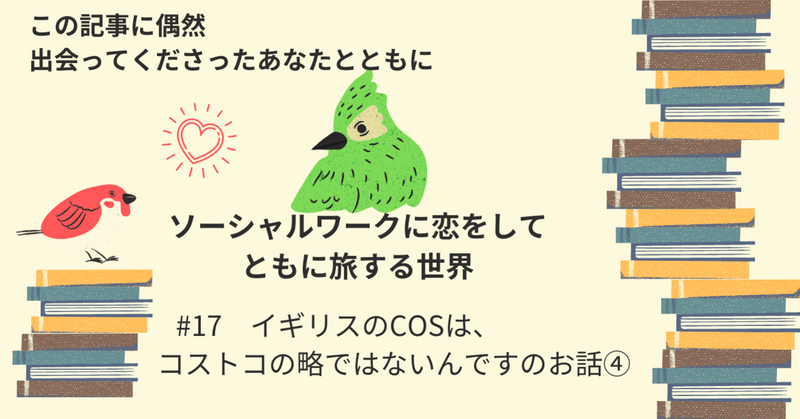
イギリスのCOSは、コストコの略ではないんですのお話ー最終章#17
皆さん、こんばんは。おやすみのところ失礼します。
モモです^^
毎週日曜日の夜にソーシャルワークに恋をしてともに旅する世界ー序章ー
初めての方はようこそ!
たまにのぞいてくださる方、ありがとうございます^^リピータの方、心からありがとうございます!
今夜も一緒にゆったりと旅をしていきましょう。
理想は「アナザースカイ」のような感じ。始める前に旅のアテンション♪
_______________________________
・連載ですが、初めてでも大丈夫。この旅だけ参加でも大丈夫。
・眠いから途中で寝ますも大丈夫。先にお伝えしておきます。
「おやすみなさい^^」
_______________________________
ざっくりあらすじ
さて、19世紀後半産業革命の時代のイギリスで、ソーシャルワークの源流地をたどる旅をしているところでした。そして、ソーシャルワークの源流といわれる、「慈善組織協会(COS)」のお話をしていたろろでした。ここで、前回の出来事を思い出しておきましょう!
前回の旅のおみやげ_____________________
COSは、Chiarity Organization Societyの頭文字をとった略称で、1869年にロンドンで設立された組織。慈善事業の組織化や救済の適正化を目指した!そして、主な活動内容の1つ目は、個別訪問による貧困家庭の現状把握と救済ニーズの確認!だった。
__________________________________
ということで、今回も前回の続きですね。(いつも続きなのですが・・・)活動内容の②調査時の記録の徹底⇒救済の重複化や不正受給の防止の確認から入っていきたいと思います!今回こそは、キリの良いエンディングを目指して!
活動内容の②って何?と思ったそこのあなたへ!前回記事のCOSのプロフィールになります↓!
目的:大きく分けて2つ!
①慈善団体の連絡、調整、協力等を行うことによる慈善事業の組織化
②救済の基準やルールがない無秩序な状況で行われていたこれまでの慈善活動による救済の適正化
主な活動内容:こんなことをしていました!
①救済(支援)が必要と思われる貧困層の家庭への個別訪問調査
②調査時の記録の徹底⇒救済の重複化や不正受給の防止
③個別訪問を行う訪問員のためのハンドブックの作成&配布
記録がなければ思い出せない不正も見逃してしまう?
①個別訪問調査でまず、「貧困家庭の現状をしっかりと把握する!」ということを目指しました。さて、把握したら次はどうするかというとことなのですが、現代では普通なのかもしれません、そう「②記録をする」です。
訪問をして生活環境を確認したり、住民から話を聞きます、そうして、この世帯は、救済が必要な貧困家庭だ!と判断されたら、カードのそのことを記録して、その世帯の住民を要保護者として救済者名簿に載せます。
これまでは、様々な私的な慈善事業が乱立していたので、記録の統一化や共有が全く行われていませんでした・・・。しかし、ここでロンドンで統一したCOSへの救済者の登録や名簿の作成が行われたことで、一気に状況が把握されやすくなり、そして不平等感の解消につながったと言えるでしょう。ちなみに、調査は、小さな地区ごとに分けて行われ、調査者は友愛訪問員と呼ばれました。
そして、そして、統一的な記録がされていくことで、同じ世帯に重複して訪問してしまったり、救済を受けられない世帯がある一方で救済を過度に受ける世帯の発生などを防止することができました。社会福祉の制度が確立した現代ではありえないことですが、これが当時の状況だったんですね。なるほど、どんなことにも最初の一歩があるものです。現代風にいうと、何かの助成や優遇の不正受給の防止!といったところでしょうか。よく問題になるやつですね。
次回以降の旅の布石コーナー
ちょっと寄り道・・・次回以降の旅の布石その1を今打たせてください笑。この世帯は、救済が必要な貧困家庭だ!と判断するその基準ってなんだろう?いわゆる貧困世帯と決める基準ですね。そのことは、どこかで頭の片隅に疑問として持っておいてください!(なんという強要、誘導。ただここが大事なんですね笑)
しつこいので、布石その2も打たせてください。一言で終わります!
「救済って何?」「これまでの失敗してきた法律の取組と違うの?」
はい!ふたことになりましたが以上です!では、もとの旅に戻ります!さて、活動内容の3つ目にうつります。こちらは簡単です、一瞬で終わります。とはいえ、一応章立てはしておこうと思います!
画期的な最新トレンド?マニュアルつくって統一化!
はい、3つ目の活動としてご紹介してのが、③個別訪問を行う訪問員のためのハンドブックの作成&配布でした。ちなみに、訪問調査のことを当時は、友愛訪問と言っていたそうです。
この言葉には、「同じ人間同士、対等な立場で、訪問員は、訪問先に家庭で友人に接するような姿勢で関わりましょう。」そんな思いが込められていたようです。これは現代にも通じますが、何かを判断したり調査をしたりとういった行為をするときには、する側とされる側でなんとなく上下関係のような関係ができてしまいがちです。そういった関係をよくパターナリズムと言ったりします。「~してあげる」そんな感覚はなくしましょうという当時の救済の際の精神が込められていたようです。このことは、現代のソーシャルワークの精神にも大きくつながるものですので、ちょっとお話ししておきました。
一瞬で終わらせるのもさみしいので、少し余談でした。ただここも大事なポイントですので頭の片隅にぜひ^^
戻ります。そう、友愛訪問員のためのハンドブックがつくられたんですね。訪問時のルールや聞き取りや記録の仕方、別の訪問員に引き継ぐ際の引継ぎの仕方など様々なことがまとめられたそうです。
いつの時代もマニュアルがあると安心ですね。以上です。ハンドブックについて深堀してもいいのですが、そうすると以前のマルサスの家の訪問時のように旅が長期化してしまうのでこのあたりで・・・。
そろそろです。いつもの文字数の件について
といっても今回は、もうすぐ3000字です。最近の記事の中では優秀な気もしますが・・・!活動内容の3つの説明が終わったので、まとめにはいって終わりしますね。(最終的には、3666字になりました・・・)
本日のまとめーやっぱりコストコじゃなかった!
前回の後半と今回の2回にわたって、COSの活動内容についての話をさせていただきました。
まとめると、3つの活動によって、ばらばらだった活動がCOSによってまとまり、貧困救済という分野での相互の連携と組織がが実現できたということですね。そして、イギリスのCOSはやっぱりコストコのコスではなかった!というそんなオチです。
次回の旅のアナウンス
さぁ、言い訳ばかりのまとめ方ばかりをしていたのですが、今回は、布石を打たせていただいていたのでスムーズに次の舞台に行けそうな気がします笑
いつの時代も、何かがあると、それに対する批判や改善点に対する解決策が提示されるもの。ということで、ソーシャルワーク源流と言われる産業革命期のコストコ、いや、事前組織協会(COS)にも改善点や上手くいかないことがあったんですね。でもいいんです、上手くいかないから次がある。この旅も続けていくことができます。
ということで、次回は、コストコじゃないCOSは、次の舞台へ!と題して、COSの取組に次に登場した貧困対策、セツルメントという取り組みのお話に旅の舞台を移していきたいと思います。
安心してください、今回も時代はぶっ飛びません。もう少しイギリスにいます。セツルメント?これまでの流れで行くと、「セメントに似ているので、セメントの略じゃないんです、固まらないんです。」とかそんなしょうもないギャグを継続しようなんてそんなことは考えていませんから。考えていませんから!
おみやげを置き忘れていました。もう簡単に!
今回の旅のおみやげ_________________________
COSは、友愛訪問員が友愛訪問をして、貧困世帯の状況を聞き取り調査をしていた。そして、記録をして共有をして連携をして組織化した!
__________________________________
ということで、今夜も、読みにくい文章にも関わらず、最後までお付き合いいただきありがとうございます。次の旅でお会いできるのを楽しみにしています!次の週末まで皆さん、フリースタイルで、各自いろいろ進めていきましょう。
それではみなさんおやすみなさい☆彡
また、この旅って何一体?と思った方は、先週お届けした記事をお読みいただけれるととっても嬉しいです。
前回の記事はこちらです^^
この物語全体のお話はこちらです^^
アナザーストーリーはこちらです↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

