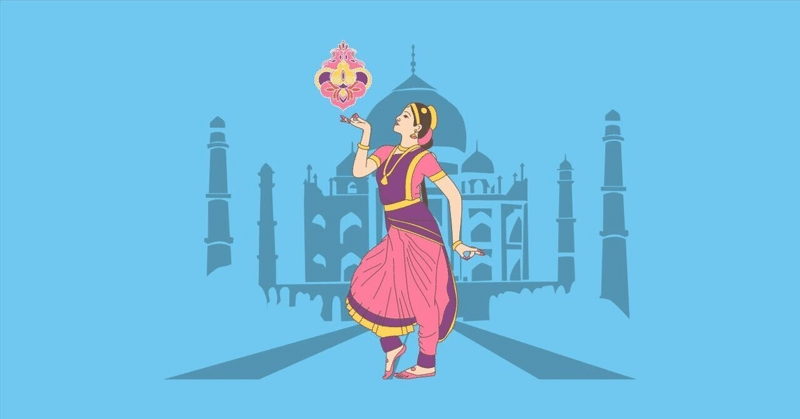
【翻訳】F・W・ベインの印度物語 ~日輪の堕落~ ②
前章につきましては以下の記事をご覧ください。
日輪の堕落
The Descent Of The Sun
英訳:フランシス・ウィリアム・ベイン
和訳:弾青娥
夜
睡りと夢
第一章:昼の蓮
アヌシャイニーは森から姿を消した。幾許もなく、流星のように地上に堕ちると、インディラーラヤ国の王の愛妻の子宮のなかに入り、人間となってその王の娘として生まれた。その刹那、アヌシャイニーは自身の体から光輝を放って産褥の間を照らした。その輝きたるや、灯火を圧倒するばかりであった。子守たち、侍女たちは仰天していた。驚くべきことに、黒くて長い睫毛がこの赤子のまぶたを囲うように飾っているのだった。その様子は、低く垂れ込むゆえに昇りゆく月輪を隠す雨雲を思わせた。出し抜けにその睫毛が帷のごとく持ち上がると、両まぶたの下からは漲る青色が姿を見せた。その色は、目に見えるようになった樟脳や白檀の香のように空間じゅうに広がり、赤子のそばにいた全ての者は五感を奪われ、ついには恍惚とする様子を少し見せていた。この者たちは、仰臥して蒼穹のはるか彼方を注視する者のように、あたかもこの空間が天の色彩に覆われたかのような心地で、日々こなしている労のことを忘れていた。女たちには知る由もないのだが、目にしていたのは月輪を紋章とする神の御稜威が映っているさまであった。
それゆえ、周囲の誰もが言葉を発さず、赤子の双眸をじっと見ながら立ち尽くしていた。長い時が経ってようやく、王が、侍臣たち、医官たち、占星術師たちを連れてやって来たが、一度深く吸うと、驚きのあまりに互いに目をやった。やがて侍臣たちの長が言った。
「王よ、これは吉祥でございます。この両目は赤子のそれではありません。賢人のものです。あるいは御神の有される両目です。この存在が単なる人間の乙女でないのは明らかです。何らかの御神であるか、呪詛のためにこの下界へと一時的に堕ち、前世で犯した罪を贖うべき運命にある御神の欠片なのでしょう。斯様なことは滅多に起こらないことではありません。化身という術をもってこの御神によって選ばれたということですから、陛下が寵愛をお受けになっているのは間違いございません」
いかなる出来事に際しても常に適切な発言のできるこの侍臣がこう話すのを耳にすると、王は欣喜雀躍としていた。稀に見るほど豪華な形で自らの娘の誕生を祝った王は、婆羅門の者たちと貧民に黄金と村を与えた。命名のことに通じた占星術師たちと婆羅門の賢者たちと相談し、娘にシュリーという吉祥あふれる名をつけた。というのも、王がこう言っていたためである。
「この子の目は蓮のようであり、蓮の棲まう池のようでもある。〈美の神〉の双眸を模したものにまさしく相違ない。御神は海から昇り、ご自身を形作った泡沫の波が打ち寄せる青い蓮のゆりかごに横たわって、彷徨う波という波を凝視しては嘲弄し、ご自身の双眸を彩るべくその波から色を収奪なさった。まさに、そのような双眸である」
時は過ぎゆき、砂漠じゅうを往く隊商のように季節が巡れば、王は老い、白髪交じりになり、老衰が王のしわだらけの耳の付け根に居を構えた。一方でシュリーはというと、幼児であったが少女となり、ようやく幼さという名の夜明けを迎え、大人の女性らしさが見えはじめた。満ちゆく月輪の角のごとく、シュリーの四肢は丸みを帯びて膨らむと、まさしく至上の美を有した無欠の宝珠と化した。美の海と言えば、それを口にした何人にも癒えることのない渇きを与え、この女神の双眸という青い湖沼の水への渇望を抑えられなくするものであるが、そのような海の塩へと、シュリーは変じたかのようであった。長き時が過ぎ、とある日を迎えると、シュリーの姿を見た父である王は自らにこう言い聞かせた。
「果実が熟れた。この実は今や摘まれて食されるべき時だ」
そこで王は、女の居室が群立するところに向かった。シュリーの母であり、自身にとっては最も大切な妃であるマディレークシャナーに会うためであった。しかし、当の妃は王が来た目的を知ると、こう口にした。
「貴方様、無駄です。私たちの娘は夫という言葉を耳に入れようとすらしませんし、ましてなされるべきことを果たそうとしませんから」
これを聞き、王は言った。
「どういうことだ? 鋤を拒む小麦畑があろうか? それに、結婚を拒む乙女がいようか? 娘は年齢からして成熟していないのか? 一人前になった一家の女子どもが未婚を貫くならば、自らにも、その親族にも現世と来世における汚名を着せるのではないか?」
すると、マディレークシャナーが返答した。
「ご自身で娘に話してください。できることなら、説得してみてください。娘は自らの意思で私に言いました――結婚など、夢のなかでも思いもしないことだったと」
そこで、王は自らの手で尋問するべく、娘を呼んだ。
しばらくして、シュリーがやって来た。娘の動きは白鳥のごとく波に揺れるかのようであれば、風になびく花のようでもあって淑やかであった。というのも、娘の腰は握りこぶしに包み込まれるかのように華奢で、胸元は稜威を放っていたからだ。子どものように父親に微笑んだ。それは口を開け、目を半分閉じながらのことで、その双眸は己のまつげという網をもって濡れた蓮の色の有する魔的な魅力を投げかけていた。娘の腰帯はまるで喜んでいるかのように金属の音を軽く奏でた。一方、きらめきを放ちながら全身を覆う装身具は色が変わったが、自分たちより強い輝きを見せる娘の双眸にゆらめく光に嫉妬しているかのようだった。老齢の王は誇り、驚き、喜びをもって娘に目をやった。そうすると、腹のなかで笑いが生じ、王は自分にこう言い聞かせた。
「〈創造主〉のご狡智ぶりは何と見事であるか! それに、女の美に潜む謎は何と不可解であるか! この身は老いたとはいえ、余はこの子どもの父である。だが、娘の前にいると、この世の支配者を面前にした恭順な従者のようになる。我が娘が若い男を狂気と恍惚の境地に至らせるのは明白だ。まったく、〈創造主〉が女というこの陶酔の化身を形作られたが、これが無益に終わるであろうか。我が娘は明らかに、人間の姿をとった、夫にとって理想的な相関物である」
そうして、王は娘に語りかけた。
「我が娘よ、早く結婚の相手を見つけるのだ。未婚の娘がいるのは、その父の一家にとって恥ずべきことであるゆえ」
その言葉を聞いたシュリーは言った。
「父上、そのようなお言葉はお止めください。私は未婚のままにこの生を全うしたいのです。結婚は私の望むことではありませんので」
それに対し、王はこう言い返した。
「何を言っているのか分かっているのか。この世に生まれてきた目的とは、夫を得ることに他ならぬだろう?」
すると、シュリーは答えた。
「夫のことを夢見るのもどうかお止めください。これには訳があります。私は他の乙女とは違うのです」
これを聞いた王は困惑してしまった。上目遣いでシュリーに目をやると、王は心のなかで言った。
「真実を語っているではないか。この我が娘が、本当に我がものであるならば、他の乙女とは一線を画していよう。あの美しさに匹敵する者など、この世のいかなる者が目にしたであろうか。結婚を拒む乙女のことを耳にした者などこの世にいるだろうか。我が家臣の見立ては正しかったのか。だとすれば、実際、この者は姿を変えた神ではないか」
毎日、王は娘を説得しつづけ、意見をぶつけ合った。だが王は、自身の骨折りが金剛石を綿の糸で貫こうとするようなものだと悟ると、とうとう狼狽えて語気を強めながらこう告げた。
「前世における余の罪科は数多にわたって醜いものであった。それゆえに、その成果として娘を得た。だが、夫に対する頑なで理解できぬその偏見は女の本質に背いており、余の救済をふいにするものとなろう」
これを聞いて、ついにシュリーはこう口にした。
「父上、お怒りにならないで下さい。本当のことをお話しいたしますから。この私も夫を欲しているのです、ただ唯一の夫を」
それを聞き、王は尋ねた。
「その夫とはどのような者だ?」
シュリーは答えた。
「見当はつきません。ですが、その方は〈日輪の蓮の国〉から私を娶りにやって来るでしょう」
王は聞いた。
「その〈日輪の蓮の国〉とはどこにあるのだ?」
シュリーは言った。
「分かりません。とはいえ、夢のなかで蓮が天より落ちるのを目にしました。それから、天の声が私にこう告げました。『急ぐことなかれ。待つことだ。さすれば、〈日輪の蓮の国〉からそなたのもとに夫がやって来よう。この者は前世にてそなたの夫であったのだから。その者の存在をそなたは徴効をもって知るであろう』と」
その言葉を耳にし、王は問うた。
「その徴効とは何なのだ?」
シュリーは答えた。
「申せません。御神と私にだけ交わされた言葉であるからです。とはいえ、今や選択肢は二つです。私の結婚を見限るか、もしくは実現できればの話ですが、〈日輪の蓮の国〉を目にしたことのある男を、王女となる階層にある私のために見つけだすかです。そのような存在が見つかれば、その者が我が夫になるでしょう。私はその方以外との結婚を望んでおりませんから」
王がこれを聞くや、唖然として言葉が出なくなったまま、シュリーに目をやった。そして自分に言い聞かせた。
「これは妙なことだ。この謎に満ちた我が娘の行いは理解不能だ。何が〈日輪の蓮の国〉だ。生娘の考える妄想か気まぐれな夢ではないか。いや、この夢は前世の存在を偽りなく示唆しているのではないか」
王はしばらく考えを巡らせると、再び心のなかで言った。
「もしかすると、娘の言うように、あの国を目にした者を探すのに努めるのが望ましいのかもしれない。損になるようなことがあろうものか。その者が見つかったとしても、考える時間は常々あるだろう。それに、娘が夫を得るのであればこの形であろう。これ以外のやり方では結婚を果たさないのが確実であろう。娘が未婚でいつづけることで余たち皆を滅ぼすことになるよりも、その者の正体が何であろうとも、夫を得てもらうことが何よりだ」
それから王は自らの娘を去らせ、侍従たちを呼んだ。そして、参上した彼らに告げた。
「触れ役を確保せよ。触れ役を都じゅうに行かせて、太鼓を鳴らしてこのように布告をさせよ。『〈日輪の蓮の国〉を目にした、高い階層にある男に、我が国をやろう。そして、我が娘と結婚させよう』と」
この命令を聞いて驚嘆する侍従たちだったが、彼らは直ちにその場をあとにし、触れ役たちに王の命令を伝えた。
第一章 完
註
※〔〕は和訳者による追加注釈。
(1)アヌシャイニーの魂が肉体から分離したということである。プラトン、バガヴァッド・ギーター(現代の神学者より論理的である)の解釈を借りて言えば、アヌシャイニーの一部をなす魂は生まれることも無ければ、死ぬことも無い。
(2)シュリーのおわす地という意。青い蓮がその一例である。そう呼ばれるのは、女神のシュリー〔ラクシュミーの別称〕が乳海撹拌時に蓮に浮かびながら現れたため。
(3)熱情を鎮めて平穏を得た者である、シャーンタのこと。そのような存在で、最たるものはシヴァである。しかし、この家臣は的外れな推察を立てて的を射ることは無かった。
(4)それゆえ、前述の都の名前が存在する。
(5)美と塩はサンスクリット語の原典において同じ単語で表されている。
(6)「甘美で魅惑的な目をした女」という意である。
(7)自分の亭主のことを呼ぶ際に女性が使うのに適した言葉である。「アーリヤ〔高貴な生まれの男〕の息子、紳士」という意である。英語で相当する語は無い。
(8)古のヒンドゥーの民は、白鳥のように歩く女性を特に称賛し、特別な言葉(ハンサガミニーという語)をあてていた。
(9)この箇所には、カマラハーサという語による、翻訳不能な言葉遊びがある。この語には蓮の蕾の開花という意も、実に魅力的な笑顔という意もある。
(10)変化を遂げる光沢を、もしくは宝石のゆらめくきらめきを表現する、ヴィヤティカラという語。
(11)カリマコス〔ヘレニズム期の古代ギリシャの詩人〕の「我に乙女を永遠に授けよ、さすればその者を危険から護ろう〔dós moi partheníen aión ion, appa, phylássein〕」という言葉と比較せよ。
(12)この雰囲気は、自らの意思で生まれた女、つまり娘という意を有する、アートマジャーという美しい語に端を発している。
(13)西洋では恐らく絶対的に知られていないというわけではないが、美は要塞のように包囲によって引き立てられるのを常に良しとしなければならない。一方、ヒンドゥーの民の地において、結婚とは生と死のように当然のことであれば、必須とされつつも、不可避かつ不可欠であり、常に場所を問わずに万人から信じられていることである。
(14)原典において直訳不可能なニュアンスがある。ヒンドゥーの民によると、蓮は〈昼の蓮〉と〈夜の蓮〉に区分され、前者は日輪を、後者は月輪を好む。当該の〈蓮〉は「黄昏と黄昏にはさまれた」日輪の蓮であるが、すなわち夜の闇のなかに埋もれ、日輪の貫禄を奪われる。このようにして今回の物語の題への暗示的な言及が初めてなされている。とはいえ、これはサンスクリット語によって一語で示されるように、英語では一語で表現できないものである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
