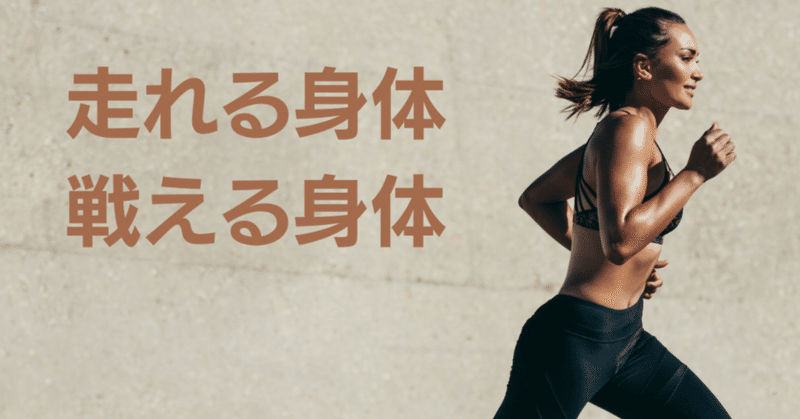
来年2023年のウルトラマラソン(100km)で自己ベストを狙うために
ニクラス・ブレンボー (2022) 寿命ハック -死なない細胞、老いない身体..新潮新書
死なない?
「老化は治療可能な病気」この研究はどこまで進んでいるのでしょう
本日は、ニクラス・ブレンボ―著の第3部からご紹介します
Ⅲ 役立つアドバイス
ここでのアドバイスは、効果の度合いは具体的には証明できませんが、たぶん良い結果につながるでしょう。という気持ちで取り組むといいと思います
■楽しく飢える
食事制限は有益か/最も寿命がのびるのは飢餓状態/腹八分目は理にかなっている
私の日常の食事の量は1.5食です。朝は炭酸水とコーヒー、昼はヨーグルトとフルーツ、夜は普通に1食頂きます。この日常の食事を大切にするために、自炊は鉄則です。野菜を中心に魚、海藻、卵、豆がタンパク質の基本です。
最近、よく作るのが小豆(炊いただけ・甘くありません)のお味噌汁です。
さらに、最も気をつけているのが調味料です。少し高くてもいいので、食品添加物や砂糖が入っていないものを選びます。
夜に友人と外食したり、昼にランチに出かけたり、旅行の時はホテルの朝ごはんを食べることもあります。しかし、この特別な食事は平均月5回です。
■歴史ある習慣を見直す
大事なのはカロリーか食事時間か/断食とダイエット/382日間食べなかった男
この書籍では
「絶食は一種の『ホルミシス』でストレス要因となって私たちの体を強くする」と説明されています。さらに、1日おきでの断食では代謝も落ちず、それどころか代謝や志望燃焼が高まるとされています。さらに、時間制限食をしながら筋トレするのと、普通に食事をしながら筋トレするのと同程度の筋肉量を得られることが研究であきらかになっているようです。
私の友人も月に1回、3日間程度のファスティングをしている人がいます。
私は、19:00~翌日の昼食(16~17時間)まで固形物を食べません。
■カーゴカルトの栄養学
栄養学の論文は矛盾だらけ/長寿の人々を真似れば長生きできるのか/ランダム化比較試験から分かること/ビタミンDはわたしたちを健康にしない
この書籍では
「いくつかの研究が食品会社から資金提供を受けている」ことを説明しています。なので栄養学が矛盾だらけなのです。
私も、健康に良いと言われている飲料は一切飲みません。体に良い栄養成分よりも、体に悪い成分(砂糖、果糖ぶどう糖液糖など)を摂取したくないからです。
また、相関関係はあっても因果関係が証明できない例もたくさん紹介されており、大変興味深いです。例えば、野菜をたくさん食べる人は長生きな人が多いという相関関係があったとしても、その人たちは健康意識が高いため、定期的な運動を行っているかもしれないし、ジャンクフードを食べていない可能性も高いという他の変数の影響を除かないと「原因」は明らかにならないということです。それらを明らかにするランダム化比較試験でほぼすべての効果が調べられるようになってきました。
その結果、延命効果があるのが
①オメガ3脂肪酸 (サーモン、さば、にしん)
②ビタミンD(あん肝、しらす干し、いくら、サーモン)
■中世の修道士から現代科学へ
血糖値コントロールが長寿への近道?/糖尿病薬がアンチエイジングに効く
この書籍では、
100歳以上の長寿者はインスリン感受性が高く、血糖をうまくコントロールできているきことを科学者たちは発見したと説明しています。
また、インスリン感受性に関して、炭水化物そのものが問題ではなく、健康的な体重で、甘い菓子ではなく自然な炭水化物を摂っていればインスリン感受性は高くなり健康でいられるようです。また食後の軽い運動も効果的と伝えています。
私は、お菓子は原則食べません。そして我が家には「砂糖」はありません。なので、甘辛い味付けの料理は食卓にででこないです。コンビニ食、そして外食も極力減らしています。自然な甘いものは大好きなので、カボチャ、さつまいも、フルーツ、干し柿などのドライフルーツで摂ります
■測定できるものは管理できる
死因の第1位は遺伝性/1日25個の半熟卵を食べる男/高血圧になりにくい人々は長生き/運動すればするほど健康に/筋肉と長寿の関係性
この書籍では、
運動は寿命延長効果のあるさまざまな適応を促進することを明かにしています。運動は安静時血圧を下げ、血糖値を改善し、炎症や酸化ストレスを減らします。運動が健康に良いのは、回復中に起きる反応のおかげのようです。
また、有酸素運動だけでなく、筋肉量を増やす運動を加えるとさらに効果がでるそうです。
私は運動は習慣になっています。天候や仕事のスケジュールの関係でバラツキはありますが、ランニング 週4回(30Km)、ヨガ 週3回。
いろいろまとめてみましたが、簡単に若返る魔法はないということですね。
みなさんも正しい習慣を作っていきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
