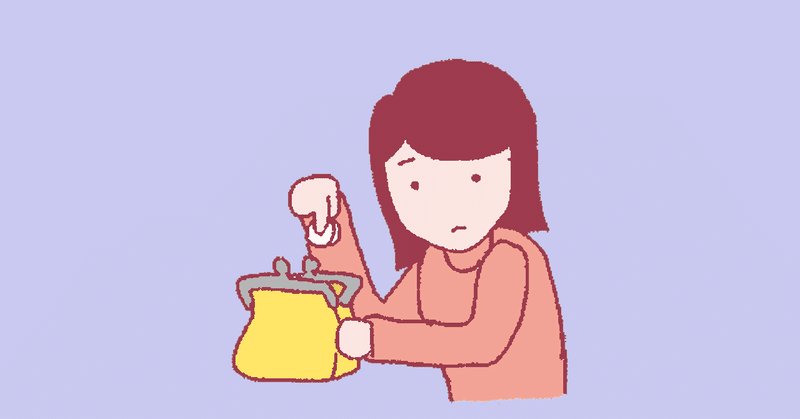
身内であっても等価交換が重視される、令和の家族観
労働分担の均衡点が変わった
女性の社会進出により、家計を支える経済力は男だけのものではなくなった。すると、次に貴重な資源である労働力をめぐり、家族間で闘争が起きる。これが令和の時代における家族観の大前提である。
なお、ここでの労働とは、ビジネスの世界における労働に加え、家事・育児・介護など全般を含んだ広い意味のものを指すこととする。
まず、従来の「専業主婦+家事・育児・介護を丸投げする夫」という構図は均衡点としては成り立たなくなっている。父親の丸投げを母親が必死に耐えてきた姿を見た娘は、同様の振る舞いを決して夫には許さないだろう。
いつまでもビジネス世界の労働にしか目を向けない人間は、パートナー間で等価交換の認識がすりあわず、行き着く先はモラハラ、DVなどを経由した家庭生活の破綻である。
結婚に暗黙のうちに紐づいていた家事労働、育児労働、義理の親族へのしがらみを切り離し、各項目ごとに擦り合わせてバランスがとれるようにしよう、というのが今の20〜30代の多数を占める結婚観なのだ。(ここについていけない人はそもそもパートナーを見つけられない)
家族内の労働分担の変化は、働き方にも影響を及ぼす。どんな時代でも営利企業の本音としては社員に限界ギリギリまで働いて利益をもたらして欲しいと願うものである。しかし、家庭維持により多くの労働が必要となったことで、会社の思惑に絡め取られまいと抵抗する社員が増えてゆく。
テレワークを望む声もその一つだ。ちなみに、テレワーク割合が多くても許される職場は、仕事内容と上司の考えが噛み合った時だけ奇跡的に立ち現れるもので、上の人間が変わった途端に突然崩れるほどの脆いものであることは自覚したほうが良い。
フルリモートを前提として職場から遠い場所にマイホームを購入したはいいが、コロナ明けに出社指令が出て頭を抱えるのはよくある話だ。
身内割引と親の介護問題
労働力闘争の重要項目はなんといっても介護だろう。老老介護とかヤングケアラーなど、なにかとニュースを賑わせている。ここでは家族間での介護労働の情勢変化を描写してみよう。
「身内の人間であるため、通常の市場価格よりも割引された状態でのサービス提供を受け入れる」ことが家族の間では普通に行われている。子供が産まれた時に親に子育てを手伝ってもらうとか、無償で親の介護をするとか、大人になっても実家暮らしをしているなど、世の中にはありふれている。
このような「身内割引」が受けられず、全て自腹で市場から買ってこようとすると、とてつもなく高くつく。身内割引の存在があるから、低い給与水準でもなんとか生きてゆける人は結構たくさんいる(子供部屋おじさんとかね)。
ところが、時代が下るとともにこの「身内割引」の水準が変化しているようだ。
具体的には「孫の顔を見せた時点で親孝行でしょ。だから子育ては手伝って。でも、うちらはあなたの介護はしませんよ。公的サービスで賄いきれない部分は自分でなんとかしてください」と宣言する人間が身の周りでも増えつつある。自分の親ですらこうなのだから、こういう人間は義理の親の介護など引き受けるはずがない。
これまでは「家族だから」という免罪符で無料でのやり取りが当然視されていたが、「いやいや、これまで受けてきた愛情とか恩恵と見合わないからその取引には乗らないよ」となるのが令和の時代だ。
そのため、歳をとるにつれて「地獄の沙汰も金次第」な側面がどんどん強くなるだろう。お小遣いをあげないと孫は寄り付かないし、手厚い民間の介護サービスを得られるかは経済的余裕に左右される。民間の介護保険の存在意義はここにあるのだが、外からの働きかけがないとなかなか気づかない。
遺産を残せるのであれば、子供も(下心を内に秘めながら)甲斐甲斐しく世話をしてくれるだろう。
ここで親の側が「遺産を狙われるのは嫌!」と思って遺産を別の人に渡そうとすると相続で揉める。どうせ財産はあの世には持ってゆけないのだから、ここはもう契約だと割り切って、介護で面倒をみてくれた人に遺産を多めに渡してもいいのではないか。
夫婦別財布 VS お小遣い制
夫婦別財布で、子供ができたら共用口座にお金を入れるようにする家庭が増えてきた。これもまた「一人一人が主体となって己の幸福を追求する」時代の潮流を表している。
一度お小遣い制になっていたが、妊娠・出産で奥さんが自由に身動き取れないのをよいことに、なし崩し的に再び夫婦別財布にするなんて業のものもいた。
観察していて気づいたのだが、どうやらお小遣い制は家庭において二つの機能を果たしているようだ。一つは「浮気&無駄遣い防止」、もう一つは精神修行である。
一つ目は直感的に分かるだろう。愛人募集のためには傍目で分かるぐらい見栄を張らなくてはいけない。当然、愛人を囲おうと思ったらさらにお金がかかる。相応の見返りがないと愛人というリスクのある立場を受け入れるインセンティブがないからだ。
お小遣い+へそくり程度ではとても維持できないだろう。このあたり、犯罪組織を撲滅するために資金源を攻めるのと理屈は一緒である。
手元にお金がたくさんあると、「体験を買う」「時間を買う」ことの優先順位が相対的に上がる。
二つ目の精神修行とはどういうことか。お小遣い制を受け入れる人たちの中には「家族全体の幸福度が上がるならばそれで満足」という境地に達している人がおり、自分の可処分所得が下がる分、節約するためのさまざまな工夫に喜びを見出していたりする。
幸福の主体が個人を超越して家族単位になっている。お小遣い制度はこういった人間的な成熟をもたらすのである。
さて、この二つの機能は令和の家庭生活においても大事だ。夫婦別財布を保ちつつ、どうやってこれらの機能を担保するかが令和の家族における一大テーマである。
・・・なんて、大袈裟な枕詞を書いておいて申し訳ないが、今のところ「パートナーがガミガミと繰り返し注意する」ぐらいしか有効な代替手段が思いあたらない。
そのため、保守的な人間は「おとなしくお小遣い制に従ったほうが楽」と思うかもしれない。「蓋を開けてみたら老後の蓄えがない」という最悪の展開を避けるためには、自分の意志の弱さを踏まえて防止策を講ずるのが重要だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
