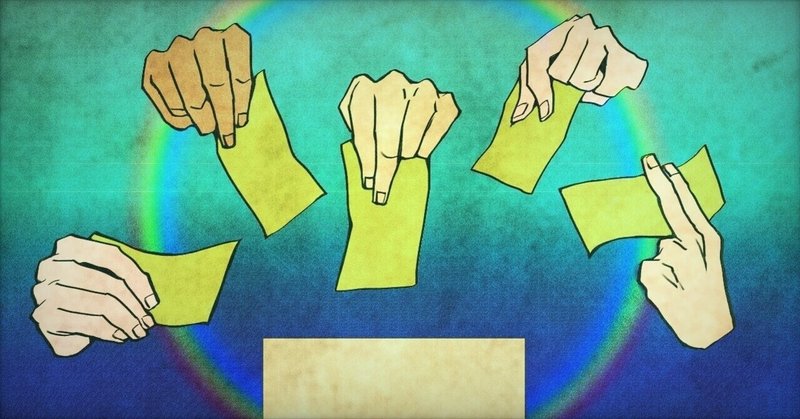
老けた高校生の民主主義考②
第二章 民主主義の現状
1.現状
近年、リベラル・デモクラシー社会は衰退しつつある。明確に民主主義が否定されている例としては、香港における民主化デモの弾圧、国家安全法の制定があげられる。香港は1997 年にイギリスから返還されてからも、一国二制度のもと高度な自治が認められ、共産党独裁政権の中国の中にありながら比較的民主的な制度で政治運営を行ってきた。近年になって、2014 年の雨傘運動など、より高度な民主化を求める運動が行われるようになっていた。2019 年、中国本土への犯罪者の引き渡しを認める「逃亡犯条例」に反対するデモが勃発し、民主化を求めるデモへと発展した。香港当局はかなり暴力的な手段で弾圧に乗り出した。活発化するデモに危機感を覚えた中国は、2020 年 5 月 28 日に、全国人民代表会議において「香港国家安全維持法」を成立させる。デモ活動に参加する人々の主張を事実上禁止すると読めるこの法律が施行されて以降、デモの参加者は 99%減少した。
また、直近の例を挙げると、民主化しつつあったミャンマーにおいて、軍事クーデターが勃発した。2020 年 11 月に行われた選挙において不正があった可能性があるとして起こされたものだ。軍は民主的選挙において大勝した、国家顧問アウンサン・スーチー氏をはじめ、NLD(国民民主連盟)の議員を軟禁し、連邦議会の開催を止め、軍政を行おうとしている。
このような明らかな民主主義の抑圧の他にも、民主主義は挑戦を受けている。近代になって民主化を果たした国では、基本的人権の尊重や報道の自由、司法の独立といった近代民主主義の基礎となる制度を破壊するような権力が、民主的に誕生するという事態が発生しているのだ。香港やミャンマーの例と違い、民主主義がその内面から崩壊しているともとらえることができ、こちらの方が深刻かもしれない。
ハンガリーは1989年に社会主義体制から脱して民主化し、チェコやラトビアなどとともに 2004 年に EU 加盟を果たすなど、新興民主主義国家の希望の星であった。しかし、2010年にフィデス(ハンガリー市民同盟)のオルバーン・ヴィクトルが二度目の首相に就任して以降、ハンガリーは権威主義的な傾向を強めていく。オルバーン政権は憲法裁判所の違憲審査権の制限や、政権の息のかかった国家メディア・報道通信庁を新設し、報道内容に介入するようになった。オルバーン首相はリベラリズムをはっきりと批判している。2014 年には民主主義は必ずしもリベラルである必要はなく、「自由な民主主義では国益を守れない」と公言した。ハンガリーはこれまでとは異なり、ナショナルなものを基礎とする「非リベラル国家」になると宣言したのだ。
ポーランドにおいても 2015 年に極右政党 Pis(法と正義)が上下院で過半数を握って以降、憲法裁判所の機能を緩和する法案が成立した。司法の人事権を政府が掌握し、司法の独立を脅かす法案が可決されたのだ。公共放送の人事を政治が握ることを可能にしようと試みたり、最終的には議会で否決されたものの、人口を増やすために妊娠中絶を禁止しようとしたりするなど、ハンガリーに似た非リベラル国家への道を歩んでいる。
これらの国の進む先には、ロシアやトルコといった権威主義国家が控えている。ロシアでは2000年から断続的に大統領を務めるプーチンが「強いロシア」の名のもとに、南オセアチアやクリミアなどの周辺諸国への介入を強化している。彼はリベラルな思想を「時代遅れ」「リベラルな価値観は消滅しつつある」と評価する。プーチン政権下のロシアでは野党幹部やジャーナリストの暗殺などが相次ぐ。
リベラルな民主的制度のもと、定期的な選挙を経ながらも、その後権威主義的な権力を誕生させた国々、すなわち民主主義と権威主義の間のグレーゾーンにある国を、競争的権威主義(政治学者レヴェツキー)と呼ぶ。このような国では、選挙は行われるものの、政府与党に不都合なことを国民に伝える報道機関への介入や、有力な野党政治家の投獄など、反対勢力の力が弱められることで、選挙は形式的なものとなり、与党の勝利が約束される。
「選挙に基づく政治」という民主主義の形式は残っているものの、その内実は個人の自由を踏みにじる権威主義なのである。
こうした競争的権威主義国家の誕生は、前章で上げた民主主義の必要条件のうち、第 2、第 4 の必要条件が脅かされている状況であるといえる。
また、民主主義が比較的実現しているような印象を持ちがちな欧米諸国においても、民主主義は危機に瀕している。一番の大きな特徴としてはラディカルな政党の台頭があげられる。ヨーロッパの大陸諸国においては、反グローバリズムと反イスラム原理主義を掲げる各国の極右政党の支持率が伸び、平均で 15%になっている。オーストリア、イタリア、スイスなどの西欧 11 か国で与党いりすらしているのである。極左政党をみてみると、こちらもイタリアやスペイン、ギリシャなどで勢いを増している。イタリアでは2018年の選挙で、極左政党と極右政党の連立政権が誕生するという事態が発生した。
ラディカルな政党の台頭は社会を分断する。異なる意見の間を取り持ち、調整をし、納得の下に結論を得るという、政治が本来担うべき役割が担われなくなる可能性が高くなる。民主主義成立の必要条件のうち第 3 の条件が脅かされている状況であるといえる。
このように、民主主義は内外から激しい挑戦を受けている。外的な要因はわかりやすいが、選挙によって選ばれた統治者による民主主義の破壊は、制度の内側に内在していた危険性が露見していると考えられ、深刻な課題である。次にこれらの問題がなぜ起こっているのかを考えていこう。
2.リベラルコンセンサスの形成と中間層の衰退
民主主義が直面する危機の 1 つとして、ラディカルな政党・政治家の台頭を上げた。この背景には「リベラル・コンセンサス」の形成があると、社会学者の吉田徹は指摘する。リベラル・デモクラシー下の二大政党の中では、経済的リベラリズム(市場経済の導入・私有財産の保障)をとり、非政治的リベラリズム(古典的な共同体の維持など)をとる保守政党と、非経済的リベラリズム(市場経済の否定、国家による再分配、社会民主主義)をとり、政治的リベラリズム(個人の解放・尊重など)をとる革新政党が、二項対立の構造を作り、お互いに拮抗してバランスを保っていた。しかし、冷戦構造の崩壊により、社会主義体制の失敗が明かになると、革新政党も市場経済の導入を認めるようになる。また価値観の多様化に伴って保守政党側もリベラルな価値観を無視できなくなり、政治的リベラリズムを認めるようになる。このように保革両党が経済的・政治的にリベラルな政策をとるようになった。これがリベラル・コンセンサスの形成だ。これに伴って今まで大きな保革両党によって内包されていた、左右双方に激しくよった人々が、既成政党によって代表されえなくなっていく。この人々がラディカルな政党を支持するようになっていくというのだ。
また吉田は、このラディカルな政党を支持する人々の多くは、第二次世界大戦後の民主主義社会が、その主流派として誕生させた中間層であると指摘する。
国家権力により抑制された経済リベラリズム=資本主義は、戦後社会の多数派として中間層を生み出した。中間層とは一般的に所得階層が中程度であり、中間階級としての意識を持ち、安定した雇用によって人生設計が可能になる階層であるとされる。また、中・高等教育を受け、専門的職業に就き、私的所有権に愛着を持ち、何らかの資産を有している層とすることも通例である。
具体的な例として当時のイギリスの状況を見てみよう。イギリスでは 1950 年代にテレビ、掃除機、洗濯機などの家電製品が爆発的に普及し、家計の消費支出が 1952 年から 64年にかけ、実質的に 45%も増えた。つまりそれだけの収入の伸びがあったということである。週当たりの平均賃金は、1950 年の 7 ポンドから、15 年間で 2.5 倍に増加した。失業率は 2%を下回り、貧困ライン以下で暮らす労働者も 3%以下と戦前(1930 年)の 10 分の 1にまで減った。この所得増を生み出したのは、戦前から持続してきた先進国の製造業であった。製造業人口は 1980 年代に頭打ちとなるまで伸び続ける。しかし、過去 40 年間で先進国の製造業の雇用者数が大きく減少している。アメリカとイギリスでは1970年と比べて半分以下、フランスでも半減している。賃金も横這いないし減少傾向にある。その一方で飲食業やマネージメント業においては、雇用者数、賃金共に増加傾向にある。比較的高度な知識や技術を必要としない製造業が衰退し、コミュニケーション能力などの文化的能力を必要とするノン・ルーティーン作業の需要が増えているのだ。この状況は「仕事の二極化」と呼ばれ、我が国日本においてもみられる傾向である。日本でも 1950 年代に農林業と製造業で労働人口比率が逆転した後、90 年代初頭には、製造業とサービス業が逆転した。
このように衰退しつつある製造業で活躍していた中間層の人々が、政治的急進主義に吸い寄せられているという事が数々の調査で明らかになっている。2016 年のアメリカ大統領選挙において、きわめてラディカルなドナルド・トランプを大統領に押し上げたのも、「ラストベルト」と呼ばれる衰退しつつある工業地帯の有権者たちだった。米ギャラップ社の調査では、トランプ氏に投票した人の割合が、非製造業者層においては 5%だったのに対し、製造業者層においては 54%であったことが明らかになっている。1970 年代~1980 年代の経済リベラリズムが生み出した高度経済成長は、高学歴で高収入の新たなエリートを生み出した。今まで社会の中の主流派であり、優位な立場にあった製造業者は、段々と経済的には下層の立場に追いやられていく。さらに、製造業の衰退は、家賃の低下や人口流出を引き起こし、非白人住人や移民を増加させる。かつて社会的マジョリティであり、勝ち組だった旧中間層の人々は、このことでもまた剥奪感を覚え、政治的・社会的急進主義へと引き寄せられていくのだ。文化人類学者アパドゥライは、この現象はその国のマジョリティが、「捕食性アイデンティティ」を持つがゆえに引き起こされると指摘する。これは自分たちがマイノリティへと転じる恐怖に怯え、台頭する他の社会的アイデンティティを抹殺することで、自分たちの社会的ステイタスを維持しようとする意識のことである。
このような要因から、旧中間層は経済的に相対的な剥奪感を感じており、「自分たちを新たなマイノリティとみなしている」と、社会学者ジャスティン・ゲストは述べている。他方で政治の世界においては、旧来の二大政党がリベラル・コンセンサスを形成しており、保守・革新ともに政治的リベラリズム的な政策を繰り広げる。政治的リベラリズムが保障する「個人」「マイノリティ」は、ほとんどの場合、女性や子供、移民や性的少数者などが主流であり、従来マジョリティの側に属してきた旧中間層の人々の置かれた状況について手を差し伸べる姿勢をあまり見せない。こうして旧中間層の人々は、経済的にも政治的にも、相対的な剥奪感を覚えるようになっていく。その結果、旧来の政党に見切りをつけた旧中間層の人々がラディカルな政党を支持していくようになっていく。これが吉田の説明である。
3.リベラリズムが内包していた課題
他方で、民主主義と一体になったリベラリズムが内包していた課題が、リベラルデモクラシー衰退の背景にあると指摘するのが、弁護士の倉持麟太郎である。詳細については彼の著書『リベラルの敵はリベラルにあり』を読んでいただく事とし、ここでは私の理解に基づいて端的に紹介したいと思う。
私たち人間の内面には、外面には表れない「本当の自分」が存在している。それはソクラテスにより、「テューモス」となづけられ、後にルターによってはっきりと価値を認められ、革命期以後の民主化運動の中で、法的にもその存在が認められるようになっていく。「本当の自分」を尊重し、「自分らしく」生きることができる社会の創造を目指したリベラル勢力は、理想の「個人像」を描き、社会設計を行った。個人の尊重の為に今まで支配的であった王権を打倒し、教会やギルドなどの中間組織を解体して個人を解放した。
しかし、ここで 1 つの問題が発生する。「個人の解放」は必ずしも「個人の幸せ」に直結しなかったのである。リベラル勢力は、「個人」は社会から支配的な規範がなくなり、選択肢が増えると、自ら多様な選択肢の中から「自分らしさ」を選択し、獲得することが可能であると考えていた。しかし、これは大きな間違いであった。リベラルが想定した「個人」像は強すぎたのだ。「生身の個人」はもっと弱い存在だった。実際に自由を得て多様な価値観の洪水の中から「自分らしさ」を発見し獲得できたのは、ごく僅かな人々だけだったのだ。想定よりも弱かった多くの人々は、多様な価値観の洪水を前にして身がすくみ、恐怖を覚えた。「アイデンティティの危機」である。それまで人々は、抑圧的な権力の支配下で生きてきた。この時代、人々は確かに抑圧されていたかもしれないが、自らで決定し、選択し、生きていく必要はなかった。敷かれたレールの上をただただ歩いていればよかったのだ。いわば自身で「自分」を発見しようとしなくても、上から「自分」を与えられ、承認されていたといえる。これを倉持は「タテの承認関係」と呼ぶ。リベラル勢力が目指した個人の解放は本来、自分が自立した意思決定を行えること自体に自尊心を持てる人間を想定していた。だが、繰り返しになるが、本当の人間はそれほど強くはなかった。リベラル勢力の隆盛により、タテの承認関係は崩壊し、さらには、地域コミュニティなどの「ヨコの承認関係」も、リベラリズムが経済的場面に侵入したことによって生まれたグローバリゼーションによって崩壊させられた。
タテとヨコの承認関係を失った個人は寄る辺を失い、新たな承認主体を求めるようになる。それを満たしたのが極めて限定的な範囲での尊厳の相互承認を行う小さなまとまりだ。特定の社会的立場への恨みや疎外感、「血」「民族」「言語」など、人間のアイデンティティを構成する一部のみを取り出し、小さなまとまりを作り出したのだ。そうして生まれたのが、リベラルデモクラシーへの脅威となるポピュリズムやナショナリズムだ。
そうした人々に「政治的なるもの」が目を付けた。個別化した彼らの承認欲求をそれぞれ満たすアピールをすることにより、彼らの票を獲得し、権力の正当性を得た。こうして政治はそのばらばらの価値観をただただ承認するアピールをする存在になってしまい、それらの間のバランスをとって 1 つの決着点を見出すという本来の役目を果たさなくなってしまった。「自分らしく生きる事」を重視した結果異なる価値観との折衝が後回しにされてしまったのだ。こうした政治を「アイデンティティの政治」と呼ぶ。
ここまでの話をまとめると、国家と個人の関係は以下のように変化してきたと考えられる。国家からの個人の解放は、いつの間にか、解放された個人の承認欲求と、その要求に呼応する政治の関係に引き戻される。承認欲求を満たすことによって票を得、権力の正当性を得たいと考える国家権力が、再び個人の承認主体となってしまった。
この経過を今度は「国家の論理の崩壊」という視点から見てみよう。
ドイツの法学者ゲオルゲ・イェリネックは、中間団体の解体と個人の解放により、「国家は個人を承認する唯一の存在」となったと説く。今まで国家と個人との間にあって、両者を仲介していた中間団体をすべて吸収した結果、国家が唯一の個人を承認できる存在になったのだ。国家は個人を承認し、同時に「国家は、人間の自由な活動を尊重し、そこには介入しないことを約束」した。更に詳細に述べると、リベラルな国家像は目に見える役割として教育、警察、交通網整備、福祉、公衆衛生などハードなインフラからソフトなインフラまで、国民生活のための社会整備を受け持つ。一方、目に見えない役割として、国民生活における、個々人の「生き方」には介入しない。我々の世界観や道徳観は、プライベートでは人を傷つけない限り自由であり、リベラルな国家の多くは、憲法典にこのルールを権利のカタログとして列挙した。そして自由な個人が形成する社会を維持するため、国家はあまたの利害調整を引き受けてきた。憲法学者の石川健治はこの「国家の論理」が成立している状態では、国家は人々が「付加なきエゴイスト」としてふるまえるようにしなくはならない、と主張する。国家はそれぞれの価値観や道徳観には立ち入ってはならず、そうしないように自己を規律しなくてはならないという共通理解が存在していた。しかし市民社会における個人の選択肢の爆発的多様化や、グローバリゼーションによる国境を越えた人・モノ・情報の移動の急加速が、従来の国家像をも溶解させる。
溶解していく国家は今まで自分自身に課していた自己拘束の一端を我々個人にも課し始める。私たちに対しても、「自己規律を持って社会を成り立たせよ、国民一人ひとりが『公徳心』と『公共性』を持って社会に関われ」と求めてきたのである。
しかし、ここに更に問題が降りかかる。国家の求める「公徳心」と「普遍性」に溢れる人間像を追い求め、必死になって頑張ったとしても、溶解しつつある国家にはもはやその頑張りを承認する能力がない。私たちがエゴイストとして自由を謳歌している間に、家族や地域コミュニティ、職場などの共同体は崩壊し、水平の承認関係もなくなっていた。リベラルな国家と個人像が目指した社会への道のりが、むしろリベラルの目指した社会像や生身の人間をずたずたにしてしまったのだ。国家の求める「意識高い系」の公徳心と普遍性に溢れた人間であろうとする努力が求められるのにも関わらず、自尊心を満たすだけの承認は与えられない。
こうして、国家が負ってきた自己拘束の分担により、非現実的なまでに高邁な存在であることを求められた個人は、拒絶し反発する。この拒絶と反発こそが「非政治の立場」そして「アイデンティティの政治」を生んだのだ、と石川は分析する。
つまり、公徳心への反発が政治への無関心を呼び起こし、普遍性への反発が広く社会に共有される価値などはさておき、他者との差異の強調や分かりやすい価値でまとまった集合体を創り出そうとするアイデンティティ・リベラリズムの形成へと発展していく。
「リベラル・コンセンサスの形成」は、主に経済的側面に焦点を当てて考察した考えであり、リベラリズムの内包していた課題は、政治思想的側面に焦点を当てて考えたものであるという事ができる。現実の社会においてはどちらかだけという事はなく、これらの要因が複合的に合わさり、民主主義の衰退をもたらしていると考えられるだろう。
続く・・・
参考文献(シリーズ共通):
『民主主義 』 文部省著作教科書 文部省 角川ソフィア文庫
『詳説 世界史 』 木村靖二 ・岸本美緒・ 小松久雄 山川出版社
『日本国憲法の論点 』 伊藤真 トランスビュー
『アフター・リベラル 』 吉田徹 講談社
『リベラルの敵はリベラルにあり』 倉持麟太郎 筑摩書房
『民主主義という不思議な仕組み 』 佐々木毅 筑摩書房
『GLOBE』 通巻 234 号 朝日新聞社
『熟議民主主義ハンドブック 』ジョン・ギャスティル他 現代人分社
『セレクト六法 』 岩波書店
『直接民主制の論点 』 山岡 規雄 国立国会図書館
『代表制民主主義と直接民主主義の間』 五野井 郁夫 社会科学ジャーナル
『日本の思想 』 丸山眞男 岩波書
内閣府「子供・若者の意識に関する調査」 2019 年実施
NHK「日本人の意識」調査 2018 年実施
言論 NPO「日本の政治・民主主義に関する世論調査」 2018 年実施
倉持麟太郎「このクソ素晴らしき世界」presented by #8bitNews #8 日本国憲法のアイデンティティ?~与野党の憲法論議に決定的に欠けているもの
倉持麟太郎「このクソ素晴らしき世界」presented by #8bitNews #6 コロナ禍における憲法の実践とは? 横大道聡(慶応大学法科大学院教授)氏と議論
スイスの直接民主主義 制作:swissinfo.ch、協力:在外スイス人協会
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
