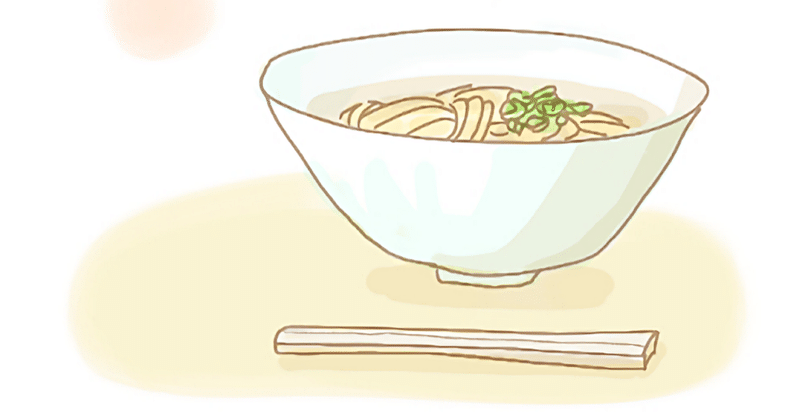
タイパの高いうどん
6月2日の日経新聞で、「丸亀製麺の「ファスト」うどん コロナ機にタイパ追求」というタイトルの記事が掲載されました。テイクアウトできるうどんが売れているという内容です。
同記事の一部を抜粋してみます。
関西で人気のお土産の和菓子といえば、「赤福」を思い浮かべる人が多いだろう。以前、赤福(三重県伊勢市)の経営者になぜ商品が誕生したのかを聞いたことがある。江戸時代、赤福発祥の地では年間数百万人がお伊勢参りに訪れていた。参拝客が殺到すると、当時の飲食店では対応に大わらわになってしまう。
そこで大量に素早くつくれるように餡(あん)を餅の中ではなく、表面に塗ったのが赤福だった。実は汁のない「伊勢うどん」も同じ理由だ。めんをゆで続け、さっと「たれ」をかけて顧客に出すだけ。必要性に迫られて発明した「ジャパニース・ファストフード」というわけだ。
そんな食の伝統を、時を超えて受け継いだのが丸亀製麺の「丸亀シェイクうどん」だ。透明カップにうどんと具材、だしがあらかじめ入り、それを振る。すると、ほどよく混ざり、そのまま食べることができる。ちなみに伊勢うどんと違い、麺のコシは強めだ。
5月16日の発売から3日間で20万食を突破し、2021年に売り出したヒット商品「丸亀うどん弁当」(発売3日間で約19万食)を上回った。「ありそうでなかった」画期的な商品として、今は3種類を販売する。
さて、アイデアはどこから生まれたのか?
丸亀製麺の山口寛社長は「新型コロナウイルス禍でドライブスルーの店を作ることを決め、車内のホルダーに置ける専用商品が欲しかった」と話す。そこで23年初めに山口社長とマーケティング担当役員、商品開発担当者らで話し合っていると、「うどんを振ってみたらどうか」という案が出て、「ドライブスルーだけでなく、全国で広げよう」と盛り上がった。
当初、社内では「そんなの売れるのか」とネガティブな意見も多かったという。しかし「マイナスの意見が多いほど、売れる」と山口社長はゴーサインを出す。新型コロナが落ち着き、店舗事業を優先する考えもあったが、今後もテイクアウト事業は不可欠と判断。シェイクうどんをその柱に位置づけた。
CMも絶妙だ。起用したのは原菜乃華さん。最近、テレビドラマへの出演が増え、映画「すずめの戸締まり」の主人公の声優も務める。世になかった商品だけに知名度抜群の女優ではなく、フレッシュさを重視した。
しかも和食のうどんなのに、CMはポップなダンスを全面的に押し出す。携帯性の良さと、すぐに食べられるタイパ(タイムパフォーマンス)感。ただし曲は米米CLUBの「Shake Hip!」だ。1980年代の音楽で、レトロ感覚も染み込ませる。伝統食は新旧の時代の価値観と共振しながら、新たな味わいを創造できるのだ。
先日、バーモントカレーをテーマに、固定観念を捨て去ることの大切さについて考えました。上記のうどんも「そんなの売れるのか」とネガティブな反応が目立った、とありますが、「これはない」「これはこうあるべきだ」といった固定観念から離れたところに、ヒット商品になるポテンシャルが見つかるかもしれないというわけです。
透明カップを振るだけでそのまま食べることができるうどんのファストフードは、これまで見たこともなく、イメージすらなかったと思います。しかしながら、うどんはラーメンやそばなど他の麺類に比べるとのびにくいという性質があります。ある程度携帯に時間をかけながら食べるような食べ方には向いていそうな気がします。イメージがなかったものが商品の形になって提案されると、「それはありかも」と思える例のひとつかもしれません。
上記記事からは、他に2つのことを考えてみました。ひとつは、タイパの広がりです。
タイパという言葉を初めて聞いたのはそれほど前ではありませんでしたが、既に社会に浸透しているようです。消費が二極化の傾向にあるという指摘を時々見かけます。自分がお金・時間をかけたい(投資したい)と思うものにはお金・時間をたくさんかけるが、そうでないものにはまったくかけないという傾向です。
車や衣服など、以前は所有するという選択肢しかなかったアイテムについても、それらに対する所有欲のない人は所有せずレンタルやシェアなどで利用するという形態が広まってきました。買ったりメンテナンスをしたりすることを含め、目的を達成するために必要な行動の時間を減らしたいというニーズは、さらに広まりそうです。
このことは、一般消費財だけではなく、法人向けビジネスでも当てはまると想定されます。労働力人口が減り、人材確保は今後さらに難しくなっていきます。タイパを高める=時間当たりの生産性を上げるというニーズは、さらに広まるはずです。タイパをテーマにした商品・サービスの提案は、今後さらに可能性が広がると考えます。
もうひとつは、独りよがりのアイデア社長にならないよう注意するということです。
経営コンサルタントの一倉定氏は、「アイデア社長は会社をつぶす」という言葉を遺しています。これは、社長がアイデアを出してはならないという意味ではないと考えます。社長が出すアイデアが結論ありきで事業を進めることの危険性を示唆しているのだと考えます。
社長は基本的に組織の中で絶対的な存在です。社長の発言は、それが根拠のない思いつきであっても、部下にとっては絶対的な命令になり得ます。社長の思いつき→経営方針として事業化→売れない→さらなる思いつき・・・と負のループが回って収益性が下がっていき、社員のモラル・モチベーションも「また思いつきをやらされる」と下がっていく可能性があります。
いかに天才的なアイデアマンの経営者であったとしても、そのアイデアに基づくマーケティングは常に当たるとは限りません。そのアイデアが事業化に適しているかの検証は、行われるべきです。
別の懸念点としては、組織が社長の出すアイデアのみに依存する体質になりかねないことです。あるいは、何か新規的な提案をしても社長の感覚と違うと否定される、なども起こると、せっかくよいアイデアを持っていたり新しいことに挑戦しようとしたりする幹部や社員がいたとしても、抑制してしまうことになりかねません。
これらは、優秀で成果を上げてきた社長であるほど、より起こりやすい事象だと思います。社長がアイデアマンであること自体はよいことですが、そのアイデアを計画化する過程でしかるべき検証をする、計画を進める担い手の社員を主体的に巻き込むなど、相応の取り組みが大切になります。
冒頭の記事では、幹部や社員と話し合う中でアイデアがまとまってきた、社内で反対意見が多く出されたなどとあり、上記の懸念には当てはまらず、(仮に失敗だったとしても)いい意味で社をあげての取り組みになる過程は経ているのではないかと見受けられます。
これは、社長だけではなく、部門長など他のリーダーでも同様に当てはまることだと言えます。独りよがりの会社をつぶすアイデアマンリーダーになっていないか。一倉氏の言葉は、振り返ってみたい示唆だと思います。
ちなみに、上記記事のCMは見たことがありますが、確かにレトロ感を感じました。CMもいろいろな工夫をしているのだなと感じます。
<まとめ>
独りよがりのアイデア社長になっていないか、振り返る。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
