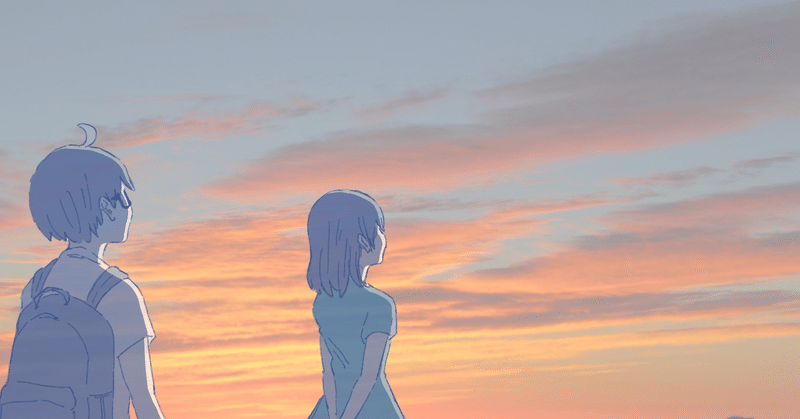
ほめのびの純正ロックに泣いた
ほめのびとは
a
ぼくはもともと歌をそんなに聴くほうじゃなくて、今まで買ったCDなりダウンロードした歌で聴ききってないのもあるし、話題だからとわざわざ新しい歌を聴いたりすることがありません。ヘッダ画像をお借りしています。
たぶんKing Gnuですら白日以外知らないだろうし、白日の入りを歌えないだろうしコーラス部分を今すぐ歌えと言われても無理かも知れない。おめがシスターズがカバーしていたMVを思い出せば歌えるかもという具合。
だけどたまに新しい歌を聴くことがある。好きなグループの新しい歌でさえ一年越しに聴くことがある。だからぼくの(もしそんなものを備えているのなら)なんらか見分けるアンテナに対して自分でもその精度を求めていない。
https://note.com/fuuke/n/n36495e49a58f
その時に何の偶然かたまたま聴いて、ああなんていい歌なんだろうと思えばその後もまた聴くだけなので、逆に精度とかはどうでもいいから心の動きにだけ従っている好例といえるのかも知れない。でもどうでもいい。
ほめのび
ほめのびがリリースされたことは知っていたけど結構前の歌です。熱心に当該歌手に対してファン性を持ったこともないけど、別に嫌いではないからこういうこともたまに起きるのでしょう。歌手が嫌いでもコンポーザが好きって場合、ぼくは多分その歌は絶対に聴けない。
で多分ランダム再生機能みたいのをプラットフォーム上で使うから、一回以上は聴いたことがある。だから心根(こころね)のどこかに一回インプットされていて、新しいものとして受け入れるためのハードルは限りなく下がっていたんじゃないだろうか。
それを別の人のチャンネルで再度聴いた。一度受け入れ体制を自己の中に構築したことがある歌を再度聴くための下地、下準備としては万全であるとさえいえる。
つまりここで再定義されたわけです。これについては後述する上に後日また話したい。
でプラットフォーム上で聴いていた時にも、なんだか普通の歌じゃないと思っていた。
改めて聴いたらイントロがものすごいロックだと思ったわけです。ロックだと思ったという前提で話しているので邦楽ロックの代表格であるスピッツを例に出しちゃうんですけど、例えばほめのびがロックって言うとそりゃ違うぜという人がいるかも知れない。
だけどスピッツにはモニャモニャという歌があって、ほめのびより全然ロックぽくないんだけど多分ロックだと思う(この文のように、ロックだと主張したい側にとっても自信がなくなるほどの静かで落ち着いた歌だ)。
モニャモニャが極端すぎるならエトランゼ……だとスピッツの中核である楽器が一切入ってなくてやりすぎかも知れないから、同じEPに入っているプチがいいだろうか。
プチもおよそロックと断じるには勇気が要る気がするんだけど、プチを構成する楽器は全部がロックの文脈できちんと機能している。
ほめのびのイントロ
ほめのびのイントロにぼくはそれと似たようなものを感じて、上記の通りもともと親しみのあるチャンネルで、唄っている本人というよりはチャンネル所有者に歌われるという形でぼくは再度聴いたんだけど、別に本人が唄ってないからいいぜってわけじゃなくて(もっとも、そういう歌も世の中には残念ながらあると思う)、その……他者の声によって再度聴いてもやっぱりものすごい印象に残った。イントロが。
コード進行がめちゃくちゃかっこいいんですよね。だからコンポーザの渡辺さん、倉内さんがすごい。
受信状況が悪くて、かすれたままラジオから聴こえてくるみたいな音飾なところも拍車をかけると思う。スピッツでまたしても例えるなら夢じゃないみたいな感じでしょうか。夢じゃないにはそんなイントロないんですけど世界観的に……イントロで言えばリコシェ号のつくりがそれだけど、リコシェはめっちゃ前向きだから例えとして控えてしまった(夢じゃないのMVがメカがもう動けないみたいな感じだから、その景色とほめのびのアウトロのねじが切れた感じとクロスオーバーしたのかもしれない)。
多分ファン目線では、本人があまり得意じゃない歌をこのように頑張ってリリースして(オリジナル一発目ということもあり)将来の礎にしたい、けどやっぱ得意じゃないから長い目で見てくださいなみたいに訴求する歌なんじゃないかと思う。ファン目線といいますかファンマーケティング的にですが……(歌はアートに属すので、「何が正解か」みたいな聴き方をしたり、「歌自体をそのように刺すのが正解である」というマーケティングに使おうとする行為自体が無為だったりするとは思う)
だけどほめのびはイントロが完璧すぎて―――完璧という言い方はちょっと陳腐であり、別にいわゆる泣きメロってわけでもないはずなんだけど――1音目のオルガンの動きから「それだけで成立しうる孤独感」がはちゃめちゃに表現されていると思えたのだった。
これはぼくが最近たまたまクラシコムという企業が提供するコンテンツを見まくっていることにも影響されているとは思っていて、クラシコムは北欧、暮らしの道具店というコンテンツで非常に素朴で、どこか孤独感があるかもしれないけど(基本的に1コンテンツ内では1個人のみ取り上げるのでそりゃそうかも知れない、脳が単純にそっちに飲まれてるだけかも知れない、単細胞なのかも知れない)、別にそのコンテンツの中で誰が一番いい暮らしだとか比べるんじゃなくてそれぞれできちんと成立している感じってことが言いたいんですね。
それがほめのびのイントロを聴いて感じた世界観だった。ほめのびとは「褒められて伸びる」の略です。だから普段は褒められていない(マイナス感情)のかも知れないと想像される。
ぼくは歌の中で恋愛が歌われてたら即聴く選択肢から外すし、何なら歌詞が重要な歌なんだったら選択肢から外すぐらい詩がどうでもいいと思っていて、歌はメロディがすべてだと捉えています。ほめのびが恋愛を唄って無くて良かった。唄ってたらこの歌を聴こうと思えなかっただろうから。
それぐらい厄介な奴でもこのイントロに惹かれた。そして歌のコンセプトにもエンゲージメントを持てたからこそ、この1音目のオルガンかアコーディオンか(現代のDTMは大体がデジタル音飾だとは思いますが)の音に対して信じられない感情移入をしてしまった。
ぼくが泣いてしまったのはイントロの最後、数え方が間違ってるかも知れないけど8小節目です。キーは採譜してないのでハ長でF G C A F G C Abの最後らへん(いま聴き返すとDm Em / C Am / Dm Em Dm Em / F G C Ab Gが近いでしょうか)。
ここでいかにも転調しますよ、みたいなコードを挟んで転調しないんですね。そこでAb使うならBb Cって続けたりDbに転調したっていいやんけと思うけど最後までそうならない。で大事なのは「別にそうなろうがなるまいが素敵(ほめのびが)」。
もはや感覚の世界なので説明するだけ意味不明かつ野暮かもしれないけど、これがなにか……ある人が一人で「暮らし(クラシコムとの共感覚)」ていて、なんかたまにヒヤッとするような(転調)気配が生活の中にはあるから、完全に一生安泰だぜみたいには到底思えないんだけど、それでも生きるだけだしな……みたいな、決して前向きなメロディ100%で創られてるわけじゃない(上述のようにマイナス感情が題名から想起されるし)のに諦観とはまた違う前向きな生命力を感じる。それが生活という言葉の意味なのだろうか、という哲学めいた考えが去来する。
褒めて欲しいって額面通り受け止めたらいわゆるアイドル業なんかにおける「応援してくれ」みたいなそれだと思うんだけど、実際ぼくはそういうのも苦手で近寄らないようにしているんだけど……この歌にはそのような感覚を抱かなかった。
たまたま一年前ぐらいに、同じMCNの大空もほめのびを聴いて泣い……てはいないけど大局的な職務の前にほめのびを聴いて自分が頑張る気になれたらしく、なにか(ぼくが「この歌聴いてこういう気持ちになっても多分いいんだろう」と)元気づけられた。
これは別にぼくの意見に後押ししてもらえる期待とかを抱いたんじゃなくて、唄ってる側が応援して欲しいのに、聴いた側が元気づけられるみたいなベクトル不明な理解が行われることに対して面白いなと思えたみたいなことだった。
だって同じMCNなんだから職性的には共感性はあちらの二人側にあるはずだし、あちらがわの共感は同色だろうけどぼくの抱いたそれとは絶対に違うはずだ。あちらがわにいる人同士だからこそ理解できた感情が歌の中にあるのかも知れない。それはこちらにはわからない。
でもさっき述べたように、歌に正解を求める行為こそが最も愚劣だし何の意味もないことだ。
純正ロック
これは願望だけど、ぼくはこのようにメロディや楽器の奏で方、さらにはそのための楽器選択すら含めて、その全てで何らかの感情を表現する芸がロックである(あってね♡)と思っています。
だから歌詞はあまり関係なくて、全部「あ」で埋め尽くされてたとて構わない。
文字から感情を得たり揺り動かされたいんなら、物語見たり俳句や短歌見ればいいんじゃないだろうか?
歌とはメロディなしにして成立しない。メロディがないラップは感情を表現するというよりは批判や主張めいたものに近いからそれはそれで成立しているんじゃないだろうか。
じゃあポップスや演歌は感情を表現できないのかよ、と聞かれてしまったら、ぼくは黙るしかないんだけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
