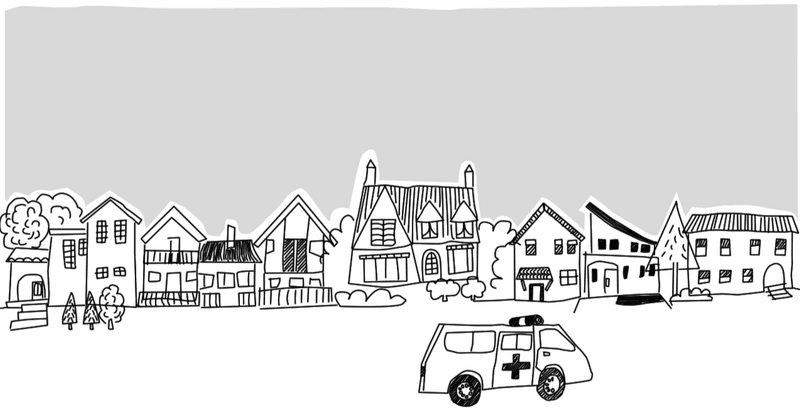
ノンフィクション小説 【マイナスをプラスに】 一日目・救急搬送
一日目・救急搬送
2023年11月4日(土)
六時五十一分。この時間が刻まれたデジタル時計の様子を今でも鮮明に覚えている。モニターに映る初めて見る機械や、それと共に鳴り響く細々とした音。右手の親指には洗濯ばさみのような何かが、左腕には昔スポーツクラブで膨らんでいくその様が面白くて遊んでいた血圧計がぎゅっと付けられている。膨らんでいく血圧計を伝い感じる自分の心拍音や、震える左腕、極めつけには明後日の方向を向き痛みを与え続けている左の膝が僕の心と体を苦しめていた。
「お兄さん、名前と電話番号言えるかな?」
痛みに耐える僕の左上から、優しそうな初老の救急隊員の声が耳に届いた。
「山下大輔(偽名)です。電話番号は……」
寒くもないのにがくがくと震えながらも、下四桁を言い終わり救急隊員の手が止まるとすかさず口を開いた。
「これ、治りますよね」
治ります。きっとそうきっぱりと答えて欲しかったのだろう。が、その救急隊員は僕の手を握ると、
「病院に行ってから先生に聞いてみよう。私じゃわからないから」
と、今思うと当然の回答が返ってきた。それでも、当時の僕は蜘蛛の糸を掴むような気持だったからか、痛みで引っ込んでいた涙が急に瞼に上がって来た。遂に救急車は大きなサイレンと赤い光を発しながら道路の上を走り出した。今まではただの街の光景と共に耳に入ってくらいの救急車のサイレンを身近で聞き、改めて今自分の置かれている状況を理解すると、ただひたすらに痛みに耐えながら数十分前に戻りたいと心からそう思った。
僕はこの三連休で、地元の名古屋市から石川県金沢市にやって来た。僕がもう十年ほど習っているカポエイラという格闘技のイベントとワークショップがこの金沢の地で開催されるとのことだったからだ。11月3日はバスが大渋滞に飲まれなんと、二時間遅れで到着したのだ。本当はその日のレッスンにも参加したかったのだが、仕方ない。僕は自分にそう言い聞かせて、4日から始まるイベントに備えようと心を切り替え、当日ある体育館に足を運んだ。
「大輔、よく来たね。昨日は大変だったねぇ」
恐らくバスの遅延のことだろう。僕は、温かく迎い入れてくれる仲間や先生たちに挨拶をしながら、イベントに向けて準備を始めていた。カポエイラはブラジル発祥の格闘技で、簡単に言うとダンスやアクロバット、その他にも楽器やポルトガル語で歌を歌ったりとあまり類を見ないような特殊な物なのだ。その日はまず子供たちのホーダ(試合のようなもの)が行われて、その後に大人のホーダが行われるというタイムスケジュールだった。子供のホーダ中に楽器を叩いていると、個々の子たちがそれぞれ自分を表現しようと楽しそうに動いているのが目に入った。始めたばかりなのか緊張している子がいる反面、その子たちをサポートしながらも自信満々に動く子供たちに心を打たれ、「はやく僕も動きたいな」と胸を高ぶらせていた。だが、事態はその後に起こった。子供のホーダが終わり辺りもすっかり暗くなってきた頃、大人のホーダまでの時間にアクロバット教室が開かれたのだ。初めは、まだ簡単な動きが続いた、体が温まってくるとバック宙の練習に入った。正直、嬉しかった。バック宙なら今までも問題なく出来ていた。だからこそ今以上に上手になる自分の姿を思い浮かべると、楽しみで仕方なくなりすぐに僕の身体は宙を浮いた。僕が先ほど『数十分ほど前に戻りたい』と言ったのはこの直前である。しかし無情にも僕の身体は一回転し、その後の着地はなぜか左足から順番に降りてしまったのだ。この先はあまり思い出したくない。一瞬で、「これはまずい」と察知し、その直後に左ひざに猛烈な痛みが走った。
「うああああああ」
僕は人目など気にしている暇もなく絶叫すると、その場でのたうち回った。何とか膝に目を移してみると、膝の関節が本来あるべきではない場所を向いてしまっていたのだ。この時に味わった恐怖を文章化する事など今の僕の力量では到底できない。強いて言うなら、十六年ほど生きてきた中で体験したことないようなレベルの違う痛みだった。そんな情けない恰好の僕を見て最初こそあまり騒ぎではなかったが、僕の様子がすぐに落ち着かない事にただ事じゃないと感じたのか、
「救急車読んで!」
と誰かが声を上げてくれた。少しすると、救急車の音が徐々に大きくなっていくのが分かった。この際も、そして救急隊員が到着して担架に乗せてくれる時も声をかけたり、手を握ってくれたりと今思っても本当に仲間には感謝でいっぱいだ。が、僕はその時感謝を言えるほど自分の心と体に余裕がなかった。それにも関わらず、ずっとそばで寄り添ってくれた仲間たちのおかげで僕は何とか近くの病院に行く事が出来たのだ。カポエイラをやっていてよかった。ケガをした直後でもそう思えるようなコミュニティに自分がいることに改めて喜びを感じていた。
そうは言えども病院に到着し、待ち構えていたのは病院の先生の
「それじゃあ痛いけど、この脱臼は戻しちゃおうか」
という、言葉だった。
「戻せるのですか?」
「今できるよ。ちょっと全身麻酔するけどいいかな?」
不安な気持ちでいっぱいの僕に先生は拒否できるはずも無い選択肢を突き付けてきたのだ。
「全身麻酔⁈」
その言葉に恐怖心を持っていた僕の口から咄嗟にそんな言葉が飛び出た。
「そう。君の太ももの筋肉が発達しすぎていて、先生の力じゃ負けそうだから」
「全身麻酔という事は、痛くないんですよね?」
助けを乞うような、眼差しで先生を見つめるも結果は無慈悲にも、
「はめる瞬間は、痛くて起きると思うよ」
というものだった。終わった。先ほどの怖ろしすぎる痛みがまた来るなんて。そう思って駄々をこねようとする頃には僕の意識は遠くなっていき、気づいたら意識が飛んでいた。なんとなく声が聞こえるなぁ。そんな風に思っていると、またもや激しい痛みによって瞑っていたはずの目が開いた。
「いたあああああああ」
そう、絶叫した記憶はあるのだが、気づいたら関節は元通りではないが先ほどまでの怖ろしい形からは大分改善されていた。
「もう五分も経ったの?」
半分寝ぼけてた僕は看護師さんに子供の様な問いかけをした。
「そうだよ」
「もう一番痛いゾーンは越えたからね。お疲れ様」
看護師さんが優しい顔で答えてくれると、さっきまで恐怖の裁判官のように見えていた先生がとても優しい人に見え、そう教えてくれた。そこからは意識があまりなかったため、レントゲンやCTを撮り、コロナとインフルエンザの検査を受け診断を待った。結果は、MRIを撮っていないため名古屋の病院で詳しく聞いてのことで、診断書には膝骸骨脱臼と書かれてあった。僕の認識では脱臼と骨折をしてしまっていた。
その後は付き添いで来てくれたカポエイラの先生が夜ごはんなどを届けてくれて、その日は入院となった。名古屋にいる母もすぐさま駆け付けてくれるようで、不安でいっぱいだった僕は申し訳ない反面、早く会いたいと考えながらベットで一夜を明かした。僕の記憶の中では救急車に乗ることも、入院することもこの日が初めてだった。そして改めて、人のやさしさや、現代の医療の偉大さを身で感じ、様々なことを学ぶ一日でもあった。
僕だって、こんな文章を書いているだけで足が痛むような気がするほど嫌な思い出だが、題名にもあるようにこの一見マイナスな出来事をマイナスでは終わらせずプラスにしたい。不便なことや不安に押しつぶされそうになっているのは決して嬉しい事ではないが、この経験をした事によって色々な人にもっと優しく出来たり、同じ境遇の人に勇気と希望を与えたりすることが出来るかもしれない。そういう思いで、これからこの怪我の治療過程を記して行こうと思う。僕にとってカポエイラは大切な生きがいの一つだ。だからこそ、少しでも早く膝を直し復帰したい。復帰してやる!そういう強い信念をもって辛抱強く治療をすることが大切であり、スポーツで怪我に苦しんでいる人たちにも諦めずに頑張ってほしいと強く思った。不可能な事など、ないのだから。
Fin
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
