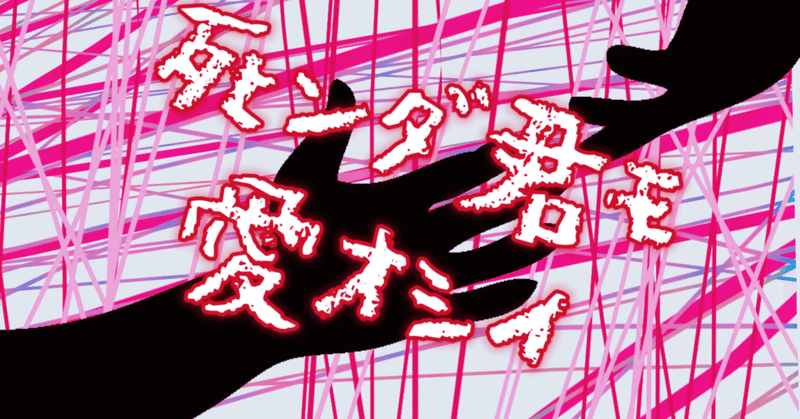
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第17話
Prev……前回のお話
「前言撤回、間に合うかな」
一矢は着替えもせず、水槽の中の金魚に向かって躊躇いがちに語りかけた。
「佐倉がなにかを隠してる気がするって言ったけど……、あれ、聞かなかったことにしてもらえるか?」
ゆらゆらと微かに揺れるだけの金魚は、一矢の話を聞いているのか、いないのか。それでも続ける。恐らく、自分のために。
「実際、隠してはいたんだ。あいつの傷を。まあ、それは知っていた。知った上で、後ろ暗い部分を怪しんだりなんかした俺は最低だと思う」
金魚は長い鰭を翻し、くるりと後ろを向く。その動きも艶やかで優雅だった。
「本当のことはわからない。わからなくてもいい気がする。これ以上、疑うのをやめようと思うのは、佐倉のためじゃない。多分、俺自身を守るため……、ふっ、何を言っても情けないな……」
そっぽを向いた金魚に、一矢は溜息を吹きかけた。
「あー、違う。疲れたんだよ。ただ、それだけだ。間違い探しもギブアップだ。もう考えたくない。アズサのことを考えるだけで胸が苦しいんだ。なのにこれ以上、関係ない人間まで――うぐッ」
突然、なにかに心臓を鷲掴みにされた。強く握られて、身体が硬直する。ぼやけた視界で自分の胸に手を当てると、誰かの腕が胸を深く抉っていた。得体の知れない恐怖に、一矢は震えあがる。
「お前……ッ」
アズサ……。
――考えるだけで胸が苦しいって? 甘えないでよね。
心臓にめり込むアズサの指。更に締め付けられて、無意識に涙が流れ、顎が震える。
――その心臓は誰のもの? 誰のために生きてるの?
「解放なんか、してあげないからね」
耳元で、たしかにアズサの声がした。柔らかい髪が頬に触れ、その顔を振り向きたいのに苦痛で身動きが取れず、胸を両手で押さえたまま無様に膝から崩れた。どくどくと胸元からなにか熱いものが溢れ出ている感触。アズサの名前を呼ぼうとしても、声が出ない。
「イチヤが悪いんだよ?」
靄の向こうで、意地悪な声が聞こえたけれど、その時には一矢の自我はどこかへ消えかけていて、ただこのまま全てを捻り潰されたい願望だけ残し、深紅の光の中に意識が途切れた。
最近、よく意識を失う。人間、こんなに倒れて大丈夫なものだろうか。落ち癖がついてしまったのかもしれない。正直、とても恐ろしかったけれど、もう少しアズサを感じていたかった。リビングの床に横になったまま、一矢は天井をぼーっと眺めて、余韻に浸っていた。あんな恐怖体験をしておきながら、余韻を味わっている自分は変態かもしれない。それは仕方ない。変態でなければ、アズサのそばにはいられなかっただろう。
しかし……なぜ突然現れたのだろう。なにを伝えたかったのか。考えるまでもない。これからもアズサを思い、苦しみ続けろと、そういうことだろう。「イチヤが悪いんだよ」と聞こえた気がしたが、いったい何の話なのか。まあ、あいつはなんでも人のせいにするから、大した意味はないかもしれない。きつく締め付けられていたせいで、今は心臓がとても軽い。バクン、バクン、と存分に跳ねている。自分の生命を感じる。でも、あのまま心臓が潰されても構わなかった。アズサの手の中で弾け飛ぶ自分を想像し、じわりと胸が熱くなる。天井に向かって、右手を伸ばしてみたら、指先の震えが止まらなかった。誰も見ていないのに、隠すように拳を握る。もう一度、アズサに会いたい。嵐の去った部屋の中は、不気味なほど静かだった。
翌日、佐倉と顔を合わせたが、意識しなくても普段通り接することができた。アズサにああは言われたが、一度吹っ切れた一矢の偏った思考は、既に停止していたのだ。ひとりで悶々と考えず、流れに身を任せて過ごしてみたら、非常に心が軽くなった。これはアズサの意図に反するので、そのうちお仕置きに現れるかもしれない。そんなことを、どこかで期待している自分もいる。やはり変態なのだろうか。
それはそうと、奈津美から悲痛な過去を引き摺っている話を聞いて、佐倉に対しての意識が変わらなかった訳ではないが、いつもの佐倉の顔を見た瞬間、余計な力は抜けて、自然体でいることができたのがありがたかった。十年以上もの付き合いだ。今更、簡単には揺らがないはずなのだ。奈津美と偶然会った話も、佐倉は既に聞いていて、週末に家に行くという予定もすんなり決まった。……ということは、勿論佐倉は一矢が事情を知ったということも、奈津美から聞いているはずだった。そのうえで、いつもと変わらないふたりの関係。事情を知っていようと知らなかろうと、隠していようと晒されようと、互いの信頼関係に大きな影響はなかったらしい。ひとつの問題をクリアしただけで、悪日続きだったトンネルも抜けたかのようだった。
金曜は朝から雨が降っていた。この程度なら電車のダイヤが乱れることもないだろうが、雨の日はいつも少しだけ早めに家を出る。一矢は傘立てに入っている四本の傘から、ちょっと作りのいいビニール傘を取り出す。簡素な傘立ての隅に、長いこと刺さったままの青い傘がちらっと視界に入ったが、思い出に耽ったりしなかった。あれから当然、アズサが現れることもなく、栞さんも金魚のままだった。それでいい。これがきっと、普通なのだ。金魚は心臓など齧らずに、パラパラの臭い餌を食んでいればいい。臭い餌は言い過ぎた。魚にとって最適な、栄養満点のご馳走を召し上がればよいのだ。
鍵を開け、ドアを押し開けた瞬間、「解放なんか、してあげないからね」というアズサの声が耳に蘇った。あいつがそう言うのなら、きっと本当に解放などしてもらえないのだろう。間違いなく、この先にあいつが待っている。平穏な日が、続くわけがないのだ。しかし、それはそれで、悪くない。
「はぁー! 急に激しくなったな」
一矢がオフィスビルに到着し、ロビーに足を踏み入れたところで、背後から声が追ってきた。傘を畳みながら振り向くと、笑顔の佐倉が前髪を少し濡らして立っている。
「おはよう、広川」
佐倉の言う通り、駅からオフィスビルまでの道中、突然雨が強くなったのだった。おまけに風も加わって、一矢のビニール傘は軽く悲鳴を上げていた。ちょっと作りのいいビニール傘だったから耐えられたものの、本格的に降る日にはやはりまともな傘を一本くらいは備えておかなければと、買ってはすぐにどこかに失くしてしまう癖を省察していたところだ。そんな一矢の隣で、佐倉はまだ少し水滴の付いた青い傘を外に向けて軽く振ると、くるくると巻き始める。見覚えのある、傘だった。よくある、シンプルな青い傘。背中にぞわぞわと小虫が這い上がる感覚がするのはなぜだろう。
「佐倉、その傘……」
「ん? これ?」
不思議そうに佐倉は持っていた青い傘を一矢に差し出す。受け取った柄の部分は少し濡れている。確認したいことがある。まさかとは思うけれど。柄の少し下の部分。そして、ネームバンド。なあ……、なぜだ、佐倉。
「これ、『バギッシュ』の限定モデルだよな」
「バギッシュ?」
「去年流行ったアニメ映画、知ってるだろ?」
「ああ。なんかあったな。それがなに?」
「この傘、『バギッシュ』の限定モデルなの、知らないのか?」
「え? そうなの? 普通に近所の店で買ったけど」
佐倉は嘘をついている様子はなく、むしろ驚いている。一矢は再び、傘に目を遣る。間違いない。限定50本の貴重な傘だった割に、模様が二か所に控えめに入っているだけの地味な傘。去年に入って三度目の誕生日、一矢がアズサにプレゼントしたものだった。
「気づかなかったけど、限定モデルだったのか」
そんなわけはない。一矢は運よく買うことができたが、限定50本を気づかないうちに買うことなんてできるわけ、ないだろう。つまり、どういうことだ?
「おい、なんでそんな怖い顔してんだよ。欲しかったならやるよ、これ。知らないで買ったやつだし、別に『バギッシュ』のファンじゃない」
「どういうことなんだよ」
「はあ? こっちがどういうことだよ。ちゃんと説明しろよ」
オフィスビルのロビーで、傘を片手に険悪な空気が漂う。まばらな人影が、遠巻きに観察している気がする。
「お前は、限定モデルだと知らずに、近所の店で普通に買ったんだな?」
「そう言っただろ」
「その傘は、最初からこの模様、入ってたか?」
「え?」
佐倉は改めて、傘の柄の部分とネームバンドを確認する。
「いや、気づかなかったけど。入ってたんじゃないの? どういうこと? なにが言いたいの、お前」
どういうことなのか。考えれば、わかる気もするが。まだ、確信は持てない。
「いや……不思議なことも、あるんだな」
「なにが?」
「理路整然とした偶然もあるって話だ」
「意味が解んねぇよ。どうした、広川」
一矢は青い傘を佐倉に手渡すが、佐倉は受け取らなかった。
「よくわかんねぇけど、お前これ欲しかったんだろ? 使い古しでよければ、やるよ」
「欲しかったわけじゃない。今はお前のなんだろ? 持って帰れ」
ええ……? と困惑した表情で、それでも周囲も気になる様子で、佐倉は躊躇いながら傘を受け取った。
「ちゃんと説明してくれよ。どうすればいいのかわからない」
「ああ、そうだよな」
異様な空気のまま、ふたり並んで、エレベーターに向かう。
「俺も、ちゃんと説明してほしい。とりあえず、少し時間をくれ」
「ん……いいけど……」
そう言いながら、エレベーターの中で自分の傘を改めて眺める佐倉。沈黙のまま、フロアを移動する機械音だけ静かに響いた。
「広川さん、ホワイトメールの件なんすけど」
PCに向かって無心で作業をしていると、背後から軽薄な声がした。仕方なく、振り向く。
「お前、ホワイトメールは柿谷に引き継いだんじゃなかったのか?」
「そのはずなんすけど、忙しいらしくってパシられてる感じっす」
「そうか。それで?」
「あー、なんかまた打ち合わせ的なのが必要っぽくって、広川さんに来てほしいらしいっす」
「誰が?」
「柿谷先輩が?」
「自分で言いに来いと伝えろ。そしてお前もパシられてないで仕事しろ」
「え? これ仕事じゃないんすか?」
「伝言ゲームのどこが仕事なんだ」
オレンジ頭を手で追い払うと、再びPCに向かう。ファイルを開いたり、閉じたりしているが、自分がなにをしているのかよくわかっていなかった。仕事しろはブーメランだが、誰にもバレていないだろう。
朝から、考えられる可能性をいくつも挙げては消していた。どれもありそうで、ありえない。傘一本で、これほど平常心を失うとは思わなかった。自分はもしかしたら、なにかわかっているのかもしれない。どうなんだ? いや、ほんとになにもわからない。頭蓋骨の中に文字や絵柄や映像や声などが充満し、それら全てが青い傘によってぐるぐると攪乱されている。酔いそうだ。吐くかもしれない。いったいなぜ、あの――
「ひ、広川さん……、すみません、さっき……」
鬱陶しい声に振り向いた瞬間、喉の奥から酸っぱいコーヒーが勢いよく上がってきて、一矢は慌てて地面に顔を向けると、開いた自分の足元に不快な胃液を噴出した。
「えっ! ええっ……すみません!」
なぜか謝っている木橋の声が頭上で聞こえるが、一矢の頭は深く項垂れたまま、荒い呼吸を繰り返すことしかできなかった。まいったな。動揺し過ぎだろ。
ばたばたと数人が動く気配がする。ほんの少し胃液を吐いただけなのに、大袈裟だ。木橋がどこから持ってきたのか、雑巾のようなもので床を掃除しようとしたので、慌ててその手首を掴んだ。
「やめろ」
「えっ」
「自分で片付ける」
すみません、と木橋はすぐに手を引っ込めた。雑巾を受け取り、反対の手で口を拭う。こんな状況なのに、木橋にだけは借りを作りたくなかった。大丈夫ですか、と数人寄ってきたが、佐倉は現れなかった。当然か。でも恐らく、遠巻きに心配そうな顔でこちらを見ていたに違いない。自分の知っている佐倉なら。
どうしようもなくコンディションが悪いので、早退することにした。静かに手早く荷物をまとめ、軽く挨拶をしてオフィスを抜ける。数日前に休んでいることもあり、同僚たちは心配そうな表情で一矢を見送った。
「気をつけて帰れよ」
佐倉の声も耳に届いていたが、片手をあげて応えただけで、顔を見ることはできなかった。家に帰ったら、確認しなければならないことがある。
雨はほとんど止んでいた。ちょっと作りのいいビニール傘を差すまでもない。今朝の雨は、何者かによる演出だったのだ。そして、今の冷静さを失った一矢をどこかから観察しているのだろう。もし、全てを知る第三者がそこにいるのなら、教えてくれないだろうか。これは、どういうことだ?
マンションのドアを乱暴に開けると、玄関の壁に寄りかかり、大きく息を吐く。どうせ、ないんだろ? 簡素な傘立ての隅に刺さった、知っているはずの青い傘をゆっくり引き抜く。柄の下の部分、ネームバンド。ほらな。
「バギッシュ」の模様はなかった。ただの青い傘だった。気づかなかったなぁ。
そこで見ているあんた。教えてくれないだろうか。これは、どういうことだ?
Next……第18話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
