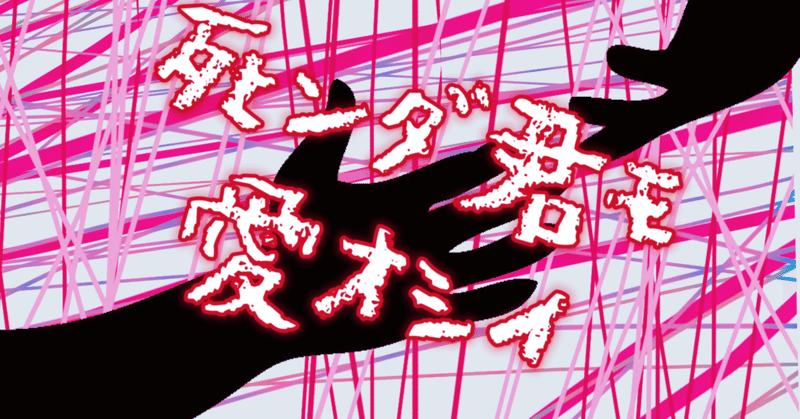
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第12話
Prev……前回のお話
井田と会社に戻ると、ちょうど打ち合わせから戻った佐倉と廊下で出会した。井田はとんでもないことをしでかしたくせに、社長の佐倉に「っす」と頭を下げただけで、さっさと自分の席へ戻っていく。まあ、こんなことを許してしまっている佐倉が悪い。これは優しさではなく、職務怠慢だ。上司はしっかり部下を指導するべきである。そこまで思ってから、いや、それは自分もか、と一矢は反省した。佐倉も一矢も中学からスポーツをやってきて、大学では一緒にバスケをやっていた。ふたりとも体育会系の世界で鍛えられてきたのに、なぜか部下に甘くなってしまう。それは、この会社を立ち上げる時に後輩たちに心底助けられたという経緯があり、もちろん井田はその後輩のひとりではなかったのだが、なんとなく部下が可愛くもあり、有難くもあり、きつく指導できない要因にもなっているかもしれない。そんな言い訳していられないか。井田はどうにかしよう、そのうち。
「お疲れ様」
「ああ、佐倉も」
オフィス入口の前の自販機で一矢が缶コーヒーを買うのを、佐倉は隣に立って待っていた。一矢も佐倉にはホワイトメール・エステートの様子を報告する義務がある。こんなところで立ち話しながら報告というのも舐めているが、一矢がレポートを纏めるようなものでもない。それは井田にやらせるとして、とりあえず無事に謝罪を終えたことだけ、伝えた。
「そうか、よかった。新規の顧客だったから、どんな様子か全然わかんなくてさ。怒られてもしかたないことだし。面倒なことを任せて悪かったな」
「いや、俺が井田にOK出したんだから当然だろ」
「それもそうか」
一矢は買ったばかりの缶コーヒーのキャップを開けた。パキッといい音が鳴る。言おうか、言うまいか。まあ、どっちでもいいけど。
「……アズサの会社だったんだ」
「え?」
「ホワイトメール・エステート。俺も今日まで気づかなかったんだけど」
「あ、ああ……そうだったのか」
佐倉は少し、声を震わせた。そんなに気を遣わなくてもいいのに。一矢も、行く前は言い知れぬ緊張を感じたが、実際に行ってみたらどうってことはなかった。勿論、色々と思うこと、感じることはそれなりにあったけれど、どうってことなかったのだ。
「大丈夫か?」
「自分でも意外なほど、大丈夫だ」
「そうか」
ボトルを上に傾け、ぐび、と一矢の喉が鳴る。コーヒーは渇きを潤してはくれない。
「梓さんはたしか、カメラの仕事をしてなかったっけ。その仕事を辞めてホワイトメールに就職したってこと?」
「いや、ホワイトメールでカメラの仕事をしてたはずだけど」
「なるほど……?」
なんとなく、ふたりして首を捻る。まあ、妙っちゃ妙なんだよな。あんな小さな不動産会社で、わざわざカメラ要員なんて雇うだろうか。うーん。でも、社長が拾った人間だから特別に仕事をあげていたと考えるとおかしくはないか。アズサは社長のお気に入りだったと言っていたしな。社長には素直に従っていたのだろうか。あのアズサが? それはなんだか気分が悪いな。
「アズサはそこの社長に拾われたらしいから結構長いこと在籍していたみたいだ」
「えっ、二十歳からずっとホワイトメールにいたのか。梓さんのカメラはホワイトメール仕込みってことなんだな。なんかちょっと変だけど」
「まあ……ちょっと変な感じはするけど……」
なんだろう。なにか引っ掛かる。カメラとは別のところ。社長? ホワイトメール?
「広川。余計なこと、考えるなよ。色々疑っても仕方ないし。気持ちはわかるけどさ……怪しい職場ではなかったんだろ?」
「いや……」
怪しいか怪しくないかで言うと怪し……くないのかな。どうだろう。なんだこのもやもやは。なにかが引っ掛かっているのに、その正体がわからない。
「とりあえず、仕事に戻ろう。よかったら今夜飲みに行かないか? 美味い焼き鳥屋を見つけたんだ」
「なあ、佐倉」
「ん?」
「お前、なんでアズサが拾われたのが二十歳だと思ったんだ?」
「え? なんのことだ?」
「さっき……『二十歳からずっとホワイトメールにいたのか』って、言ったよな? 俺はアズサの過去の話はしていないはずだが」
友達のことをこんな風に詰めるようなことはしたくない。疑うつもりはない。そもそも、なにを疑えばいいのかもわからないし。でも、佐倉はなにかを隠しているのではないか?
「おいおい、やめてくれ。特に意味はないよ。なんとなく、二十歳から社会人なのかなって思っただけ。成人っていうか……あ、今は成人って18なんだっけ?」
詰めたくないと思いつつ、蟠りが解けないのも嫌で、どうすればいいかわからない一矢は黙っていた。佐倉は大事な友人だからこそ、このままにしたくない。でも……もし、本当にただ勘違いしただけなのだとしたら? それも十分あり得るか。そして実際、アズサが働き始めたのは恐らく二十歳ではないのだ。行く当てのないアズサを社長が拾ってきたと言っていた。だとすると、勘当されて行き場のなくなった高校生の時じゃないか? どっちみち、二十歳から働くっていう勘違いは不自然だよなぁ。大卒の佐倉が、社会人になる年齢をなぜ二十歳と思うのか。高卒でも大卒でもない、半端な年齢な気がするが。本当にただの勘違い? しかし、目の前の佐倉は特に動揺している様子もない。たしかに、疑い出したらキリがないな。それだけ、謎の多い人間だったってことだ。生きているうちに、もっと謎のヴェールを剥いでおくべきだった。
「悪かった。お前がそう言うなら、そうなんだろう。思い込みってあるもんな」
「うん。わかってくれたならいいけど……」
気まずい空気に、なんとなくお互い動きづらい。いい加減、デスクに戻りたいが。
「なあ、焼き鳥は……」
「……それは今度な」
佐倉の誘いを断ったものの、実は他にも返信しなければならないお誘いがあった。一矢はオフィスに戻って自分の席に座ると、PCを立ち上げるのと同時にスマホでLINEを開いた。静流からのメッセージ。
【元気にしてる? 焼き鳥でも食べに行かない?】
こいつも焼き鳥だったか。どうしよう。一矢なら本来、迷わず断るところだ。先週会ったばかりだし、会って話すこともない。焼き鳥は悪くないが、さっき佐倉の誘いを断ったくせに静流とふたりで行くのも気が引ける。かと言って、佐倉も一緒に、と誘うつもりはなかった。今は、佐倉とはなんとなくそういう気分になれない。それはまだ佐倉のことをなにか疑っているというわけではない。一瞬でも疑ってしまったことが、後ろめたいのだ。どうしても気持ちが晴れなくて、柄にもなく誰かに会いたい気分だった。頭の中に、静流の屈託のない笑顔が浮かぶ。少し悩んでから、一矢は静流にOKのスタンプを送信した。
「あ、あの……広川さん」
声に顔を上げると、木橋美沙が半端に離れた位置から覗き込んでいた。妙な距離だな。一応、こいつなりにパーソナルスペースを侵さないように気を遣っているのだろうか。今のところ、木橋の気遣いは裏目に出ることが多いから、余計なことを考えないでいただきたい。
「以前、佐倉さんとカメラの話をしているのを聞いて……私のカメラを見ていただこうかと……」
「ええ?」
佐倉とカメラの話なんかしたことあっただろうか。ついさっきしたけれど、そのことじゃないよな? ああ、そうか。佐倉がアズサに会いたがっていた頃のことか。なんてタイムリーな。
「いや、俺はカメラに詳しくはないし、見てもなにも分からないよ」
「あ、で、でも……見るだけでも……」
木橋は両手に持った小さなデジタルカメラを差し出してくる。見せてどうするつもりだ、と思いながら、チラッと視界に入った画面に映る写真がとてもおぞましいものに見えて、慌てて目を逸らした。そうだ、こいつ、こういう奴だった。
「やめろ、変なもの見せるな」
「えっ……どこが変ですか? これ、なんですけど」
「だからやめろって」
「や、やっぱりこれ、壊れてるんですか? 広川さん」
「お前、ほんと……」
顔ごと背けているのに、木橋はぐいぐいとカメラを押し付けてくる。
「なんなんだよ、もう。勘弁してくれ」
堪らず、顔面に迫って来る小さなデジカメを片手で押し返した。
「あっ……す、すみません……。つい……」
我に返ったように、一歩引いて両手でカメラを握ったまま、木橋は肩を落として首を垂れた。なにかに取り憑かれているのだろうか。ある意味、井田と同じくらいタチが悪い。
「悪いけど、カメラに詳しいのは俺じゃないんだ。あと、変なものを持ってきて俺を脅すのをやめてほしい」
「おど……脅す?」
「あー、脅すってのは言い方が悪かったかもしれないが……とにかく、もう変なものを持って来るな」
「はぁ……。すみません……」
失礼しました、と小さく呟いてから、木橋は去っていった。その背中を見送りながら、酷い罪悪感が湧いてくる。今のはともかく、差し入れや落とし物は木橋の善意だったのに、いくらなんでも言い過ぎた。はぁぁぁ、と一矢は深い溜息とともに項垂れる。今朝は頗る調子よかったはずなのに、いつの間にかこれ以上ないくらい最悪な日になっている。
「てっきりアズサって下の名前だと思ってたよ。苗字だったのか。はじめまして、柚希さん。ずっと会いたかった」
佐倉にアズサを紹介するのは、当然ながら簡単ではなかった。アズサが一矢の友達になど、会ってくれるわけがない。そんなことはわかっていたし、一矢だって別に紹介したいわけでもなかったけれど、たまたまタイミングがよかったのと、アズサの気まぐれで、少しだけ顔を合わせる機会が訪れたのだ。それは二年前、カフェで佐倉と新しい会社についてのミーティングを兼ねた休憩をしている時に、アズサが近くにいることを知って、呼び出した。店に現れたアズサの姿を見た瞬間、佐倉は派手にトレーをひっくり返したのをよく覚えている。佐倉がそんなヘマをやらかすのは珍しい。こんな綺麗な人だとは思わなかったよ、と動揺していた。
「もしかして、梓さんてカメラの仕事をしてるの?」
仕事帰りだったのか、アズサがカメラを肩から掛けているのを見て、佐倉は尋ねた。アズサは面倒臭そうに適当な返事をしていたが、佐倉は興味を持ったようだ。いや、カメラというより、アズサに興味を持ったようだった。
「俺もカメラが趣味なんだ。色々、教えてほしいな」
そんな趣味聞いたことがなかったけれど、厭らしさは感じなかった。佐倉がアズサに対してどんな感情を抱いたか、正確にはわからないけれど、きっとあの魔性のオーラに魅了されてしまったんだと思う。奈津美がいるのに、なんてことは関係ない。アズサとどうにかなりたいとか、恋愛感情とは別に、つい目の前のものに夢中になってしまったのだと、その時は思った。本性を知ったら、そんな甘い気持ちは吹っ飛ぶだろうが、初対面だし衝撃は強かったかもしれない。だが、その後も佐倉は度々、何かにつけてアズサに会いたがった。カメラの話なんかも持ち出したりして、少し必死な佐倉に一矢は戸惑わされたりもした。実際、アズサがその気になるはずもなく、再び会うことはなかったのだけれど。
……少なくとも、一矢が知る限りでは。
仕事を早めに切り上げ、佐倉よりも先に会社を出た。あれから、ほとんど顔を合わせていない。靄がかかった気持ちと、罪悪感、気まずさ、それと少しの寂しさ。今まで佐倉とは、何回か喧嘩をしたことはあるけれど、ぶつかり合いはいつも理由や気持ちがはっきりしていて、今のような割り切れなさを感じたことはほとんどなかった。正面からぶつかることもできず、相手が考えていることもわからない。不信感とは認めたくないが、似たような感情は自分の中に芽生えてしまっているのかもしれない。なぜだろう。アズサがホワイトメールに拾われたのが二十歳だと佐倉が誤解したから? そんな根拠の無いことで揺らぐ関係ではないはずなのに。もしかして、どこかで佐倉のアズサに対する執着が引っ掛かっていたのだろうか。でも、アズサに会いたがったり、知りたがったりしたのは最初のうちだけで、いつの間にかそんな熱も冷めて、話題にすることもほとんどなくなっていた。一矢も当時のことを忘れていたくらいだ。忘れていたから、だろうか。ほんのちょっとしたきっかけで、心に靄がかかる。一刻も早く冷静になりたい。明日だって、会社で顔を合わせるのだから。
「一矢! こっちこっち!」
LINEで教えられた焼き鳥の店に入ると、奥のカウンター席で長い手をぶんぶん振っている陽気な男の姿が見えた。来てよかった。まだ席にも着く前に、一矢は心からそう思った。
Next……第13話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
