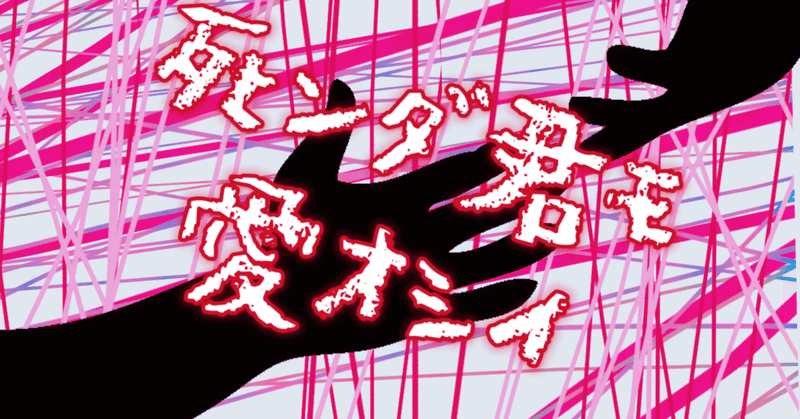
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第22話
Prev……前回のお話
「じゃあ、俺帰るけど……ほんとに大丈夫?」
「大丈夫だから」
「うーん……」
玄関まで来て、静流はまだ躊躇っていた。
「ねえ、ほんとに食べ物あるの? 俺買ってくるよ?」
「あるって。大丈夫。ありがとな」
「うーん……」
半ば追い出すように、さりげなく、強引に、ドアまで促した。
わざわざここまで来てくれたのは、とてもありがたかった。佐倉に頼まれたからとはいえ、親身になって話を聞いてくれたし、ケアは十分過ぎる程だった。でも、少しだけ、時間がほしい。間違い探しをやめようという静流の提案は魅力的に思えた。できることなら、自分だってそうしたい。穏やかな気持ちでアズサのことを思い続ける……そんなことが許されるのなら。許される? いったい誰にって話だ。アズサなのか、栞さんなのか、もしくは両方なのか。今の自分は死んだ人間と金魚に拘束されている。あまりにも馬鹿げているが、ほんとのことだから仕方ない。間違い探しをやめることも、穏やかな日常を送ることも、奴らは許してくれないのだ。でも、静流にはうまく説明できなかった。それどころか、「もしも辛いなら……」と妙な提案をされそうになった。わかってるんだ。今の状態で病院にでも行ったら、なにかしらの病名が付けられて、病人のレッテルを貼られるのだろう。病院に行かなければ、無駄に病人にさせられることもない。自分ではよくわかっているが、これはそういうアレじゃないから。静流も本気で言っているわけではないと思うが、今日はお帰りいただくことにした。このままでは話が変な方向に行きそうだ。静流とは気まずい関係になりたくない。
結局、渋々帰った静流は、15分後にまた戻ってきた。そして、玄関先でハンバーグ弁当を手渡すと、心配そうな顔をしながら今度こそ本当に去っていった。どこまでも、いい奴だ。失いたくない。ああは言ったが、実は冷蔵庫に食べ物はなかった。静流はキッチンで冷蔵庫を覗いていたし、そんなことも把握していたのだろう。正直、食欲は全くないし、このハンバーグ弁当の匂いで少々吐き気を催しているのだが、でも、まあ、うん……ゆっくりいただこうか。
考えても仕方ないけれど、静流もアズサと繋がっていたということが、未だに受け入れがたかった。あいつもまた、自分の知らないアズサを知っているということか。アズサと初めて出会った日の、墓参りの様子を想像してみる。登場人物はとりあえず三人。佐倉、静流、そして黒い服のアズサ。アズサの姿を見つけ、激昂する佐倉。恐らく、静流はやんわり宥めたりして。そしてアズサはきっと、何も言わない。一方的に佐倉にもう二度と来るなと言われ、無言で立ち去っただろう。
ここまで想像して、一矢はやれやれと首を振った。こんなにもリアルに頭の中で再現できてしまう。それだけ、人物像がはっきりしている証拠だ。まあ、そうは言っても、この妄想上のアズサは、自分の知っているアズサとは異なる。一方的に責め立てられたりしたら、馬鹿にしたように笑ったり、神経を逆撫でするような言葉を吐いたり、少なくとも、自分の前ではそうだった。でも話を聞く限り、佐倉や静流の前では、恐らく違ったのだ。佐倉の母親にさえ、目に見えた反抗はしていなかったのだろう。どっちが本当のアズサなのかなんて、どうせ考えてもわからないのだ。
しかし……。一矢は冷蔵庫から水の2Lボトルを取り出し、直接口をつけてぐびぐびと飲み下しながら考える。佐倉に二度と来るなと罵倒された後、その足で亜季の父親の個展に顔を出しているのだ。用もないのに? しかもアズサは亜季の父親とも知らず、偶然だったと言っていた。んなわけねぇよな。ぷはぁ、とボトルから口を離し、キャップをきつく締めて、冷蔵庫に戻す。その場で腕組みをして思考を巡らせる。墓参りの件を知らなかったから、アズサがあの個展に訪れたのはたまたまだと言っても否定はできなかった。でも情報を得た今なら、それが不自然だとわかる。え? そうだよな……? 今の自分の感覚にいまいち自信が持てないのだが、やはり胸糞墓参りの後にたまたま亜季の父親の個展に行きつくことはないと思う。かと言って、亜季のことを思ってあの個展を訪れたというのも、ピンとこない。墓参りは飽くまでも「お世話になった佐倉の父親」への恩義によるもので、ただ過去に告白してきたというだけの女の子の思い出のためにわざわざ足を運ぶ奴ではない。っていうことは、どういうことだ? なにかしらの、用件があったのだ。
そこまで考えて、一矢はテーブルに置いたままのスマホを取りに急いだ。間違いない。偶然な訳がない。スマホを握る手が強張る。もしかしたら、また新しいことを知るかもしれない。それは自分にとって、いいことなのか、悪いことなのか。どんな新情報も、聞いて嬉しい話なんかないように思える。しかし、知らなければいけないのだ。一矢はスマホの連絡帳を開くと、躊躇うことなく亜季の父親に電話をかけた。
RRRRR……。
……出ないか。まあ、こちらの番号は知っているし、気がついたら折り返しかかってくるだろう。自分ももう少し落ち着く必要がある。それにしても、改めて思う。初めて出会った日、歩道橋の上でアズサはどんな気持ちだったのだろう。なぜ、笑っていたのだろう。
――考えすぎて、ラビリンスに迷い込んでいるようですね。
「やっぱりラビリンスなのか、ここは。抜け出せる気がしない」
そう言いながら、周りを見回すと、リビングだったはずの景色が蔦の絡まるコンクリートの迷路に変わっていて、どこも行き止まりのように見えた。頭上を見上げるとダークパープルの空にカラスが数羽飛んでいる。まさかアホカラスではないだろうな。
「もう、うんざりだ。この先に進みたいとも、思えない。でも、それは許されないんだろ? 俺はアズサを追い続けなければならないんだろ?」
一矢は迷路の中を三歩ほど進んでみたが、ゴールまでの道を探す気力もなく、壁にもたれてしゃがみ込んだ。その一矢の視線の先に、ちらちらと姿を見せる妖美な朱色の衣。まるでかくれんぼでもしているようだが、こちらは追うつもりもない。
「間違いを見つけたところで、解放されるわけでも、終わるわけでもないのに。それなのに、この調子じゃ間違いが無限に出て来そうだ。一周回って間違いじゃなかったような気もするし。そもそも、間違いってなんだ? もうわからないよ」
蔦コンクリートの陰から顔を覗かせると、栞さんはゆらりゆらりと真っ直ぐ近づいてきた。妙な迫力がある。
――例えばですが。
一矢の顔面から15㎝ほどの距離で、ゆったりと尾鰭を振りながら語り掛けてくる金魚に、まるで脅迫でもされているかのような圧を感じる。
――私が、間違いかもしれない、とは考えませんか?
ごくり、と喉が鳴った。栞さんが間違いだと……?
「いや、間違いだろ、普通に」
一矢が言うと、金魚はコロコロと笑っているようだった。
――間違いにも色々ありますね。
今更だろ?
翌朝、気持ちも体も非常に重かったが、耐えられない程ではなかったので、予定通り会社に行くことにした。こんな状態でまともに仕事ができるか自信はあまりないが、でも会社的にもいないよりはいいだろう。そうしているうちに、気力も体力もすぐ回復するはずだ。佐倉と顔を合わせるのは気まずいけれど、いつまでも避けられるわけでもないし。余計なことを考えず、モブだと思えばいい。モブ社長。うん、いけそう。
「おはようございます」
「おはよう」
広川一矢はいつも通り、細身のジャケットに黒のパンツ、緩くセットした髪に意外と重そうな鞄を脇に抱え、そしていつも通りの缶コーヒーを片手に持って、朝九時に出勤した。アズサがこの世を去ってからひと月が経つ。デザイン事務所の同僚は未だに心配の目を向けていたが、一矢は淡々と仕事をこなしていた。(冒頭より)
「うわ、目バキバキっすけど大丈夫っすか」
「はあ?」
いつの間にか井田獅子が、脇から顔を覗き込んでいた。
「すげぇ、両目に龍でも宿らせてるんすか? かっけー」
「いい加減にしろ……。何の用だ」
そう言いながら片手で瞼の上を強く押さえ、少し揉む。バキバキだったか。
「あ、ホワイトメールの件なんすけど」
「ああ……」
「向こうの社長サンが会いたがってるらしいっす」
「誰に」
「広川さんに?」
「はあ? なんで……」
井田の顔を振り向いたが、「知らねっす」と首を傾げるだけだった。まあ、こいつに聞いてもしょうがねぇか。
「お前いつまでパシられてんだ。柿谷を寄越せ」
「あ、柿谷先輩今日休みっす」
「ええ……? 会いたがってるってなんなんだよ。いつ? とりあえず柿谷に連絡して、先方のメールをこっちに転送させろ」
「無理だと思うっすけど。柿谷先輩、今海外なんで」
「なんだよ、それ。聞いてねぇぞ」
「まあ、年上の彼女できたばっかなんで」
「どうでもいい情報を織り交ぜるな」
どうすればいい? 俺に会いたがってるって、どういうことだ。少し考えて、隣にアホ面で立っている井田に気づき、「戻れ」と手で追い払った。頭が回らない。あーもう。とりあえず、顔でも洗ってくるか。
鏡を見たら、井田の言う通り、たしかにバキバキで酷い顔をしていた。水で洗うくらいではこの顔は改善されないだろう。まあ、それでも多少の気分転換にはなる。
一矢が冷たい水で顔を洗っていると、隣に誰かが立ち、そいつも顔を洗い始めた。バシャバシャと二人分音が響き、一矢が顔を上げると、隣の男も顔を上げた。
「ああ、おつかれ……」
気まずそうに佐倉は小さな声で言うと、ペーパータオルを二枚取り、顔を拭く。一矢も同じようにペーパータオルで顔を拭った。ごわごわして肌に悪そうだった。
「あのさ、広川……」
佐倉の顔を鏡越しにチラッと見ると、珍しくだいぶ肌荒れしている。いつもつるんとした顔をしているのに……と思いかけ、ハンドクリームでテカテカした佐倉の顔を思い出した。いい気味だ。
「今日、来てくれてありがとう」
「え……?」
佐倉はこちらを向いているが、一矢は視線を合わせることはできなかった。鏡越しに、一応視界には入れておく。
「あんなことがあったから……このまま会社に来てくれなくなったらどうしようかと思ってた」
「別にお前のために来たわけじゃない」
「まあ、そうだろうけど。それでも安心したよ。ありがとう」
このまま立ち去ることもできたが、なんとなくそうはせずに、洗面台に手をついて、下を眺めていた。もう少し、どうにかした方がいいと思う。どうにかってざっくりしているが、どうできるのかわからない。ただ、ふたりの関係を諦めるには惜しい仲だ。それでもやっぱり、許せる気はしなかった。
「でも無理するなよ。来てくれて安心はしたけど、しんどかったら帰ってもいい。色々辛かったと思うし……俺が言うのもなんだけど……」
「そうはいかないらしい。ホワイトメールの社長が会いたがってるんだと」
「え? なんで?」
「知るか」
うーん……と佐倉は唸っている。
「ホワイトメールってゆず……アズサさんのいた会社だよな? それは関係してるのかな……。んー……でも、デザインのことで、っていうのもなくはないのか。今、担当は柿谷だっけ? 責任者の広川と直接話がしたいとか? あいつ何やらかしたんだ……」
「まあ、わかんねぇけど……とりあえずアポ取って行ってくるよ」
「悪いな。でも無理は――」
「無理じゃないから大丈夫だ」
自分の席に戻ると、手早くホワイトメールの連絡先を調べ、メールを送った。すぐに返信が来て、今日にでも会いたいとのことだった。急用なのか? なんにせよ、顧客の呼び出しを無下にはできない。そういうわけで、午後四時には再びHヶ谷のホワイトメールを訪れていた。今回はひとりで。用件が全く読めないが、気は抜くな。何せ、アズサの職場の人間だ。どんなトラップが待ち受けているのか予測不能だ。
「わざわざ悪かったわね。ホワイトメールの代表、茅野です」
強者特有の悠然とした笑みで一矢を迎えたのは、五十代中盤くらいの、派手な女性だった。
Next……第23話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
