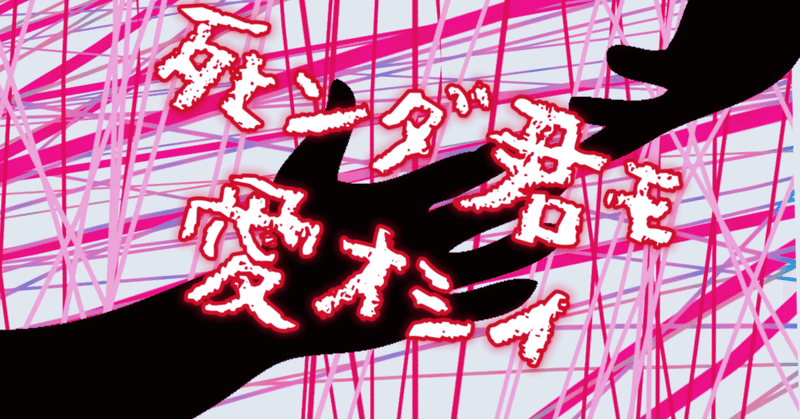
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第18話
Prev……前回のお話
右手にだらしなく青い傘をぶら下げたまま、一矢は狭い玄関の壁に寄りかかって虚空を見つめていた。ショックを受けているわけではない。何のショックなのかわからないからだ。ああ、でも何かしらの衝撃は食らっているわけだから、ショックは受けていないというのは語弊があるか。ただ、それよりも理解が追い付かずに、謎の虚無感、それと喪失感。何を失ったのかも、わからずに。
アズサにプレゼントした傘を、佐倉が持っていた。しかも、本人はそれに気づいていない。ここから、どんな状況が考えられるだろうか。できれば何も考えたくないけれど、脳内がゆっくりと、おかしな回転を続けてしまう。これは……走馬灯? 見たことのないシーンばかりだけれど。
いつまでそうしていたのか、気がついたら夜だった。いや、でも、早退した時に既に夜だったような……いや、まだ明るかったか? 曇り空だったから明るくはなかったけれど。昼前だったような気もする。どうでもいいな。そもそも、今が本当に夜なのかも怪しい。周りは暗いが、どこかの闇の中に落ちたのかもしれない。そこは永遠に続く夜暗の砂漠で、思念体が彷徨うこの世の墓場なのかもしれない。
ヴーッ、ヴーッ……。
右の臀部に馴染みのある振動を感じ、青い傘を手放してスマホを取り出す。なんだ、まだ夕方の5時前じゃないか。あっさりと夜暗の砂漠から帰還し、画面の明かりに顔を仄かに照らされながら、鈍い頭で通知を確認すると、花絵からだった。ハンカチを返したいから週末いかがですか、というような内容。ハンカチ……そんなもの、貸した覚えはないけれど。週末って……ああ、今日は金曜なのか。明日が土曜で、明後日が日曜ってことだろうか。特に予定はないから、構わないが、あまり気が進まない。なぜだろう。
ぼんやりと足元を見ると、靴の上になにかが乗っているようだった。屈んで手に持ってみると、傘……、傘か。青い傘だ。そうだった。予定がないわけがない。律儀な一矢は、花絵に返信をした。
週末は、やらなければならないことがあるので。
こんな時こそ、栞さんと話がしたい。なのに栞さんは澄んだ水槽の中で、ゆらゆらと気怠げに舞っているだけだった。
「おい、金魚。これは大きな間違いだな?」
変わらずゆらゆらと反応のない栞さんを睨む。金魚に罪はないけれど、大事な時に放置されている気がして、憎かった。
「見つけに行くよ。……お前の求める答えを」
RRRRRR……。
「もしもし? ああ、広川……大丈夫か?」
「佐倉、聞きたいことがある」
「ああ、うん……」
「明日、サークル棟の裏の階段に2時に来い」
「え、だってサークル棟は新校舎のために取り壊されただろ?」
「ああ、だからあの階段には人がいないんじゃないか?」
「なんかお前……変だぞ。何を考えている?」
「考えてもどうしようもないから、お前に直接聞きたいんだ」
少し間があってから、佐倉は呟いた。
「ああ……。そうか。お前は……なにかに気がついたんだな」
「そうらしいな」
既に明らかだったけれど、この佐倉の言葉で隠された事実の存在が確定した。しかしその内容は全く予想不可能だった。どんなものが飛び出してくるのか。流石に佐倉も覚悟を決めたようだったので、誤魔化さずに真実を語るだろう。なにを聞いても、受け止めるしかない。アズサはもういないし。どうか、誰も憎まずにいられますように。
翌日、土曜は清々しい陽気だった。ほんのり羊雲が浮かぶ空は優しく晴れていて、散歩にでも出かけたくなるような、少し枯れた香りのする乾いた空気がひんやりと気持ちよく、ああ、なんでこんな日に、青い傘を持って足取り重く、親友を詰めに行かなければならないのか。
「アホ」
馬鹿にした声が聞こえて、頭上を見上げると、ビルの手すりにカラスがいた。
「アホ」
「仕方ないだろ。こうするしかないんだ」
「アホだ、アホ」
わさわさとどこかからカラスが集まってきた。口々にアホだと罵ってくる。頭上に手をかざし、カラスから避けるように後退りしながら、反撃する。
「どうしろって言うんだよ! ほっとくわけにはいかないだろ!」
「目を背けろ、全てから! アホ! 馬鹿!」
「そんなわけにいくか!」
カラスの群れに罵倒されながら、一矢は背を向け走り出した。非常に屈辱的ではあったが、もしかしたら親切心なのかもとほんの少しだけ、思ったりもした。カラスに同情され、しかもアホだと罵られる。それでも、目を背けることはできない。これがアズサの遺した間違いならば、答えを見つけなければならないのだ。金魚のために? アズサのために? 自分のためではない気がする。できることなら、大事な親友は失いたくないから。
「あー、ここは変わんないんだな」
先に着いていた佐倉が、古く少し崩れた荒いコンクリートの階段に腰かけていた。周りの景色は大きく変わってしまったが、この階段の部分だけ、取り残されたように昔のままだった。使い道のない、余分なエリアだったのかもしれない。学生の頃、よくここに屯して、だらだらと無駄な時間を過ごしていた。空き時間や、授業をサボった時とか、誰を待つでもなく、なんとなくここに来れば誰かがいた。そんな、思い出の場所を選んだのは、恐らく帰りたかったからだ。あの頃の、なにかに。
「その青い傘……」
一矢が片手に掴んでいる傘に目を遣り、佐倉は少し苦笑した。
「俺の、傘なのか?」
一矢は黙って佐倉の足元に放り投げる。バサ、と無機質な音がして、佐倉の足の上に青い傘が横たわった。ゆっくり、佐倉は手に取って、眺めている。
「全然、気づかなかったよ」
階段に腰かけたまま、傘を手に、佐倉は目の前に立つ一矢を見上げる。意外なことに、それは冷めた瞳だった。もっと動揺していたり、もしくは悲しい目をしたり、申し訳なさそうな表情を想像していたのに、随分と冷めた瞳で一矢を見据えている。一矢の眉がぴくりと動いた。
「説明してもらおうか」
「だから……わかるだろ? 取り違えちゃったんだよ。似てたから」
「そんなことを聞いているんじゃないって、お前こそわかってるよな?」
「んー……」
すぐに吐きそうな雰囲気だったのに、佐倉は暫く沈黙した。だいぶ長い沈黙に感じる。それでも一矢は急かすことはなかった。何が語られるのか、正直、聞きたくはない。どんな内容だろうと、一矢にとって、いい話なわけがなかった。だから、じっと待つ。待ってやるから、よく考えてしっかり答えろ。
しかし、散々待たせておいて、佐倉は大きな溜息をついただけだった。
「はぁぁぁぁぁぁ……」
「おい」
質問攻めになんか、したくないから、自分の口で説明してほしい。冷めた瞳で一矢を見上げていた佐倉は今、大きく開いた足の間に項垂れて、動く気配がない。
「何回、会ったんだ」
アズサに会ったことは明確だ。それも、雨の日に。
「その様子だと、たまたま出会ってお話しただけ、なんてことはないんだろ」
一矢が攻めても、佐倉は変わらず項垂れたまま、何も言わない。
「言えないような、ことなのか? やましいことがなければ、話せるだろ! 何回か隠れて会っていても、それだけで怒ったりしない。でも違うよな? 言えない理由があるんだろ? 何とか言えよ!」
「広川さぁ」
佐倉はゆっくりと顔を上げて、再び一矢を見上げる。この目の表情は、読み取れない。
「アズサさんて、料理うまかった?」
「は? なんで急に……」
佐倉の言葉の意図が全く読めず、一矢は動揺した。そして、料理を食べたことがないということも、言いたくはなかった。
「え……? もしかして……食べたことないのか?」
「関係ないだろ」
肯定しているも同然だが、それどころではない。今までよく知った仲の佐倉が、まったく理解できない人間になっていて、もはや何の話なのかもわからない。
「は、マジか……。残念だったな。あいつは、父さん直伝のオムレツ、作れたのに」
どういうことだろう。アズサが佐倉の亡くなった父親のオムレツが作れるって? 一矢は困惑しながら、佐倉の手に握られた青い傘を眺める。この傘の話をしていたはずだ。オムレツ? 直伝っていつ……。
「ほんと、びっくりしたよ。お前の恋人を見た時は。こんなことってあるんだな。『アズサさん』に会えるの、楽しみにしてたのに……まさか柚希だったとはな!」
「お前……アズサを知ってたのか」
え? 初対面ではなかったということ? まいったな、頭が追い付かない。あらゆる覚悟をしていたはずなのに。
「マジでなんも知らないんだな。あいつらしいわ。そうやってお前のことも騙してたんだ」
「え……」
佐倉の、アズサに対する感情が、いいものではないことだけは、わかる。なぜ? あまりにも予想外の展開で、言葉が出ない。
「父さんが拾ってきたんだよ。知り合いの知り合いの……なんだか知らねぇけど、家を追い出された可哀想な子どもを、見捨てらんなくて。レストランで働かせるっていって、住み込みでさ」
そんな昔からのアズサと知り合いだったのか……。いや、まて。
「住み込みって、まさか……」
「あれ……お前知ってるんだっけ? はは、そう。母さんの愛人が柚希だ」
「何言ってんだ! 流石にそれはないだろ!」
「はあ……」
再び、佐倉は大きな溜息をわざとらしく吐き、どこかをきつく睨んで、黙った。
「母さんはもともとそういう趣味があったのか……知らないけどさ。柚希に夢中になって、色んな服をプレゼントしたり、買い物につき合わせたり。いい歳してみっともないよな」
「だからって、あいつが愛人になんかなるとは思えない」
「どうだろうな、知らねぇよ。もう、どうでもいいんだよ。だけど、母さんはあんな女じゃなかったんだ。あいつが来てから頭が狂って……。父さんだって、母さんの変化に気づいてたはずなんだ。でも、あいつを追い出さなかった。追い出すどころか、アホみたいに料理を覚えさせて。あの日だって、あいつが作った料理なんか食べたから……ふたりとも死んだんだ!」
「はあ……?」
佐倉は青い傘を階段の下に思い切り叩きつけた。こんな佐倉の顔は見たことがない。こめかみに血管を浮き上がらせ、首にも、顔面にも、眼球にも血が駆け巡っている。アズサが関係していなければ、一矢だって同情するところは勿論あった。しかし、これは話が違う。
「愛人に毒を盛られたって、そういうことか。お前、自分の両親の心中をアズサのせいにしてたんだな? あいつが自分の料理を絶対に食わせてくれなかったのは、お前のせいじゃねぇか」
「は……。自分が毒を盛った自覚があったんだろ……」
「ふざけんなよ! あいつが傷ついてた証拠じゃねぇか!」
一矢は佐倉の胸倉を掴んで、力いっぱい引き上げた。佐倉の腰が階段から浮き、首を仰け反らせて、肩で息をしている。
「そんなの……俺は……くっ……」
佐倉は自分の首を締め上げる一矢の手首を掴み、立ち上がった。
「知るか、そんなの! あいつが狂わせたんだ。お前だって毒を盛られてんじゃねぇか! なんであいつなんだよ……なんでお前の大事な人が柚希なんだよ! おかしいだろ!」
「……毒か」
呟いて、一矢は佐倉の胸元から手を離した。なんだろう、この感情は。やり場のない熱。本当に、自分はアズサのなにも知らなかった。なぜ生きているうちに、知ってやることができなかったんだろう。勝手に、理解の及ばない特別な生き物に仕立て上げてしまっていたんだ。
「それで……そんな憎い相手と、なんでお前は会っていたんだ?」
「会うつもりなんかなかったんだよ……」
佐倉は柔らかい茶色い髪を、ガシガシと掻き毟る。
「五年前だったか……墓参りに来てたあいつと出会して、二度と来るなと言った。それでもう、俺も忘れるつもりだったんだ」
五年前、墓参り、佐倉の両親の命日を考えると、一矢に初めて会った時のアズサが黒い服を着ていた理由がやっとわかった。あの時の眩しそうに目を細めたアズサの笑顔。泣き出しそうな顔にも見えた。でもあいつの表情はいつも複雑だったから、どんなことを考えているかなんて読み取れなくて、泣いているようにも、バカにしているようにも、蔑んでいるようにも、愛でているようにも見えて、表情豊かな奴だったのに、本当の顔は見えなかった。あの時、アズサは何を考えて、何を感じていたのだろう。
「まさか……お前の恋人として現れるなんて、思わないだろ……」
それはまあ、そうだろうけど。足元に転がる青い傘。アズサにこれをプレゼントしたのは、去年の10月。その後、数回使って、いつの間にか傘立てに放置されるようになった。きっとアズサは気がついたのだ。傘を取り違えたことに。そうなると、ふたりが会ったのは随分前になりそうだが……それが最後とは限らない。
「なあ」
ありえないよな。こんなこと、一瞬も考えたこともなかったけれど。思いつきもしなかったけれど。
「あいつが死んだのは、お前のせいなのか……?」
Next……第19話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
