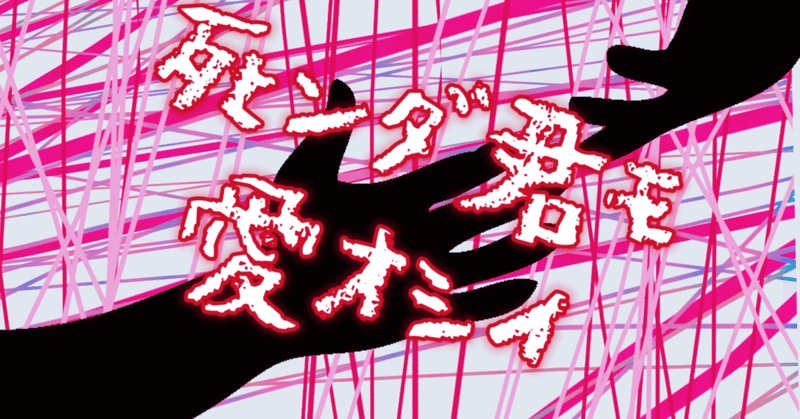
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第13話
Prev……前回のお話
大原静流イチオシの焼き鳥屋「鳥連荘」は、会社のひとつ隣の駅にある、大きな提灯が目印の綺麗な店だった。ダークブラウンを基調とした和モダンな内装で、カウンター席もゆったりしている。
「元気だった?」
「先週会ったばっかだろ。元気じゃなかったら、こんなとこに来ない」
「そうかなぁ」
静流が首を傾げてこちらを見ている。実際、自分でも「元気じゃなかったくせに」と内心思った。しかし、そんなことはこいつにわかるまい。誤魔化せる自信もある。今日は気分転換さえ、できたらいいのだ。
適当に串の盛り合わせやサラダ、納豆オムレツなどを選び、一矢がレバーを注文に加えた。
「お前は?」
「俺はいいや。レバーはちょっと苦手」
「こんな美味いものを」
ご注文承りました、と頭を下げて去っていく女性の店員がどことなく木橋に似ている気がして、少し気分が落ち込んだ。会社のこと、特に今日の出来事は忘れたい。井田から始まり、佐倉、木橋……悪夢三連荘だ。まあ、その中で考えると木橋の件はマシな方か。
「そうだ、これ」
静流はそう言いながら鞄を漁ると、12、3センチほどの小さなチューブを取り出した。
「あげる」
「なんだこれ?」
受け取りながら、手渡された銀色のチューブを眺める。
「ロクシタンのハンドクリーム」
「なんでそんなものを。俺には必要ないよ」
一矢は静流の意図がまったく理解できず、戸惑いながら返上しようとした。女じゃあるまいし、手荒れなど気にならない。そもそも、ハンドクリームなんて塗る男がいるのか? 自分が塗る姿を想像すると、酷く滑稽に思えた。
「これね、すごくいい匂いがするんだ。すべすべになって触ると気持ちいいし」
「いやいや、だから要らないって」
「落ち着くんだよ。心が」
ああ、そういうこと? と、一矢は動きを止めた。なるほど、ハンドクリームにそんな効力があったとは。考えたこともなかった。じっと手のひらの上のチューブを見つめると、どことなく薬のようにも見える。
「これが、俺に必要だと思うのか?」
「誰にでも必要だと思うよ。俺も時々使うしね」
「ふーん、そうか……」
ありがとう、と呟いて、受け取ることにした。納得したわけでもなかったが、静流の優しさにどこか安心する。理由もわからず泣きたくなったが、理由がわからなかったので我慢した。たしかに、今の自分にはこのチューブが必要かもな。
ふたりの前にビールのジョッキが置かれ、たこわさの小鉢が添えられた。軽く乾杯をして、喉を鳴らして飲み下す。なぜビールのひと口目は競い合うようにぐびぐびと飲むのだろうか。無論ひと口目が一番美味いと言われる所為もあるだろうが、こういったところで大胆にいけないと格好がつかない気がする。そんなことを思うのは自分だけだろうか。半分になったジョッキを眺め、一矢はアズサのことを思った。アズサもぐびぐびやる奴だった。どこかでアズサには負けたくない気持ちがあり、意識してぐびぐびやっていたような気もする。
「ふっ」
「どうかした?」
「いや……ビールが美味いな」
そうだね、と静流は微笑んだ。
「一矢、ちゃんと寝れてる?」
「なんだ突然」
「こないだ疲れが取れないって言ってたから」
「そんなこと言ったか?」
思い返してみると、そんなニュアンスのことを言ったような気がしなくもない。だとしても、独り言レベルの、些細な呟きだったはずで、聞き流してくれてよかったのに。
「ああ、言ったかもな。でも昨日は信じられないくらい寝た。土曜に寝落ちして、目が覚めたら今朝だったんだ。信じられるか?」
「えええ……」
露骨に心配そうな目でこちらを見ている静流に、一矢は慌てて付け足した。
「じゅうぶん寝溜めして、今朝は驚く程すっきりしてたよ」
「うーん……寝溜めかぁ……。丸々一日以上、目が覚めなかったってこと?」
「そうだな、一日半くらいか」
「そんなぁ……」
困惑している静流を見て、思わず笑ってしまう。だよなぁ、普通信じられないよな。いいネタができたかもしれない。くすくす笑いながら、一矢はビールのジョッキを傾けた。
串の盛り合わせが出てきた頃には、ふたりとも二杯目を注文していた。ペースが速い。前回の様子から、静流もかなり酒が強そうだが、まだ月曜だということを忘れてはならない。ほんと、月曜から飲むなんてどうかしている。誘われてつい、乗ってしまったが、本来の一矢ならありえないことだった。数年ぶりの友に会うわけでもないのに、なぜ週末まで待たなかったのか。明日の仕事を控えた酒なんて、制限をかけられているようで存分に楽しめない。そういえば佐倉は酒が強いわけでもないのに曜日関係なく飲む男で、その親友の静流なら同類でもおかしくはない。こいつらは月曜から頭が開放されているのだろうか。
「佐倉とは……よく会うのか?」
「うん、二週に一回くらいで会ってるよ。特に用があるわけでもないんだけど、なにかと会う機会があるんだよね」
「ふーん」
ふと、佐倉の言葉を思い出した。一緒に暮らしていた時期があったと言っていたから、想像以上に親しい関係だったのだろう。信頼関係が築けた同居人。築けなかった同居人もいたようだったな。
「あいつ……母親の愛人って奴と同居してたのか?」
「愛人?」
母親の愛人の話を奈津美から聞いた。当然静流も知っていると思ったが、言わない方がよかっただろうか。
「ああ、うん、そうだなぁ……俺は愛人ではなかったと思うけど。知宏から見たら、そう見えるとこもあったのかもね」
「そうか……」
愛人ではない人間が愛人に見えたり、そいつが毒を盛ったのだと思い込んだり、自分の知らない佐倉の闇が今頃になって浮かび上がる。十年以上の付き合いだから、なんでも知っているつもりになっていた。
「あいつも、苦しんでいるんだな」
「大事な人を突然亡くすって、そういうことなんだよ。惨ければ惨いほど、刺さったナイフは深く、抜けない」
そうだよな、と呟きつつ、静流がこちらを見る目に気づいて、自分のこともそう捉えられているのだと感じた。どうだろう。抜けないナイフ。少し前なら、完全に否定していたはずだが、今はよくわからない。仮に刺さっていたとして、それを抜きたいとは思っていないけれど。
運ばれてきたレバーは、思った以上に丸々としていて、ボリューミーな一品だった。この歯ごたえが苦手だという人も多いらしいが、柔らかさの中にある微かな食感が風味の奥深さを増進させている。
「その……最近は金魚さんと話したり、してる?」
レバーのまろやかな苦みを味わいながら、静流の言葉の意味を考えたが、なにを聞きたいのか見当がつかなかった。
「まあ、毎日ではないけど」
「遺書だっけ。アズサさんの……」
「うん、まだ意味はわからないが、とりあえず間違い探しのゲームをしてる」
「間違い探しって、どういう……?」
静流はなにかが気になるようだ。もしかしたら、これが本題なのだろうか。
「多分、アズサの遺した間違いがいくつかあるんだ。それを見つけて、答えを出すのが栞さんのゲーム」
「栞さん?」
「あ、金魚」
「ああ……」
なにかを言いたいのか、聞きたいのか、静流の態度が煮え切らない。慎重に、熟考しているようだった。
「はい、お客様」
突然、背後からハンディーターミナルを持った若い男性店員に声を掛けられ、飛び上がりそうになる。注文を促す視線で見上げてくるが、覚えがない。
「え、いや、呼んでません」
「あっ、失礼しました!」
慌てて去っていく店員の姿を目で追いながら、なんだったのだろうと静流と少し笑う。水を差され、何の話をしていたか忘れてしまった。一矢は手元に残った最後のレバーに齧り付いた。
「その間違いってさ、どんな間違いがあったのか、教えてもらうことってできるかな」
ああ、そうだ、栞さんの話だった。呑気な一矢とは温度差があるほど真剣な顔でこちらを見ている。なにが気になるのだろう。
「別にいいけど……なんで?」
「んー……ちょっと、気になって」
困った顔で笑う静流。世話焼きの性なのか、カウンセラーの癖なのか。どちらにしても、一矢のことを心配しているのは間違いない。
「こういう、『間違い』みたいなものを追求していくとさ、最終的に自分の所に行きがちっていうか。余計なお世話かもとは思うんだけどね、ちょっと心配で。あ、友達としてね」
なるほど……と一矢は唸った。友達としてとは言っているが、カウンセラー的な思考なのだろう。
「そんなこと、考えもしなかった。たしかに、なくはない話だな。まあ、でも……間違いが自分に行き着いても、俺は大丈夫だよ」
「うん、一矢は大丈夫だと思うよ。ただ、せっかく話してもらえたからさ、間違いについて、ちょっと教えてほしいなって思ったんだ」
静流の話し方はとても優しい。これは職業柄というより、こいつの性格なのだと思う。
「わかった。間違いを見つけたら、報告する」
「ありがとう」
三杯目のハイボールを飲みながら、一矢は頭の中で整理をしながら話した。
「今までに見つけた間違いはひとつ。それはアズサに出会う前のことなんだけど――」
一矢の話を静流は黙って、時々頷きながら聞いている。こんな話を他人にするつもりは全くなかったが、相手が静流なら悪い気はしない。
「なるほど……。ひとつ目は、一矢が誤解していたアズサさんの過去ってことなんだね。そういう間違い探しだとすると、最終的には誰も知らない、なにかの真実に辿り着くような気もする。それが金魚……栞さんの意図ってことなのかな」
「ゲームの意図か。多分、そういうことなんだろう。それが栞さんの意思なのか、アズサの意思だったのか、よくわからないけど」
「うーん……金魚の意思かぁ」
静流が気掛かりな様子で頭を抱えているから、なぜだか重い空気が漂ってしまう。そんなに心配するようなことではないのに。
帰り際、ひと駅分だけ同じ電車に乗って、他愛もない話をしていた。昼飯を買いに行った弁当屋のおばちゃんの話、そのおばちゃんに似ている親戚の叔父さんの話。先程までとは打って変わって、面白おかしい静流のトークに一矢も時々笑う。でも、もうすぐ自分が降りる駅に着くという時に、静流は真剣な眼差しで声を潜めた。
「一矢、あのね。助けが必要な時は、すぐに呼んでほしい。絶対に力になるから」
「ありがたいけど……」
相手が静流でなければ大丈夫だからと即座に断るところだが、彼の誠実な人柄を理解しているからこそ、気持ちは受け取りたい。
「でも、なんでそこまで? 出会ったばっかなのに」
「知宏の大事な友達だから。もちろん、今は俺の友達でもあるけどね」
「ああ、そうか……」
静流は柔らかく微笑むと、じゃあね、と言って電車を降りた。閉まるドアの向こうで、軽く手を振る。佐倉のことで、もやもやしていた気持ちはだいぶ晴れていた。それは自分の中で有耶無耶のまま誤魔化しただけではあるが、不審なものは見えないフリをしたかった。少なくとも、静流に頼むほど自分のことを気にかけてくれているのは事実なのだ。
それにしても、なぜそんなに心配するのだろう。静流の言っていた「助けが必要な時」がどんな時なのか、想像もできない。もしかして、まだ様子がおかしいなどと思われているのだろうか。
電車に乗っているうちに、雨が降ってきた。一矢は折り畳み傘を持ち歩かない主義で、朝から晴れていた今日は、勿論傘なんて持っていない。この時期に冷たい雨に当たるのは避けたいが、家までの数分のために傘を買うのも気が進まない。厄日っていうのは、こういう日のことを言うのだろうか。
人がまばらな駅のホームに降り立ち、階段まで向かう途中、目の前に腹がばっくりと開かれた男が立っていた。まるで理科室の標本のようだ。「ふは、ふはは」という誰かの笑い声が聞こえる。こういう感じの映像を、ホラー映画で見たことがある気がする。呆然と立ち尽くす一矢の前で、その男の腹から腸がずるずると零れだし、それに引き摺られて肝臓らしきものもどろりと垂れ下がった。ふっ、ふふはは。男は自らの手で、なにかを探すかのように引き裂かれた腹の中を漁る。みちょ、ぬちょ。露出狂? 助けを求めるってこういう時だろうか。いや、駅員を呼ぶ? 警察……、救急車も。この場合、誰がピンチなんだ? どうしよう、声が出ない。頭が冷たくなってきた。意外と自分はホラーが苦手だったらしい。あと、レバーもしばらくは無理かもしれない。
「ふは、ふは、はは」
どさり、と自分が倒れる音が、意識の遥か遠くで響いた。
Next……第14話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
