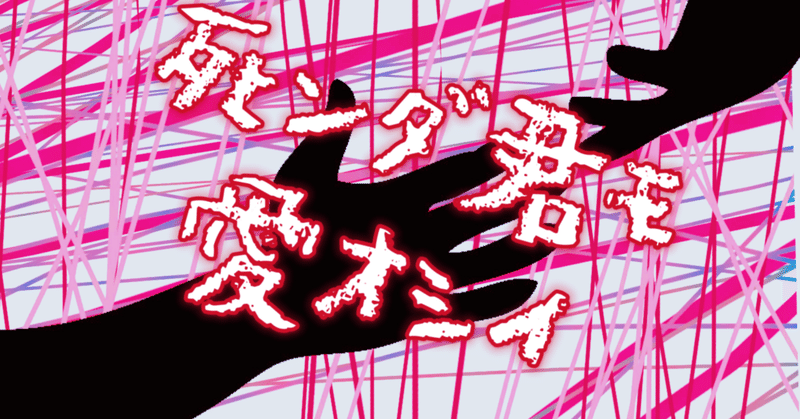
【小説】死ンダ君モ愛オシイ 第20話
Prev……前回のお話
はっ、はぁ、はあ、はあ、はぁぁ、はあぁ……。畜生、この階段はどこまで続いているんだ。赤いペンキで足が滑り、大きくバランスを崩した。もう力が入らない足が、今にも縺れて転がり落ちそうなのに、立ち止まることもできず、只管階段を上り続ける。
どうやって帰ってきたのか覚えていないが、この階段は自宅マンションのものだと思う。だから早く、一刻も早く、い、家……おうちに帰りたいのに! もういつからこの階段を上り続けているのかわからない。上層部から赤いペンキがドロドロと流れてくる。いつまで、こんな……。おうちに帰りたい。アズサが待っている。料理を作って待っていたり……それは流石にありえないか。でも伝えたい。たとえ毒が盛られていたとしたって、喜んで食ってやるのに。もしそれがアズサに狂う毒だというのなら、俺はとっくに侵されている。ほら……見えるだろう! だから安心して、アズサ。はやく。ここに! 帰るんだ、今帰る……すぐ帰るから。はっ、はあ、はぁ、はぁあ、はあぁ……アズサ。
あれは……。
ふと見上げると階段の踊り場に見える華奢な後ろ姿。間違えるはずがない。
「アズサ!」
慌てて駆け上がろうとして、足が縺れて階段に手をつくと、赤いペンキがドロリと一矢の右手を飲み込んだ。生温かく、厭らしく纏わりついてゾッとする。すぐに右手を引き抜き、体勢を立て直してアズサ目掛けて階段を上る。アズサは振り向くと、一矢を見下ろして冷たく微笑んだ。
「アズサ!」
手を伸ばしたら届きそうなのに、ドロドロの赤黒い血溜まりに足を引き込まれて階段を上ることすら阻まれる。そんな一矢を黙って見下ろしたまま、アズサは動かない。藻掻けば藻掻くほど、じわじわと血の海に飲み込まれていく。むせ返るような血の香りに頭が痺れてきた。待って、アズサ。今、そっちに……ああ、いい香り。金属とレバーをとろとろに煮込んだような、纏わりつく刺激的な温もりの中に居心地の良さを感じ、このまま血の海に沈みたいと思ってしまう。そんな一矢にアズサは小さく笑って、踵を返して去っていく。アズサ、ごめん。もう無理かもしれない。全身を甘噛みされているように気持ちよくって、嘘みたいに力が入らない。さっきまで酷使していた両足の感覚が遠くなっている。この中に溶けてしまいたい。アズサ。アズサ? アズサ! ダメだ。助けて。行かなきゃ。待って……帰りたい。心臓が痛いんだ。すごく気持ちいい。もっときつく……。そしたらこのまま……あれ? えっと……。どこかに……。アズサ?
「アホ」
はぁ、はあ、はぁぁ……。
「アホだ、アホ! 目を覚ませ!」
「は……はぁぁ?」
朱殷の泉に沈む一矢の頭上に、カラスの群れが騒ぎ出した。
「アホ! 目を覚ますんだ! 馬鹿! ゴミ!」
「帰ってこい! アホ! 馬鹿! ネズミ!」
「そのまま逃げろ! アホ! ネズミ! シャー芯!」
「シャー芯!」
「シャー芯!」
「シャー芯!」
シャー芯……? 少しだけ、齧ったことがある気がする。
……ポキッ。
ここは。
見慣れた我が家の狭い玄関。空気が冷たくて、肌がピリピリする。ああ。おうちに帰ってきた。なぜ真っ暗なんだろう。今って、えっと、何時……あれ、なにしてたんだっけ。そうだ、アズサ。オムレツ。シャー芯。
「ただいま」
オカエリ。
ドアの向こう、薄明かりの中に揺らめく、人の気配を感じる。
「アズサ!」
勢いよくドアを開けると、見覚えのある落ち武者が振り向いた。
「あ……どうも」
一矢が言うと、落ち武者はペコリと頭を下げる。アズサじゃなかった。そうだ、アズサは死んだんだっけ。なんで家に帰ればアズサがいると思ったんだろう。足元をのそのそと大きなハリネズミが横切っていく。一矢はハリネズミの邪魔にならないように、一歩引いて、大きく深呼吸をした。よかった。日常に帰ってきた。さっきまで、少し頭が混乱していた気がする。
――おかえりなさい、イチヤさん。
声を振り向くと、眩しい光の中カーテンが大きく翻り、宙を揺蕩う輝く金魚が姿を現した。
「栞さん……」
なんだかとても懐かしい。この存在を忘れていた。あれ……涙が溢れてくる。なぜだろう。安心したから? 友達とケンカして、涙を我慢して家に帰ったらお母さんが優しく迎えてくれた時のような、意味のわからない涙が止まらない。
「栞さん……」
気がついたら子供のように泣きじゃくっていた。前にもこんなことがあった気がする。原因も理由もわからないけれど、本能的に泣いている。きっと、排泄と大して変わらない。ただの生理現象だ。
――間違いをひとつ、見つけたようですね。
「間違い……。えっと……そう、そうだ」
一矢は慌てて袖の二の腕の部分で涙を拭い、呼吸を整えた。あまり生々しい現実と向き合いたくはないけれど……。
――貴方が見つけた間違いと、その答え。
そう、見つけてしまった。少し記憶を遡れば、ぼんやりと、組み敷かれて顔を歪ませる佐倉の姿を思い出す。パクパクと動くあいつの口から零れた言葉を拾う作業。
じわりじわりと、記憶が蘇ってきた。不快な熱いものが腹の底から迫り上がる。ああ。思い出したくなかった。これからどうすればいいのだろう。今更こんなことを知って、できることも残されていないのに。
「間違いを見つけてほしかったのは、アズサなのか? それとも栞さん……?」
――これは、ただのゲームですよ。
「ゲーム……。それにしたって……」
趣味の悪いゲームだ。アズサの意思なのかどうかは、結構重要なことに思える。結局一矢は、アズサのことを全く知らなかったということを痛いほど思い知ったが、アズサは一矢に、自分のことを知ってほしいと思っていたのだろうか。段々、乱高下していた頭が落ち着いてきた。
「なあ、待てよ」
立ち上がり、服を払って去ろうとしていた一矢に、顔をテカらせた佐倉が仰向けになったまま縋るように声を掛けてきた。聞く気はなかったが、なんだか体が怠くて一矢は足を止めた。
「俺、何度もあいつにお前と別れろって迫ったんだよ」
「は?」
力なく足元の佐倉を見下ろすが、佐倉は佐倉で、力なく宙を見ていた。
「お前と一緒にいたら広川が死ぬかもしれないって、脅迫まがいのこともした。広川を殺すなって……。あいつは答えなかったけど、お前と別れる気配もなかっただろ。あいつ……なんにも執着しなさそうな奴だったけど……お前のことは大事だったんだな」
気がつけば、少し冷たい風が吹いていた。早く帰ろう。
「佐倉」
「ん……?」
「お前、ほんと最低だな」
今更知ったところでどうにもならないことばかり。こんな間違いを集めて、いったい何の意味があるのだろう。
「解放なんか、してあげないからね」
アズサの声が脳に蘇る。ああ、そうか。そういうこと? 苦しむ俺が見たいって? なら、しょうがないか。でもアズサ、苦しんだところでどうしようもないって、俺は気づいてしまっているから、お前を最後まで喜ばせることはできないかもしれない。苦しませ続けたいなら、心臓を掴んだ手を緩めるなよ。
どうしようもなく疲れている。このまま眠ってしまおう。人の気配を感じたまま眠りたいから、みんながいるこのリビングで。ソファにゆっくり横になったら、電池が切れたように一瞬で落ちていった。
ピンポーン。ピンポン、ピンポーン!
なんだか酷い悪夢をみていた気がするのに、誰かが強引に現実の世界に呼び起こそうとしている。まだこの夢をみていたいんだ。邪魔しないでくれ。
ピンポーン! ダンダンダン!
おいおい、ドアを叩くな。乱暴だなぁ。朝から非常識な奴。一体どこのどいつだ。仕方なく目を開けると、まだ薄暗い。こんな早朝に? 近所迷惑だろ!
ピンポーン! ダンダンダン!
一矢はどかどかと音を立てて玄関に向かうと、魚眼レンズを確認もせずに思い切りドアを押し開けた。誰かがぶつかる鈍い音と、「いてッ」という声が聞こえる。
「一矢! 大丈夫?」
ドアの向こうの非常識な人間は、静流だった。
「え、なんでお前……」
「ちょっと入るよ。いいよね?」
強引に部屋に入ってくる静流を、流されるまま迎え入れてしまう。寝ぼけた頭はこの状況についていけない。遠慮なく部屋の中に進む静流の後を追うと、突然静流が振り向いた。
「一矢、靴脱がなきゃ」
「え」
たしかに、靴は脱がなきゃいけないな。だが、ここは俺の家なのに今来たばっかのお前に指図される覚えは――。
「ほら、ここ、肩に掴まって。足上げて、そう」
気づけば靴を脱がされている。
「ねえ、昨日からずっと靴履いたまま過ごしてたの? 部屋の中、泥が落ちてる」
「そう……だったかもしれないな……」
なんでだろう。全然気がつかなかった。
「ちょっと掃除するよ? 雑巾どこ?」
「え……そこ、洗濯機の下……っていうかお前何しに来たんだよ。俺の家、なんで……」
そう言いながら、なにかがチカッと頭の中で光った。まさかとは思うけれど。
「あ、これね、雑巾。洗面所借りるよ?」
「ああ、うん……」
「寒くない? エアコンは?」
「えっと……」
「ほら、上着も着っぱなし? エアコンつけて、それ脱ごう? あ、ちょっとそこどいて。今拭くから」
「あ、はい……」
ええ……? お母さん? 戸惑う一矢の横で、静流はせっせと床を拭きながら、荒れた部屋を整えていく。
「なんでこんな早朝に……」
「一矢、もうすぐ夜になるよ」
「え、そうなのか……」
なんだか気まずくて一矢は俯いた。こんな姿、他人に見られたくなかったなぁ。
「……なんか聞いたのか?」
住所もしらない静流が押しかけてくるなんて、それ以外にない。
「うん……知宏に……一矢のこと、頼まれた」
一矢を振り向きもせず、背を向けて床を拭きながら静流は答えた。
「でも、頼まれたから来たわけじゃないよ。話を聞いたら、俺も一矢のことが心配になって」
そう言うと、雑巾を片手にゆっくりと立ち上がり、溜息をつきながら一矢を振り向く。
「ごめんね、俺も話を聞いてたのに。まさか一矢の大事なアズサさんが、柚希のことだとは気がつかなかった」
「お前もアズサのこと、知ってたのか……」
衝撃に眩暈がする。知らなかったのは、自分だけなのか。
「いや、そうじゃなくて。当時の柚希のことは、俺も知ってるけど、その後のことはなにも……。待って、ゆっくり話そう。あ、エアコンのリモコンこれ?」
そう言いながら、ピッとエアコンをつけると、雑巾を濯ぎに去っていった。完全に静流のペースだ。
なんだか自分が酷く滑稽に思えてきた。見えないところで、みんな繋がっている。俺のアズサと。ああ、そうか。たしかに静流は「愛人」について言及したことがあった。あの時、静流はアズサの姿を思い浮かべていたのか。なんだこれ。笑えてくる。よくできてるなぁ。
「あ、これ。もう冷めちゃってるかもしれないけど。あったかいココア、落ち着くから」
静流はテーブルに置かれたビニール袋からホットのペットボトルをふたつ取り出して、片方一矢に差し出した。ココアなんて、何年ぶりだろう。受け取ると、まだちゃんと温かくて、じわりと手のひらから癒されるようだった。
「ごめんね、なにも知らなくて」
「いや……」
むしろ、知ってたんだろ? 俺の知らないアズサを。ソファの隣に腰かけた静流は一矢の顔をじっと見て、まるで心を読んでいるようだった。気まずくて視線を逸らす。
「俺が知っていることと、知らなかったことを、説明するね。その後で、一矢の話を聞きたい」
話すことなど、ないけれど。カウンセリングのつもりなら、やめてほしい。こんな状況、惨めになるから。
アズサ、どこかで見てるのか? お前が説明してくれよ。お前の話が聞きたかったのに。
お前はそんなに、甘くないか。
Next……第21話はこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
