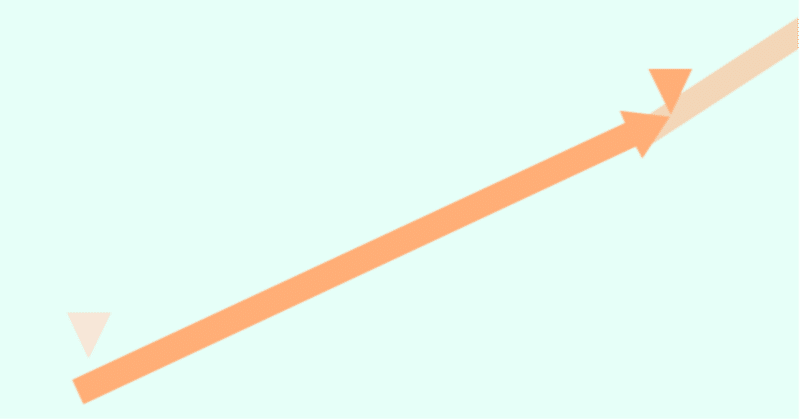
完全自動運転の電気トレーラースマートハウス 【1000文字小説 #002】
コンパートメントの入り口に足をかけたとたん、音が鳴った。僕のデバイスの何かの通知音と同じだったものだから、自分の体をまさぐった。
「重量オーバーよ」と彼女。
なんでも、彼女の車両は、彼女の体重と、家財道具の重さを厳密に計算して、走行時のバッテリーがもつように最適化されているそうな。もうすでに、積載量がぎりぎりであるらしい。自分以外の誰かがコンパートメントに乗り込むことを、とうに期待しなくなっていたなんて。
その日は、僕の体重分の本を一時的に外に出して、彼女のハウスでの時間を過ごした。
しばらくは僕が訪問するたびに、本を外に出すという作業をせねばならなかった。
僕は提案した。読まない本を、僕のとこに置いておくのはどう? と。彼女は簡単には承諾してくれなかった。今の僕たちのどっちつかずの関係が、それなりに居心地いいのだ。ことによると、本一冊分の価値は、僕1人に匹敵、あるいは凌駕すると思っている節もある。
僕は作戦を変え、三冊借りて二冊返す、を繰り返し、彼女のハウスの重量をそれとなく削っていくことにした。幸いなことに、彼女の蔵書にはいわゆる〝鈍器本〟が多く、計算では二、三十冊持ち出せば良いはずだった。
しかし、さすがは完全自動運転の電気トレーラースマートハウスで生活している偏屈者だけある。僕が持ち出して軽くなったのを幸いと、こっそり本を買い足しているようなのだ。
僕は痺れをきらし、どうしてもと言って、「失われた時を求めて」全巻を無理やり借り受けた。
「やあ、腰がいっちゃいそうだ!」
超重量級の全巻セットを持ち上げて、僕は高らかに言った。とうとう彼女のトレーラーハウスから、僕の体重をそっくり抜き取ることに成功したのだ。
僕は家に用意した彼女文庫のスペースにそれを収めた。1人分の重さのかたまりを達成感とともに眺めた。
「今日はどこにいるの?」僕は送った。
郊外の激安大型スーパーまで出てきているという。嫌な予感がした。
思ったとおりだ。スーパーから出てきた彼女は、小学生くらいの大きさがある、育ててるところも調理されてるところも見たことがない、巨大キャベツを抱えていた。一度買ってみたかったらしい。
「やあ、腰がいっちゃいそうだわ!」
彼女はこれまた小学生みたいに笑った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
