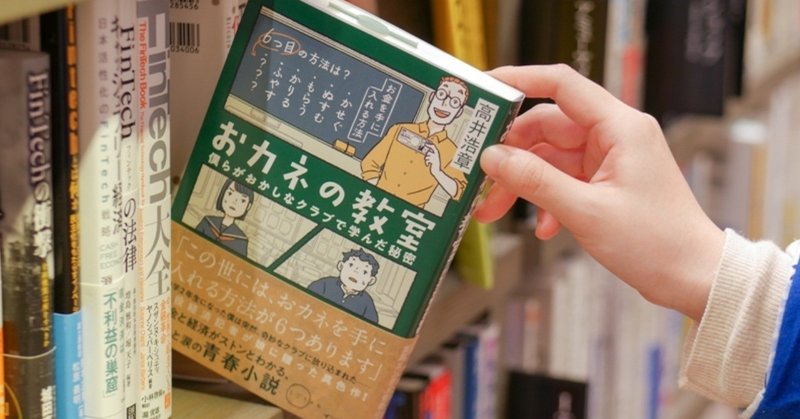
乱読家のための読書リスト
私にはめったやたらと人に本を薦めるという悪癖がある。
これなんかはその悪癖の発露なのだが、おかげさまで未だにコンスタントに読まれる大ヒットとなった。ビュー、1万2000超えてます。
今日からツイッターで、こんなネタアンケートをやっている。
#note 公式のオススメ認定のおかげで、フォロワー急増してホクホクの高井さん、調子に乗って久々のネタアンケート!
— 高井浩章@おカネの教室 (@hiro_takai) May 16, 2019
読みたいテーマをお選びください。私は全部書きたいので、どれでも良いです(笑)
ここでも、隙あらば本を薦めたいという魂胆が見えみえだ。
明日5月18日いっぱいが期限なので、気が向いたら清き1票を。ついでにフォローもお願いします!
ここまで前置きです。
今、何気なくPCのファイルを整理していたら、過去に書店のイベントなんかで頼まれて書いたおススメ本の寸評を発掘してしまった。
今、ざっと見て、自分で何冊か再読したくなっている。
再利用&ジャンルもごちゃごちゃの乱読リストではありますが、ここにシェアします。一部は「理系本」とかぶってますが、そこはご愛敬。
まずはhontoのブックツリーのブックキュレーターとして、若者向けの選書として寄稿したもの。元サイトはこちらです。
世界の面白さに通じる「窓」を探す
世界は、人間は、人生は、面白い。学校の授業が退屈なのは文部科学省と先生の責任で、君のせいじゃない。何の役に立つかわからない数学や「この21世紀になぜ」と思う古典文学にも夢中になれる奥深さがある。現国がつまらなくても「読まなきゃ人生損」という小説は実在する。無味乾燥な現代社会だって本当は面白い。読書はその「窓」を開く。
1.脳を鍛えるには運動しかない!
忘れがちだが、脳はタンパク質でできた臓器だ。臓器としての脳と、運動の深い関係をさまざまな角度から解説する。学習力アップだけじゃなく、ストレスや心の病への対処法まで一生モノのノウハウが満載。まずは「脳力」を上げて、心身ともに世界を楽しむ準備体操をしよう。
2. 放浪の天才数学者エルデシュ
数学者の伝記は、数学の奥深さと「美」を味わえる傑作・秀作が多い。家も財産も持たず、わずかな着替えをスーツケースに詰め込んで世界を旅して史上最多の共同論文を残した伝説的な数学者エルデシュの足跡を追う本書もその1つ。強烈な変人ぶりと表裏一体の高潔さが胸を打つ。
3.これで古典がよくわかる
このタイトルは正直、正確ではない。「これを読んでから古典を読め」と改題したい。白状すると、私は学生時代、古典が大嫌いだった。「あのころ、この本に出会えていたら」と本気で思う。「なぜ古典を学ぶのか」「どう学べば良いのか」という二大疑問に、天才・橋本治が鮮やかに答える。
(追記:橋本治さんが亡くなる前に寄稿しました。ご冥福をお祈りします)
4. 獣の奏者
あなたが「小説は読まない人」なら、とにかく第一巻の半分まで読んでみてほしい。ほぼ確実に最終巻まで一気読みさせられて、あなたは「小説を読む人」に変わり、次に読む小説を探すだろう。これは「指輪物語」「ハリーポッター」に匹敵する世界的な傑作ファンタジーだ。
5.おカネの教室
お金や経済のことは、ややこしそうで、面倒くさそうで、大人でも敬遠しがちだ。でも、基礎を知らないまま社会に出るのは、ルールもわからずにギャンブルに参加するようなもので、危険極まりない。しかも、実は、経済は面白いのだ。青春小説好きの方も、是非ご一読を。
と、自著の宣伝をさりげなく(?)こなしたところで、次は「おカネの教室」の発刊記念に、京都の丸善さんで展開してもらった選書イベントの際に用意した短評をご紹介。
丸善さんでは店内で「おカネの教室 LIVE」もやらせてもらい、90分間、質問に次ぐ質問にアドリブで答えまくる、大変楽しい時間を過ごした。
またやりたいなぁ、ああいうやつ。誰か、呼んでください(笑)
ということで、以下、選書コメントです。
反脆弱性(ナシーム・ニコラス・タレブ)
地震で倒れる木造家屋が「脆弱」。揺れに耐えるビルが「頑健」。では、「反脆弱」とは?何百年、数々の大地震に耐えた五重の塔のようなしなやかさこそ、最善の生存戦略だと哲人タレブは説く。自分の人生にどう反脆弱性を取り入れるか。リスクを他人に押し付ける既得権者に寄生されない生き方とは。知的刺激に満ちた個人主義賛歌。
「ビットコイン」のからくり(吉本佳生/西田宗千佳)
革命かバブルか。最近の仮想通貨関連の議論では、相場の急騰・急落の影響か、偏ったポジショントークも目立つ。こちらは2014年とブーム前の刊行なのがミソ。2人の著者の分担が奏功して、金融・貨幣論からマイニングの仕組みまでバランス良くカバーしている。困ったら、Wikipediaより、Blue Backs。
囚人のジレンマ
人類史上屈指の天才フォン・ノイマンの生涯を縦糸に彼が創始したゲーム理論のエッセンスをたどる読み物。四半世紀前の本だが、理論の本質を学ぶテキストとしては申し分ない。アインシュタインやゲーデルがいたプリンストンで「人間ではない」とまで言われたフォン・ノイマンの変態的天才ぶりのエピソードの数々だけでも楽しい。
うしろめたさの人類学(松村圭一郎)
この春(注 2018年)、2年のロンドン駐在から戻り、いまだに日本の社会の在り様に違和感が消えない。システムとしての強固さの副産物である息苦しさは「外」から見ると異常だ。エチオピアでのフィールドワークをベースに、硬直な社会を解体・再構築する触媒として「うしろめたさ」という人間の本性を提示する視点がユニーク。
すべては1979年から始まった(クリスチャン・カリル)
切り口一発で面白さ確定という本の典型例。鄧小平、サッチャー、ホメイニ、ヨハネパウロ2世の4人を既存概念への「反逆者」だったと位置づけ、彼らが1979年に始めた「市場」と「宗教」の復権が冷戦終結につながり、21世紀の形を決めたと説く。こういう腕力と筆力をもった書き手の厚みが欧米ジャーナリズムの底力だ。
マネーの進化史(ニーアル・ファーガソン)
賢人J・K・ガルブレイスは、バブルとその崩壊という愚行が繰り返される理由の1つに「金融の記憶が極めて短い」を挙げる。それなら、歴史に学ぶに如くはない。メディチ家まで遡る銀行・紙幣・クレジット市場の歴史を豊富なエピソードでひもとく。豊富な写真・図版の手触り感で、人間の顔が見える通史になっている。
海から見た世界史(シリル・P. クタンセ)
制海権を握り、交易で富を集積する。エーゲ文明以降の地中海世界から現代中国の「真珠の首飾り」戦略まで、この帝国形成の定石をたどる。地政学と経済の密接な結び付きと国家の発展・衰退について、大局的な歴史観を学び取れる。オールカラーの地図・図版が秀逸で、情報量が極めて多い。何度も見返したくなる本だ。
投資で一番大切な20の教え
これから株式投資を始めるつもりなら、一度は目を通して損はない本。運用会社の創業者である著者が、長年培った投資哲学を共有している。「20の教え」はどれも基本中の基本だが、それをくどいほど何度も徹底して説く本書のスタイルそのものが、これらの基本を貫くことの有効性への著者の確信を物語る。
ヒルビリーエレジー(J.D.ヴァンス)
トランプ大統領誕生の母胎となった白人貧困層の実相を描いた作品として知られるが、純粋に読み物として無類の面白さがある。特に「粗にして野だが卑ではない」を地で行く著者の祖母の存在感が強烈。バイオレンス要素多めのアメリカ版「佐賀のがばいばあちゃん」。リリカルな文体を滑らかな日本語に移植した訳文も秀逸。
ナニワ金融道(青木雄二)
癖のありすぎる絵柄で大量の「食わず嫌い」を生んでいるのは想像に難くないが、二十歳を過ぎたら全日本人に通読を義務付けたいほどの名作。多彩なキャラが織りなす群像劇は文句なしに面白い。お金と人間の恐ろしさ、残酷さという負の側面だけでなく、随所ににじむ人情味やある種の諦念が深みのある読み味につながっている。
以上でございます。
以下、本の推薦的な投稿とマガジンをまとめておいておきます。
良い本との出会いの一助になりましたら幸いです。
=========
ご愛読ありがとうございます。
ツイッターやってます。投稿すると必ずツイートでお知らせします。
たまにネタアンケートもやります。こちらからぜひフォローを。
無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。
