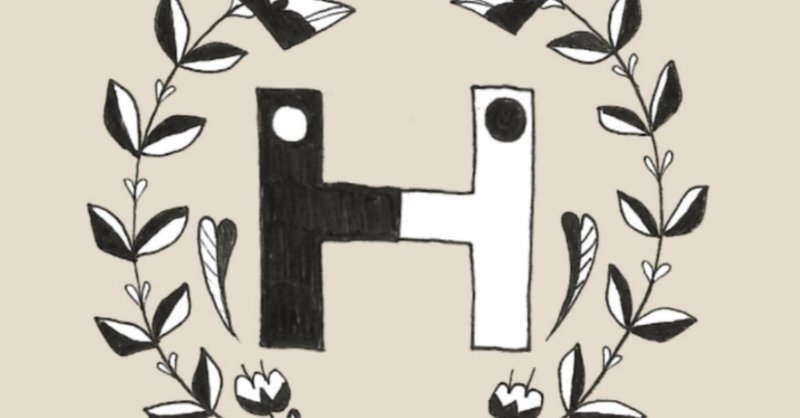
全文公開 童話「ポドモド」
Kindleストアで発売中の童話「ポドモド」を全文公開します。
お話を父・高井浩章、表紙・イラストを次女が担当した親子合作童話です。元は2000年生まれの長女が低学年だったころに家庭内連載したファンタジーで、「おカネの教室」同様、我が家で三姉妹が楽しんでいた読み物でした。2017年夏にKindle版を出す際、中学生だった次女がイラストを追加してくれました。
以下、Amazonの紹介文を抜粋します。
気がついたら僕は、見知らぬ池のほとりにいた。記憶をなくした、名無しの迷子として---。
不思議な世界に降り立った少年は、自分の名前を求めて旅に出る。
仲間になった動物たちと旅を続けるうち、少年は思いがけない運命に巻き込まれていく。
そして、「ポドモド」という謎の言葉の秘密が明かされるとき、少年の身と世界に何かが起きる。
肩の凝らない読み物です。息抜きにどうぞ。

1 出会いの池
誰かにまぶたをつつかれて、僕は目をさました。
黒いかげが顔におおいかぶさっている。
「わっ!」
声をあげると、足元にさっとカラスがとびすさった。こいつがツンツンしてたんだな。
寝ぼけまなこであたりを見回す。
(ここ、どこ?)
目の前には小さな池がある。
まわりは白い、小さな石ばかり転がっていて、草一本はえていない。
池はぐるりと森にかこまれている。
僕とカラスのほかは、カエルもいなけりゃ人間もいない。
「ここ、どこだろ?」今度は声に出してみた。カラスにきいたって、しょうがないけど。
「モノをたずねるまえに、こんにちは、くらい言ったらどうだい」
とびあがるほど驚いた。口がきけるカラスなんて、お目にかかったことなかったから。
「えーっと。あの、こ、こんにちは」
「カア、カア、カア。おう、こんちは」
人にあいさつしろと言うわりに、ずいぶんえらそうだな。
「えー。それで、ここはどこかな?」
「そんなことより、お前さんこそ、どこの誰だい? ここらにゃ、ヒトはこないはずだぜ」
カラスにきかれてみて、僕はここがどこかだけじゃなくて、自分がだれかもわかんなくなっていることに気がついた。
落ち着け、僕。
困ったらまず深呼吸するんだって、いつもお父さんが言うもんな。
僕はいっぱい転がっている白い石をひとつかみひろった。
僕は川原や公園の石を集めるのが好きなのだ。
すべすべした石をさわっていると不思議と心が落ち着く。ドキドキしそうな運動会や発表会のときには、いつもお気に入りをポケットにしのばせておくことにしている。
石はどれもすべすべで、ビー玉みたいにまん丸だった。こんな石、見たことがない。
落ち着くはずが、かえってドキドキしてしまった。三つほど、さっとポケットにしまった。
「あの。なんか、僕、じぶんの名前がわかんなくなってるみたい。だから、どこの誰だか、答えられないんだけど」
カラスはパタパタはばたいて、ちょっと飛びはねた。
「ほっ! こいつはおかしいや。名前がないってんなら、おまえさんは誰でもないってことになるぜ。そいつは、やっかいだ」
よくわからないけど、なんだか困った気持ちになってきた。
「うーん。どうしたらいいかな?」
「決まってるじゃねえか。探すのさ。何かをなくしたら、よく探すもんだぜ」
たしかに。しっかりしたカラスがいるものだ。僕はほとほと感心した。
「うん、そうする。でも、僕、ここらのこと、ぜんぜん知らないんだ。きみ、よかったら、いっしょにさがしてくれないかな」
カラスは目をむいて、大きな声で食ってかかってきた。
「おい、そんな頼み方があるかい! そういうときはまず、相手に忙しくないかをきいて、きちんとアタマをさげてお願いするのが筋ってもんだぜ!」
いやはや、カラスに説教されてばかりだ。
僕はちょっと考えてから、こう切り出した。
「では、お願いごとのまえに、まずお名前をうかがえますか」
ていねいな物言いが良かったのか、カラスはすこぶるご機嫌なようすで答えた。
「オレ様はカピー。カピー様でも、カピー様様でも、すきに呼んでいいぜ」
僕は、またちょっと考えてから、答えた。
「サマ、とか、サマサマ、とか、どうかなあ。長たらしいし、よそよそしいよ。友だちなら、カピー、だけの方がすっきりするよ。それか、カッピ、とかさ」
最後のひと言が余計だった。
「カッピだと? それはオレ様のオヤジの名前だ! だいたい、いつ、オレ様がお前と友だちだなんて、ややこしいもんになったんだ!」
バタバタと僕のあたまのまわりを飛び回りながら、キーキーと高い声でまくしたてる。
「もうカピー様様じゃないと、ゆるさないぞ!」
やれやれ。
「わかった、わかった。では、カピーサマサマ。お時間がございましたら、僕と一緒になくなった名前を探してもらえませんか」
すると、足元にすっと舞い下りて、カピーがふんぞりかえっていった。
「うむ。いまは、たまたま、やることがない。そこまで言うなら、ひとつ、オレ様が骨折りしてやってもいい」

僕は池のふちまで歩いていった。水はおそろしくすんでいて、かなり深いところまで光がとどいていた。底はみえない。
手ですくってみると、水はひんやりと冷たかった。森にかこまれて、あまり日が差さないからだろうか。
僕はそのまま、口をつけて水をすすってみた。ぜんぜんいやなにおいはなくて、甘みがある。いくらでも飲めそうだ。
「カア、カア、カア。カア、カア、カア」
カピーは池のまわりを忙しそうに飛びまわっている。その方が考えがまとまるんだろう。
僕も鼻を指でこすると、いい考えが浮かんだりする。くせっていうのは、人それぞれだ。
しばらくして、カピーが僕の足元に下りてきた。そして、池の向こうの森を指差した(というのは変か。羽根指した?)
「まず、トーポに会いに行こう。やつは日がな一日、森のなかを見張っているんだ。お前の名前をみかけなかったか聞いてやろう」
言い終わると、さっさと池を越えて飛んでいってしまった。
「おーい、待ってよ。僕は飛べないんだから」
あわてて池を回りこんで追いかけようとしたとたん、ふいに池から声が聞こえた。
「やつには気をつけな」
びっくりして声がした方をみると、池のふちにカエルがちょこんとすわっていた。
こんどはしゃべるカエルですか。けっこうおじいさんのカエルかな。
「どうして? 何に気をつけろっていうの?」
カエルはため息をついた。
「おまえ、アイツの何を知ってる? この先の森のことだって、何も知らないだろう? なのに、ひょこひょこついていくとは…」
そしてひと言、小声でつけたした。
「それに、アイツ、カピーなんて名前じゃないぜ」
言い終わると、ぴょんと池に飛びこんだ。
しばらくまってみたけど、カエルはもう姿をみせなかった。
ふう。
しゃべるカラスってだけで驚いてるのに、そのうえ名前がうそかも、なんて。
(でも…)
僕は右の人差し指で鼻の横をすりすりしながら考えた。
(カピーでもクプーでもぺポーでも一緒だよな。だって、リンゴとかカボチャとかなら意味があるけど、カピーなんて、音だけだもん)
ポケットに手を突っこんで石をさわってみる。
「うん。自分でカピーだっていうなら、それでいいんだよ」
ひとりごちていると、ひときわ大きな声がした。
「おーい! いつまで待たせる気だ!」
考えごとで時をわすれるのは、僕のとくいわざだ。それは決して悪いことじゃないって、お父さんは言う。
「いまいくから!」
僕はかけ足で森に向かった。
「おまたせ、カピー。じゃなくて、カピーサマサマ」
ようやく少し先の木に止まっていたカピーに追いついた。
「ここらにゃヒトはあまりいないから、こんなにノロマな生き物だとは知らなかったぜ」
ずいぶん、いらいらしている。
「ノロマなうえに、いちいち、サマサマ、サマサマいってると、日が暮れちまう。もう、カピー、だけで許してやる」
僕はにっこり笑ってうなずいた。
「ねえ、僕、ちょっといい考えが浮かんだんだ」
「ふん。ためしに聞いてやろう」
「僕、もう、自分で勝手に新しい名前を決めちゃえばいいんじゃないかな」
カピーが僕の目をのぞき込むように見た。僕はだまって見つめ返した。
「たとえば、ポドモド、みたいにか?」
「え? 何それ」
カピーは、もっと心の深いところまで見透かそうとするように、僕の目をじっと見つめた。
僕はしばらく我慢していたけど、ついに吹き出してしまった。
「カピー、いくら何でも、そんな変な名前は嫌だよ。ごめんごめん、ただの思いつきだから。トーポさんのところに急ごうか」
カピーはもう一度だけじっと僕の目をみてから、スッと飛び立った。
2 トーポのすみか
カピーは枝から枝へ、どんどん森の奥に入っていく。僕はその少しあとをかけ足で追いかける。
森の木々の高さは二階建ての家ぐらいある。一本一本がみっしりと葉をしげらせている。花や果物をつけている木は見当たらない。日の光はまばらで、あたりは薄暗く、ひんやりしていた。
カピーは僕の通り道なんてお構いなしに飛んでいく。僕はぼうぼうに伸びた草やしげみをよけて、あっちこっちジグザグに走るはめになる。
「カピー、カピー、ちょっと待ってよ。もうちょっと、歩きやすい道はないの?」
カピーは手ごろな枝にとまってふりむくと、すっと目を細めて、くちばしをしゃくって先を示した。
「もうつく。トーポの木が見えるだろう」
すこし先のひらけた場所に太い幹の大木がみえた。
「ずいぶん、りっぱな木だね。トーポって、えらい人?」
カピーはふんっ、と鼻をならした。
「はっ! ヒトなわけがねえ。年寄りのふくろうだ」
カピーは僕をにらんで、こう釘をさした。
「いいか。トーポの前ではいい子にするんだ。いらない口はきくな。聞かれたことだけこたえるんだ。それとオレ様の名前を呼ぶな。いいか、忘れるなよ」
僕はキョトンとしてたずねた。
「どうして? なにかつごうが悪いの?」
「いいから、言うとおりにしな!」
カピーは顔をしかめてどなると、パタパタと飛んで、クスノキの大木のうろのなかに入っていった。
(名前を呼ぶなって、やっぱりカピーってのは、うそなのかな)
クスノキのうろのなかは意外と広かった。立って歩き回るわけにはいかないが、狭苦しいってわけでもない。
「トーポさん、いつも見回りお疲れ様です」
こんどはカピーの口ぶりがばかにていねいなのに驚いた。
「おやおや、カッピのところのおチビさんじゃないか」
トーポはまっ白なふくろうで、黄色の大きな目をキョロキョロと動かしながら話す。目は忙しそうなのに、話し方はずいぶんゆったりしている。
「こんにちは、トーポさん。あなたが探しものの名人だってきいて、お願いにきました」
トーポは二、三度、パタパタはばたいて僕に向き直った。大きな目がきらきら光る。
「やあやあ、ヒトの子供とは珍しい。しかも、わたくしにお願いをするヒトの子供とは、なお珍しい」
なんだか機嫌がよさそうだ。
「トーポさん、実は僕、名前をなくしちゃったみたいなんです。気がついたら、自分が誰だかわかんなくなってて。困ってたら、この…」
「ウ、ウホン」
カピーがわざとらしくせきをした。
(あ。名前は言わない、と)
「この、親切なカラスさんが、あなたに聞くのが一番だって教えてくれたんです」
トーポはちょっと小首をかしげてため息をついた。
「やれやれ。これはおかしな話だ。いろんな探しものを頼まれるわたくしだが、名前をなくしたとは、はてさて。うーむ…」
トーポはじっと目をつむって考えこんでしまった。そのまま前に後ろにゆったりゆれている。寝ちゃったのかな。

カピーと目があった。顔つきまで別人、というか別のカラスみたいだ。カピーはぷいと目をそらした。
トーポがはっと目を開いた。
「うんうん。わたくしが思うに、君のなくした君の名前っていうのは、君にそっくりにちがいない。名前とは、そういうものだからのう。うんうん」
そうかなあ。名は体をあらわす、とはいうけど。
「だが、わたくしはこの森をいつもすみからすみまで見回っておるが、君にそっくりのものなぞ、何もみかけたことはない」
そりゃ、そうだろうな。
「つまりだ、君の落とした名前は、ずっと遠くにいってしまったか、すっかりどこかに消えてしまったか、どちらかだろう。だから…」
話についていけなくなってきてボーっとしていたら、カピーがわりこんだ。
「トーポさん、つまり、あなたにはこの子の名前がどこにあるかわからないのですね」
トーポは少しむっとした。
「誰にもわからんだろうと言っておるのだ。この森の外、たとえば北の森とか、西の野原あたりに飛んでいったかもしれんが、そうも考えにくい。あまりに遠いからな」
トーポが正しいかは分からないけど、やみくもに探したってみつかりそうもないのはたしかだ。
「名前がすっかりなくなっちゃってるとしたら、僕はどうなっちゃうんですか? どうしたらいいですか?」
「ものをたずねるときは、ひとつずつな」
トーポはわが意を得たりとふんぞり返った。今日はつくづく鳥にふんぞり返られる日だ。
「名前がなければ、君はこの世にいないのと同じだ。誰でもないんだから。それは実にやっかいだ」
カピーと同じこと言ってら。
「で、どうしたらいいかだが…。わたくしもよくわからん。おそらく、新しい名前を決めなければならんだろう。しかし、そんな話、どこから手をつけていいものやら…」
なんだか、もう面倒になってきたな。
「もう、いいよ。このさい、てきとうに自分で名前を決めるよ。そしたら、僕はその新しい名前の誰かってことになるでしょ? えーっと、何だっけ。うん、たとえばポドモド、とか」
僕がその名前を口にしたとたん、カピーが飛び上がって僕の口をふさいだ。
トーポの、ただでさえ大きな目が、もう一回り大きくなって、目玉がこぼれ落ちそうになっている。
あまりの反応に僕もびっくりしてしまった。
しばらく誰も声も上げず、動きもしなかった。うろの中が静まりかえった。
ようやく少し落ち着いたトーポは、カピーをらんらんと光る鋭い目つきでにらみつけた。
「今のはわたくしの胸のうちにしまっておきましょう。しかし、そんな名前をもてあそぶことは、時に命取りにもなる。いいですね」
カピーに強い口ぶりで言い聞かせると、今度は僕の方に向きなおり、ひと言ずつ、さとすように言った。
「いいかい、おチビさん。名前ってのは、誰が誰だかはっきりさせるための、かけがえのないものだ。それは、おまえさんが生まれる前から、おまえさんのためだけに決まっているものだろう。それをかってにかえるなんて、とんでもない」
ずいぶん妙な話だなあ。
「名前って、赤ちゃんが生まれたら、お父さんとお母さんがつけるものでしょ?」
トーポが首をかしげた。
「おかしなことを言うね。親が名前を決めるなんて」
「えっ! じゃ、トーポさんの名前は誰がつけたの?」
トーポはさも不思議そうに僕の顔を見た。
「わたくしの父がトーピン。だからわたくしはトーポ。わたくしの子供はトーパル。そのまた息子は、これはまだ生まれておらんが、トープスになる。その次は…ちょっとすぐには思いだせん。ミルシ様にうかがえば、すぐわかるがな」
ん? ミルシって誰だろ。
それはさておき、なんとも変な話だ。
まだ生まれてもいない子供や孫まで、もう名前が決まってるなんて。
「なんでそんなややこしいことをするの?」
「ややこしいとは。名前というのは、命の次に、いや、命と同じぐらい、かけがえのないものであろう。それをきちんと決めるのに、ややこしがるものがあろうか」
カピーもしきりにうなずいている。
「そもそも、名前もないのに生まれてきた赤子は、生まれてすぐ、誰でもない名無しになってしまうではないか」
聞けば聞くほど、あたまがこんがらかってくる。
「えーっと、つまり…だれそれの子供の名前はかれこれって決まってるってことだよね? じゃ、僕のお父さんとお母さんの名前がわかれば、僕の名前もわかるわけ?」
トーポの目がきらりと光った。
「なかなか賢い子だ。まさに、そのとおりだ。さて、君のお父さん、お母さんの名前はなんとおっしゃるのかね」
僕はうーんとうなった。
ポケットの小石をさわったり、鼻をすりすりこすったりしてみた。でも、だめだった。
「あーあ。自分のだけじゃなくて、お父さんとお母さんの名前も忘れちゃった。いやになっちゃうな」
ここでカピーが突然、きっぱりとした口ぶりで言った。
「トーポさん、僕たちこれからミルシ様のところに行ってみます」
またミルシが出てきたぞ。様、がつくところをみると、えらいヒト(ふくろうかも)みたいだ。
トーポが顔をしかめた。
「ミルシ様はとてもお忙しい。そう軽く考えてはいかん」
カピーが食い下がる。
「でも、トーポさん、すべての名前を知っているミルシ様なら、きっと良い考えをおもちなんじゃないでしょうか」
「ふむ…」
トーポは目をつむってだまりこみ、また頭が前に後ろにゆれだした。これがトーポのくせなんだろう。
「たしかに、これはもう、わたくしの手には余るようだ。では、君たち、これから北の森のミルシ様に会ってきなさい」
カピーが僕を見た。僕はうなずいた。善は急げだ。
僕とカピーがうろから出ようとしたとき、トーポが声をかけた。
「ミルシ様に会ったら、きちんとお願いするようにな、カップン」
3 カピーの告白
トーポの木を後にして、僕たちはまた森をジグザグ追いかけっこで抜けていった。
しばらくして、僕はついに音を上げた。
「ちょっと待って。もうクタクタ。のどもかわいたし」
池のほとりを離れてから、僕は水一滴だって口にしていなかった。不思議とお腹はぜんぜんすかない。でも、のどはカラッカラで、つばを飲みこんでもひっかかってしまうくらいだ。
カピーはちょっと先から戻ってくると、
「だらしがねえ。そんなこっちゃ、日が暮れちまうぜ」
と毒づいた。すっかり別人、いや別のカラスみたいな口ぶりだ。
僕はできるだけ何気ない調子で聞いた。
「ねえ、カップンってのがほんとうの名前なの?」
カピーの肩がピクンとゆれた。そして僕の顔を鋭い目つきでにらみつけた。僕は、こんなに怒るなら、言い出さなきゃよかったな、と後悔した。
「カピーでも、カップンでも、僕としてはどっちでもかまわないよ。でも、はっきりしておかないと、なんか落ち着かないからさ」
カピーの怒りはおさまりそうもない。
僕たちはだまりこんだまま、じっと見つめあった。
どこか遠くで、ピーヒョロロと鳥が鳴いて、僕は声がした方に目を向けた。鳴き声は一度きりだった。
カピーに目を戻すと、僕をにらみつけていた目が急にゆがんだ。次々とポロポロと大粒のなみだがこぼれおちる。
「あの…その…なんだか…ごめんね」
やっぱり、こんなこと言い出さなきゃよかった。
僕は、うつむいて泣き続けるカピーをじっと見ていた。また、どこかから、ピーヒョロロと鳥の声が聞こえた。

「そうです。僕、カップンっていうんです。だましてすいません」
カピー、じゃなくてカップンがようやく口をひらいた。
「池でたおれてる君をみかけて、僕のことを知らない子なら、僕をすっかり違うカラスだと思うだろうって考えて、うそをつきました」
「どうして名前をかえたの? 僕にとっては、カピーだろうが、カップンだろうが、一緒なんだけど」
カップンはぶんぶんと首をふった。
「とんでもない。大違いですよ。カップン、ていうのは、カッピの息子の名前なんです。カッピの息子はカップンであって、カピーじゃありません」
またこんがらかってきたぞ。
「んー。カップンじゃなくてカピーだと、何が違うの?」
泣きべそだったカップンが、よくぞ聞いてくれましたとばかりに誇らしげな顔つきになった。
「カピーっていうのは、僕が考えた名前なんです。しかも、いいですか、よく聞いてください、カピーっていうのは、誰の名前でもないんです」
言い終えると、カップンはふわふわと柔らかくはばたいて僕の肩にとまった。
「でも、不思議だなあ。名前がかわっただけで、ずいぶん様子がかわっちゃうんだもの」
カピーが耳もとでささやいた。
「ええ、ええ。それはそうです。だって、すっかり違うカラスですから」
そんなものかな。
僕は急に思い当たった。
「カップンは、もしかして生まれ変わりたかったの? カピーみたいな、元気な子にさ。それで名前をかえたの?」
カップンはちょっと恥ずかしそうにうなずいた。
「僕、これからもカピーって呼ぶよ。それで、カップンはカップンじゃなくて、カピーのままでいる。どうかな」
うん。我ながら名案だ。
でも、カップンは浮かない顔で首をふった。
「そうもいきません。さっきまでは、あなたが僕をすっかりカピーだと思っていたからよかったんです。でも、今はもう、僕の名前がカップンだって知っているでしょう。だから、カピーと呼んでくれても、それはうそになってしまうんです」
そうか。それはそうかもしれないな。
「わかった。じゃ、しかたないね。あらためて、よろしくね、カップン。ミルシさんのところには、一緒にいってくれるよね?」
カップンはうなずいた。
歩き始めて、僕はもう一つ、気になっていることを聞いた。
「ねえ、ポドモドって、何なの?」
カップンが首を強く左右に振った。
「その話は、決して、二度と出さないでください。教えた僕が悪かったのです」
これ以上、聞き出すのは難しそうだ。僕は話題を変えることにした。
「それで、ミルシのところまではまだだいぶあるの? 僕、ちょっとくたびれてきたんだけど」
「もう少しです。じきに水の音がきこえてきます。ミルシのすみかはこの先の滝つぼです」
水。のどがごくりと鳴った。
「善は急げだ。行こう!」
僕たちはまた、パタパタ、ジグザグ、森の中の追いかけっこにもどった。僕は、これじゃ善は急げっていうより、急がば回れだな、と思いながら、カップンをおいかけた。
4 ミルシの滝つぼ
カップンが言ったとおり、しばらくすると、かすかに水の落ちる音がきこえてきた。
でも、音はすれども姿はみえず。すぐにでも水をがぶ飲みしたくて、僕はカップンを追いかける足をはやめた。
トーポのクスノキのあたりより、北の森の木はみっしりと葉を茂らせている。木の数も多い。ジグザグ走りでよけるのが大変だ。滝のおかげで木がぐんぐん育つのだろうか。
水音がはっきり聞こえるようになったと思ったら、ようやく滝が見えてきた。
滝の高さは大人の背ほどだが、横幅がやたらと広い。水の落ちっぷりはチョロチョロという感じで、量はさほどでもない。
それでも遠くまで水音が聞こえたのは、森の中が薄気味悪いほど静かだからだと気づいた。カップンの羽音と僕の足音、そして滝の水音だけが響いている。
僕はようやく滝つぼのほとりで待つカップンに追いついた。
「この水、飲んでも大丈夫だよね?」
返事をまたないで、僕はひざをついて、手で水をくんでは飲み、またくんでは飲みほした。
うまい!
のどのかわきがおさまると、水の味がはっきりわかるようになってきた。
この甘みは、カップンと会った池の水と同じだ。
水の色も、あの池と同じように、おそろしくすんでいる。
のどのかわきがおさまって、僕はペタンとその場にすわりこんだ。こんなに走ったのは、お父さんと山にセミとりにいったとき以来だ。
「滝つぼにすんでいるってことは、ミルシさんは魚なの?」
「しっ!」
カップンがすばやく、羽で僕の口をふさいだ。
「ミルシ様は誰よりも長生きの森の長でいらっしゃいます。魚だなんて間違いをいってはいけません。それに、さん、ではいけません。ミルシ様とお呼びするように」
(カップンだってミルシ、ミルシって呼び捨てだったじゃないか)
納得がいかないけど、郷に入れば郷に従えだ。
「で、そのミルシ様は、どちらにいらっしゃいますか」
カップンは返事もせずに飛び立ち、さっと滝をくぐってしまった。僕はポカンと口をあけて見おくるしかなかった。
(ついてこいってことかな。着替えもないし、ぬれたらやだなあ)
とりあえず、待ってみよう。
ただ待つのは退屈だ。あたりをよく調べるとしよう。
滝つぼは小学校のプールと同じくらいの広さだ。滝の幅はバスが二台ならんだくらい。チョロチョロと水の落ちる音が幾重にも重なって音楽のように聞こえる。
滝の流れおちるもとを見上げると、木々が一段高く、こんもりと茂っている。一段上に浅い池があって、そこから水があふれ落ちてきているのだろうか。その先には川があるのかもしれない。カップンは滝の裏側の洞穴か何かに入っていったのだろう。
今度は滝つぼのまわりを見回した。そして僕は、おかしなことに気づいた。もう一度すみからすみまでよく見た。やっぱりおかしい。
どこにも水が流れでていく川がないのだ。
かなりの水がひっきりなしに滝つぼに落ちている。どこかに水が逃げないと、あふれかえっちゃうはずだ。
(どうなってるんだろう?)
僕はすりすりと鼻をこすった。わからない。もっとこすった。
滝つぼをのぞきこんでみた。
水はすみきっていて、奥までふかい緑色が続いているけど、底は見えない。見つめていると、すいこまれそうだ。
しばらくして、僕はこんなことを思いついた。
滝つぼは底なしで、水がどんなに流れこんでもいっぱいにならないんじゃないだろうか。
それで、底なしの先は、地球の反対側につながっている。そこからどんどん水があふれ出てくるので、そのあたりは一面、海になっているのだ。
うん、我ながら、これはうまい考えだ。
滝は安心していくらでも水を落とせる。
森も水びたしになる心配がない。
地球の裏側では、魚やタコがきれいな水できもちよく泳げる。
一人でうなずいていたら、ザバッと音がして、滝からカップンが飛び出してきた。頭からおしりまでぬれそぼって、ひとまわり小さくなっている。
僕は思いついたばかりの滝つぼの秘密をおしえてやろうと口をひらきかけたが、カップンの顔つきをみて、思いとどまった。けわしい目つきで滝つぼをにらんで、くちばしはきっと固くむすばれている。
「すぐにミルシ様がいらっしゃいます。くれぐれも、いい子にしてください」
滝つぼの真ん中あたりの水面がゆらりと揺れた。黒い影が近づいてきたと思ったら、真っ黒な小山が浮かび上がった。
僕は息をのんだ。
でかい。
シロナガスクジラかなと思ったが、こんなところにいるはずがない。それに、よく見ると手足があった。
ようやく分かった。それはオオサンショウウオだった。見たことも、聞いたこともない、特大のサンショウウオだ。頭だけで車一台分、体もいれたら車五台分はありそうだ。
黒い肌は、てらてらと鈍く光り、日の光を跳ね返しているようにも、吸いこんでいるようにもみえる。滝つぼから顔だけ浮かべた姿は、大きな潜水艦みたいだ。
顔の両わきにくっついている目が、僕をギロリとにらんだ。目玉だけで、僕の頭ほどはある。
どう話を切りだしたものか迷っていると、オオサンショウウオの口からひっきりなしにささやき声がもれているのに気がついた。
「…アモの子はアラミとアモナ、アラミの子はラミン、ラミンの子はラミーネとラミル、ラミーネの子はラミリ、ラミルの子はラーミス…」
それは名前のら列だった。どうやら、片ときも休まず、親から子へ、子から孫へ、名前のつながりをつぶやきつづけているみたいだ。
「ミルシ様」
カップンの緊張した声が響いた。それでもミルシは名前のら列をやめない。
「ミルシ様」
もう一度、カップンが声をかけると、ようやくミルシのつぶやきがやんだ。そして、さも面倒そうに言った。
「この子が、名無しの迷子かね」
ああ、そうか。
僕は、名無しなうえに、迷子なんだ。
それはたしかにやっかいだ。ずばりと言われて、ようやく納得できた。
「そうです、ミルシ様」
「ふむ…」
ミルシはちょっと僕を見やっただけで、また名前のら列にもどってしまった。
「ミルシ様」
カップンの声が、ちょっとイライラしている。
ら列をやめたミルシがため息をついた。風がきて、僕の前髪がふわっと浮きあがった。
「わたしは忙しいのだ。名無しの迷子にかまうひまはない」
僕はがまんできなくなって、口をはさんだ。
「どうしてずっといろんな名前を並べたててるの? 忘れちゃわないため?」
カップンが僕をにらみつけるのが、横目でみえた。
「わたしがおこたえしましょう」
突然、ミルシの声が高くなった。なんだろ、と不思議に思ったら、驚いたことに、ミルシの口のはしから小さい(といっても、僕よりは大きい)別のサンショウウオが出てきた
「あの…あなたは…」
「わたしは、ミルシです」
小さめのサンショウウオがこたえた。
またややこしい話になってきた。僕は手早く鼻をこすり、さっと考えをまとめた。
「つまり…あなたがほんとうのミルシさんで、こっちの大きいのは、着ぐるみっていうか、おうちみたいなもの?」
小さいミルシは首をふった。
「いいえ、わたしたちは親子です」
なんだ。当たり前すぎて、がっかりだ。
「でも、なんでまた、お父さんの口の中にかくれてたの?」
「かくれていたわけではありません。わたしはいつも、父の口のなかで教えをうけているのです」
「教え?」
「父のあとを継ぐために、この世の生き物の名前をすべておぼえているのです」
またまた驚いた。あんなにひっきりなしに続く名前をぜんぶおぼえるなんて。
「それって、大変じゃない?」
小さいミルシは、ほこらしげに言った。
「父が名前を一通り言い終える間に、十と七つの夏と冬がやってきます。それを繰り返して、まずわたしが名前をおぼえます。すっかりおぼえたら、次にわたしが名前を言って、父に聞いてもらいます。これもまた繰り返して、父にしっかり覚えているかたしかめてもらいます」
ちょっとまってよ。
「えーっと、それって、何百年もかかっちゃうよ。君たち死んじゃうでしょ」
小さいミルシはまた、ほこらしげに言った。
「父は十が十集まったのが三つに、十が五つ、それと八つの夏と冬を過ごしました。わたしはまだ十が十ほどの夏と冬しか生きていません。わたしたちは、とても長生きなのです」
えーっと。大きなミルシが三百五十八歳で、小さいほうが百歳くらいってことか。
こんな話、聞いたことがない。
次から次へと聞いてみたいことが浮かんできた。
そして、あたふたしたあげく、一番どうでもよさそうなことを聞いてしまった。
「じゃ、きみもいつか、お父さんみたいに大きくなるの?」
「はい。そして、そのころには、この子が今のわたしと同じくらいの大きさになるでしょう」
そういって口をあけた小さいミルシのなかに、手のひらほどの大きさのサンショウウオがいた。すやすや眠っている。
ピンときた。
「この子も、ミルシって名前だね」
小さいミルシ(今はもう中くらいのミルシだ)がうなずいた。
「まだうまれたばかりですが、わたしのあと継ぎになります」
僕は、こんな変な話、ほんとに聞いたことがないな、と信じられない気持ちでいた。

5 名前の秘密
「ミルシ様。どちらのミルシ様でもけっこうです。とにかく、ミルシ様」
もっともっと聞きたいことはあったが、カップンにさえぎられてしまった。
「この子は名前をなくしてこまっています。どうしたらいいでしょうか」
そうそう、そうだった。びっくりして大事なことを忘れてた。
中ミルシがこたえた。
「名前をなくしたという話は、聞いたことがありません。父もないそうです。だから、どうやって探すのか、わたしにも分かりません。でも、名無しで困ったらどうするかは、はっきりしています」
中ミルシは僕とカップンの顔をゆったりとながめて間をとった。ずいぶん、もったいぶるなあ。
「それで、僕はどうしたらいいの?」
うながすと、中ミルシが満足げにつづけた。
「よくある名無しは、みなしごです。名前をおぼえるまえに親が亡くなったり、親からはぐれてしまって、名前がわからない、というみなしごはときどきいます」
それはありそうな話だ。でも、僕は迷子だけど、お父さんもお母さんも、死んだわけじゃない、と思う。顔も名前も忘れちゃってるけど、どこかで生きている。それはなんとなくわかる。
「でも、ミルシ様。この子は、名前をなくしただけで、みなしごと決まったわけじゃありません」
まさに、それが僕の言いたいことだ。えらいぞ、カップン。
「みなしごなら、まずは何とかしてその子の親が誰かをしらべます。親さえわかればその子の名前はすぐ分かります」
全部の名前をおぼえているなら、理屈ではそうなるか。
「でも、どうしても親が誰だかわからないこともあります。みなしごは誰でもないってことになってしまいます。この子の話はそれと似ています」
「で、そういうときは、どうするの?」
すると中ミルシは「みなしごは誰かのもらわれっ子になります。そうすれば、親の名前から、みなしごの名前もすぐにわかります」と、こともなげに言った。
僕はあっけにとられた。
しばらく、誰も口を開かなかった。いや、大ミルシだけは、ひっきりなしに名前のら列を続けていた。
滝の落ちる音と大ミルシのつぶやきだけが混じって流れている。滝からふきつけるかすかな風としぶきが冷たい。
「では、ミルシ様。この子はこれから、もらわれっ子になるため、親を探さねばなりませんね」
ようやくカップンが言った。
中ミルシは大きくうなずいた。
「そうするしかないでしょう」
いやいやいやいや。ちょっと待ってよ。だんだん腹が立ってきた。かってに話をすすめすぎ!
「そんなのいやだよ! 知らないヒトの子に急になるなんて! しかも、それが名前のためだなんて! そんなのおかしいよ!」
一気にまくしたてると、勢いがついてとまらなくなった。
「もういい! 僕、さっさと新しい名前を決めちゃう。このさい、空いてるてきとうな名前をおしえてよ」
中ミルシが僕をにらんだ。体が怒りですこし赤みをおびた。
「だめです。この世には、もう、名前はあまっていません。たとえ今誰かがつかっていなくても、いつか誰かがつかうことになっていたり、昔の誰かの名前だったりするのだから、あなたがかってに使えるわけがありません」
そんなバカな。
いや、何かがひっかかるぞ。
何か、変だ。
何だろう…。
ポケットに手を入れると、右手にちゃらちゃらとすべすべの小石があたった。
石の手ざわりがじっくり考えろって言っている。
(森中の生き物と、その子供と、そのまた子供のってずっと続けると、名前はすごくたくさんになっちゃう。でも、それにしたって、どんな長たらしい名前でも、どんなへんてこな名前でも、だれか持ち主がいるなんて、おかしいぞ)
急にだまりこんだ僕を、中ミルシとカップンがじっと見ている。大ミルシはおかまいなしにぶつぶつを続けていた。
(どんなへんてこな名前でもぜんぶ誰かの名前になってて、それをぜんぶおぼえなきゃいけないなんて。いくら長生きでも言い終わる前に死んじゃうよ)
ここまで考えて、はっきりとわかった。
中ミルシはうそつきだ。
たぶん、自分たちがおぼえたのとちがう名前を誰かが使うのが、いやで仕方ないのだろう。
そんなあちらの都合でもらわれっ子になるなんて、まっぴらごめんだ。
右手から左手に小石をもちかえたときに、うまい考えがうかんだ。
「ミルシさん、名前はぜんぶ売り切れだって言ったよね。でも、僕、誰のでもない名前をしってるんだ」
中ミルシはうたがわしげに僕をみた。僕からカップンに目をうつす。
カップンは「何のことやら」という感じで小首をかしげた。
「カップン、自分で言ったこと、忘れちゃったの?」
「あっ!」
カップンがあわてて僕の口をふさごうと飛びあがった。僕はさっと身をかわして、早口で言った。
「僕、いまからカピーって名前になるから!」
「カピー…カピー…カピー…。はて、そんな名前、どこから出てきたのですか」
中ミルシは身をのりだし、滝つぼから岸にはい出て僕たちの足元に近づいてきた。
「はっ! 知ったことか! 大きなお世話だ!」
僕は、自分の言葉使いに、飛び上がるほどおどろいた。
今のは、たしかに僕の声だった。でも、僕の言葉じゃない。口ぶりといい、言いまわしといい、池で出会ったカピーそっくりだった。
カップンの黒い顔が青ざめたようにみえた。たぶん、僕の顔も青くなってると思う。自分ではみえないけど。
心はとまどっているのに、口はとまらない。
「カピーってのは、カッピの子でもなきゃ、カップンなんて気弱なカラスでもねえ! 親もなければ、子もいねえ。名無しが名乗るにゃ、もってこいの名前だぜ!」
顔の赤みがました中ミルシがカップンをにらみつけ、カップンはすくみあがってしまった。カピー(というのは、僕のことだけど)も言いたいことを言ってしまったようで、だまりこんだ。
奇妙な間ができた。
「カピーはカープルの子、カープルはカッピートの子。カピーの子はカリピーとカルプン」
とつぜん大ミルシの低い声が、地面をゆらすように力強く響いた。
中ミルシははっとした顔で大ミルシをみると、ゆっくりとうなずき、それからカピー(くどいけど、僕のこと)とカップンに向きなおった。
「カップン、あなたの子供の子供の子供の、そのまた孫の孫の孫が、カッピートです。カピーは、そのカッピートの孫です。だから、名無しの迷子さん、あなたがカピーと名乗ることはできません。もうそれは、だれかの名前なのですから」
そうきっぱり言うと、中ミルシは大ミルシの方に振りむいた。大ミルシがゆっくりうなずいた。
「へっ! だからってなんだい。どうだってかまわないよ。僕は僕で、好きなようにやらせてもらうぜ! ほっといてください」
あれ?
僕のいつものしゃべり方と、カピーの口ぶりがまじっちゃった。
中ミルシがにやりと笑った。
「ほらみなさい。あなたはもう、カピーだなんて言いはれなくなってるんです」
だめ押しされて、すっかりそんな気分になってしまった。
「ふう。これっていったい、どういうこと? 別のヒトになっちゃった気分だったよ」
中ミルシは僕の質問を無視して、カップンをしかった。
「あなた、この子に何かふきこみましたね。おそらく、カピーという名前を自分が考えついたのだと思いこませたのでしょう。名前についてうそをついた罪は重いですよ」
カップンはすっかり小さくなってしまった。僕は断りもなくカピーという名前をもちだしたことを、とてもすまなく思った。話をかえてしまおうと、わざと明るい声で言ってみた。
「でもさ、やっぱり僕、よその子になるの、いやなんだ。ほかに何かうまい手はないかなあ」
口を開きかけた中ミルシをさえぎって、カップンが叫んだ。
「まだそんなことを言ってるんですか!」
カップンがたたみかける。
「あなたにとってやっかいなのは、よその子になるってことじゃありませんよ。親になってくれる誰かを見つけなきゃいけないってことです。この森でほかのヒトをみかけましたか? 僕だって、ヒトをみたのはかなり久しぶりのことですよ」
そうか。
名無しの迷子の親になってくれるというやさしいヒトをみつけないと、僕はカラスやふくろうやサンショウウオのもらわれっ子になっちゃうかもしれないのか。
それは勘弁してほしい。
うーん。どうしたらいいかな。
よし。
まず、僕以外の人間を探そう。うまくすれば、そのヒトに、もらわれっ子にならずにすむ手をおしえてもらえるかもしれない。
僕は中ミルシにきいた。
「誰か、僕の親になってくれそうな人間って、この森にいる?」
「森の中にはいません。西の野原のはずれに、ヒトがたくさん集まっている村があります。狩りがうまいので、森の生き物たちは近づこうとはしません」
なんだか、人間なのがすまないような気になった。
「西の野原って遠いの?」
カップンがこたえた。
「あなたの足なら日の出から日暮れまでかかります。今日はもうおそいから、明日の朝に出ることにしましょう」
いつの間にか、あたりは暗くなりかけていた。
6 夜の森
僕はこれまで、夜の森に入ったことがなかった。
木の枝からもれる月の光のほかは、明かりはなにもない。
昼間でも木々が日の光をほとんどさえぎっていたのだから、月の光はいかにも頼りない。
きょうが満月でなかったら、トイレの中でとつぜん電気を消されたときみたいに、とっても心細くなっていただろう。
ミルシ親子との話し合いは明日、西の野原に向かうことでけりがついた。
「あなたの親が決まったら、またきなさい」
そう告げると、中ミルシは身をよじって滝つぼにもどり、あんぐりとあいた大ミルシの口の中に戻った。大ミルシはゆらりと向きをかえ、滝の向こうに姿をけした。
それを見届けてから、カップンが言った。
「もう寝ましょう。じきに暗くなります」
ふわふわと木の枝にとまり、さっさと目をとじてしまった。ことの急なはこびにとまどっていると、カップンが片目を開いた。
「夜は冷えます。あなたもどこか良い寝床をさがしたほうがよいですよ」
寝床って、どうすりゃいいのさ。
カップンはもうぐっすり寝てしまったようだ。
もしかしたら、僕がカピーって名前を持ち出したことを根にもって、寝たふりをしているのかもしれない。
どっちにしても、呼んでも返事しないのだから、僕としてはどうしようもなかった。あたりは一段と暗くなり始めていた。
カップンと離れてしばらくすると、空気がすっと冷たくなった。
滝つぼからしみでる冷気があたりを包んでいる。
(どこかにもぐりこんで寝ないと、風邪ひいちゃうぞ)
僕は手さぐり足さぐりで体を押しこめる物陰やうろはないかと探した。
そうやって寝床さがしをしていて、水音が遠くなり、滝から離れすぎたかなと思ったときのことだった。
「チチチッ!」
右手のしげみから、するどい舌打ちのような音がした。
僕の背中に冷たいものが走った。
「チチチチチチチ!」
さっきより長く、はっきりときこえた。
とっさに音と反対の左のしげみに飛びすさり、地面にふせた。
草と土のにおいが鼻の奥に入ってくる。
息を殺す。
風のない夜の森は、おそろしく静かだった。
「ガサッ!」
静けさをやぶり、しげみから細長い黒い影がはいでてきた。
おどるように伸び上がったり、ゆれたりしている。
(ヘビだ! 特大の!)
僕は肝をつぶした。
ヘビはかま首を右へ左へとめぐらせて、あたりをうかがった。
でかい。
闇夜ではっきり見えないけど、背伸びするように立てたかま首だけで、大人の背ほどはある。太さだって、あたりの大きな木の幹とどっこいどっこいだ。
(見つかったらおしまいだ)
僕は最近、本でヘビのことを読んだばかりだった。
その本によると、でっかいヘビは獲物を丸のみしてしまう。
だから、ゾウをのみこんだヘビは、ぽっこり体の真ん中がふくらんで、山高帽みたいなかっこうになってしまうのだ。
僕はゾウよりずっとちっちゃいから、かんたんに丸のみされてしまうにちがいない。
音をたてないよう気をつけながら、身をにじらせてしげみの裏に体をかくした。
ヘビは右に左にかま首をふりながら、
「おかしいね。ここらにいるはずなんだけど…」
とつぶやいた。口からはちろり、ちろりと長い舌が出入りしている。背中にまたぞっとする冷たさが走った。
ヘビは身をくねらせると、頭をすっと低くした。かま首をせわしなく左右にめぐらせる。
(これじゃ、じきにみつかっちゃう)
走って逃げるか?
だめだ。すぐ追いつかれるにきまってる。
戦う?
いや、どう考えても、勝ち目はない。
まさに八方ふさがりだ。
僕は、これまで生きてきて一番ってくらい、必死で考えた。
鼻をこする指も、これまでで人生で一番のいきおいで動かした。
こする、こする、こする。
もっと、こする。
もっと、もっと、こする。
うん。
よし。
一か八か、この手しかない。
僕は覚悟をきめてあたりを見まわした。
うまいぐあいに、すぐ近くに手ごろな枝がみつかった。
僕が枝をシャツの背中にかくしたのと、ヘビが僕をみつけたのはほとんど同時だった。

ヘビは僕をにらみ、にやりと笑うと、口から長い舌をチョロチョロさせた。月明かりで目があやしく赤く光る。
「ついてないね、おチビさん。あきらめてあたいのおなかにおさまりな。あたい、もう、腹が減って、腹が減って、目が回りそうなんだ」
みかけによらず、ヘビの声も口ぶりものんびりしていた。
「ヘビさん、僕、あきらめるからさ、せめて苦しいのとか、痛いのは勘弁してくれない?」
声がブルブルふるえる。
ヘビは目を細めて、舌なめずりした。
「いいさ。ちゃんと傷をつけないで丸のみしてやるよ」
たしかにこの特大の口なら、キバにひっかからないでのみこんでもらえそうだった。
「じゃ、おっきく、おっきく、口をあけてよ。そしたら僕、飛びこむから」
ヘビは大口をあけてわらった。
「こいつはいい。あたいもいろんなモノを丸のみしてきたけど、そっちから飛びこもうってやつにはお目にかかったことがないね」
ヘビはするすると僕ににじりよると、「じゃ、とびこみな」と大口をあけた。
ぬれた大きなキバがてらてらと光り、のどのおくはほら穴のように真っ暗だ。生ぐさい息が鼻をつく。
僕は鼻をゆびでつまむと、「えいっ」と景気づけのかけ声とともに飛びこんだ。
7 まるのみニッキー
おしくらまんじゅうみたいに、体がぐいぐいしめつけられる。
身をよじると、ますますしめつけがきつくなり、ぬるぬるとした壁にしぼられて奥へ奥へと吸いこまれていく。
しばらくして、ようやく手足がうごかせるようになった。
どうやら、胃袋にたどりついたみたいだ。
すっぱいにおいが立ちこめて、手足も服もベタベタする。
こんなところに長居したら、しまいにはとけてヘビのウンチになっちゃうぞ。
僕は急いでシャツの背中にかくしておいた枝を取りだした。
「さあ、一寸法師作戦、うまくいくかな」
僕は逆手にぎゅっとにぎりしめた枝を振りかぶると、思いきり胃袋のかべに突きたてた。
「ンギャー!」
くぐもった悲鳴が、頭の方から聞こえてきた。
かまわず「えいっ!」ともう一度、突きさす。
「ギョワー!!」
さっきよりひときわ大きな悲鳴だった。続けて泣き声まじりのなげきが聞こえてきた。
「なんだい、なんだい、どうしてこんなに腹が痛くなるのさ? 痛い、痛いよ!」
気の毒になってきた。
でも、ここは心を鬼にしなければ。
もう一刺し!
「アギョエー!!!」
ヘビは僕を吐きだそうとさかんにえずきだした。
掃除機ですわれるみたいに、僕の体が引っぱり上げられていった。
「ウー、ペッ!」
最後の一声で、僕は地面に放りだされた。
そのひょうしにドスンとしりもちをつき、コロコロころがって頭のうしろをしたたか打った。かなり痛かったけど、僕はすばやくにぎりしめていた枝を背中にかくした。
ポロポロと涙をながしながら、ヘビがにらみつけてきた。
「やい、あたいに何しやがった!」
一息ついてから、僕はすっとぼけて言った。
「なーんにも。おなかに入ったとおもったら、君が急に叫びだしたんだ」
ヘビはうたがわしげに僕をあたまからつま先までねめまわした。
「おかしいね…とがったつツメも、キバも見あたらないし…」
僕は肩をすくめた。
「何のこと?」
そして、ちょっと間をおいてから、急に思いついたような調子でこう言った。
「あ…もしかして…僕、毒入りかもしれない」
ヘビはギョッと目をむいた。のけぞったせいでかま首がすこし持ち上がった。
よし。ここが勝負どころだ。
「昔、うちの犬が僕にかみついたことがあったんだ。そしたら急にキャンキャンなきだして。それで何日もおなかを下しちゃってさ」
ヘビののど(どこからどこまでがのどか、よくわからないけど)がごくりとなった。
「でも、気のせいかもしれない。もう一度、のみこんでみてよ。それでまた具合がおかしくなるなら、毒入りってことかもしれないけど」
ヘビは目を大きくひらくと、ブンブンとかま首をふった。
「と、と、とんでもない! あんた、あたいがどれだけ苦しかったか、わかってないね! 腹に穴があいたかと思ったよ。あんなの、もういやだ!」
よしよし。
僕は続けて、できるだけすまなそうに言った。
「それじゃ、君の晩ごはんになるのは、むずかしそうだね」
「あんたなんてのみこむくらいなら、ひもじくてくたばったほうがましってもんよ。まったく、ヘビのあたいでも毒なんて持ちあわせてないってのに、なんてヤツだい!」
よし、なんとか逃げられそうだぞ。
「はあ、しょうがない。やっと見つけた獲物が毒入りだなんて、ついてないよ、まったく」
大ヘビがため息をついた。
僕はいまにも逃げ出したい気持ちでいっぱいだったけど、大ヘビに飲み込まれた怖さと助かって安心したのが重なって、腰がぬけたようにその場に座り込んでしまった。
「おや、おチビさん、どうしちゃったんだい、へたりこんじまって」
「いろいろあって、心と体がびっくりしちゃったみたい」
大ヘビはふうん、と面白そうな顔をした。
ふと目が合い、僕らはなんとなく笑いあってしまった。
笑ってみたら少し落ち着いてきて、僕はあらためて大ヘビをじっくりと見た。
よく見ると、大ヘビはのんびり屋な感じで、ちょっとあいきょうのある顔をしている。
僕はちょっと気になっていたことを聞いてみた。
「この森のヘビは、みんな君みたいに大きいの?」
「そんなことないさ。やたらと腹が減るから、なんでもかんでものみこんでたら、あたいだけ、こんななりになっちまって。大きくなると、またやたらと腹が減るわけ。うまくないよねえ」
なんだか気の毒になってきたな。
「ほかには君みたいに大きな生き物はいないの? 大きなクマとか、シカとか」
「いないねえ。みんな飲み込みやすい大きさのヤツばっかりさ」
何でもかんでも、飲み込めるかどうかという考え方をするんだな。
あれ。何でも飲み込んじゃうってことは。
「ねえ、君、友だちって、いるの?」
ヘビが不思議そうに首を傾けた。
「友だちってのは、なんだい?」
「仲良しな、ほかのヘビとか生き物はいないの?」
「あたい、これまで仲良くなったやつは、みんなのみこんじゃったよ。だって、ひもじいときに、となりでいいにおいをさせるんだもの」
あきれた。
「食べちゃうなんて、それは友だちじゃないよ」
ヘビが「ふう」とため息をついた。
「食べられないなら、何の得があるんだい、そんなものに」
「何か得があるから友だちになるなんて、変だよ」
ヘビは小首をかしげている。
なんてかわいそうなヘビだろう。
片っ端から友だちを食べちゃうなんて、いつも一人ぼっちってことだ。
「で、いいこともないのに、なんで誰かと友だちなんてものになるのさ」
どうして友だちになるのか、か。
鼻を少しこすると、思い出した。同じことをお父さんに聞いてみたことがあるぞ。
お父さんはそのとき、たしかこう言った。
「何かの縁、だよ。とりあえず友だちになってみればいいんだ。気があえば、ずっと友だちでいられる」
「ふんふん」
「で、だめなら、いつかさようならになる」
「なるほど」
「親も子もえらべないけど、友だちはえらべるってわけ」
相づちにつられて、お父さんが言ってたことを全部しゃべっちゃった。ヘビはさかんにうなずいている。
「君、ほんとに友だち、一人もいないの?」
ヘビはこくんとうなずいた。
「同じヘビだと、食べもののとりあいになっちゃうからねえ」
うん。これも何かの縁かもしれない。
「ねえ、僕なら、どんなにお腹がすいても、食べる気がしないでしょ。僕、君のごはんにはなれないけど、友だちにならなれると思う。とりあえず友だちになってみない?」
僕らはじっと見つめあった。
ヘビは少しだけ考えてから言った。
「そうしてみるかい。物は試しってことで」
日がくれてどれほどたったのだろう。
あたりからはすっかり昼のぬくもりがきえていた。
「で、友だちってのになったら、あたいら、どうしたらいいんだい」
「自己紹介からかな。君、名前は?」
言ってすぐ、しまったと気づいた。
「あたいはニッキー」
弱ったぞ。
「えー…ニッキーね、よろしく。えーと…実は、僕は…その…」
ニッキーがぽかんと口をあけて僕をみている。
「あの…じつは僕、自分の名前がわからないんだ。どうも、なくしちゃったみたいで…名前を」
ニッキーはおおいかぶさるように僕に顔を近づけた。あまりに図体が大きいので、友だちだと思ってもビクビクしてしまう。
「名前をなくすって? 落としたとか、盗まれたとか、そんなのかい? するとあたいは、どこの誰でもない友だちができちゃったわけかい?」
最後のところは、とてもがっかりした言い方だった。
「うん。ごめんね。だから、僕、新しい名前をもらうために、西の野原の村までいかなくちゃならないんだ」
ニッキーはうんうんとうなずき、僕にきいた。
「さて、こういうときは、友だちってのは、どうしたらいいのかねえ」
僕はまた、お父さんが言ってたことを思い出した。
「困ったときは助けあえばいい。いっしょにいて楽しいなら、いっしょにいればいい。あとは、なんだっけ…そうだ、いいところはマネして、ダメなところはダメ、って言ってあげればいい」
まだほかにもあったはずだけど、おぼえているのはこれだけだ。
「ってことらしい」
僕はなんだか照れくさくなってつけたした。こういうのを蛇足というのだな、と考えて、クスリとひとりで笑った。ヘビの友だちを相手に、ピッタリすぎる。
ニッキーは何度も大きくうなずいた。
「よーし。あたい、手伝うよ。困ったら助けあうっての、気に入った」
ニッキーはぴょこんとかま首を小さくのばした。
「さ、背中にのって。村って、おかしなヒトの巣が集まってるところだろ? 急げば明け方には着くさ」
「張り切ってるとこ、ごめん。ニッキー、僕さ、もうがまんできないぐらい眠いんだ。夜は寝るものだよ。でかけるのは朝にしよう。ここらに僕が寝られるところってないかな」
ニッキーはかま首をかしげた。僕の言いたいことがよくわからないみたいだ。
「こんな寒いところで寝たら、僕ぜったい風邪ひいちゃうよ。小さなほら穴とか木のうろとか、ないかな」
「ああ」
やっと話が通じたのはよかったけど、ニッキーはうんうんうなって考えこんでしまった。
かま首をひねるうちにぐるりと一回りしてしまい、そこからまたもうひとひねりしたものだから、ニッキーはねじりん棒みたいに地面にころがってしまった。
ヘビがなやむと、ずいぶんいい運動になるのだな。
感心してながめていたら、ねじりん棒のニッキーがふと我にかえった。
「いけない、いけない。こういうときこそ、じっくりとトグロをすえて考えろって、母ちゃんがいつも言ってたもんさ」
ニッキーは器用にねじれをほぐすと、長い体をおりたたむようにきれいな特大のトグロをまいた。あまりに見事なので拍手をすると、得意そうにチロチロと舌をだしてみせた。
でんとかまえて考えこむニッキーをみて、ひらめいた。こういうときにピンとくるのが僕のいいところなのだ。
「ねえ、ニッキーのトグロって、中はすき間があるよね。その中に入ってもいい?」
ニッキーは感心した目で僕をみた。
「それはいい考えだ。あたいもトグロのまま寝られるし。さあ、さあ、そうと決まれば、早くいらっしゃい」
そう言うと、もぞもぞと体をずらして、僕がくぐれるくらいのすき間をあけてくれた。
ニッキーのぬめりとした肌をかきわけて、なんとか体をトグロのなかにねじこむ。
どすんと尻もちをついて落ちてみると、中は思ったよりずっと広かった。
「ニッキー、こりゃいいよ。ポカポカするし。さっそくだけど、僕、寝ちゃってもいい?」
薄暗くて、生温かくて、押入れのなかにかくれんぼしているみたいだ。
ニッキーは少しだけトグロをといて、天井からのぞきこむように僕をみた。
「ほいきた、それきた。あたいもちょっと寝るとしよう。おチビさん、ゆっくりおやすみ。明るくなったらおこしてやるから」
「うん、ありがと」
僕はお礼もそこそこに、横になって丸まった。
「あら。ヒトもあたいらみたいにトグロをまいて寝るのかい。ついぞ知らなかった」
ニッキーの声がとおくに聞こえたけど、くたびれきっていて、もう、とても目をあけていられなかった。

8 遠くの声
(…どうしたんですか…)
(…ほんのちょっと…)
(…まずいな…)
9 夜明け
「おチビさん、朝だよ」
天井からふってきた声におどろいて飛びおきた。日の光も頭の上からふってきた。
「ここ、どこ?」
「おチビさん、寝ぼけてるね。どこっていえば、そりゃ森の中だし、あたいの中でもあるし」
ああ、そうだ。ニッキーのトグロの中で寝たんだった。
「西の野原を突っ切るなら、早く出た方がいい」
うん、すっかり思い出したぞ。僕は名無しの迷子で、これから誰かのもらわれっ子になるんだった。
ニッキーがトグロをといて伸びをした。急に明るくなって目がちかちかする。
「おはよう、ニッキー。早くしたくしなきゃね」
僕はふと、気になってニッキーにきいてみた。
「起こしてくれるまえに、誰かとおしゃべりしてた?」
ニッキーはかま首をひねった。
「まだ寝ぼけてるね、おチビさん。ここらにゃあたいたちしかいないし、あたいは独り言をいったりしないよ」
おかしいな。確かに誰かの話し声がしたんだけど。夢かな。
「ま、いいや。はやく行こう。僕、滝つぼで顔を洗ってくる」
「そうこなくっちゃ」
朝一番の日差しが森を照らし、夜の不気味さはうそのように消えていた。
僕はふと、ニッキーにあのことを聞いてみたくなった。
「ニッキー、ポドモドって知ってる?」
「ん? なんだい、それは。うまいモノかい」
「ううん、なんでもない」
ニッキーは知らないみたいだし、今の会話も気にもしていない様子だ。
それにしても、あらためて見ると、ニッキーはびっくりするほど特大のヘビだ。体はそこらの木の幹より太い。
「ああ、腹が減った」
ニッキーがぼやいた。
腹が減る…。
そういえば、何かおかしいな。
「僕はさ、昨日からちっともお腹がすかないんだ。いつもはご飯がまちきれない腹っぺらしなのに」
「うらやましいねえ」
ニッキーは伸びを繰り返して朝の運動をしていたので、僕は一人で滝つぼにむかった。
滝つぼの近くまでくると、すぐそばの木にカップンが止まっていた。まだ寝ている。
よし、昨日、先にさっさと寝ちゃった仕返しに、ちょっとおどろかしてやろう。
「おはよう! 朝だよ!」
すぐ近くでさけぶと、カップンが勢いよく飛びあがった。
「カア! カア! カア!」
あわてて寝床にしていた木のまわりをグルグルと飛びまわってから、くちばしをとがらせて僕の目の前にもどってきた。
「ひどいじゃないですか!」
「だって、もう、起きなきゃ」
「カラスには、カラスなりの起こされ方ってものがあるんです!」
「どんな?」
「まぶたをやさしくくちばしでつつくんです!」
「僕、くちばしなんてないよ」
それに、まぶたツンツンなんて、そっちの方がおどろくよ。
「ごめん、ごめん。それより、早く行こうよ。けっこう遠いんでしょ? 善は急げ、っていうじゃない」
カップンは気を取り直したようだ。
「そうしましょう」
「うん。まず、顔を洗おう」
僕らは滝つぼにかがみこんで顔を洗った。水が冷たくてきもちいい。口をすすいでから、一口、二口、飲みほした。
うまい。
カップンもくちばしを突っこんで、ぴちゃぴちゃ飲んでいる。
「ニッキー! 気持ちいいし、おいしいよ! おいでよ!」
僕は振りかえって叫んだとたん、カップンがギョッとした顔つきになり、滝にむかってすっ飛んでいった。
「ま、まさか…」
すぐにサワサワと草をかきわける音がして、ニッキーが姿をあらわした。
「おチビさん、すんだかい? あたいは顔を洗ったりってのは、やりつけてないから、よしとくよ」
「えー。お父さんやお母さん、怒らないの? ニッキー、このカラスは僕の友だちのカップン。カップン、この大きなヘビは…」
「丸のみニッキー!」
僕の声にかぶせるように、カップンが叫んだ。
「カップン、ニッキーのこと、知ってるの?」
カップンはすごいいきおいで滝すれすれを飛びまわっている。
「この森で丸のみニッキーを知らないものはいません!」
「へえ。ニッキー、すごいね」
「まあね」
ニッキーは気のないようすで僕とならぶと、チロチロと舌をだして水を飲んだ
「何してるんですか! 早く逃げて!」
カップンはまだ、しっちゃかめっちゃかに飛びまわっている。
「大丈夫だよ、カップン。ニッキーとはもう友だちになったんだ。一晩いっしょに寝た仲だし、丸のみにしたりしないよね」
「おチビさんはね。そっちは朝めしにぴったりのカラスだねえ…。毒もなさそうだし…」
ニッキーの大きな口のはしからよだれがたれた。にらまれたカップンは、すくみあがって滝つぼにぽちゃんと落ちてしまった。
僕は池におどりこもうとするニッキーにたちふさがった。
「だめじゃないか、おどかしちゃ! カップンは僕の大事な友だちなんだ。友だちの友だちは友だちでしょ。ニッキーとカップンも仲良しになろうよ」
ニッキーは困った顔で僕を見た。そのうち、かま首をかしげて身をよじった。
こうなると、もうとまらない。
あっという間にねじりん棒になってしまった。
ねじりん棒のままニッキーが言った。
「わかった、おチビさん。あたい、おチビさんの友だちはのみこまない。でも、ちっとも友だちでもないモノまでは、そういうわけにはいかないよ。あたい、ひもじくって死んじまうもの」
「うん。ありがと、ニッキー」
ふり向くと、カップンは滝つぼでおぼれかけていた。
「ということで安心してよ。人間の村はとおいみたいだから、ニッキーの背中にのせてもらったほうが早いでしょ」
ようやく岸までたどりついたカップンは、僕の足元にかくれてニッキーの顔色をうかがった。
「あなたがそうしたいなら、止めません。でも、僕は僕で、ひとりで飛んでいきます。おかまいなく」
さっと飛び上がると、ニッキーからかなりはなれた枝にとまった。僕はニッキーに肩をすくめてみせた。
「じゃ、いこうか。どうやって背中にのったらいいかな」
ニッキーは僕のおしりのほうに口を近づけ、ズボンのはしをくわえてもちあげると、背中にのせた。
うろこでぬらぬらしていて、つかまるところはない。
ニッキーがはいすすむと、右に左に体がくねり、僕はすぐにおっこちた。
「ありゃ、おチビさん。気が早いね。まだまだ先だよ」
ニッキーがのんきな声で言った。
「ちがうよ。こんなにゆれちゃ、のってられないよ。もっとうまいのせ方ってないの?」
「誰かをのせたことなんてないからねえ。ゆれなけりゃいいなら、あたいの頭の上にのるってのはどうだい、おチビさん」
カップンはもうかなり先まで行っている。
「それでいいよ。さっきみたいに、ひょい、とやってよ」
僕はもう一度、背中に乗せてもらい、頭までおっこちないように、そっと歩いていった。そして、おでこのあたりにデコボコしていてうまくお尻を落ち着けられる場所をみつけた。
「いいかい」
ニッキーがかま首をゆっくりもちあげた。
「わー」
木に登ってあたりを見下ろしたときのように、とても見晴らしがよくなった。
これはなかなかいい気分だ。
ニッキーが進み出した。できるだけ頭を動かさないようにしてくれているみたいで、乗り物酔いする心配もなさそうだ。
「道すがら、メシをすませないとね。それとも、村までこらえて、久しぶりに一人や二人、のみこんじまおうかな」
「かんべんしてよ。のみこんだのが僕のあたらしいお父さんだったらこまるじゃないか」
しばらくいくと、僕らは森を抜けた。
目の前に西の野原が広がった。

10 リンゴルンゴの木
ニッキーの頭に乗るのにすっかりなれたころ、肩にふわりと重みを感じた。
カップンだった。
「やあ。ニッキーにもなれた? 怖くないでしょ?」
カップンは小きざみに首をふり、ささやいた。
「気をゆるしてはいけません。でも、まあ、さすがに頭の真上のものまではのみこめないでしょう」
「村はまだ遠いのかな」
「かなりあります。先に何か食べましょう」
僕はあいかわらずお腹がちっともすかなかったからどちらでもよかったけど、ニッキーが腹ペコのままなのはまずい。
「西の野原の真ん中に良いところがあります」
「ああ、それはいい考えだね。あそこなら、腹ごしらえはばっちりだ」
ニッキーが返事した。
しばらく行くと、原っぱに立つ大きな木が見えてきた。
「あ! すごい! なに、あの木!」
「リンゴルンゴの木です。夏でも、冬でも、いつでも大きなリンゴの実をつけている、ありがたい木です」
それはとんでもない大木だった。トーポの木なんて目じゃない。でっかい観覧車くらいの高さはある。幅もとんでもなく広い。四方八方にはりだした枝が、巨人のかさのように緑のひさしをつくっている。
枝にはそこかしこに赤いリンゴがなっている。実もとんでもなく大きい。サッカーボールほどはある。
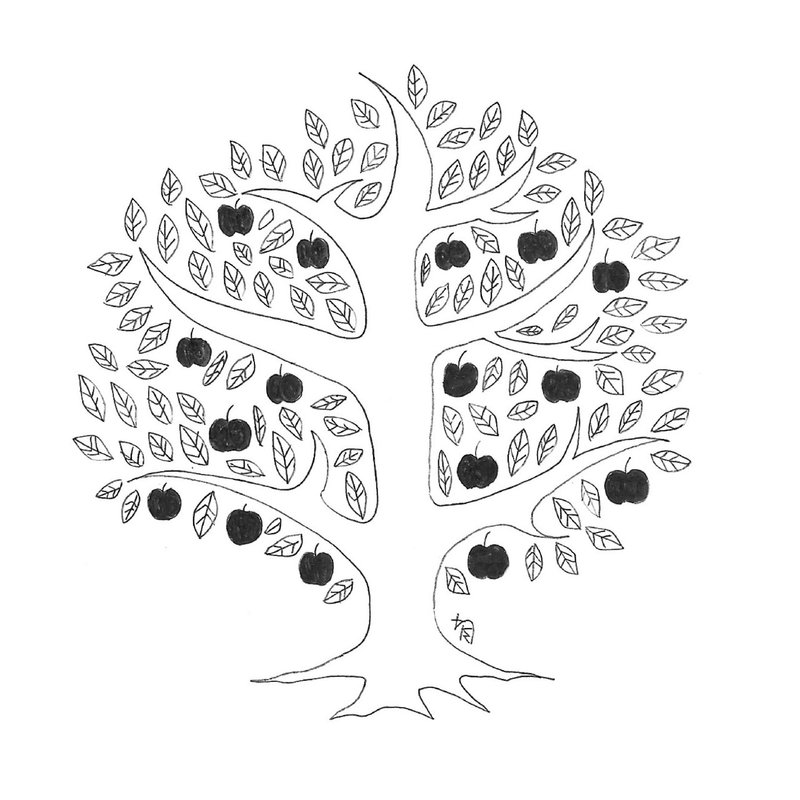
僕はぴょんとニッキーの頭からとびおりると、幹に向かって走りだした。
落ちている実をよけながら、ぐんぐん走る。
僕はかけっこではいつも一着の運動会のヒーローなんだ。
幹にたどりついたときには、五十メートル走のあととかわらないくらい、息が切れていた。なんて木だろう!
へたりこんでいる僕にニッキーがするする近寄ってきた。
「おチビさん、気でもふれたかい、急にかけだして」
「いや、あんまり大きな木だから、わくわくしちゃって」
「へえ。わざわざお腹がすくようなことするなんて、ヒトの子どものやることはわかんないねえ。でも、気をつけな。ここらにゃ、あたいみたいにおチビさんを食べちまおうって狙ってるけものがウヨウヨしてるだろうよ」
ドキッとして、あわててあたりを見まわした。何もいないけどな。
「子どもをおどかすのはおやめなさい。丸のみニッキーのすがたをみて、みんなさっさと逃げ出しましたよ」
カップンはいつのまにか枝のうえでリンゴをつついている。ニッキーは残念そうにあたりをみた。
「うまくいけば活きのいいメシにありつけると思ったのにねえ。しかたない。たんまりリンゴをいただくとするか」
ニッキーは太い幹を器用にのぼり、手ごろな枝に身をからみつかせた。
「おチビさん、ちょいとどいてな」
そう一声かけると、身をくねらせてゆっさゆっさと枝をゆすった。
僕はあわてて頭をかかえて逃げた。大きな実がぽとぽとと落ちてきたからだ。
別の枝に移ってもう一度、そのあと別の枝でもう一度、同じことをすると、足の踏み場もないほど一面のリンゴだらけになった。その間、僕は必死でリンゴをよけつづけた。
「おチビさんもおあがり」
ニッキーが木から下りてきた。
僕は一つ、大きなリンゴを抱えあげるようにして持ち上げてみた。
重い。
リンゴのおしりをかいでみると、甘酸っぱいにおいが鼻の奥にひろがった。口につばがわく。お腹はすいていないけど、のどはカラカラだった。
大きく口をあけて、なんとか一口かぶりついた。
おいしい!
またかぶりつく。
シャリシャリした歯ごたえといい、どうにも止まらないおいしさだった。
となりでは、ニッキーが次から次へとリンゴをまるのみしていた。
しっぽでリンゴをかき集めておいて、長い舌で一つずつひろいあげては、休みなくのみこんでいく。百個くらいはあったリンゴは、あらかたなくなっていた。
僕はなんとか普通のリンゴ四つ分くらいをかじったところで、幹にもたれかかってすわりこんだ。もう入らない。
ふわり、と肩にカップンがとまった。
「いつも、このリンゴルンゴの木は生き物でいっぱいなんです。でも、今のこっているのは、枝の小鳥たちと、すばしっこさにおぼえのあるサルたちだけです。どうです。あのヘビのおそろしさがわかるでしょう」
「でもさ、もう友だちなんだから、僕やカップンをのみこんだりしないって」
僕たちのわきをぬけて、ニッキーがまた幹にとりついた。
あれだけ食べて、まだおかわりするのか!
別の枝からふりおとしたリンゴを、ニッキーはまた次から次へとのみこんでいく。
(これだけ大食いじゃ、僕はともかく、カップンがこわがるのはしかたないか)
「ねえ、やっぱり、ニッキーとは、もう、さよならした方がいいかな?」
「シッ!」
カップンがあわてて僕の口をふさいだ。
「気はゆるせませんが、道連れは助かります。恐ろしいケモノたちも寄ってきませんし」
なんだか、ニッキーをだましているようで、嫌な気持ちになった。
おやつにとっておこうと小ぶりのリンゴを探していると、ニッキーが近寄ってきた。
「ふう、やっと落ち着いた。すぐにおチビさんをのせられるように、ほどほどでやめておいたからね」
あれで?
「ありがと。じゃ、出発しよう!」
すこし離れてから、僕はニッキーの頭の上からリンゴルンゴの木を振りかえった。
木のまわりには動物たちがたくさん戻っていた。
ニッキーがいなくなるまで隠れていたのだ。
僕は動物たちにも、ニッキーにも、すまない気持ちになった。
11 ヒトの村
ニッキーの頭にすわりつづけて、お尻ががまんできないくらい痛くなりだしたころ、肩にとまっていたカップンがさっと飛びたった。
「見えてきました。あのけむりが立っているあたりです」
うっすらと上がるけむりを目で追うと、確かに三角屋根のテントみたいなものがポツポツとならんでいる。
「ヒトは火なんておそろしいものを、ちゃんと使いこなせると思いこんでいるんです」
まだ遠くてはっきりしないが、テントの数はかなりのもので、思ってたよりたくさんの人がすんでいるようだ。
これなら誰か名無しの迷子の親を引き受けてくれるかもしれない。
カップンはもう一度、肩にとまって言った。
「わたしはヒトが苦手なので、ここから先は行きません。村のはずれの底なし池のあたりに隠れています」
言い終わると高く舞い上がり、けむりのすじを越えるように飛んでいった。気持ちよさそうだなあ。
「行っちゃった。ニッキーも人間は苦手? それなら僕一人で行くけど」
「どっちかって言うと、おいしいから好きだね。でも、たくさんいるところにはあまり近づくなって母ちゃんが言ってた。一人ずつは弱っちいけど、集まると強くなるって」
「どうしよっか。あの村、たぶんたくさん人間がいるよ」
「今日のところはもめるつもりもないし、おチビさんについていくよ」
「ありがと。ほんとは一人じゃ心細かったんだ」
話しているうちに、村まですぐというあたりまできていた。
三角屋根は木の枝と草や葉っぱをくみあわせたテントのようなものだった。
天井は大人の頭がぎりぎりつっかえないくらいの高さにみえる。
そんな家が百くらいはある。家一つに二、三人として、村人はみんなで三百人ほどだろうか。
テントは五つくらいがまとまったかたまりになっている。そのかたまりがまた五つずつくらいで円をつくって並んでいる。その円の真ん中に穴があり、そこで火を使うようになっているようだ。
僕らからいちばん近い穴のまわりで、十人ほどが忙しそうに働いていた。男も女も長い髪を後ろで一つにたばねている。ヒゲがあるのが男で、ないのが女だろう。子供も何人かちょろちょろしている。みんな着ているのは毛皮のようだ。
よく見ると、村人のほおには、指の太さほどの線が描いてあった。一本だけだけど、ネコのひげみたいだ。おしゃれなのか、家族の印かなにかか、よくわからない。赤、青、黄といろんな色がある。
つぼで何かをまぜていた二人の女の人たちが、僕たちの方を見た。
そして、ニッキーに気づくと、叫んで、飛びあがって、二人ともひっくり返ってしまった。
その近くにいた男たちも僕らに気づき、口々に叫びだした。
「大ヘビだ! また大ヘビが出たぞ!」
「女子供は恵み池までにげろ!」
「ヤリをもて!」
「長をよべ! はやく!」
弱ったぞ。
僕だけできたほうがよかったかなと思ったが、後の祭りだ。
立ち止まった僕らから少し離れたあたりに、あっという間に二十人ほどの男たちがヤリを片手に集まった。
「ヒュン!」
こちらから声をかける間もなく、ヤリが飛んできた。
木にとがった石をくくりつけただけのものだが、当たったらただではすまないぞ。
「ヒュヒュン!」
続けざまにヤリが二本飛んできて、一本がニッキーの体に当たった。かたいウロコがすべるようにヤリをうけながす。ニッキーは痛くもかゆくもないようだ。
(ニッキーは大丈夫でも、僕は当たったら大ケガしちゃう!)
ニッキーが大声をあげた。
「まちな、あんたら! あたいの頭の上をみてみな! そいつがおチビさんに当たったら、どうすんだい!」
村人たちの間にざわめきが広がった。いままでニッキーに気をとられて僕が目に入らなかったのだろう。
でも、とまどいながらも、男たちはかまえたヤリを下ろさない。
村人は五十人ちかくにふくれあがった。ヤリを何本かかかえてきて、くばりあるく男もいる。人数が増え、男たちは殺気立ってきた。
(もうダメだ…)
僕が目をつむってふるえだしたころ、するどい声がひびいた。
「まて!」
よくとおる、甲高い男の声だった。
村人はいっせいに声の主の方をふりむいた。あたりが静まりかえった。
村人たちが道をあけ、男が前に進み出た。
驚いた。
体は僕より二まわりほど大きいけれど、まだ子供といってもいいほど若い。
ほおには赤、青、黄の線が三本入っている。右手には、ヤリではなく、数珠のようなかざりを頭につけた杖をにぎっていた。

少年はニッキーの前に恐れ気もなく立つと、しずかに言った。
「わたしはこの村の長、パパンギスだ。ヘビよ、なぜヒトの子をつれて村をおそうのか」
こんな若いのに、村長さんとは。
僕は何か答えようとしたけど、舌がもつれて声にならなかった。
「このおチビさんをつれてきただけで、村をおそう気なんて、さらさらないよ。そっちがいきなりヤリを投げつけてきたんじゃないか」
ニッキーがかわりに答えてくれた。
パパンギスがするどく言い返す。
「ヘビよ、おまえはこの前の春が終わるころ、村人をおそったではないか。わたしたちはそれを忘れていないぞ。ヤリでこたえるのは当たり前だ」
そこまで一息に言うと目を上げて、ニッキーの頭の上でふるえている僕をにらんだ。
「そこの子よ。おまえはヘビの仲間か。あるいは子ヘビがヒトの子に化けて、わたしたちをだまそうとしているのか」
答えようとしても、どうしても歯の根があわない。
ニッキーがかま首を下げ、パパンギスの前に僕をおろしてくれた。地に足をつけると、少しふるえがおさまった。
「あの、僕は、ニッキーとは友だちだけど、ヘビではないよ。あ、ニッキーってのは、このヘビの名前なんだけど…」
「丸のみニッキーを知らぬものはない。友とは、どういうことか。そのヘビを、どうやって手なずけたのか」
うたがわしげに僕をにらんでいたパパンギスが、ふと、目を少し下げた。
すると、みるみるうちに顔色がかわり、赤みをさしていたほおがすっと青くなった。
「…それは…まさか…」
なにかつぶやきながら、ふいに僕の両肩をつかみ、ぐいっとまっすぐ向きなおらせた。
パパンギスの目は食い入るように胸のあたりに注がれていた。
あごをひいて自分の胸元を見下ろしてみて、パパンギスがシャツの柄をみつめているのに気づいた。
顔を上げると、パパンギスと目がばっちりあった。
パパンギスは大きくうなずき、後ろにむらがる村人たちに杖をもった右手を高くあげてみせた。
そして、上げた杖をすばやく下ろしながら僕に向きなおると、杖を地面に突きさし、片ひざ立ちでひざまずいた。村人たちもパパンギスにならった。
僕はただ、ポカンと口をあけてそれを見ていた。
パパンギスが言った。
「おゆるしください。あなたがあの方だったとは、気がつきませんでした」
12 しるし
何のことやら、さっぱりわからない。見上げると、ニッキーもかま首をかしげている。
落ち着かないので、頭をかきながらポケットに手を入れ、すべすべの石をさわった。
誰も何も言わない。僕がどう答えるか、みんな、まっているみたいだ。
でも、どう答えたものか、見当もつかない。
きまずい。
答えがわからないのに勢いで手をあげて先生に当てられちゃったような気分だ。モジモジしている自分に気づいて、もっとモジモジしてしまう。
「わたしたちには、わかります。その胸の印が動かぬ証です」
パパンギスが先にしゃべってくれてほっとした。
もう一度、胸元をみてみた。なんてことのないシャツだよな。
「その二つの柱がささえあう印こそ、あの方の証です」
僕のとまどいをよそに、パパンギスがきっぱり言い切った。
シャツには、青い生地の真ん中に太く白い線で「H」、と描いてある。
言われてみると、二つの柱がつっかい棒で支えあっているように、見えなくもない。
「あのね、これ、英語のエッチって字なんだ。印とかじゃなくて」
パパンギスはけげんな顔つきをしてから、はっと顔をふせた。
「もうしわけありません…今おっしゃったこと、さっぱり何のことだが…エーゴやら、エッチやら、ジーやら…」
「ジーじゃないよ、エッチ。あ、じゃなくて、字。ジ、だけ。のばさない」
パパンギスはいっそう困った顔になった。
「つまり…その印の名前が、ジ、ということでしょうか。わたしたちもそれを、ジ、と呼べばよいのでしょうか」
「ちがう、ちがう。印じゃなくて、字は字。で、この字の名前が、エッチなの。あーややこしい。僕までこんがらがってきちゃった」
パパンギスも村人も首をかしげるばかりだ。
まてよ。僕はようやく思いあたった。
「もしかして…きみたちは、字をしらないの? 漢字とか、ひらがなとか、なんでもいいんだけど」
「いえ…その…カンギやら、ヒラゴナというと…」
「わかった、わかった。僕がわるかった。えっとね、字っていうのは…」
困った。なんて説明すればいいんだろう。
字って、なんだろう。
みんながじっと僕を見ている。
弱ったな。どうもこのところ弱ってばかりだ。
こういうときは、とりあえず思いついたことから話すのが意外といいのだ。
大事なのは、話す中身より、相手をよくみること。
相手をみながら、話を足したり、はぶいたり、横道にいったりすると、案外うまく伝わる。お父さんの受け売りだけど。
「字っていうのは、たとえばこういうのだよ」
僕は近くのヤリをかりて、地面に「リ」「ン」「ゴ」とかいてみせた。村人たちがパパンギスの肩ごしにのぞきこむ。
「これで、リンゴ、ってよむんだ。こうしてモノの名前や言葉を、目でみえる形にしたのを、字、っていうんだ。口に出すかわりに、よんだヒトが何のことかわかるってわけ」
パパンギスは「リンゴ」の字をみつめて何度も小さくうなずくと、僕の胸を指差した。
「それでは、その印は、どんな言葉なのでしょうか」
またまた弱ったぞ。「H」って、これだけで意味なんてないよな。
「リ」だって「ン」だって「ゴ」だって、ただの音だし。
「んー。この字は、一個だけじゃ、ダメなんだ。言葉にならない。一個だけでエッチって読むんだけど、意味はない。リも、ンも、ゴもそう。音だけ。しゃべる音のかわりに字にしてあるだけ」
こんな説明でわかってもらえるかな。
パパンギスは深くうなずいた。
「では、そのジというのは、音を組み合わせる印で、生き物や食べ物を絵にかくように、言葉を木の板や土の上にうつしておくものですか」
ああ、このお兄さん、僕よりずっと頭がよさそうだ。
「そう。言葉を書きのこしておくんだ」
パパンギスはじっと考えてから言った。
「わかったようで、わかりません。なぜそんなややこしいことをするのですか」
どうしてって言われても…。どうしてかな。
「字で残しておくと、忘れずにすむし、しゃべる人がそこにいなくも、話ができる。昔の人の考えたことも、知ることができる。いろいろ役にたつんだよ」
パパンギスは何度もうなずいた。
「なんとなくわかりました。でも、その胸の印が、そのジなのかどうかは、わたしたちは気にしません。わたしたちには、その印がなにかはっきりわかるのです。それは、わたしたちの名付け親となる方が身につける印です」
また話が妙な流れになってきた。パパンギスはかまわず続ける。
「この印をもつ方が、わたしたちに正しい名前をさずけくださるのです。わたしたちは、ずっと長い間、このときをまっていました」
僕は鼻をひとしきりこすった。そして、やっとの思いでこたえた。
「あの…名無しでこまっているのは、僕の方なんだけど」
また、みんな、だまりこんでしまった。
パパンギスはひざまずいたまま、じっと考えこんでいる。
僕はなんだかえらそうにしているみたいで落ち着かない。
パパンギスがすっと立ち上がった。
「父に会っていただくのがよいと思います。印のことも、すべて父からお話いたします」
パパンギスが先にたち、その後ろに僕、ニッキーが続き、ヤリをもった男たちもぞろぞろとついてきた。女の人と子供はテントに身をかくして様子をみている。
村のちょうど真ん中に少しだけ大きめのテントがあった。パパンギスが入り口からのぞきこみ、なにやら二言、三言話すと、ふりむいた。
「父は病でふせっていますので寝たままでおゆるしください」
パパンギスにつづいて入り口をくぐった。ニッキーはかま首だけぬっと中につっこんだ。
テントの屋根は真ん中の木の柱で支えられている。
中はがらんとして、草のむしろのような敷物があるだけだ。
「よくおいでなさった」
暗がりから声がした。目をこらすと、白髪の男がむしろの上に横たわっている。
「こんにちは。パパンギスさんのお父さんですか」
「いかにも。あれの父、クパパンギですじゃ。前の夏から腰がたたなくなりましての。寝たままでもうしわけない」
顔のしわも深く、お父さんというより、おじいさんの方がぴったりくるくらいの年寄りだった。
クパパンギはじっと僕の服をみた。
「おお。せがれの言ったとおりじゃ。その衣の印は、まさにあの方の証。この老いぼれにもしっかとみえるよう、もう少し近うによって下さらんか」
僕は柱を回りこんで、クパパンギのわきにしゃがんだ。老人は苦しそうに首をもちあげると、シャツをじっとみた。ほんの数秒で、ばたっとあおむけにもどった。
「ああ、まちがいない。長い、長い間、おまちしておりました。わたしの父の、父の父の父の、そのまた父の父の父の、それよりもっと前より、我らはあなたをまっておったのです」
なんだか、いたたまれなくなってきた。
だって、どう考えたって、これは、かんちがいか、いきちがいだろうから。
「あの…僕は昨日から迷子になっている、ただの名無しです。ここには、誰か僕の親になってくれる人をさがしにきただけなんです」
クパパンギは小さくうなずいた。
「わかっておりますとも。あなたが名を求めておられることは。それも言い伝えのとおりじゃ。そして、あなたがいらっしゃったら、どうすればよいかも。おい、あれをもて」
僕のうしろにひかえていたパパンギスが、ノートほどの大きさの木の板をさしだした。板には見慣れない絵がかいてあった。
「あ」
思わず声がもれた。パパンギスがうなずく。

確かに、「H」にみえる。
「恵み池の大石からうつしとったものじゃ」
僕は板をうけとった。
ずしりと重い。
もようの黒いところは木がけずられてへこんでいて、炭かなにかで色もつけてある。
「その印には、こんな言い伝えがあります。いつか、我らの前に印を身につけた方がやってくる。その方はうその名前をもたず、正しい名前をさがしている。その方がきたら池の主をよべ。その方が正しい名前を得たときに、我らにも正しい名前があたえられる」
そう言われてから見てみると、板のもようは黒い人が白い人に、あるいは逆に白い人が黒い人に、何かを手わたしているように見えなくもない。
「で、まさか、僕が、その…」
「そうでなくて、どうだとおっしゃる。印のついた衣をまとった名を求めるもの。まちがいない」
名前をもらいにきたのに、名前をくれと言われるなんて。
ツイてるとツイてないでわけると、ツイてない、になるのかな。
「父上。わたしはこれから、池の主を呼びだしてまいります」
「いや、ちょっとまってよ。急にそんなこと言われても…僕がそんなたいそうな方とは、とても思えないんだけど…」
口ごもっていると、クパパンギが言った。
「今から呼んでも、主はすぐにはやってこない。ぼちぼち日もかたむく。姿をあらわすのは明日になるじゃろう」
一晩で心の準備をすませろってことか。強引だなあ。
パパンギスが出ていこうとするのを潮に、僕もクパパンギにおじぎしてテントの外に出た。
たしかに、もう空はうっすらと夕焼けにそまりかけていた。
「主を呼ぶって、何をするの」
パパンギスが「これから池にむかいます。ついてきていただけますか」と答えた。
13 恵み池
村のはずれの池は、小学校のプール二つ分ほどの広さで、思ったより小さかった。
池の真ん中にある石は、水の上に出ているところだけで車くらいの大きさがある。小さな池とつりあいが悪い。
クパパンギの言ったとおり、石には例の「H」の印がついている。自然にできたとは思えない、はっきりしたもようだ。
池のふちにかがんでみると、水はおそろしくすんでいた。
ミルシの滝つぼのように、光は深い、深いところまでとどいているけど、底はみえない。
この池も、地球の裏側までつきぬけているのかな。
「僕、のどがかわいてるんだけど、この水、のめるよね」
「はい。わたしたちが生きていられるのは、このくんでもくんでもなくならない池の水のおかげです。だから、恵み池とよんでいるのです」
話を聞きながら、手ですくってごくごくと水をのんだ。ついでに顔をあらって、さっきのいざこざのときにかいた冷や汗を洗いおとした。
最後に一口、水をふくんでみた。ほんのり甘い香りや味はミルシの滝つぼにそっくりだ。
「それで、主を呼ぶって、どうするの?」
パパンギスはさっと手をあげた。
それを合図に、十人ほどの男たちが池のまわりにちらばった。手にはヤリをもっている。
「ハイヤ!」
パパンギスがかけ声をあげると、何人かの男たちがヤリでパシャっと水面をたたいた。
「ソイヤ!」
こんどは別の数人が交代で池をうつ。
「ハイソイヤ!」
「ハイソイハイヤ!」
「ハイソイハイヤ!」
パパンギスは調子をとりながら、次々に合図をおくる。
どうもかけ声が振り付けの記号みたいになっているようで、そのつど、ヤリをうつ男が入れ替わる。
「ハイヤ! ソイヤ!」
かけ声がぐるりと元にもどり、あとは繰り返しになった。いつの間にか、男たちがそろって声をあげはじめている。みんな息がぴったりで、お祭りのかけ声のようだ。
パパンギスはかけ声を男たちにまかせると、少しはなれたところに僕をつれていった。そして池のふちにかがみこみ、水面に片耳をつけたまま僕にうなずいた。
僕もしゃがんで耳をつけた。ひやっとしたあと、すぐに音楽がきこえてきた。ヤリが水を打つ音が歌うように響いているのだ。
うん、これは、歌だ。うれしいときに歌いだしたくなるような、そんな歌だ。
顔をあげた僕にパパンギスがほほえんだ。
「この歌をきくと、池の主がやってくるのです」
僕はずっと気になっていたことを聞いた。
「主って、なに?」
「とても大きな、手足の生えた魚のような生き物です。数え切れないほどの夏と冬をすごしてきた、とても年寄りの」
ひとしきりヤリうちが終わると、パパンギスが男たちに手をあげて合図した。
男たちはぞろぞろと村に引きあげていった。
「あたいには、さっぱりわかんないんだけど。つまり、おチビさんの名前はどうなったのさ? ここらでみつからないんなら、よそを当たったほうがいいんじゃないかい?」
ずっとガマンしてだまってついてきていたニッキーが口をひらいた。
「そうじゃないみたいなんだ、ニッキー。といっても、なにがどうなのか、僕にもよくわからないんだけど」
ニッキーもパパンギスも、じっと僕をみている。
ここは考えどころだ。僕はポケットのすべすべ石に手を伸ばした。
パパンギスには悪いけど、僕はただの名無しの迷子だ。あの方、とか、そんな大そうなものじゃないと思う。
「H」だって、たまたまそういうシャツを着ているだけだ。
この服がとてもお気に入りなのは確かだ。
でも、なぜ気に入っているのかは、名前と同じように忘れてしまって、分からない。
あの方、とかいう落ち着かない部分をのぞくと、パパンギスの話は、すごく気になる。
うその名前じゃなくて、正しい名前ってところが。
誰でもないのがまずいから誰かの子供になるってのより、本当の名前がわかったほうがずっといい。
うん。そうだよな。
池の主と話してみよう。本当の名前をさがす手がかりがみつかるかもしれない。
僕はパパンギスにきいた。
「池の主って、ミルシのことでしょ?」
パパンギスは目をむいた。顔色がみるみる青くなった。
「その…主の名前は…口にしてはならないとされています。わたしたちは…ただ、主、と呼ぶ…のです」
なんとかここまで言うと、散々迷ってから付け加えた。
「でも、主の名前は、そのとおりです。なぜ、わかったのですか。やはり、あなたはあの方なのですね」
僕はぶんぶん首をふった。
「ちがう、ちがう。ここへくる前に、僕はミルシのところに行ったんだ。ニッキーとも、そこで友だちになったんだよ。手足の生えた魚ってきいて、ピンときたんだ。ということは、この池とあの滝つぼは、つながってるんだね。深い、深い、底の方で」
滝つぼが地球の裏側までつきぬけているという、あのとき思いついた考えは、まちがっていたようだ。僕はがっかりした。
いや、まてよ。
こことあそこと地球の裏側がみんなつながっているってこともありうるか。
よし、とにかく、考えがまとまった。
「ニッキー、僕、明日までまって、ミルシに会ってみるよ。君もつきあってくれない?」
「もちろん、おチビさんがそうしたいなら、あたいはお供するよ。なんたって、友だちだもの」
村に戻るころには夕方になっていた。
ここらは高い木がないので、見晴らしがいい。
ふりかえると、池の先に続く野原の向こうに森が広がっていて、その上に山々がつらなっている。お日様はその一番高い山のわきに沈もうとしていた。
「みなが、あなたを迎えるうたげを開こうとまっています」
「ちょっとまって。どうも、僕はその、あの方ってのに決めつけられちゃうのに弱ってるんだよね。お祝いは少しおあずけにできないかな」
「それは困ります。もうおいしい物をどっさり作って待っているのです」
あいかわらず、僕のお腹はへらない。けど、村人たちは楽しみにしてるだろうなあ。
「じゃ、みんなでごちそうは食べよう。でも、僕が何者かは、明日ミルシと話してみてから決めよう」
パパンギスは少し考えて言った。
「わかりました。たくさんめしあがってください。食べきれないほど作ってあります」
「食べきれないってことはないよ。あたいがいるんだから」
横からニッキーが口をはさんだ。僕とニッキーは目を合わせてわらった。
村の真ん中のかまどにいくと、村人たちが僕たちをまっていた。
大人も子供も年寄りも、みんなごちそうに手をつけるのをがまんしているみたいだ。
パパンギスが場の真ん中に進み出た
「ついに、わたしたちのもとに、あの方がいらっしゃった! わたしたちはやっと、正しい名前を手にできるのだ!」
村人から歓声が上がった。パパンギスが続けた。
「正しい名前がいただけるのは明日、池の主と話がついてからだ。今宵は前祝いだ! さあ、大いに食べ、飲もう!」
少しだけ村人からどよめきがおきた。それをさえぎるように、パパンギスが言った。
「ルンゴランゴをあけよ!」
ごちそうの山のなかに、リンゴルンゴの実があった。
村人たちは実のへたのあたりに木のナイフをあてると、つぼのフタをあけるようにして切りひらいた。その中に木のお椀をつっこみ、次々に白いにごったジュースをくみだした。
村人の一人が、僕に木のお椀を手わたしてくれた。リンゴジュースのいいにおいがする。
ごちそうの山は、くだものや木の実、干し肉や焼き魚などもりだくさんだ。

僕はあいかわらずお腹はすいていなかったけど、あまりにおいしそうなのですぐにでもかぶりつきたくなった。
「さあ、のもう! 歌おう!」
パパンギスの合図で村人たちはいっせいにお椀を高くかかげた。
そして、ひときわ大きな歓声をあげたあと、一息にジュースを飲みほした。
僕もまねして、ぐーっと飲んでみた。
「これ、おいしい!」
口に含むと舌にからまるようなとろみがあり、のどを通るときには甘いにおいが鼻を通り抜ける。
こんなおいしいリンゴジュース、飲んだことない!
乾杯がおわると、みんないっせいにごちそうに手を伸ばした。
「あたいもいただいちゃっていいのかね」
僕のうしろでトグロをまいていたニッキーが、ぬっとかま首を伸ばした。
これくらいのごちそう、ニッキーならひとのみだろう。
「うーん。みんながお腹いっぱいになるまで、まってあげられる?」
ニッキーはすこしがっかりした様子でトグロをといた。
「じゃ、あたいはそこらで獲物を探すとするか。じきに戻るから、おチビさんはゆっくり楽しみな」
ニッキーはそう言い残すと、うたげの輪から離れていった。
すると、それまでニッキーを怖がって近づきにくそうにしていた村人たちが僕のまわりに集まってきた。
みんな、すこしずつ僕にごちそうを分けてくれる。
つまんでみると、どれもとてもおいしい。
僕のすぐ横にすわったお母さんくらいの年ごろの村人が、にっこり笑ってリンゴジュースのおかわりをくんでくれた。
ぐいっと飲み干すと、あたりの村人から
「ほー!」
と声が上がった。パパンギスがにっこり笑いかけてきた。僕も思わずほおがゆるむ。
すかさず二十歳ぐらいのお兄さんがジュースを注ぎたしてくれる。お兄さんが器をもって乾杯のしぐさをするので、僕はまたぐーっと一気に飲んだ。
うまい!
と、思ったのもつかの間。
急に地面と空がぐるぐると回りだした。パパンギスの顔も、ナスビみたいにぐにゃりとゆがんでみえる。村人たちの声が遠くなる。
どうしたんだろう。
だめだ、立ってられない。
それでもなんとか踏ん張ろうとしたけど、だめだった。
ひざがおれ、ひっくり返ると、突然、目の前がまっくらになった。
14 遠くの声、再び
(…もっと、つよく!…)
(…ひえきっているな…)
(…まだか…)
15 カップンとの約束
ツンツンとまぶたをつつかれて、目が覚めた。
「やっとお目覚めですか。朝までぐっすりかと思って、気が気じゃなかったですよ」
「あ、カップン、どこにいたの? その前に、ここどこ?」
「ヒトの村ですよ。みんな、もう寝てしまいました。あなたみたいにリンゴのお酒をたらふく飲んで、ひっくり返ってます」
ああ、あれはお酒だったのか。
まわりをみると、たしかにごちそうの残りといっしょに村人がいっぱい雑魚寝している。もう起きている人はいないみたいだ。
「みつかるとやっかいだから隠れていました。池であなたたちがミルシを呼び出しているときも、すぐそばにいましたよ」
「ニッキーは?」
「しりません。ここらは村人が狩りで荒らしてしまっているから、なかなか獲物にありつけないのかもしれませんね」
寝起きでのどがカラカラだった。
あたりを見まわしても、リンゴのお酒が残っているだけで水は見あたらない。
「カップン、のどがかわいたから、ちょっと池までつきあってよ」
歩き出すと、カップンがふわっと肩にとまった。
「カップンも明日、一緒にミルシと話をしてくれるよね?」
「いえ、僕は隠れています」
「どうして?」
カップンは黙りこんだ。
たき火の明かりが届かないので、池のあたりにくると、ほとんど真っ暗だった。
今夜は雲が出ていて月明かりも薄い。
カップンがようやく口をひらいた。
「ミルシ親子は、一筋縄でいかない相手です」
僕は手ですくって池の水を飲んだ。
リンゴジュースよりおいしい!
すくっては飲み、すくっては飲んで、ようやく落ち着いた。
お父さんが、酔い覚めの水はカンロの味って言ってたのを思い出した。カンロってなんだろ?
「ニッキーには、そばにいてもらったほうがいいです。何かあったときのために」
何かって何さ、と聞こうとしたら、シュルシュルという音と一緒に暗がりから声がした。
「言われなくたって、あたいはおチビさんから離れないよ」
「あ。おかえり、ニッキー。お腹ふくれた?」
ニッキーは返事もしないで池に首をつっこむと、ごきゅっ、ごきゅっと音をたてて水を飲みだした。しばらくして首をあげると、牛十頭分くらいの特大のゲップをした。
「だめだね、今日は。もう水をがぶ飲みしてごまかしておくよ」
言い終わると、またすぐに首を池につっこんだ。
僕はカップンに、さっき聞きそびれたことを聞いてみた。
「ミルシの何がやっかいなの?」
カップンはまたしばらく考えこんだ。
「村人たちはミルシを呼び出すのになれていると思いませんか」
僕は呼び出しの儀式を思い出した。
「そうだね」
「村人たちは新しく子供が生まれるたび、ミルシを呼ぶのです。名前を教えてもらうために。森の生き物も同じです。子供が生まれると、ミルシの滝つぼにつれて行ったり、親が名前を聞きに行きます」
なるほど。
ヤリでかなでる呼び出しの歌がうれしそうな音楽だったのは、赤ちゃんが生まれたときの歌だからなんだな。
「で、それとミルシがやっかいなのは、どうつながるの?」
「明日、ミルシは子供が生まれたのだと思って村にくるのです。なのに、来てみたらあなたがいて、村人があなたをあの方だと言い出す。そして正しい名前をあなたからもらうと告げるのでしょう。あの親子が黙っているはずがありません」
何となくわかるけど、肝心のところが分からないままだ。
「あのさ、あの方って、つまり、何なの?」
カップンはまた考えこんでしまった。そして、言葉をえらぶように、ゆっくりと話し出した。
「僕にもよく分かりません。ただ、いつかあの方がくれば、だれもが正しい名前をもらえるのだと言い伝えられてきました。ヒトだけでなく、森の生き物たちの間でも」
カップンは少し間をおいた。
次に口をひらいたときには、ずいぶん声が小さくなっていた。
「森の生き物たちのほとんどは、そんなことどうだっていいと思っているでしょう。でも、今の名前はなんだかしっくりこない、と思っている生き物たちは、村人たちのように、いつかあの方がくるかもしれない、と待っているのです」
「カップンは僕がその、あの方だと思う?」
「分かりません」
カップンの声はいっそう低くなり、僕は聞き取るために、ぐっと耳をくちばしに近づけなければならなかった。
「トーポのところで話をしているうちに、もしかしたら、とは思いました。明日、ミルシと会ってみればはっきりするでしょう」
カップンはそんな気がしたのか。わけもなく、僕もそんな気がしてきた。
「ところで、僕を起こしたのは、何かワケがあるんだよね」
カップンはニッキーをちらりと見た。まだ首は池の中だ。それでも聞かれないように用心してか、カップンはくちばしをさらに近づけてささやいた。くちばしの先が耳をくすぐる。
「お願いがあります。次に僕に会ったときには、カピーと呼んでください。カップンではなく」
「ん? カピーって、呼べばいいの?」
「はい、忘れずに、そうしてください」
なにがなんだか分からない。
でも、カップンがあまり思いつめた顔で言うので、僕は思わずうなずいた。
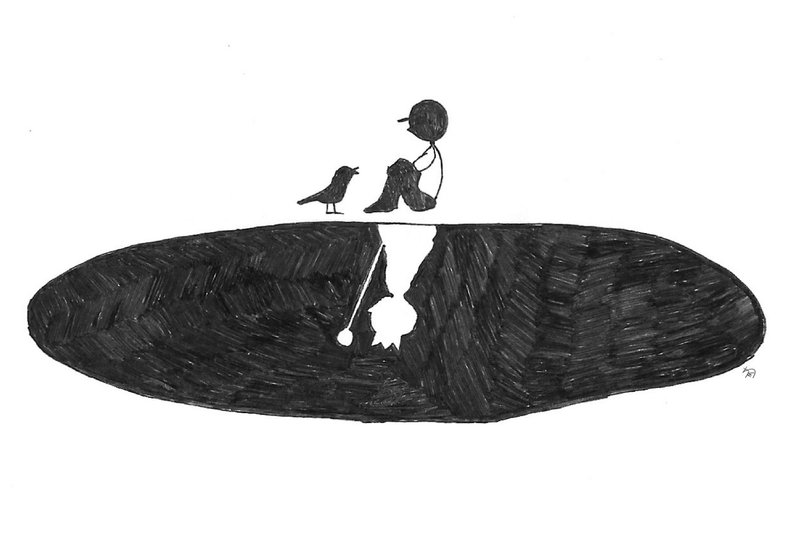
カップンは安心したようすでさっと飛びたった。
「僕はそこらでねぐらを探します。明日にそなえて、あなたたちもよく寝るといいでしょう」
あっという間にカップンの黒い姿は闇に溶けてしまった。入れ違いに、ニッキーが首を池から上げた。さっきのよりもっと大きな、超特大のゲップが闇夜に響いた。
「うい。もう飲めない」
ニッキーの体は水風船のように一回り大きくなった。
「さ、おチビさん。水っ腹がしぼんじまわないうちに、寝ようか。昨日みたいにトグロの中に入るかい?」
「うん。ありがと」
ニッキーが柔らかそうな草の上を選んでするするとトグロをまいてくれた。水ぶくれしたお腹のせいで、ちょっと丸みをおびたトグロになった。
僕は昨日よりちょっと狭めのすき間からもぐりこみ、まくらにする地面のこぶをみつけて寝支度した。
「おやすみ、ニッキー」
僕が声をかけたときにはニッキーはもう寝息を立てていた。
僕もすぐ眠りに落ちた。
16 遠くの声、三たび
(…水はもう…)
(…あとは…)
(…まだか…おそすぎる…)
17 村の朝
トグロのすき間から差しこんだ日差しが目に入り、目が覚めた。
ニッキーはまだ眠っている。
起こすのは悪いので、僕はトグロの中で朝の体操をすることにした。飛んだりはねたりはできないけど、背伸びしたり、手足を動かすには不自由しない。
ふとんなしで二晩寝て、体中が痛い。
あっちを伸ばし、こっちを伸ばし、一通りほぐれたころ、トグロの天井がさっと開いた。
「おはよう、ニッキー」
「おはよう、おチビさん。朝から張り切ってるね」
僕は池のほとりに寄って冷たい水で顔を洗った。
ニッキーはかま首をつっこんでまた水を飲んでいる。
「おはよう。よく寝られましたか」
ふりかえると、パパンギスが立っていた。
「昨日はすばらしい飲みっぷりでしたね」
「お酒だとは思わなかったんだよ」
パパンギスは用心深くニッキーに目配りしながら、僕の近くまで来てささやいた。
「主はおそらく昼前に姿をあらわします。今は日の出と昼のちょうど真ん中ころです。村のものたちもそろそろ集まってくるでしょう」
そうだ。これからミルシに会うんだった。
「僕はどうしたらいいのかな? 何かやっておくことある?」
「いえ。あなたは、ありのままで良いのです。あなたがあの方なら、おのずと道は開けます」
そんなものか。
でも、訳が分からないままミルシと話をするなんて、気が進まない。
僕の心配を見透かすように、パパンギスが言葉を足した。
「父があなたと主を仲立ちします。今、若者たちが父をのせるみこしを整えています」
そうこう話しているうちにも、村人たちが一人、また一人と集まってきた。
「来ました」
パパンギスの声にギクッとして池をみた。早すぎるよ!
ミルシが来たと思ったのは僕の早とちりだった。パパンギスの目を追うと、木の棒で作ったみこしみたいなものを強そうな若者がかついでいる。クパパンギだった。
僕たちの脇までくると、クパパンギは板のうえで首を起こした。
「いよいよですな。なに、すべて、わしに任せてくだされ」
クパパンギの目の色や顔つきは昨日とはまるで違った。今にも立ち上がってヤリをかついで走り出しそうだ。
「何がなんだかわからないので、とにかくお任せします」
若者の一人が、腰にくくりつけてきた毛皮の袋を僕にさしだした。
中身はリンゴだった。リンゴルンゴの特大の実ではなく、普通のリンゴだ。朝ごはんってことか。
「ありがと」
僕は実にかぶりついた。うん、うまい。
リンゴを食べ終わるころには、池のまわりは村人たちでいっぱいになった。パパンギスは大きな石の上に立つと大声で語りかけた。
「みなのもの。もうじき、主があらわれる。主と、この方と、父が話をする。誰も口をはさんではならぬ。ヤリにも手をかけてはならぬ」
村人たちはしんと静まりかえった。男たちはヤリを次々に近くの地面につき立てて、手ぶらになった。
パパンギスはそれを見届けると、石から降りてクパパンギの横に立った。僕をはさんで右にニッキー、左にクパパンギ親子が並ぶかっこうになった。みんなの目は池の水面に集まっている。
僕はずっと気になっていたことをパパンギスに聞いた。
「村人とミルシって、あまり仲良くないの?」
パパンギスはじっと目をつむると、長いこと黙りこんだ。
寝ちゃったのかなと思ったころ、すっと目が開いた。
「わたしたちは、かけがえのない名前を、主から授けられます。でも、村人のなかには、よそ者のケモノから名前をもらうのをきらうものもいます」
パパンギスは一息継いだ。
「でも、勝手に付けた名前は長持ちしないのです」
「どういうこと?」
「勝手に名付けた赤子が育ち、歩き出し、話し出し、賢く、体も強い子供になったとしましょう。でも、なぜかある日、その子の別の名前に誰かが気づいてしまうのです。いつ、どうやってかは分かりません。朝起きると、父や母や村人たちが、その子の名前が変わっているのに気づくのです」
「それでどうなるの?」
「おしまいです。新しい名前を呼ばれたとたん、その子の心はバラバラになってしまうのです。昨日まで走り回っていた子が、目をおよがせて、ずっと座ったままになります。古い名前を呼んでも、もう答えません」
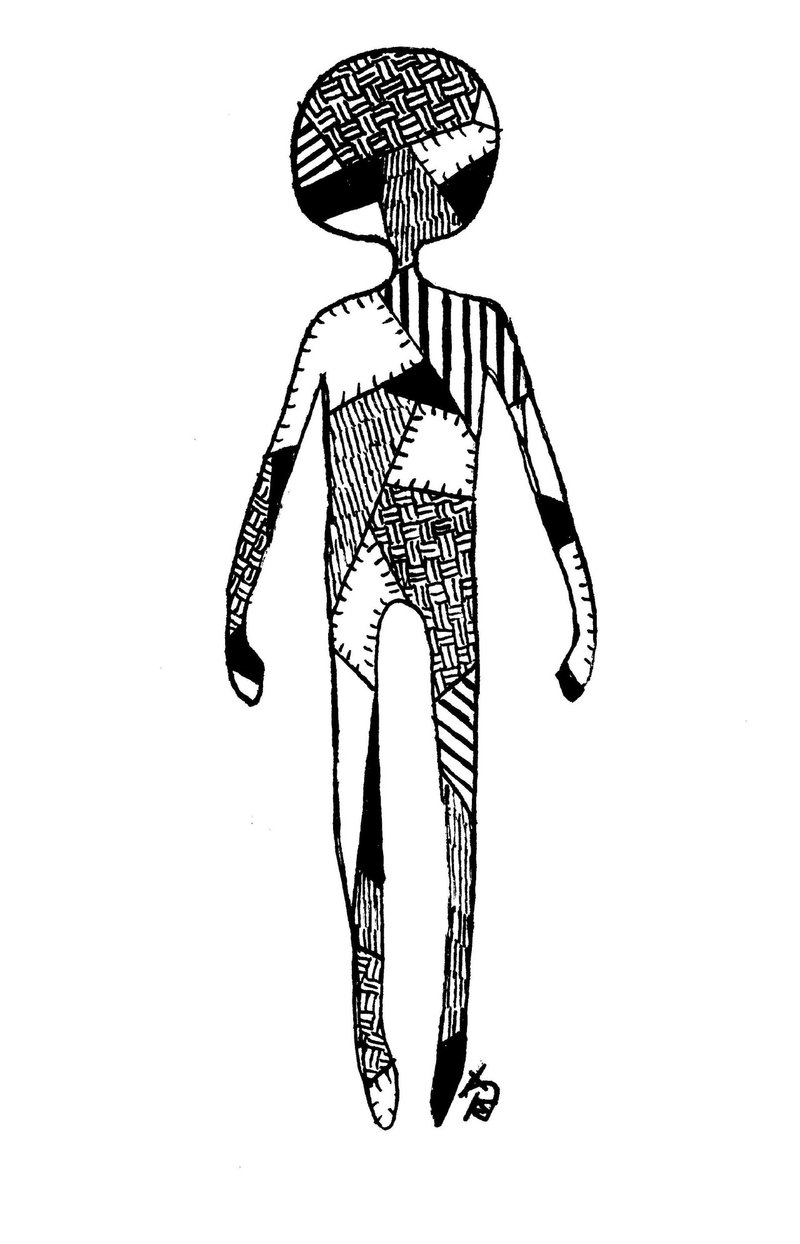
僕は息を呑んだ。
「その子は、ずっとそのままなの?」
パパンギスは首をふった。
「月が幾度か満ち欠けするころには、少しずつまともになります。でも、元には戻りません。すっかり別の子になってしまいます。話し方や、笑い方まで」
まるで、カピーだったのにカップンに戻っちゃったカップンや、名無しからカピーになってまた名無しに戻った僕と同じだな。
「あのさ、実は僕や友だちのカラスもさ…」
「しっ!」
パパンギスがするどい声でさえぎった。
「来ました。主です」
池に目を向けると、ちょうど「H」の石と僕たちをむすぶ真ん中あたりに、ブクブクとあわが立っていた。
池のふちに近づいてのぞきこむと、ずっと深いところにかすかにゆらりと揺れる黒い影がみえた。
18 秘密の名前
ミルシの気配に気づいた村人たちが、いっせいに片ひざでひざまずいたり、土下座したりしだした。
パパンギスはクパパンギの乗ったみこしの横で踏ん張るように立っていた。僕も立って待つことにした。
ザバッと大きな音がして大きな頭がのぞいた。
僕の頭ほどもある目玉をぬめりと光らせ、ミルシは静かにこちらに近づいてきた。
体を半分岸にのり上げ、僕たちとまっすぐ向かいあった。
「まだ生きておったか、クパパンギ」
低い、ゆったりした声だった。大ミルシだ。
「名を知りたい赤子はどこだ」
「主よ。今日は赤子が生まれたから来てもらったのではない」
クパパンギがきっぱりと言った。パパンギスに支えてもらって体を起こし、体も目も声も力がみなぎっている。
「では、何事ですか」
甲高い別の声がした。中くらいのミルシだ。
「話がある。ほかでもない、ここにおわす方のことじゃ」
大ミルシの口の端から中ミルシの顔がのぞいた。
「この方の衣と、主よ、そなたの後ろにある石の印を見比べてみよ」
クパパンギの声に力がこもる。
「この方こそ、我らの待ち望んだあの方なのじゃ」
大ミルシが僕に向かってゆっくりと首をめぐらせた。
その拍子に、中ミルシの体が口からぬるりと抜け出た。
「あなたは名無しの迷子でしたね」
中ミルシの声は冷たかった。僕のほうを見てはいるけど、言葉はクパパンギに向けられているように感じた。
「繰り返そう、主よ。この方こそ、あの方なのじゃ。胸の印がはっきりそう告げておる。これからは、この方が我らに正しい名を授けてくださる。我らには、主よ、そなたはもういらない」
池のまわりから音が消えた。誰も、大ミルシでさえ、ひと言も声をあげなかった。
どのくらいたったのだろう。
ほんの少しだったような気も、ずっと長い間だった気もする。
とにかく、僕は後ろからシャツのえりをぐいっと引っぱられるまで、身動き一つできなかった。
「あたいの後ろに隠れな」
ニッキーだった。
僕が引っ張られて後ずさりすると、するどい、耳障りな声が響いた。
「逃げる気か!」
目が合うと、中ミルシの顔も、声も、一変していた。
口は大きく裂け広がり、さらに甲高くなった声は細くふるえ、心をざわつかせるようにひび割れて響いた。
村人たちがおびえる声をあげ、子供は泣き出した。
僕をにらみつける中ミルシの目が、赤く光った。
「面白い! たかが名無しの迷子ごときが、わたしたちにとってかわるとは!」
中ミルシはクパパンギに顔をむけた。
「おい、老いぼれ。くたばりかけておかしな夢をみたようだな。そいつがあの方とやらかどうか、ひとつ、これから試してやろうじゃないか」
中ミルシの言葉を合図に、大ミルシが池のふちに前足をかけてガバッと体を立てた。
大ミルシの肌は火の入った炭のように赤黒く光りだしていた。
パパンギスはヤリを構えてクパパンギを守ろうとしている。
村人たちも地面に突き立てたヤリに手を伸ばした。
そのときだった。
突然、高く、するどい音が鳴り響き、頭に割れるような痛みが走った。
あわてて耳をふさいだが、とても立っていられない。
僕はその場にしゃがみこんだ。
中ミルシをみると、顔が裏返ったかと思うほど大きな口をあけ、天を仰いでいる。
この音は、こいつのせいだ。
音は耳を押さえた手のすき間から容赦なく滑りこみ、頭の痛みはひどくなるばかりだ。
パパンギスは何とかヤリを構えているが、片ひざをついて苦しそうにしている。
村人たちはうずくまったり、のたうちまわったりしている。
クパパンギは気を失ってしまったようだ。
大ミルシは、後ろ足で立ち上がり、僕たちを追い詰めようとしていた。
下から見上げると、津波がおおいかぶさってくるような重苦しさを感じる。
ズシン。
大ミルシが一歩、僕たちに近づいた。
逃げなきゃ。
でも、体が動かない。
もうだめだ。
と、観念したそのとき、僕の手を誰かが引っぱり、耳のおおいが引きはがされた。
頭の痛みが鋭くなる。
「………ド!」
パパンギスが何か叫んでいる。
苦しそうに顔をゆがめながら、両手を僕の耳元に押し当てた。
「ポド…ド!」
中ミルシの雄たけびにかき消されてはっきり聞こえない。
こんなときに、何だって言うんだ?
「あ…たの、なまえ、…ドモ…」
名前?
僕の名前?
ズシン。
大ミルシはもう目の前だ。
パパンギスが手をどけて、じかに口を耳の穴にくっつけた。
「ポド、モド! ポド、モド!」
やっと聞き取れたのは、例の、おかしな名前だった。
「ポドモド? それがどうかしたの?」
「もっと、大きな、声で!」
えい、もう、やけくそだ。
「ポド!モド!」
僕は今まで生きてきたなかで、一番の大声を張り上げた。

耳をつんざく中ミルシの雄たけびがおさまり、急にあたりは水を打ったように静かになった。
聞こえるのは子供たちの泣き声だけだった。村人たちも顔をあげ、こちらをみている。
「ポドモド!」
パパンギスが叫んだ。
「ポドモド!」
「ポドモド!」
村人たちが続く。
その声が耳に入るたび、からだの中から強い力がわいてくるのを感じる。
「その名をどこで知ったのか。その名はこの世にあってはならないものだ」
大ミルシが低い声で言った。肌をいっそう赤く光らせて、目をパパンギスに向けた。
「クパパンギのせがれ、お前か」
パパンギスは体を起こし、ヤリを握りしめている。
「この日、この時まで、我らが語り継いできたのだ。主よ、お前の覚えている名前のなかに、この名前はあるまい」
「思っていたより、お前たちはやっかいな親子だったようだな」
中ミルシが耳障りな高い声で叫んだ。
「これまでだ。おとなしく新しい親を探せばよかったものを」
中ミルシは向きを変えてまっすぐ僕を見ると、大きく口を開いた。のこぎりのような鋭いキバが並んでいる。
「おい名無し、お前が先だ。老いぼれとせがれはその後だ」
中ミルシは身をかがめると、体に力をこめた。
「シャー!」
次の瞬間、不気味な叫び声とともに、黒い影が宙に舞い、僕めがけて目にもとまらぬ素早さで飛びかかってきた。
やられた!
僕には、目をつむってしゃがみこむくらいしかできなかった。
あれ。おかしい。
確かに襲いかかられたはずなのに、どこも痛くない。
どうなったんだ?
僕はおそるおそる顔を上げた。
そこには、かま首をもちあげたニッキーがいた。
「あたいの友だちに手を出すやつは、ただじゃおかないよ!」
中ミルシは、見当たらない。
キョロキョロまわりを見回していると、くぐもった妙な声が聞こえてきた。
中ミルシのあの嫌なさけび声だと気づいたが、音はずっと小さかった。
ニッキーが一つ、大きなゲップをした。
「ひどい味だ」
ようやく分かった。
ニッキーが、飛びかかってきた中ミルシをのみこんだのだった。
19 決着
「大ヘビよ。わが息子と孫を吐き出せ。今ならゆるしてやろう」
そうだ。中ミルシの口の中には、小さいミルシもいるんだった。
「さもなくば、お前の命はない。腹を切り裂いてやる」
大ミルシの怒りにふるえる声は、打ち上げ花火を近くでみたときのように、僕のお腹に響いた。池の水もふるえている。
ニッキーは目を真っ赤にしてかま首をさっとめぐらせた。
「へっ! あいにく、あたいはのみこんだ獲物は吐き出さないことにしてんのさ。毒入りの友だちだけは別だがね」
大ミルシとにらみあいながら、かま首を揺らして体を折りたたんだり、伸ばしたりしている。特大のばねが伸び縮みしているみたいだ。
でも、これはどうみても、ニッキーの分が悪い。
大ミルシが大きすぎるのだ。
いくらニッキーでも、ひとのみにはできっこない。
「では、死んでもらおう」
ズシン。
大ミルシが一歩、前に踏み出した。
ニッキーはいっそう身を小さく折りたたむ。
ズシン。
あと一歩というところまでくると、大ミルシは大きく足を振り上げた。
踏みつぶすつもりか!
ニッキーは身を縮めたまま、動かない。
大ミルシの足がふり下ろされたと思ったそのとき、ニッキーがばねのように体を伸ばして飛び上がった。
「踏みつぶそうったって、そうはいかないよ!」
ニッキーは大ミルシの足をかわして、太い首に巻きついた。
「ウ、ウ、ウグ、グ…」
ふいをつかれた大ミルシが苦しそうなうめきをもらす。
ニッキーは容赦せず、しめつけをいっそう強くした。
大ミルシの体が、赤黒くそまる。
もがけばもがくほど、ニッキーの体が首にくいこんでいく。
大ミルシは、首を縛り上げられた巾着袋みたいになっていた。
「まだまだ! とどめはこれからだよ!」
そう言うやいなや、ニッキーは裂けよとばかりに口をひらき、大ミルシの大きな頭にかじりついた。
「あ!」
無茶だ。
ニッキーはゆっくりと大ミルシをのみこんでいった。
一口のみこむたび、ニッキーの体は風船みたいにふくらんでいく。
どうやってあんな大きなものがお腹に収まっていくのか、僕には分からなかった。
まるでゾウをのみこんだ、お話のなかのヘビを目の前で見ているようだった。
僕はニッキーの苦しそうにゆがんだ顔を見た。
あんなに広げたらあごは痛くてしょうがないだろうし、口がすっかりふさがって息だってできないはずだ。
僕は胸が苦しくなった。
「ニッキー、無理だよ! 吐き出して! ニッキーが死んじゃうよ!」
駆け寄ろうとしたとき、パパンギスに肩をつかまれた。
「巻き添えになります。あなたに何かあれば、あの大ヘビだって悲しむでしょう。あなたには、ほかにやるべきことがあります」
「やるべきことって?」
「あなたの力を使うのです」
「僕の力?」
「あのヘビに、名前をお与えください」
こんなときまで名前か!
「そんなこと言ってる場合じゃないよ!」
パパンギスは引き下がらなかった。
「あの者をじっと見るのです。そして、正しい名を呼ぶのです」
僕は振りかえってニッキーを見た。
もう大ミルシを半分ほどのみこんでいる。顔はさっきよりもっと苦しそうだ。
「目を、あの者の目を見るのです」
パパンギスの声がニッキーにも届いたのか、僕らの目が合った。
「ポドモド!」
「ポドモド!」
中ミルシの叫びから解放された村人たちの呼びかけが、だんだん大きくなっていく。
僕は、体に力がみなぎるのを感じた。
気がついたら、僕の口が自然に動いていた。
「クチルナ」
パパンギスが後ろから僕の肩を痛いほどつかんだ。
「もっと、大きな声で!」
戸惑いながらも、その声に背中をおされるように、僕は大声を張り上げた。
「クチルナ!」
その声が耳にとどくと、苦しそうにしていたニッキーの顔が力強さを取り戻し、見開いた目がきらりと光った。
そして、次の瞬間、大ミルシのお腹から足までを一息にのみこんでしまった。
ズーン、と大きな音がした。
大ミルシをのみこんだニッキーが、力尽きるように地面に倒れ込んだ。
「ついにやった!」
「大ヘビが主をたおしたぞ!」
村人たちが声をあげた。
僕はニッキーというか、クチルナというか、とにかく、僕の大事な友だちの大ヘビに駆け寄った。
「大丈夫?」
本に出てきたゾウをのみこんだヘビよりも、もっとお腹がふくらんでいる。
「やあおチビさん…さすがのあたいも、こんなにお腹がふくれたことはないよ」
僕の友だちは、苦しそうにあえぎながら、かま首をこちらに向けた。
「クチルナってのは、おチビさんが考えてくれた名前かい? いさましくて、あたいにぴったりだね。たよりなさそうなニッキーってのより、ずっとしっくりくるよ」
クチルナが大きなゲップをした。
「それより、おチビさんの名前は分かったのかい? ポドモドってのが、あたいの友だちの名前ってことで、いいのかい?」
クチルナとちがって、僕には、新しい名前はぜんぜんしっくりこなかった。
ポドモドなんて。
変なの!
「間違いありません。この方は、ポドモド様です」
パパンギスが口をはさんだ。
僕は首をふった。
「悪いけど、とてもそうは思えないよ。ポドモドなんて、そんな変な名前、聞いたこともないし」
「でも、言い伝えのとおり、あなたは主を倒しました。そのヘビに正しい名前と力を与えたではないですか」
それはそうだけど、とにかく、しっくりこない。
僕はポケットに手を入れて、小石に手をふれた。
こんども、あまり落ち着いた気持ちにはなれなかった。
「だいたい、ポドモドって、何なのさ?」
パパンギスがまっすぐ僕を見た。
「誰よりも早く名前を持つもの、の名前です」
ますます訳がわからない。
僕はまた、首をふった。パパンギスの顔がくもった。
「ポドモド様」
クパパンギの声がした。中ミルシの雄たけびで気を失っていたのが、ようやく治ったのだ。
「ポドモドというのは、今は使われなくなった、古い、古い言葉なのですじゃ」
クパパンギはひと言ずつ、区切るように話した。
「もとはそう難しい言葉ではない」
「じゃあ、やさしく言うと、どういう意味?」
「はじめの、という言葉じゃ」
クパパンギが言い終わらないうちに、目がくらみだした。
池や地面、パパンギスたちやクチルナまで、すべてがいっせいにぐるぐると回りだした。
「おチビさん、どうしちゃったんだい?」
クチルナの声がする。
めまいはひどくなるばかりで、自分がどっちを向いているのかも分からなくなってしまった。
怖くなって、目をつむっった。
でも、体がゆさぶられるような感じは消えない。
耳鳴りがする。まわりの音がうまく聞き取れない。
もう、目が覚めているのか、夢の中なのかも分からなかった。
ああ、遠くで、誰かの声がする。
(…じめ…おい…しっかりしろ…)
これは、聞きなれた、大好きな人の声だ。
「…ドモドさま…ポド…」
パパンギス?
(…よし…もうすこし…)
誰だろう、これは。
「…チビさん…どうしちゃった…」
クチルナ?
(…はじ……じめ…)
「…オレさ…カピー…カピー…ピー…」
ああ、今の声は…。
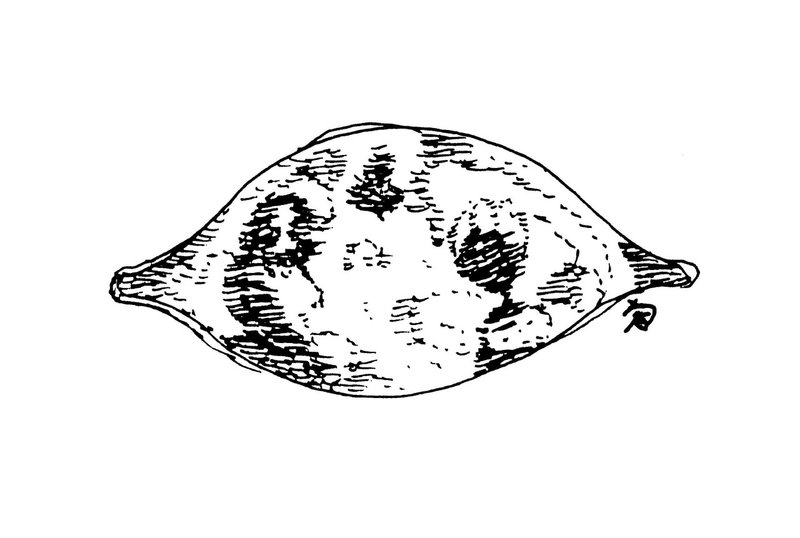
20 森の池
「ハジメ!」
日の光が痛いほどまぶしい。
「大丈夫か、一! ああ! よかった!」
あれ、お父さん、泣いてる。
いつもは僕がころんで涙ぐむと、男なら泣くなって言うくせに。
さむい。
と思ったら、髪の毛からお気に入りのシャツ、くつまで、びしょぬれだ。
僕はお父さんに赤ん坊みたいにだっこされていた。
「もう大丈夫。もうすぐ救助隊がきてくれる」
「お父さん」
しゃべってみて、自分の声があまりに弱々しいのでびっくりした。
「僕、なんでこんなびしょぬれなの?」
「池に落ちたんだ。カエルでも取ろうとして、足を滑らせたんだろう。お父さんが見つけたときには気を失って池にうかんでいた」
そうだ。思い出した。
池で特大のカエルをみつけたんだ。
いや、あれはカエルなんかじゃない。
いつか図鑑でみた、オオサンショウウオだったはずだ。
「お前、息してなかったんだぞ。この人たちのおかげでなんとか助かったんだ」
僕はまわりに立っている大人たちを見上げた。
夫婦っぽいおじいさんとおばあさん、それにヒゲを生やして大きなリュックサックをせおったおじさんが、僕をじっと見ていた。
僕はヒゲのおじさんに聞いた。
「おじさん、この池、オオサンショウウオがすんでない?」
おじさんは怪訝な顔をして、こう言った。
「ああ、聞いたことがあるな。ここらの池に、天然記念物がいるとか、いないとか」
おじさんがくすくす笑い出した。
「しかし、ボウズ、大したヤツだな。あわや死にかけたってのに、逃した獲物が気になるかい」
くすくす笑いがカッカとした大笑いに変わり、つられてみんな笑い出した。
お父さんの顔が泣き笑いでくしゃくしゃになった。僕も少しだけ声を出して笑った。
「うん、大丈夫そうだな、一。よし、その森の先の山小屋で暖が取れる。おぶってやる。行こう」
「いいよ、おんぶは」
僕は体を起こそうとした。でも、まったく力が入らない。
「ボウズ、こんなときくらい、おやじさんの言うとおりにするもんだ」
ヒゲのおじさんが僕の頭をなでた。
僕はお父さんの丸っこくて温かい背中にへばりついた。
僕らの後に、おじいさんとおばあさんが続く。
ヒゲのおじさんは、救助隊とすれ違いになるといけないからといって池に残ってくれた。
木々がみっしり葉を茂らせていて、森の中はひんやり冷たい。
お父さんとくっついているお腹や手足は温かかった。
「お。ちっこいカラスや」
おじいさんがつぶやいた。
おじいさんの目の先、山道から少し入った木の枝にカラスがいた。

カラスはじっとこちらを見ている。
僕らが少し進むと、カラスも次の木をみつけてさっと飛び移り、またこちらを見る。
「人懐こいカラスやな。あとをつけてきよる」
おじいさんが笑うと、おばあさんも「ほんまやなあ」と笑った。
僕とカラスの目が合った。
「カピー…」
ふいに口から言葉がもれた。
「ん? どうした、一。さむいか?」
お父さんが肩越しに顔を向けた。
「カピー!」
僕は、考えるより先に、声を振り絞っていた。
カラスの耳にも届いたはずだ。
カラスは二度、三度、枝の上で翼をはばたかせた。
「おい、大丈夫か?」
お父さんが心配そうに僕をみた。
「ううん、何でもない。大丈夫だよ」
僕はお父さんの目をみかえして、できるだけ元気に聞こえるように答えた。
目を戻したときには、もう、木の枝にカラスの姿はなかった。
「カア、カア、カア」
鳴き声をたよりに空を仰ぎ見ると、黒い小ぶりのカラスが、くるりと円をえがいて飛んでいた。
カラスはそのまま森を越え、元気いっぱいに、どこか遠くに飛び去っていった。
(おわり)
===========
ご愛読ありがとうございます!
ツイッターもやっています。フォローはこちらから。
経済青春小説「おカネの教室」も絶賛ヒット中!ぜひご一読を!
無料投稿へのサポートは右から左に「国境なき医師団」に寄付いたします。著者本人への一番のサポートは「スキ」と「拡散」でございます。著書を読んでいただけたら、もっと嬉しゅうございます。
