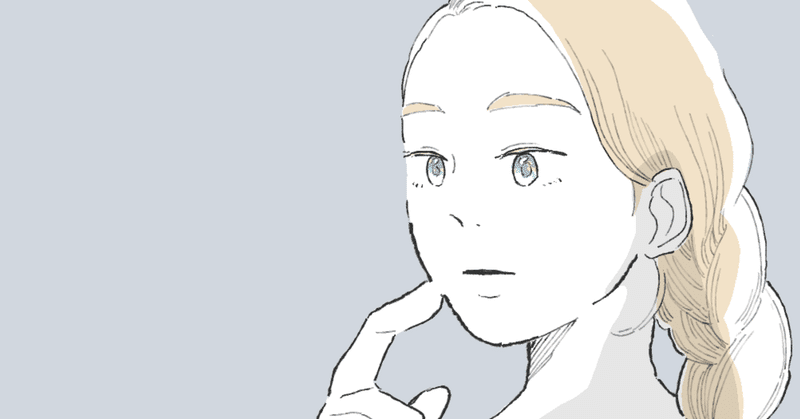
ハラスメント相談窓口に、エッセイを書いた
傷ついた言葉を残すなんて、性格がわるい。
「今日はどうですか?」
愛する人に聞きたいことがある。淋しさと比例して、独り言が増えた。声を、物語のように伸ばしながら生きている。窓も割れんばかりに声を張り上げて歌いたいときもあれば、ささやき、自分にだけ渡す声帯と色彩。
「わたしは大抵、恵まれている」
そう思うことにした。
捻れる心と、弧を描く太陽。
宙の瞬きみたいに、人は強くなっていく。
外側しかさわれない。むしろ撫でるふりをして、ふれてすらいない。「大丈夫だから」と言って、相手の方を見て自分に言い聞かせている。
「人が好きだ」
でも、人が好きなんじゃない。わたしは「おしゃべり」が好きなのだと思う。それできっと、結果的に人が好きになる。
毎朝起きて、ベランダで育つ植物の様子を見ている。詳しくもなければ、詳しくなろうともしていない。水が好きか、光が好きか、なんとなくは知っているけれど、ぜんぶそれが「正解」じゃない。99%、周りに合わせた方がうまくいくとしたら、君が1%かもしれない。だからずっと「表情」を見て、寄り添っている。 愛をお互いで、渡し合っている。
「隣にいると香るし、泣いちゃうよ」
傷つける、それは怖いことだ。けれども、自分自身が傷つく、それに勝る恐怖がいまのところ思いつかない。自分に一番やさしく生きる。自分を犠牲にして誰かを守るのは、もうやめる。
考えすぎてしまうから、起きて、決めていた。快楽と冷たさが混ざったカーテン。ゆっくりとそれを開け、愛する人の瞳に朝が入りすぎないように。「一生、離れないよ」じゃない、「今日も一緒にいよう」が、一生続いたらいい。
わたしは恋人の彼と、一つ屋根の下で暮らしている。焼けた針を刺され、痛んだ胸と向き合っていた。昨日、たった一言叫んだだけで喉ががらがらだ。彼の前ではいつもおしゃべりのわたしも、少し哀しそう。保護者みたいなもうひとりのわたしが笑っている。「自分」だけだとしても、味方がいるのだ。恵まれている、ほんとうに、恵まれている。
三週間ほど前、彼がパニック発作で倒れ、救急車で運ばれた。それがきっかけだったのか、病院では「うつ病」と診断され、いまはわたしの隣で療養している。
言うまでもないが、いまも彼を愛している。倒れたその日、わたしは職場である飲食店で働いていた。「家族」のわたしに病院から連絡が来たので、すぐさま店を抜け出す。「恋人が倒れたので、行ってきます」。もちろん、店の状況を判断し、周りの従業員には許可をいただいた上でだ。
それが今度、わたしへの"きっかけ"になった。
今年28歳のわたしへは、日常的に降りかかる話題がある。恋人の存在や、結婚についてだ。別に「おしゃべり」の中であれば、なにも言うことはない。ただ相手からの無意識な口撃と"何故か"日々闘っている。「彼女早く作った方がいいですよ」「結婚できなかったら両親が悲しみますよ」と、なんとなく心に空洞を掘り、流していた。直接抱けば、それだけでわたしの感情は埋もれてしまう。
そして、そこからさらに日常は、痛い方へと変わる。
「ゲイだったんですね」
今度は失望に似た色で、わざわざ確認をされる毎日になった。いままで恋人の、彼の存在を隠していたわたしがわるかったのかもしれない。
後日、恋人の元へ走ったわたしに対する周りの疑問は「彼女いたんですか?」だった。それに対して、冷静さを欠いたわたしが返した言葉は、「男の恋人がいます」の一言。いまでも思う、間違っていない。ただそこから、土砂降りのようにわたしへの口撃が職場で始まってしまった。
「ゲイなの?ウケる。絶対長続きしないじゃん」
「女同士ならまだしも、男同士は気持ちわるい」
「ゲイの人、邪魔なんですけど」
「ゲイが男の客と話してる」
「ゲイに好かれたら怖いね」
「泣くなよ、こっちがわるいみたい」
「やっぱり女々しい」
「女みたい」
「男なのに力がない」
「ゲイだと思ったら、なんかキモチわるい」
ひとりで、ただ黙々と言われてきた言葉を並べている。わたしは性格がわるいのだろうか。
尖った言葉が伝染し、従業員のほとんどから針を刺される。あっという間にわたしは孤立していた。
ひとつも言い返せなかったのだ。それで相手を傷つけるのが怖かった。自分がされていることを、自分から"イジメ" や、"セクハラ"と叫べない。
愛する人がいるだけで、こんなことになると思っていなかった。持て囃されたかったわけではないが、認めてもらえるとどこかで安心していた。ここで彼とのエッセイを書いている日々、添えてもらえる言葉はいつだってやさしかったから。
誰かに言ってもらいたい、助けてもらいたい。その感情は、動かずに「愛されたい」と願う瞬間に似ているのだろうか。わからない、ずっと。ただ動かず、濡れたサンドバッグになっていたわたしが昨日職場で、初めて「声」を上げた。「五月蝿い」と。
意思のない塊かなにかだと思っていたのだろう。声を聞いた相手は、わかりやすいくらいに怯んでいた。そこから特に謝られるわけでもなく、スッと、わたしをより鋭く軽蔑するような視線を向けられる。人を傷つけるのが怖かったわたしは正直、ほんの少しだけ後悔をしている。ただそれを吹き飛ばせるほど、彼の隣で愛を蓄えている。気づけば今日、店の本社へ言葉を送ることができる、「ハラスメント相談窓口」のサイトをわたしは家で見ていた。
知っている人も多いかもしれないが、2020年6月から「パワハラ防止法」ともいわれる労働施策総合推進法が改正されていた。
やはりわたしは、恵まれている。企業には、ハラスメントに関する相談に対応する義務が生まれていたのだ。当然、うちにもそれがある。
使う。自分の意思で、闘うのだ。
.
.
初めてのことは緊張する。
彼と初めてキスをした、体を重ねた。街で手を繋いだ。彼の前でワンピースを着た。そして、笑った。愛し合っていたから。
わたしたちの想いは残せる。だからここ(note)で、エッセイを書くのがわたしは好きだった。
「書かなければいけない」
仕事の文章でも、プレッシャーを感じている文章でもない。書いて、自分が伝える存在だと思っていたから、立ち上がっていた。
このままではわたしを救ってくれた言葉が傷つけられた言葉で埋もれ、見えなくなってしまう。それは、いやだ。どんなことをされてもわたしは許すしかできない人生だった。その理由は、わたし自身が許されたかったから。
けれどもう、違う。
わたしは許さない相手を決め、正当に闘う道を選んでいた。
窓口へ向けて、わたしが受けてきた言葉を並べる。それだけではない。状況や、彼とわたしの関係。相手と、わたしの関係。丁寧な言葉を使い、怒りの言葉、涙の言葉は一滴もこぼさない。
わたしは変わる。サンドバッグから昨日、卒業したのだ。意思のある、「人」になるのだ。
.
.
「でもこれを送るのって、また"迷惑"になっちゃうかな」
心から漏れる音。
この窓口はあるだけで、本当は誰の話も聞きたくないんじゃないかと失礼な考えが浮かぶ。「いつでも相談乗るよ」と昔、わたしに言ってくれた上司は、いざわたしが泣きながら寄りかかったとき、手で払うような動きをしていたから。
ぜんぶがそうではない。
むしろわたしは、1%しか知らない。
真剣に見つめ、ふたたび文章を窓口へ向かって書いていた。必死に、必死に。何度も手が止まった。それでも想いを綴る。ただ折れそうだ、やっぱり辞めよう、わたしが飲み込めば、"全員"、平和でいられる——
「感情」が、彼に香ったのだろうか。
ベッドの上で休んでいた彼がわたしに向かって言葉をくれた。
「しをりさん、いま"エッセイ"を書いていますか?」
ひょいとわたしの近くに顔を寄せながら、しゃべる。いつもと違う表情をしていたのだろうか。普段パソコンで文章を、エッセイを家で書いているわたしだが、彼は基本そういうとき、なにも言わずに隣にいてくれる。その彼が珍しく、笑っていた。口元からさらに零れる、一滴の言葉をわたしは掬う。
「あまりに綺麗で、声をかけずにいられませんでした」
◇
闘うわたしを、「綺麗」と言ってくれた。
愛する彼が、背中をさすってくれた。
愛する彼が、背中を押してくれた。
療養中の彼には、わたしが職場で受けている状況を伝えていない。わたしひとりで闘おうと思っていたから。けれど、伝わったのかもしれない。大切な彼が、わたしと一緒に闘っている。
「『エッセイ』を書いているんだ」
そう思えた瞬間、わたしの手は艶めき、瑞々しく動き出す。想いを乗せ、窓口へ言葉を送信していた。
傷つけ返すのが目的ではない。わたしは自分で自分を尊重する選択をしている。
返信はすぐには来ないかもしれない。
それこそ本社で丸め込まれてしまうかもしれない。
なかったことにされてしまうかもしれない。
そうだとしても、ここにわたしが書いて、残している。「声」をきちんと出した、そんな自分を今日は褒めてあげたい。
わたしの行動が、また他の誰かに伝わってほしい。
"許さない"という言葉を柔らかく言い換えるのであれば、口撃してきた相手を、わたしは"救いたい"。二度とあなたが、人を傷つける意思を持たないように。
そのために書いている。
伝えたいことがある、人生。
これからも、わたしは残していこう。
わたしここでエッセイを書いていて、よかった。
書き続ける勇気になっています。
