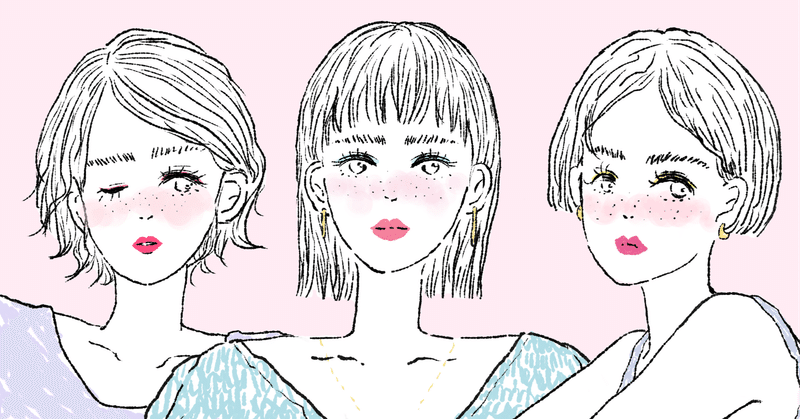
ツイートがバズったわたしは、口紅を買えていない
仕事を辞めた翌日、わたしは生きていた。
「当然である」と、言えるだろうか。わたしは自分のことを"よくやっている方"だと思っている。意味もなく宙を見上げ、水滴を仕舞う。人生を都合のいい妄想へ預けなければ、硝子のように心が割れてしまいそうだ。
「大丈夫ですか?」
歩きながら眠っていた。目が血走り、足が痙攣する。どこかから声が聞こえた気がしたが、辺りを見渡しても人は少なかった。ロクにごはんも食べていない。生命の境界線を、平均台を渡るようにしてふらふらと進む。
常に不安と手をつなぎ、勇気の破片をかき集めている。「これから先どうしよう」、「あと何日、家がある生活を続けられるだろう」。柔らかい糸なんかではない、有刺鉄線のような息吹。体力が残っているのかどうなのか、自分で判断ができない。酒に酔っている状態より冷静なぶん、恐怖が波打つ。
——早く帰らなくては。
恋人の彼と、わたしは一つ屋根の下で暮らしている。先月うつ病になり、家で療養している彼の分まで、わたしが働かなければならない。
結婚はできないけれど、誓ったのだ。最期まで彼を愛すること、なにがあっても寄り添う体。わたしとのキスで、溶けるあなたでいてほしい。
ぼんやりしている暇などない。疲れているのかどうなのか。そんなことを考えるより、食べて、動かなければいけなかった。
.
.
「ゲイはきもちわるい」
「ゲイと話したくない」
「ゲイだと思ったら受けつけなくなった」
突然、頭の中を大きな杓文字のようなものでグロテスクにかき混ぜられる。とあるきっかけでわたしに"男の恋人がいる"、その事実が職場で広まり、そのままわたしは居場所を失った。
いままでが嘘のようだった。
愛する人がいる、たったそれだけのことでわたしの声が届かなくなった。自分がいるのに、いないみたいだった。
挨拶は誰も返してくれない。仕事で必要なやりとりもできなくなり、わたしのミスはわかりやすく増える。陰で嗤われ続け、言い返すこともほとんどできなかったわたしは、溺れるようにして退職していた。
.
.
「愛しています」
無職初日。
最低限の食料を買って、家に帰ろうとしていたところだった。1円でも安いもので済ませたかったわたしは少し遠くのスーパーまで足を運んでいた。いつもと違う帰り道。駅を西口から東口へと通り抜けようとしていたら、目に飛び込んできたデパート、景色——
「しをりさん!また一緒に遊びましょうね」
今度は、幻聴ではない。大切に、胸に入れていた記憶を取り出していた。わたしには友達がいる。ずっと、エッセイを書いてわたしは生きてきた。
noteで文章を書いていたらできた友達。"女の子になりたい"わたしを知っている、大切な人。
「公園で、お散歩でもどうですか」
先週、休日を合わせて、友達ふたりとわたし。
三人で、人の少ない公園で過ごしていた。深緑と、それに近い青。包む空気に乗って、どこまでも走っていけそうだった。紫陽花と風が抱き合い、音を生む。一緒に隣を歩いてくれる、ただそれだけで満たしてくれる関係。微笑む彼女たちの間で、わたしも女の子になってしまいたかった。
「しをりさん、渡したいものがあるんです」
その日、解散をする前、友達があるものをプレゼントしてくれた。それは、27年間、人生の全ての勇気を使っても買えなかったもの。
何度も、何度も挑戦した。どこにでもありそうなドラッグストアに、それは並んでいる。目の前にあるのに買えない、法律に違反しているかのような危うさだった。
「あ…あ…」
うまく言葉が出てこなかった。差し出された桃色の紙袋の中に、上品に入っていた雫。どうしても塗ってみたかった。その気持ちをやさしく、受け入れてくれた。
「あ…ありがとうございます…」
終わりが見えないほど、さめざめと泣いた。わたしの姿を見て、ふたりはゆっくりと、淑やかに微笑んでいる。昔からずっと泣き虫だった。
ただ、「男なら泣くなよ」、「女々しい」なんて言葉は飛んでこない。手の甲に乗った小鳥が、こぼれずに踊っている。
家に帰って、わたしはすぐにマニキュアを塗った。人生で初めてのそれを、ひたすら塗った。初めて絵の具を使う子どものように、手は乱暴に、そして鮮やかに光る。
帰りに除光液も買っていたので、何度も練習ができた。薬指だけ、恋人の彼にお願いをした。それはほとんど、「結婚」のよう。わたしは、自分のしたい生き方ができていたのだ。
——出来上がった指先。
吸い込まれそうなほど美しかった。なにかと比べて美しいとか、そういうことではない。わたしが、わたしを見て、美しいと思った。それは一生残る、贅沢。指輪は、恋人とのお揃いだ。

.
.
取り出した記憶を撫でながら、視界をもとに戻す。
そこに広がっているであろう景色は、より、勇気のいる場所。デパートの化粧品売り場だった。
そういえば友達も言っていた。
「いつか一緒に行きたいですね」
わたしに"準備"が必要なこともわかった上での、"いつか"だったのだと思う。
「行けるかもしれない」
たったひとり。隣には友達もいないし、愛する彼もいない。化粧品売り場ってどんな感じなんだろうと、ふと思う。見たことはもちろんあるけれど、いまのわたしは変わっている。どうしても見たい、景色があったのだ。
大きなドラマがあったわけではない。
宝石を扱っているかのような仕草で唾を飲み込む。体が勝手に、デパートの中へと入っていった。
◇
フロアマップを、なるべく自然に見る。このご時世だったからか、お客さんはほとんどいなかった。それでも店が営業している。人が待っている。立っているわたしも、"お客さん"だった。
「三階か…」
いつものエスカレーターが、どこか、甘いお城につながる絨毯のよう。左右には花束と、艶めく女神の楽譜。脇から、天然の琥珀が流れる。心臓が、口から出てきそうだった。
降り立つそこは、乳白色の世界。
わたしの姿は、黒いTシャツに、ジーパン。当然、ここへ来る予定ではなかった。爪は塗っていないし、いつもつけている大ぶりのピアスもない。マスクの下は、力強く根を張った髭。一億人に聞いたら、一億人がわたしを「男性」というだろう。そんなこと、わかっている。誰のせいでもない。
その階も、目で数えきれるくらいの人数しかお客さんはいなかった。ただもちろん男性の姿はないし、化粧室も、赤い部屋だけだ。
ぐるりと、まずは一周しよう。そう思った。ありえない姿をしたわたしがいる。明らかな"男"が歩き、手に持っているエコバッグには、一つ80円くらいの惣菜がいくつか入っている。顔から火が出そうだ。逃げ出したいのに、足はぐんぐんと前に進んだ。
さりげなく、瞳に入れる。
ちょうど中央に化粧品売り場があった。店員さんは女性ふたり。わたしと同じくらいの年齢に見える。誰もお客さんのいない空間。それでも勇気を出して探した、欲しかった「口紅」を——
挙動不審だっただろう。
そんな中、ふたりのうちの、ひとりの店員さんと目があう。目尻は海豚のように弧を描き、綿雲のように微笑んでくれた。
その瞬間、心臓を鷲掴みにされた。恋に落ちたとか、それとはまた違う色。ゆっくりとわたしに向かって店員さんが近づいてきた。
「だめだ」
怒られてしまうと思った。なんの用ですか?と言われてしまう。けれど、芯から疲れ切っていたわたしの体は、思うように動かず、植物を帯びた大岩のよう。店員さんと向かい合い、そのままわたしは、ありえないほど涙を流した。マスクの中に湖を作り、目の周りを撫子色に焦がした。
どこからどう見ても泣いているわたしを見て、店員さんは初め、なにも言わなかった。マニキュアをくれた友達と同じように、ひたすら、包んでくれた。
「あ…あ…」
男性のわたし。腕からは毛を生やし、骨格は才能とも言えるほど男らしい。背もそれなりにある。わたしは…わたしは許されない。そう思った瞬間、店員さんは言葉をくれた。
「この色、とっても素敵ですよね。試してみますか?」
声は出なくなったのに、会話ができた気がした。このデパートに、わたしはお客さんとして来ている。わたしは、わたしの口紅がほしい。
目を見ただけで、感じ取ってくれた。
初めてのわたしを、瞬時に引き込む。
お化粧をほとんどしたことのないわたしから見てもわかる。上手で丁寧で、涙が千切れるほど、店員さんの姿は「手本」だった。醜く嫉妬してしまいそうなほど、わたしにないものを持っている気がした。
.
.
恋人の彼とお付き合いをする前から、「女の子」を夢みていた。
昔、初めてひとりでワンピースを買った日、わたしは店員さんに言われていた。
「プレゼント用ですか?」
自然すぎる質問だった。これ以上ないほど適切だと思った。それなのに、鼻の奥の方で、暗い滝が現れる。考えて、考え抜いてわたしが出した言葉——
「はい。(わたしへの)プレゼント用です」
特にそこから大きなやりとりが起きることもなく、少し豪華な袋にワンピースが包まれる。
汗が止まらなかった。それはきっと、心を隠していたから。それでも自分らしく生きるために、わたしは嘘をつかなかった。
.
.
化粧品売り場の店員さんは、わたしを見ても「プレゼント用ですか?」とは言わなかった。どちらが "正しい"というわけではない。ただその瞬間だけを切り取れば、"わたしにとって"、口紅を買おうとしたその日の方が嬉しかったのだ。
「試してみますか?」
その言葉を聴いて、涙を垂らしながらわたしは首を横に振った。せっかくわたしを抱きしめてくれたのに、勇気がなかったのだ。
ここからはわたしの考えだ。世の中をおかしいと言いたいわけではない。単なる、想いの話——
お化粧は、贅沢なのだと思う。
みんなしているから、人はお化粧をしているのだろうか。生きて、働いている。人と会って、話をする。そのためにお化粧をしている女性はきっと多い。ただ、女性だからお化粧をしなければいけないわけではないし、男性だからお化粧をしているとおかしいわけでもない。
等しく贅沢なのだ。
女性も、男性も、そうでない人もいて、もしも目の前の人がお化粧をしていたら、目一杯褒めてほしい。だってその人は、懸命に歩いて、走って、贅沢を手にして"特別な日"を踊っているのだから。お化粧は、そのためのものであってほしい。
本来、無理にするものではないと思う。
造形の美しさだけで人は測れない。そう思いたいのも、わたしに大きなコンプレックスがあるからかもしれない。だとしても、贅沢を堪能している人は、際限なく美しい。
その日の前日、わたしは仕事を辞めていた。勢いで来てはしまったが、口紅を買う余裕などない。繰り返しになるが、なぜならお化粧は、贅沢だからである。
わたしは、初対面の店員さんに泣きながら話をした。
勢いで来てしまって申し訳ないということ。いまはお金がないこと。でもこの口紅をいつか自分の唇に塗りたいこと。女の子として生きたい人生のこと。最近、初めてマニキュアを塗ったこと。家に帰れば、着れるワンピースがあること。一緒に暮らしている、男の恋人がいること。
口紅を塗りたいわたしの方が、人よりおしゃれをしているわけではないし、同性を愛しているわたしの方がより純粋に恋をしているわけではない。ただ自分らしく生きた先に口紅があった、彼がいたのだ。
その日、わたしはどこもお化粧をしていなかった。お化粧をしていない人は、しているより劣っているのか、それは違う。
お化粧をしていないとき、人はとびきり笑うことができる、なにも気にせず涙を流すことができる。お化粧をしているときの表情とは違う。それこそ純粋な人の美しさが皮膚から描かれる。
「試してみますか?」
後から気づいたけれど、それは来店した多くのお客さんを掬う、魔法の言葉なのだと思った。なにも、絶対に唇に塗れとは言われていない。自分用として来たわたしはそのまま口紅を試すことができ、プレゼントだった場合は、手の甲などで色味を確認して実際に見る動作に入れる。
ただ結局、わたしは口紅を試すことすらしなかった。
滞在したのは、ほんの数分だったと思う。
店員さんの名前は当然聞かなかった。あくまでわたしは客で、相手は店員さんだから。とはいえいつかわたしが自分の力で、自分のしたい化粧品を手に取り、身に纏えたとき、"あなたに"届けたいと思う。
わたしは、"わざわざ"最後、店員さんに訊いた。
「わたしが口紅を塗ってもいいですか?」
人の言葉を誘導しようとする弱さがわたしにはある。それでも言ってほしかった。どこからどう見ても男性のわたしを見て、店員さんは言う。
「もちろんです。もうすでにわたしは、お客様に似合うお色が、見えていますよ」
店員さんは、最後まで"わたしに合った"言葉で寄り添ってくれた。
わたしはまた、新しい一歩を踏み出す。人生を愉しむ希望と共に、歩んでいく。そのたび、出会う心に感謝していたい。
精一杯、わたしは心の中で、一方的な約束をした。
これからも、自分らしく生きるために。そのときはきちんと、買わせてください。
「また来ます」
.
.
さいごに、これが昨日わたしがしたツイート。
今日帰り道、デパートの化粧品売り場に寄ったんだけど、そこで"欲しかった"口紅を眺めていたら店員さんがわたしに「この色とっても素敵ですよね、試してみますか?」と言ってくれた。「プレゼント用ですか?」と聞かれなかったのだ。男のわたしに対しても、こんな接客がもっと広まったらいいな。
— いちとせしをり (@liegirl_1chan) July 15, 2020
読んでくれたあなたが、人へ渡す言葉を考える機会になればと思い、載せている。
リプライや、引用リツイートなどの欄を見れば、様々な意見があるのがわかる。ほとんどがあたたかい言葉ではあったが、もちろん、皆がわたしのような生き方をしているわけではない。苦しくなるような言葉もあった。ただ店員さんの生きる姿に、わたしは感動していた。
今回は、化粧品売り場での話だった。それこそ接客の方法は無数だろう。だとしてもこのエッセイは他の場面でも通ずる。
完璧に全ての人を包むのは難しいかもしれない。ただどんな人でも救えるよう、言葉を選ぶ力を諦めてはいけない。もしも少しずれてしまったとしても、真剣な表情を前に、きらわれることはない。そういう想いは言葉を飛び越して、より濃く伝わってくるものだ。
多様に生きられる時代——。
信じられないほど恵まれている。
仕事はない。それでもいま、わたしは生きていた。男性として、ではない。「人」として生きている。瑞々しく、これからもわたしは「自分」を愛し、人と手をつないで笑いたい。
あなたがあなたらしくいられるように、文章を書いて、これからも届けたいと思う。
書き続ける勇気になっています。
