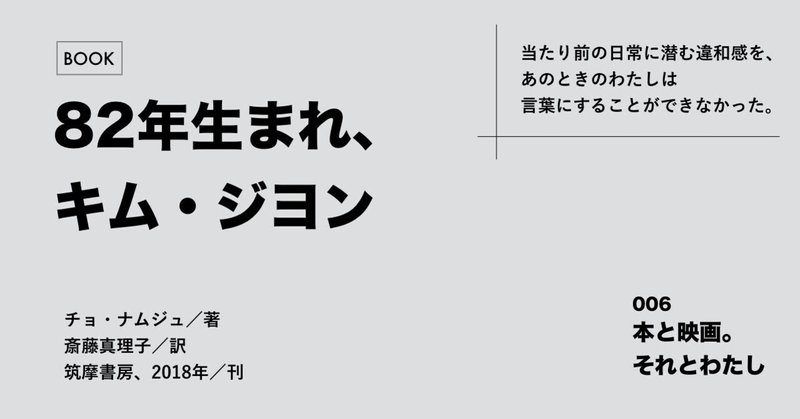
キム・ジヨン氏と、フェミニズムに目覚めたわたし
当たり前の日常に潜む違和感を、あのときのわたしは言葉にすることができなかった。
フェミニズムに目覚めたのは、高校生のころだった。わたしが通っていたのは進学校で、それはそれは宿題が多く、部活と勉強以外に何をしていたのか、まったく思い出せない。そんなある日、自宅のリビングでちょこっとくつろいでいると、父が「ジンコ、洗い物しろ」とわたしに声をかけた。そのあとテスト勉強か何かをしようと思っていたわたしは、隣りでゲームをして遊んでいる当時小学生だった弟に目をやり、「◯◯にやらせてよ」と返す。しかし、父はこう言い放ったのだ。「◯◯は男の子だからやらなくていい」。
そのとき、自分のこころの中に芽生えた「違和感」を、わたしは言葉にして反論することができなかった。でもしばらくして、「男の子だから」というのは洗い物をしなくていい理由にはならないことに気づいたのである。父に悪気がないこともわかっていたが、あとから振り返ってみれば、このことがわたしにとってジェンダーの問題を意識するきっかけになったのだと思う。
本作の主人公であるキム・ジヨン氏がそういった「違和感」を覚え始めるのは、なんと5〜6歳のころ。5歳下の弟が家族の中で「特別扱いされている」とまでは思わなくても、「なんだかくやしい」という気持ちが、ちいさな女の子のなかですでに芽生えていた。そして、キム・ジヨン氏が成長するにつれて、「違和感」を幾多の場面でも経験することになる。この世界はあまりにも多くの不平等や不条理が当たり前のこととして成り立っている、とわたしたち読者も思い知らされるのだ。
小説だけれど、この作品には韓国のリアルが描かれている。韓国ってこんなにひどい女性蔑視があるのか、かわいそうに……と見過ごすことなかれ。「あれってもしかして」と自分の立場や周囲の環境を振り返ることで、日本だってそう変わらない状況であることに気づかされる。実際、2020年のジェンダーギャップ指数は、日本は韓国よりも順位が低い。
日常の違和感を言葉にすることは、はっきりいってむずかしい。ちょっと不満を口にするだけで、フェミニストと煙たがれて終わる世の中だ。それでも、疑問に思うことはやめてはいけない。キム・ジヨン氏はそんなわたしたちのちいさな声を代弁し、日本のフェミニズムに改めてちいさな火を灯してくれたのではないだろうか。
82年生まれ、キム・ジヨン
チョ・ナムジュ/著
斎藤真理子/訳
筑摩書房、2018年/刊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
