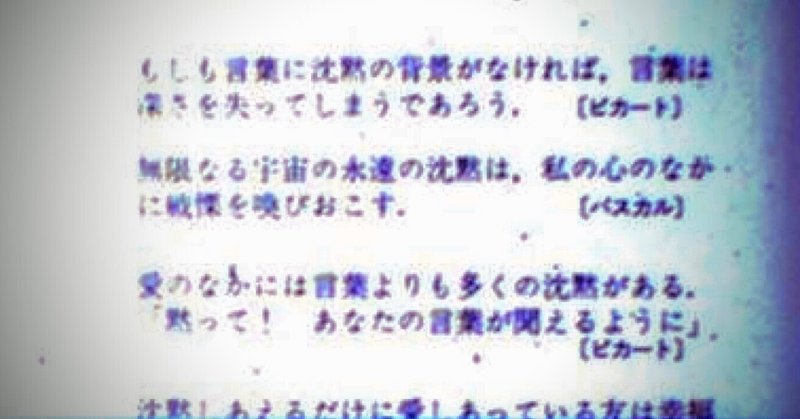
お守りとしての『沈黙の世界』
思想や文学などを好んで読み、なおかつ古本屋に通う習慣があるひとであれば、みすず書房のあの「いかにも」な装丁と、ふと目にしただけで湧いてくるなんとも言い難い「安心感」は、探しものがなくても、あるいは、衝動買いを行う余裕が全くないときであっても、大食漢を誘い入れるとんこつスープの匂いがごとく、古書店へと立ちいらせてしまう理由としてはおおいに常であることだろう。
あれら装丁がみすず書房という出版社が手掛けた刊行物であることを初めて認識したのは、スイスの医者であり神秘思想家であるマックス・ピカートの主著とされる『沈黙の世界』という思想書によってであった。
ピカートの著作は同じくみすず書房から多く翻訳されていたが、このタイトル以外のものに出くわすことはあとにも先にもほとんどなかった(特に『騒音とアトム化の世界』と『われわれ自身のなかのヒトラー』はレア中のレアで、ぼくが運よく両方とも遭遇したときは、砂金を掘り当てたみたいに一目散にレジへ運んだ)。
にもかかわらず、この『沈黙の世界』に関してはどの古本屋にも必ず1冊は置いてあるような、ヒット作が後に安い値段で大量に叩き売られる現象にも似た様相を呈していたことが一時期あり、タイトルの格好良さとその値段に惹かれ、思想の「し」の字も知らなかったぼくも1冊購入した。のちに徒歩で日本を縦断する旅に出かけた時には、お供として道連れにしたりもした。
ひとり旅とまでいかなくとも、道中の時間潰しのために文庫本を持ち歩くひとは今もいるであろうが、みすず書房の単行本をテントなどの装備品と一緒にリュックに入れるひとがどれぐらいいるかはよく知らない。旅そのものがハードだったせいもあったが、大方の予想通り、ページをめくった回数は一度か二度に留まった。
ではそんな固いハードカバーの『沈黙の世界』が、その旅において全く何の役にも立たなかったといえばそんなことはなかったのだ、と今になって思う。その題名や、パラパラとめくる度に万華鏡を覗き込んだ時のように目に飛び込んでくる何行かの印象的なセンテンスは、ぼくの無意識に通奏低音的ななにかを刷り込み、単にマゾヒスティックな身体の酷使でしかなかったその旅を、精神的な側面からサポートし先導してくれる無人格のメンターのような役割を担っていたのだ。
日中の明るい時間帯のうちに歩けるだけ歩き、日が暮れそうになるとテントをはれそうな人気のない場所を探す。ひとり旅において、やれることはそれぐらいしかない。もちろん話し相手もいないし、周りで話し声が鳴っていることもない。夜になり、テントの中で寝そべっている時などは、自分の歩く音すらも恋しくなるほどに静かな、まさに『沈黙の世界』の只中にいるわけで、わざわざページを開くまでもなかったのである。
文庫本でもハードカバーでも、紙の本はまずもって1つの物体であり、物体である以上、読まずともただひたすら「そこにある」ということだけで世界に重みを与え、情報量の不均衡を空間に与えることができる。つまり、空間に「波」を生むことができる。本という物体は、作られる時には内容が装丁よりも先に立つが、物体になったあとは内容が後回しにされるのが常である。まだ読んでいない本の「まだ知らない内容」はひとに「知らないことがある」ことを知らせる。これが本の放つ「波」である。
ページとページの隙間から、字と字の隙間から、静かにこぼれてくる「波」の後を追いかけることで、ようやくひとは本の内容を「ひらく」ことができる。それまでの過程で得たものすべてが、テクスト解釈の方向性を決定する重大な要素として還元される。読書とは道すがらで起きた体験を含めた一連の運動なのだ。
ピカートは『沈黙の世界』について考え、ぼくもまた『沈黙の世界』について考えながら旅をした。本とは、同じ事柄について思いを巡らせてくれている、時間を超えた友達のような存在だ。友達のように身近に感じるぬいぐるみを、お守りとして外出に連れ出す人も多いかもしれないが、本もまた同じような意味において「お守り」といえる存在なのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
