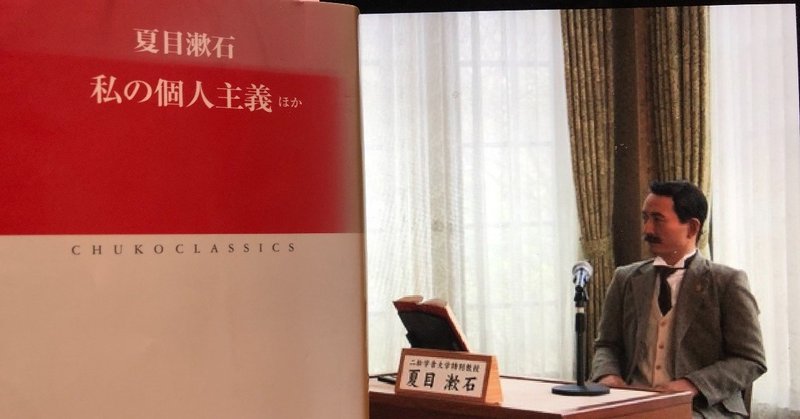
vol.74 夏目漱石「私の個人主義」を読んで
これは、1914年(大正3年)11月25日、学習院での講演録。
明日は、漱石の誕生日。また偏屈な漱石に触れたくなった。久しぶりにこの講演録を読み返した。今度は、YouTubeに素晴らしい音声朗読もあったので、ジョギングしながらそれも聞いた。
この時代、講演の4ヶ月前に第一次世界大戦が勃発している。またこの年に連載された『こころ』で乃木希典のことが書かれている。そして乃木は1912年まで学習院の総長を務めていた。その学習院で、天皇の「ご学友」や上流社会の弟子たちを前にして行われたのがこの講演だった。(東京大学院教授 小森陽一の資料を参考)
漱石は、松山や熊本の教師時代からイギリスに留学した時も、文学とはどんなものであるか煩悶を繰り返し、そして「自己本位」という概念を自ら作り、それが支えになったと語っていた。

この時代、世間では、西洋人が評すれば、自分の腑に落ちようが落まいがその評を鵜呑みにし、わがもの顔にじゃべって歩く。また、みんながそれを褒めていた。漱石はそんな「他人本位」な世間を批判していた。また、見識ある国民の一員として、英国人の意見に流されずに、世界に共通な正直という徳義を重んじる点から見ても、私は私の意見を曲げてはならないと、それが「自己本位」だと説いていた。
そんなことをこの講演の第1編として語っていた。
何か誤解を招きそうな「自己本位」という言葉、もっと他の言い回しはないものかと思ったが、その思いは伝わる。そして重要なのは、他人の「自己本位」も尊重するということだと説いている。
第2編では、「権力と金力」について語ってた。
上流社会の弟子ばかりが集まっている学習院の関係者にこう語り出した。「あなたがたに付随してくるもののうちで、第一に挙げなければならないのは権力であります。あなたがたが世間に出れば、貧民が世の中に立った時よりも余計権力が使えるということです。(中略)権力に次ぐものは金力です。これもあなたがたは貧民よりも余計に所有しておられるに相違ない。ですから、権力と金力を持っているあなたがた学習院の関係者が世の中に出たらどうしなければならないのか。」

今なら、中央官庁に集まる東大法学部のスーパーエリートたちへのメッセージということになるのだろうか。
論旨をかいつまむと、「第一に自己の個性の発展を成し遂げようと思うならば、同時に他人の個性も尊重しなければならないということ。第二に自己の所有している権力を使用しようと思うならば、それに付随している義務というものを心得なければならないということ。第三に自己の金力を示そうと願うなら、それに伴う責任を重んじなければならないということ。つまりこの三カ条に帰着するのであります。」と述べている。
漱石は講演の結論をこの三カ条に集約し、それを『私の個人主義』としていた。
同意しやすい三カ条だけど、実践するのは難しいのではないだろうか。人間はそうなっていないのではないだろうか。悲しいけど、そんなことを思ってしまった。
今、「他人の個性を尊重しなさい」と教えられるけど、調和の取れない個性は、潰されてしまう。権力とセットのはずの義務は、指摘がなければ都合よくやり過ごす。指摘があってもすり替える。金力と責任に至っては、重んじるどころか、責任も金力で処置することに疑問もない。
この講演から100年以上経った今でもこの普遍的な議論が展開されている。虚しい気持ちは、人を妨害し、権力を濫用し、金力で腐敗をもたらす、そんな社会の一面に出くわすことがあるからなのかもしれない。
最後に漱石はこう結んでいる。「ある程度の修養を積んだ人でなければ、個性を発展する価値もなし、権力を使う価値もなし、金力を使い価値もなし」と。
一国民として思う。今、権力分立の中でも執行者の「人格」は大前提だと。この漱石の講演録を読んで、時代は変わってもこの一点だけは見つめ続けようと思った。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
