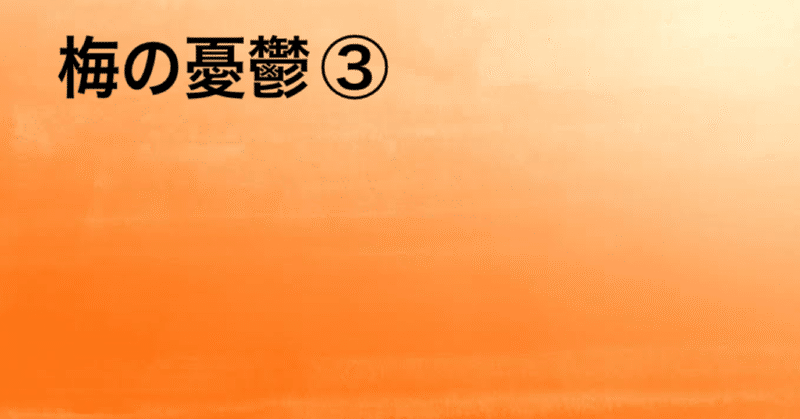
【短編小説】梅の憂鬱③
僕は部屋へ戻り、何をするということもなくぼんやりとしていた。部屋に夕闇が垂れ込めていたが、僕は電灯をつけることもしなかった。僕は夕闇の中でじっとしていた。しばらくすると、たきが晩御飯を知らせに来た。僕はそれに従って食堂へと向かった。
食堂のテーブルには、颯爽とした白い食器の上に西洋料理が並んでいた。それはスープやサラダやオムレツ、ビフテキの類だった。だが僕はどれも手につかなかった。下女らが食事を慇懃に勧めたが、僕はスープを一口か二口飲んだっきり、カトラリーにも手をつけることができなかった。
僕は数分経つ間もなく、席を離れた。廊下に消えていく僕をたきが不安そうに見つめていた。
僕は部屋に閉じ籠った。暗い早春の部屋に夜気が垂れ込めていた。僕は障子の隙間から梅と夜月とを眺めた。
梅の花が月明かりに照らされて、闇の中に白く陰鬱に浮かんでいた。月光が苔むした庭の上に乱れ立っていた。
僕は奇異な心持であった。僕が夕刻に思い出したその人の印象が、夜になるとより不鮮明になり、より曖昧になったからだ。本当に僕はその人のことを待っているのか、その人は本当に実在していたのかどうか、不信の念が募った。
僕は布団を敷いて、暗闇の中で目を瞑る。枕元には梅の香が薫っている。僕は眠ろうとするが、意識は乱れている。
輪廻や生まれ変わりといったそんな不鮮明なものを、僕は今日の夕刻に疑いようのない本当のこととして信じていたけれど、それは夕焼けの感傷的な気分の内に夢見ていたに過ぎなかったのではないか?
僕の心には始終このような疑問が渦巻いていた。僕はまた目を開ける。障子の隙間からは青白い月光が陰鬱っぽく差し込んでいた。僕はまた目を閉じる。僕は梅の香の中で深い眠りに落ちようとする。しかし、そんな僕をはぐらかすように、眠りが幾度となく去来しては離反していったが、そのいじらしい焦燥の内で、気がつくと僕は寝ていた。
僕は次の日、学校の授業を放擲した。僕は本郷を抜けて御茶ノ水を歩いていた。ニコライ堂がその頭部を白昼の青空に高く突き上げていた。路面電車が街路を疾駆する横を僕は何ということもなく打ち歩きながら、早春の雑踏に紛れていた。雑踏は、僕の乱れた自我意識を幾分も和らげていた。僕は洋服屋やカフェエの店先を横切っていく。
「お兄様」
すると僕の後ろで声がする。僕はその声につられて振り返る。
そこにはいつかの見慣れた姿があった。
「千恵子…」
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
