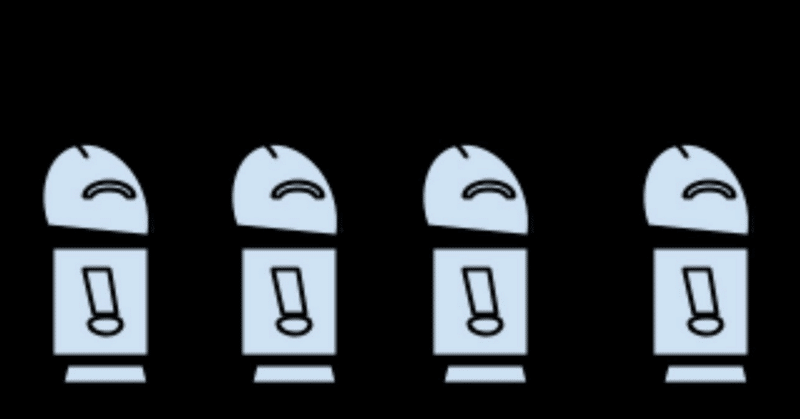
生きる意味を探して
子どもの頃、死ぬことがとても恐ろしかった。
死とはなにかも曖昧なままに、とにかく死ぬことが恐ろしくて仕方なかった。
潜在的な死の恐怖と生への執着は、いったいどこから始まって、どのような形で成長を遂げていったのだろうか。
今日は僕が子どもの頃に抱いた価値観を紐解きながら今一度、生と死の本質を見つめ直してみたい。
***
不思議の国のアリス症候群というのをご存知だろうか。不思議の国のアリス症候群では、自分の体が大きくなったり小さくなったり、時間が経つのを早く感じたりといった奇妙な感覚が起こる。これらはルイス・キャロルが『不思議の国のアリス』で描いている現象で、英国の精神科医ジョン・トッドがこの童話にちなんで名付けた。主に片頭痛を持つ子どもが患う症状らしい。
僕がこの名称を知ったのは遥か後年、大人になってからだったが、小学校低学年頃に僕もよくこの症状に罹っていたことは確かに自覚がある。昔からよく頭痛に悩まされていたのも関係しているようだ。
僕の場合は、自分の手や目の前にあるものがとてつもなく大きく見えて、数メートル離れた人や物は豆粒のように小さく見える症状だった。壁にかかった時計が豆粒サイズに見え、それでも記された数字は正確に読み取れる。視力自体は良かったので、どんなに小さく見えても細かく読み取れるのだ。サイズ感と遠近法だけがとにかくバグっていた。
しかし不思議の国のアリス症候群だなんて、なんともロマンチックな名前じゃないか。確かにあれは不思議な体験だった。その症状も、成長と共に現れることはなくなっていった。童話の子どもが大人になるにつれて妖精や魔法の世界が見えなくなっていくように、あの体感が二度とこの身に訪れないと思うと少し切ない。
そんな体験も潜在意識に残っているからだろうか、僕はいつも、他人が見えない世界の認知を探していた気がする。
本当はこの世界はみんなが思ってるような世界じゃなくて、目に見えない魔法や解き明かせない秘密に包まれてるはずだと確信していた。大人になって改めて思うのは、やはりこの世界は人間の知識や理解が遥か追いつかないほどの複雑さと壮大さを伴って存在している。
しかし自分以外の全ての人間はそれを疑問に思うことなく、誰もが予定調和の日々を過ごし、規範に従い規則を守り、ロボットのように時間通りに決められた動きをしているだけな気がして、この世界を恐ろしく思っていた日々もあった。僕と僕以外の人間は、なにかが違う決して相容れない存在なんだろうと、子どもながらに孤独と違和感を感じていた小学1年生の頃の記憶が蘇る。
当時考えていたことは、みんな姿かたちは僕と同じ人間だけど、本当は誰も意識を持っておらず神のような上位概念の存在が操って動かしているだけなんじゃないか? というものだった。だってそうじゃなきゃ、言われた通りに教科書を開き、解る問題に手を挙げ、起立や礼や着席を疑問も持たずにこなす、あんなに品行方正な社会的動物になんかなれるわけないもの。他人の喜怒哀楽の反応さえも機械的に感じて無機質な印象があった。これをされたら笑い、これをされたら泣く。全部が予定調和に映った。
実はこの世界できっと僕だけが、自分の頭で物事を考えているんだ。僕以外の全ては、神が僕の反応を試すために存在しているんだ。
そんな一見ヤバい6歳の僕の思考は、振り返れば過剰な自意識と極端な社会性の無さから生じたものだったのかもしれない。
僕は僕以外の人をロボットだと思っていたけど、考えていたのは哲学の世界で語られる哲学的ゾンビのことだ。先取りしてたぜ。
哲学的ゾンビとは、心の哲学で使われる言葉である。「物理的化学的電気的反応としては、普通の人間と全く同じであるが、意識(クオリア)を全く持っていない人間」と定義されている。
カート・ヴォネガット著『チャンピオンたちの朝食』にも哲学的ゾンビと同じ思想が描かれていたのを高校生の頃に読んだ記憶があるな、たしか。
僕のこの世界に対する異質感、異邦人としての自己の存在は、自意識に対する特別感から意識の消失=死を極端に恐れさせた。
自分を特別な存在だと認識することは多くの少年少女が通る道だと思うが、僕の場合は容姿や肉体、または知識や能力に対するものではなく、自意識そのものに対する特別感だった。
たとえ肉体の消失が起こっても、霊魂さえ不滅なら死を恐れることはなかっただろう。外界に一切の影響を与えず、また一切の影響を受けることもできない全くの無力な存在になったとしても、思考し続けることさえできるのであれば幾分の不満はあれど恐怖はないくらいに、僕は意識こそ生そのものであるように感じていた。
***
つまり僕は幼少期からそれほど強く死を恐れていたのだけど、しかし人は必ず死ぬという現実を、いつかは受け入れる時がやってくる。
僕も、この文章を読んでくれている貴方も、今いる人類はあとたった150年も経たずに、一人残らずこの地上から消えていなくなるだろう。150億年の宇宙の歴史、地球誕生から46億年の時の長さと比べれば、瞬きにも満たない僅かな時間で舞台を去ることになる。
ならば、逃れることのできない死と真正面から向き合ってこそ、生まれてきた本当の意味を見つけることができるのではないだろうか。
生きる意味をありきたりな種の保存法則で済ませても、言葉を変えて愛や絆と呼んでみても、そんな予定調和で生を終えるだけの人生では虚無感に包まれて絶望するしかなくなるほどには、もう僕の自意識は肥大化し過ぎてしまっている。僕に限らずきっと誰でも、自分だけの生まれてきた意味を考えることは、生の充実のためには不可欠なはずだ。
さて、小学校も高学年に入ると運動会では組体操が毎年行われていた。
組体操の目玉であるピラミッドは 、5・4・3・2・1で組まれて、15人でやることになる。僕の小学校ではクラスの男子が18人くらいだったから、必然的に2〜3人は余ることになる。クラスの中で特に運動能力の低い子が余り、補佐という名目で横から支える役割を担うことになる。
組体操は大人に命じられた子どもの仕事だった。僕は集団意識が低く真面目にやる気がなかったとはいえ、補佐に回るのは耐え難い羞恥が子どもながらにあった。大人は誰も言わないとはいえ、ピラミッドの構成員に選ばれないことは運動できない落ちこぼれの烙印を押された子を意味しているのだと、クラスの全員がハッキリと認識していた。
その中には入りたくないという僕の見栄とプライドが、内発的動機がどこにも見つからない組体操のピラミッドという演目を真面目に取り組ませていた。外発的動機はポジティブなものだけとは限らない。落ちこぼれ扱いされたくない、周りからバカにされたくない、そんな逼迫した感情や見栄とプライドが原動力になって子どもを突き動かすこともある。
どこにもやる意味を見つけられなかった仕事を真面目にこなして、ひいては社会活動に真面目に取り組んで、外発ばかりを生きる動機とすることに慣れてしまって、振り返った時には自己がどこにも無い人生を送り続けて、「あの人はいい人だったね」とか言われて惜しまれつつこの世を去るのだろうか。
僕は絶対に、そんな人生は嫌だ。
学校教育の必修科目である体育とは、字の如く体を育てるためにあるはずなのに、それが長らくスポーツ競争の場となってしまっていた。
運動会なんて軍事教育の名残だろう。行進、組体操、騎馬戦と、戦時中の学校でやっていたことそのまんまだ。
僕は言葉で言い表せない違和感や嫌悪感を抱いていたが、それは主義ではなく気質からくる感情だろう。体育会系や集団主義が極めて苦手で、帰属意識は低く独立心や自律性が強い気質によるものだ。それに小学生の僕に大した主義なんてないからね。
性格を形成するのは環境や価値観よりも気質や生理の影響が強いと思う。結局のところ僕の思考も自意識も、他人に感じていた哲学的ゾンビの概念と似たようなもので、生まれながらの気質が育んだものでしかないことは否定し難い。
しかしそれでもなお、自己のない人生を送りたくはないと強く思う。
***
現代社会では死が隠されているように感じる。
代わる代わる入れ替わる命のバトンをスムーズに繋いでいくためには、死を隠して予定調和に社会を進めていく方が都合がいいのだろう。
断末魔の叫び声は誰も聞きたくない。世界の片隅で日夜流される誰かの血も、他者の命を奪って自身の命を繋ぐしかない生命のルールも、隠していた方が都合がいい。
僅かばかりの時を経たら舞台を去らねばならないのに、社会倫理を設定して、社会貢献には賛辞を送り、その気になって頑張って踊る舞台俳優を作り上げ、舞台の裏側を覗かせないように仕向けられているようだ。
……いや、別に陰謀論者じゃないけどさ。
工業化したシステムの中で搾取され続ける畜産動物の形態も、遠国で権力者たちが始めた戦争で亡くなった大勢の死体の山も、残酷なものは見せなければいい。不都合な真実をひた隠して、社会は動いているように感じる。
しかし本当に、生きることとは、現代社会の中だけで完結していいものなのだろうか?
死が隠された社会では、生命力もまた軽視される傾向にあると思う。死と向き合わず、死を意識せずに平和な日々を過ごしているだけなら、死に抗う術を持つ必要はない。愛と平和の音楽だけが流れる心地よい世界に身を投じていればいいのだ。
けれどカマキリがカマを備えて生まれてくるのも、ウサギの耳が長くて大きいのも、托卵によって生まれたカッコウが血の繋がらない親鳥に育てられるのも、愛する相手を抱き寄せるためでもなく愛の言葉を聞き逃さないためでもなく真実の愛を見つけるためでもない。彼らは生き残るために知恵と武器を持って生まれてくる。
我々人間もまた、森を追われた弱い猿が必死に生き残るため、頭を使って知恵を持ち、拳を握って殴り合い、道具を使って火を起こして、生存と繁栄を続けてきた。
旧約聖書によれば我々は知恵の実を食べて楽園を追われたアダムとイヴの子孫である。楽園で過ごしていれば今も知恵を持たずに、羞恥心を抱かずに裸のままで弱い猿として生き続けていただろう。カマキリもウサギもカッコウも、楽園にいれば今ある姿にはなっていなかったはずだ。
愛や平和や幸福ばかりが賛美される現代社会において、生き抜くために備えた死に抗う術の価値を見直すべきではないだろうか。武器を自分の中に眠らせたままでは、果たして本当に生きていると言えるのだろうか。
本来、生と死は表裏一体だ。生あるところに必ず死は寄り添っていた。
それが今では死は隠され、価値を奪われて、人は余計なことを考えずに舞台を成立させるためだけにイベント進行させ続けるよう促されている。自己を置き去りにした人生を求められ、応じるがままに生きていても、最期の時に責任を取ってくれる他人は誰もいない。それは果たして、幸福な生涯だろうか。
本当は、死と向き合ってこそ生が見えてくるのではないか?
***
現代において日本人の平均寿命は80歳を超える。
宇宙や地球の歴史と比べればあまりに短いけれど、それでも動物の中ではかなりの長寿だ。
しかしその長寿は、先天的なもの以上に環境面による支えが大きいと思わせる出来事が先日あった。
人間にもっとも近い種であるチンパンジー。チンパンジーの野生下での平均寿命は12歳というデータがある。しかしこれはあまりに短命だと感覚的に思う。さすがにチンパンジーの寿命が犬や猫と同じではないだろう。厳しい野生下で天寿を全うできないからこその短い平均寿命なのだろう。
国内飼育個体に限れば平均寿命は28歳だという。これくらいの数字になれば妥当な線だろうと思っていた。
先月、僕が働く動物園でチンパンジーの赤ちゃんが産まれたのだけど、母親の年齢はなんと推定46歳である。人間でもかなりの高齢出産にあたる年齢でチンパンジーも出産できることに驚いた。
そうなると、本来の寿命はチンパンジーも人間に肉薄するくらい長い可能性も高い。そのチンパンジーの野生下での平均寿命の短さを鑑みると、我々動物は天寿を全うするように作られてはいないのかもしれない。
今でも死ぬことは恐ろしい。
でも前ほどではなくなったように感じる。
死と向き合うことから逃げず、死に抗う刹那にこそ生きる力は湧き上がることを知り、闘うことで虚無感からほんの少し解放された。
全て消え去る運命だとしても、僕は用意された舞台に上がり続ければ脚光を浴びれたとしても、ロボットの歓声よりもこの世の真実を求めて舞台セットの裏側を覗いてみたい。
いつの日か訪れる死の際に、振り返れば自己がある足跡を残しておきたい。確かに僕は僕の人生を生きてきたんだと、納得する生き方をしていきたい。
その日がたとえ明日でも、天寿を全うできなくたって、死と向き合い己を見つめて生きてきたんだと思えるほうが、社会的成功を収めるよりも他者からの愛に満たされるよりも、よっぽど有意義な生涯ではないだろうかと僕は考えている。
サポートしていただくと泣いて喜びます! そしてたくさん書き続けることができますので何卒ご支援をよろしくお願い致します。
