
カルチャーこそすべて
こんにちは。KESIKIの井上裕太です。
私は企業変革を10年以上にわたり仕事としてきました。マッキンゼーで経営コンサルタントとして働いたり、スタートアップスタジオのquantum設立に関わったりを経て、KESIKIの創業に携わり、今年、正式参画しました。
KESIKIは「カルチャーデザインファーム」を標榜しています。
カルチャーとは一体何か。矛盾するようですが、私たち自身も一言で言い切れるほどはっきりと言語化できているわけではありません。でも、良いデザインには、プロダクトであれ組織であれ、根底を貫く「何か」がある。そのことは、メンバー全員が実体験をもって確信しています。
愛される会社や組織に存在する目に見えない何か。人々を魅きつける存在。それをカルチャーと呼ぶとして、私なりの考察から話を始めてみます。
シリコンバレーは「退屈」になった
私にとって、ずっと憧れだった街があります。シリコンバレーです。
日々新たなプロダクトが生まれ、ハッとさせられる世界観が提示され、驚くような速度で社会に実装されていく。ニュースを一つ見逃せば、未来の兆しを一つ掴み損ねることになる。そんな気持ちで、日本にいながらシリコンバレーについての記事を貪るように読んでいた時期があります。
しまいには、その熱気を肌で感じたいという気持ちが抑えきれなくなり『WIRED』日本版の特派員になって現地に渡ったほど。ダメ元で当時の正副編集長に直談判したところ、あっさりと「じゃあ、やってみれば」と。2011年のことです。

しかし、ふと気がつくと、私の心の中でずっと燃えていたシリコンバレーへの憧憬の炎は消えていました。憧れ「だった」と過去形で書いたのはそのためです。
あんなに好きだったシリコンバレーは、この10年の間に、私にとってすっかり普通の場所になってしまいました。胸躍らせながら渡米したあの時期にあの地で渦巻いていた熱気の正体。それは、カルチャーと深い関係があるのではないかと考えています。
2011年にシリコンバレーに訪れたとき、そこは名実ともに世界を未来へ導くイノベーションの震源地でした。まさにTech Is Kingの時代。テクノロジーとテックスタートアップが世界の革新のエンジンで、世の中をより良い場所にしていく主役だったのです。ここからより自由で平等な社会が切り拓かれていくのだという確信に溢れていました。
当時の私の憧れはAirbnbやStripe、Dropboxを輩出したY Combinatorで、魔法のように新たなイノベーションが生み出され続けるその場所を取材出来た時の高揚感は今でも忘れられません。
もちろん、シリコンバレーは今でもイノベーションの中心であり続けています。テックの覇者であるAppleもGoogleもFacebookもNetflixも、トヨタを時価総額で抜いたテスラも、みんなシリコンバレーの企業です。先ほど挙げたStripeやAirbnb、そして上場が決まったPalantirもシリコンバレー発。ガーディアン紙によれば、シリコンバレーがもし一つの国だとしたら、世界で最も裕福な国なのだそう。 そこに疑念の余地はありません。
それでも私は、まるで強迫観念に駆られたようにシリコンバレーへ頻繁に足を運ぶことや、ニュースを読み漁ることをやめてしまいました。新たなプロダクトから驚きや希望を感じる頻度が徐々に減ってきたからです。ニュースで取り上げられる事象も少しずつ、FANGなどテックジャイアント間の競争やテクノロジーの弊害についての存在感が増しはじめました。
2014年に起きた「Googleバス」(社員送迎バス)に反対するデモやPando Daily(現・Pando)のサラ・レイシーによるUberの”Asshole Culture”への追求、2016年の米大統領選挙におけるフェイスブックの役割が象徴するように、テクノロジーは局所的にも、また社会全体としても、人々の分断を加速し、あるいは古い価値観を温存して強化しうるのだということが明らかになりました。私の中にあったテクノロジーとその頭目たるシリコンバレーへの憧れは薄れていきました。
2010年前後のシリコンバレーにあって、今はなくなってしまったものは何なのか。なぜシリコンバレーは、未来を切り拓く希望を生むイノベーションの中心たりえたのか。
スタンフォード、UCバークレー、カルテックなど優秀な人材を輩出する複数の一流大学の存在。ハングリーな移民が多く、またかつての半導体産業の遺産として優秀なエンジニアが多いこと。金融センターであるサンフランシスコが間近にあり、ベンチャーキャピタルの集積地であるSand Hill Roadがあること。ゴールドラッシュ以来の挑戦と失敗を賞賛する風土と、「天気がよくて何もない」からこそプロダクトに集中できる環境……。 様々な理由が挙げられます。
でも私は、そこに強いカルチャーがあったことが最も重要な鍵だと考えています。
オタクのプライドとヒッピーの精神
Y Combinatorの創業者、ポール・グレアムは投資家、経営者、エンジニアとしての顔以外にも、エッセイストとして有名(Googleの英語版で”essays”と検索すると、彼のエッセイサイトが上から3番目に表示される)です。そんな彼のエッセイ集『ハッカーと画家』、特にその前半部分に、シリコンバレーのカルチャーの一側面が色濃く出ていると私は考えています。
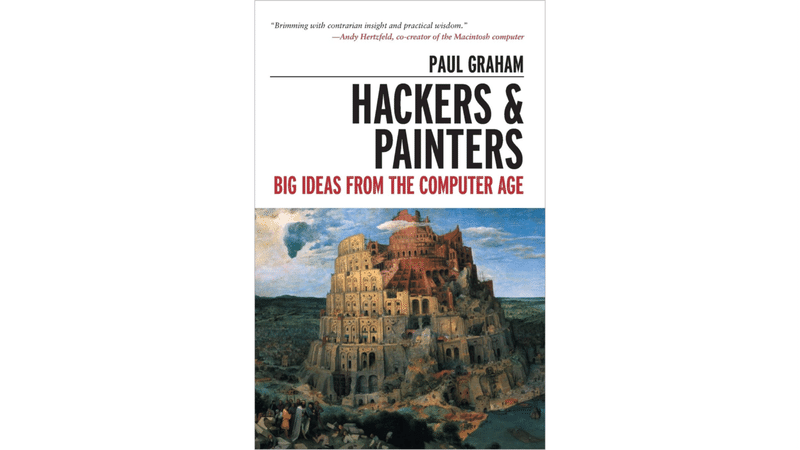
本や彼の他のエッセイの中では、彼の学生時代について様々な回想がなされます。「スクールカーストの中でいかにオタク(geek)が虐げられているか」「スクールカースト最上位のアメフトプレイヤーたちは学校生活を謳歌した後、MBAを取り、東海岸的エリートとして大企業や投資銀行に就職し、スーツ族として社会を牛耳ることになる」「本当は彼らなんかよりもずっと頭が良いオタクこそが世界を変えるんだ」「既存の慣習や利権に囚われず、技術で世の中を前進させるオタクこそがこれからの主役だ」。そんな心の叫びが繰り返し書かれています。
東海岸のエリートやスーツ族たちへのカウンターとしてのオタクのプライド、geek prideこそが、シリコンバレーの原動力。かつて自分たちを組み敷いた既得権益を、頭脳とエンジニアリングで破壊することが自らの存在意義。彼のエッセイはまさにその象徴のような文章です。
そして、シリコンバレーのカルチャーを形作るものとして忘れてはならない要素がもう一つあります。ヒッピーカルチャーです。Wikipediaで「1960年代後半にアメリカ合衆国に登場した、既成社会の伝統、制度など、それ以前の保守的な男性優位の価値観を否定するカウンターカルチャーの一翼を担った人々、およびそのムーブメント」と定義されているこのカルチャー。米国におけるムーブメントの中心地はサンフランシスコでした。その遺産が、シリコンバレーのカルチャーを形作ったのです。
ヒッピーカルチャーの申し子のひとりが、アップルの創業者スティーブ・ジョブズです。アップルを追放されたときに受けたインタビューを収めた有名なドキュメンタリー映画「Steve Jobs: The Lost Interview」の中で彼は「あなたはオタク(nerd)か、それともヒッピーか」と問われ、「間違いなくヒッピーだ」と答えています。そして「私が一緒に働いてきた人もほとんどがヒッピーだ」と続け、インタビュアーを驚かせています。

「60年代後半には、家族や仕事、ガレージの2台の車、キャリアなどの日常を超えた『何か』があった。それが何かを探し求めたのがヒッピームーブメントだ」というスティーブ・ジョブズは、言葉を探しながら「そこには、銀行員よりも詩人になろうというような、何かがあったんだ」と最後にニヤッと笑いながら言うのです。
そして「パーソナル・コンピュータは、そんな『何か』をプロダクト化したものなんだ」という、宣言とも取れる言葉を残します。
人生の意味を追い求め、日常のくびきから解き放たれること。既存の価値観を否定し、より自由な社会を希求すること。お金や権力よりも詩を愛すること。そういった精神がテクノロジーと出会い、シリコンバレー的価値観、シリコンバレーのカルチャーが生まれたのです。
シリコンバレーを輝かせた、オタクとヒッピーの二つの精神。それらがどこかで失われていったのではないか。そしてその輝きを陰らせたのではないか。私はそう考えています。理由はたぶん複層的です。
かつてスタートアップであったテックカンパニーが巨大化し、彼らが憎んでいたはずの東海岸的な株主資本主義システムに組み込まれていったこと。徐々にそのカルチャーはエリート化し、既得権益を作り出していったこと(ピーター・ティールは「競争するな。独占しろ」と言った。この記事にあるように「当たり前を疑い、ひとのやってないことをやれ」という意味のこの言葉はしかし、独占を賛美する言説においてもよく引用される)。白人男性ばかりのコミュニティの中で、多様な視点や価値観が醸成されにくかったこと。テクノロジーが様々なものを飲み込み(“Software is eating the world”)、政治にまで意図しないほどの大きな影響を及ぼすようになったこと。
その中で、カウンターであったはずのギークやヒッピーは気づけばメインストリームとなり、詩よりも資本やパワーを愛するようになった。その過程でカルチャーが失われていった。
少し単純化しすぎかもしれませんが、これがかつて大好きだったシリコンバレーの変化について私が感じていることです。
巨艦を突き動かすもの
身近な体験としても、カルチャーの重要性を噛み締めたことがあります。以下は、私が長らく経営コンサルタントとして企業変革に携わってきたなかで過去に関わった、とある組織の話です。
その組織の母体の大企業は、誰もが知る業界の代表プレーヤーであり名門企業。でも、産業そのものが岐路に立たされており、大きく変化することが求められていました。
しかし、巨艦を動かすのは簡単ではありません。そこで、その変革の尖兵たる組織が立ち上げられます。成果が出るに従い、一部の変人たちによる取り組みから変革の象徴へと周囲の認識も変わり、社内外から尖った人材が集うようになりました。
結果、目覚ましい成功を収めるプロジェクトも生まれ、売上も大きく伸び、組織も巨大化し、業界内で注目される組織へと育ちました。でも、大成功…のように思えたそのプロジェクトに、私は大きな後悔を残しました。カルチャーを育てることができなかったのです。
変化の兆しを捉えた事業、よく練られたビジネスモデル、そしてその結果集まる尖った人材。そういったメンバーの間で交わされるフラットな議論と、外部にも開かれ多くのコラボレーションによってプロジェクトを進める姿勢。彼ら彼女らによってプロジェクトは成功に導かれ、それらの積み重ねで売り上げと存在感は順調に伸びていきました。しかしそれらは、いわば自転車操業でしかなかったのです。
一見根付いていたかにみえた組織文化は、実は一部の強い想いとこだわりを持ったメンバーにより保たれていました。組織が巨大化するに従って徐々にそのカルチャーは保守化し、尖った人材にとっての魅力を失っていきました。結果、カルチャーを担っていたキーマンたちが離脱。すると組織はみずみずしいビジョンと機動力を失い、組織運営の核であったメンバーすらもモチベーションをなくすという悪循環がはじまりました。

なんだ、よくある話じゃないか、と思う方もいるかもしれません。「しっかりしたビジョンがなかったから、ビジネス面では上手くいっても人材を惹きつけきれなかったのだ」、あるいは「キーマンが抜けて組織が崩壊するなんて、情報やノウハウが属人化しないようにしっかり仕組み化や制度の作りこみをしなかったのが原因だろう」などと感じる方も多いでしょう。
でも、この話のポイントは、そういった取り組みはカルチャーの喪失の前では大きな力を持ち得なかったというところにあります。初期に魅力的な人材を惹きつけた力強いミッションはそこに存在し続けていた。その結果、集ったメンバーによって、プロダクトの継続的な強化、業務プロセスの磨き込み、ブランドの確立、組織や人事制度の設計などが行われ、ビジネスは安定しました。
でも、実はキーマンによって保たれていたのはビジネスそのものよりも、その基盤たるカルチャーだったのです。
どれだけ魅力的なミッションを策定しても、丁寧な仕組み化を行っても、そこにカルチャーがなければ組織が輝き続けるのは難しい。カルチャーは、制度では担保しきれないギリギリの局面での意思決定を左右し、ミッションでは描ききれないディテールへの異様なまでのこだわりを後押しし、最も組織にストレスがかかる時期に皆がふんばるエネルギーを生み出します。そういった、いわば組織にとっての「生き様」を、保てなかった。
私にとって大きな後悔と、そして学びとなった出来事でした。
カルチャーとは愛である
ここで話を最初に戻します。そもそも、カルチャーって何なのでしょうか。cultureの語源は、ラテン語のcolere。colereは「耕す」という言葉。また「崇める」という意味も持つそうです。信じるものを耕し育むこと、カルチャーにはそんな意味が込められているようです。
太宰治の『正義と微笑』という作品の中に以下のような文章があります。(青空文庫にあるので、気になった方はぜひ一読を)
お互いに、これから、うんと勉強しよう。勉強というものは、いいものだ。代数や幾何の勉強が、学校を卒業してしまえば、もう何の役にも立たないものだと思っている人もあるようだが、大間違いだ。植物でも、動物でも、物理でも化学でも、時間のゆるす限り勉強して置かなければならん。日常の生活に直接役に立たないような勉強こそ、将来、君たちの人格を完成させるのだ。何も自分の知識を誇る必要はない。勉強して、それから、けろりと忘れてもいいんだ。覚えるということが大事なのではなくて、大事なのは、カルチベートされるということなんだ。カルチュアというのは、公式や単語をたくさん暗記《あんき》している事でなくて、心を広く持つという事なんだ。つまり、愛するという事を知る事だ。学生時代に不勉強だった人は、社会に出てからも、かならずむごいエゴイストだ。学問なんて、覚えると同時に忘れてしまってもいいものなんだ。けれども、全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残っているものだ。これだ。これが貴いのだ。勉強しなければいかん。そうして、その学問を、生活に無理に直接に役立てようとあせってはいかん。ゆったりと、真にカルチベートされた人間になれ!
太宰治は、カルチャーとは心を広く持つこと、愛するという事を知ることだと考えていたようです。それは必ずしもわかりやすく結果に現れるわけではない。でも、砂金のように残る、と。私も、カルチャーは必ず目に見える形で滲み出てくるものだと思っています。スティーブ・ジョブスがヒッピーカルチャーをプロダクトとして具現化したものがパーソナル・コンピューターだと述べたように。

先ほど紹介したインタビューで、ジョブズはこう続けています。「だからみんなマッキントッシュを愛しているんだ。プロダクトが愛されるなんてなかなかないだろう?」そして、「マイクロソフトにはそれがないんだ」とも。(実はマイクロソフトはその後、カルチャーの変革によって蘇ることになるのだけれど、それは続編で)
カルチャーとは愛であり、愛されるための要素である。カルチャーこそがすべてだ。
私はそう言い切ってしまいたいと思います。
では、カルチャーによって組織はどう変わりうるのか。KESIKIが今、カルチャーをどう捉えているのか。このあたりは続編にて改めて。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
