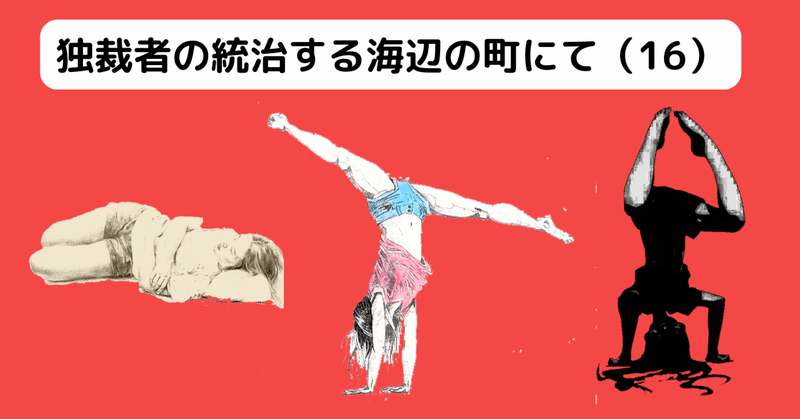
独裁者の統治する海辺の町にて(16)
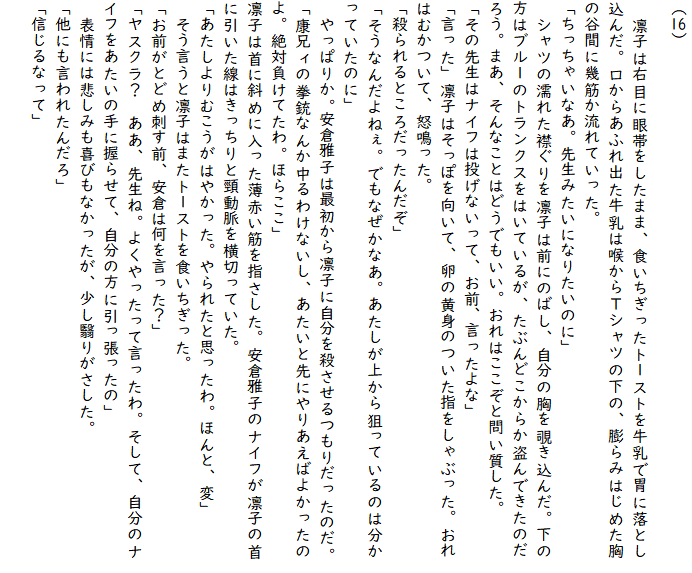
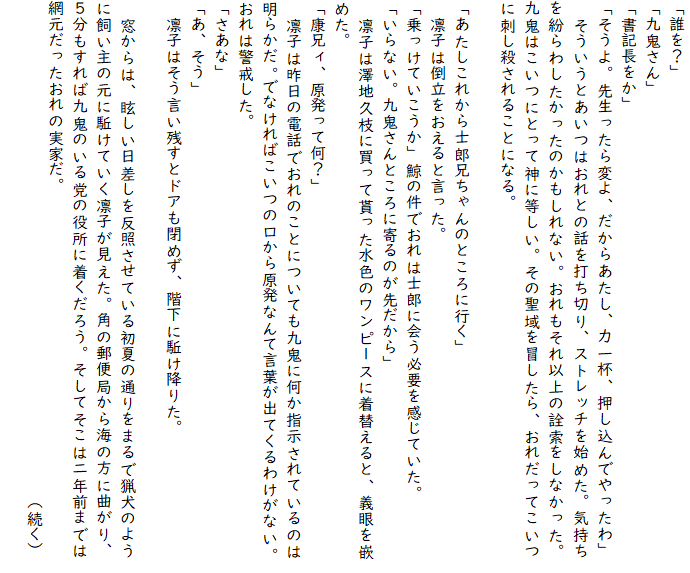
凛子は右目に眼帯をしたまま、食いちぎったトーストを牛乳で胃に落とし込んだ。口からあふれ出た牛乳は喉からTシャツの下の、膨らみはじめた胸の谷間に幾筋か流れていった。
「ちっちゃいなあ。先生みたいになりたいのに」
シャツの濡れた襟ぐりを凛子は前にのばし、自分の胸を覗き込んだ。下の方はブルーのトランクスをはいているが、たぶんどこからか盗んできたのだろう。まあ、そんなことはどうでもいい。おれはここぞと問い質した。
「その先生はナイフは投げないって、お前、言ったよな」
「言った」凛子はそっぽを向いて、卵の黄身のついた指をしゃぶった。おれはむかついて、怒鳴った。
「殺られるところだったんだぞ」
「そうなんだよねぇ。でもなぜかなあ。あたしが上から狙っているのは分かっていたのに」
やっぱりか。安倉雅子は最初から凛子に自分を殺させるつもりだったのだ。
「康兄ィの拳銃なんか中るわけないし、あたいと先にやりあえばよかったのよ。絶対負けてたわ。ほらここ」
凛子は首に斜めに入った薄赤い筋を指さした。安倉雅子のナイフが凛子の首に引いた線はきっちりと頸動脈を横切っていた。
「あたしよりむこうがはやかった。やられたと思ったわ。ほんと、変」
そう言うと凛子はまたトーストを食いちぎった。
「お前がとどめ刺す前、安倉は何を言った?」
「ヤスクラ? ああ、先生ね。よくやったって言ったわ。そして、自分のナイフをあたいの手に握らせて、自分の方に引っ張ったの」
表情には悲しみも喜びもなかったが、少し翳りがさした。
「他にも言われたんだろ」
「信じるなって」
「誰を?」
「九鬼さん」
「書記長をか」
「そうよ。先生ったら変よ、だからあたし、力一杯、押し込んでやったわ」
そういうとあいつはおれとの話を打ち切り、ストレッチを始めた。気持ちを紛らわしたかったのかもしれない。おれもそれ以上の詮索をしなかった。九鬼はこいつにとって神に等しい。その聖域を冒したら、おれだってこいつに刺し殺されることになる。
「あたしこれから士郎兄ちゃんのところに行く」
凛子は倒立をおえると言った。
「乗っけていこうか」鯨の件でおれは士郎に会う必要を感じていた。
「いらない。九鬼さんところに寄るのが先だから」
凛子は澤地久枝に買って貰った水色のワンピースに着替えると、義眼を嵌めた。
「康兄ィ、原発って何?」
凛子は昨日の電話でおれのことについても九鬼に何か指示されているのは明らかだ。でなければこいつの口から原発なんて言葉が出てくるわけがない。おれは警戒した。
「さあな」
「あ、そう」
凛子はそう言い残すとドアも閉めず、階下に駈け降りた。
窓からは、眩しい日差しを反照させている初夏の通りをまるで猟犬のように飼い主の元に駈けていく凛子が見えた。角の郵便局から海の方に曲がり、5分もすれば九鬼のいる党の役所に着くだろう。そしてそこは二年前までは網元だったおれの実家だ。
(続く)
#小説 #創作 #短編小説 #連載小説
#文学 #組織 #少女 #漫画原作 #連載小説漫画
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
