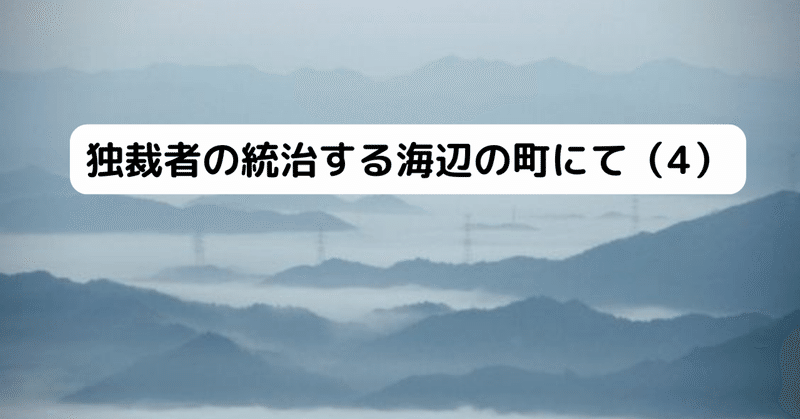
独裁者の統治する海辺の町にて(4)
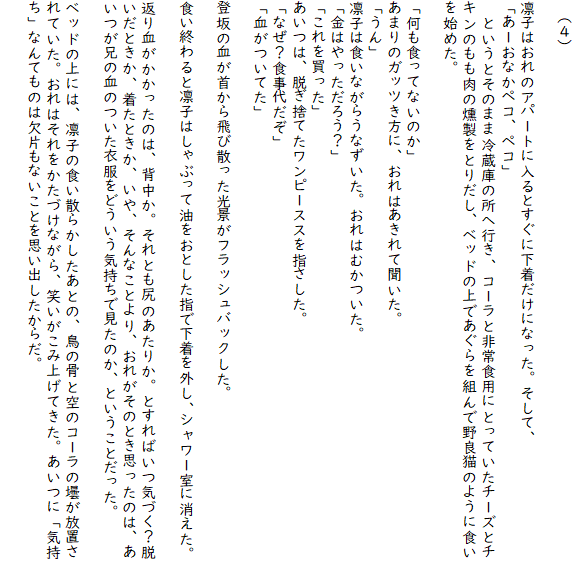

凛子はおれのアパートに入るとすぐに下着だけになった。そして、
「あーおなかペコ、ペコ」
というとそのまま冷蔵庫の所へ行き、コーラとおれが非常食用にとっていたチーズとチキンのもも肉の燻製をとりだし、ベッドの上であぐらを組んで野良猫のように食いを始めた。
「何も食ってないのか」
あまりのガッツき方に、おれはあきれて聞いた。
「うん」
凛子は食いながらうなずいた。おれはむかついた。
「金はやっただろう?」
「これを買った」
あいつは、脱ぎ捨てたワンピーススを指さした。
「なぜ?食事代だぞ」
「血がついてた」
登坂の血が首から飛び散った光景がフラッシュバックした。
食い終わると凛子はしゃぶって油をおとした指で下着を外し、シャワー室に消えた。
返り血がかかったのは、背中か。それとも尻のあたりか。とすればいつ気づく?脱いだときか、着たときか、いや、そんなことより、おれがそのとき思ったのは、あいつが兄の血のついた衣服をどういう気持ちで見たのか、ということだった。
ベッドの上には、凛子の食い散らかしたあとの、鳥の骨と空のコーラの壜が放置されていた。おれはそれをかたづけながら、笑いがこみ上げてきた。あいつに「気持ち」なんてものは欠片もないことを思い出したからだ。
あいつはは振り向いた登坂の喉笛を跳び上がるやいなやかっ切った。なんのためらいもなく。
シャワーの音がやむと、凛子はおれの前を横切り、扇風機の向きを変えるとベッドに腰掛け、身体を拭き始めた。
「今日はここにいていい?」
「家があるだろう」
背筋にひやりとした影がながれた。殺されたやつの家に殺したやつが戻れるわけはない。
「あそこは、組織のおじさんたちがいっぱいいたの」
「書記長のところへいけばよかっただろう」
「九鬼さんが、康雄兄ちゃんのところへ行けって」
凛子とおれには血のつながりはない。おれは、幼い頃から敬虔なクリスチャンだった母親につれられて教会に通っていた。そして登坂がおれと同じ年であるため、日曜礼拝以外にも教会によく遊びに行き、泊まったこともある。だから彼女がおれをそんな風によぶのも不思議なことではない。
だが、九鬼書記長がおれの所へ行けというのはありえないことだった。組織においてはメンバーが任務以外に交流を持つということは禁じられていることだからだ。
おそらく、凛子は九鬼とは会っていない。行く先がなかったというだけだ。それはそれでいい、それよりもおれが気になったのは、組織が教会の家宅捜査をしているということだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
