
【いざ鎌倉:人物伝】源通親
今回は人物伝・源通親です。
村上源氏のプリンス。

言うまでもなく公家源氏でして、鎌倉将軍家をはじめとする武家源氏の清和源氏とは別系統。
村上源氏の代表として摂関家の代表・九条兼実、鎌倉将軍家の代表・源頼朝らと政界で渡り合った大政治家と言っていいと思います。
しかし、失脚したわけでも殺されたわけでもなく、病死ということで本編での最期はあっさりとした記述となってしまいました。
これまでの出番も多い人物でしたのでまとめておこうと思います。
高倉天皇の側近として
源通親の青年時代というのは、平清盛が平治の乱に勝利し、平家の勢力を拡大する頃と重なります。
通親の前半生は平家との関わりなしに語れません。
父・源雅通が平清盛の妻・時子の妹である建春門院滋子の皇太后宮大夫であった関係から、通親はその皇子である高倉天皇の側近として活動することとなり、清盛の弟・平教盛の娘を妻としています。
平家の縁戚となったことで、通親は平清盛からも信頼される貴族の一人となります。
治承3(1179)年、平清盛はクーデターにより後白河院を幽閉し、院政を停止させます。
通親は引き続き高倉天皇に仕え、譲位後の治承4年3月の厳島神社行幸にも同行しています。

厳島神社
上皇による譲位後初の神社参拝は日枝・加茂・石清水・春日といった京・南都の神社に参るのが伝統であり、遠く安芸国(広島県)にある平家の崇敬篤い厳島神社への参拝は反発を呼び、政治問題にまで発展しました。
同行した通親は往復およそ1か月についての旅行記を記しており、『高倉院厳島御幸記』として残されています。
親平家公卿として
治承4(1180)年5月27日、高倉上皇の御前で開かれた議定(会議)は緊迫したものとなります。
以仁王の挙兵に協力したとされる園城寺と興福寺に対する対処が議題となったからです。
興福寺は藤原不比等が建立した藤原氏の氏寺です。
摂関家をはじめとする藤原氏は、軍事侵攻を辞さない平家の強硬論から興福寺を守らねばなりません。
ただ、清盛が平家一門の身分を大きく引き上げたとはいえ、一門の多くはまだまだ議定への参加資格がありません。
高倉上皇御前での議定となると藤原氏を中心とする興福寺擁護派が数の上で有利でした。
この場で平家の主張を代弁し、強硬論を唱えたのが通親です。
「ただちに官軍を送り込んで攻撃し、荘園も全て没収すべき」と発言し、出席者の度肝を抜きます。
村上源氏の彼にとって藤原氏の氏寺・興福寺に手心を加える必要はありません。
これに対し猛烈な反論を加えたのがライバルとなる九条兼実です。

「以仁王が逃げ込んだ証拠はないし、まずは使者を送って事情を聴くべき」と発言します。
結局、激論の最中に以仁王の戦死の報が届けられたため、この時点での興福寺攻撃は行われませんでした。
九条兼実はこの日の日記において通親ら強硬論を主張した公卿に対し、
「恥を知らずといふべし」と記しています。
源通親と九条兼実のライバル関係の第1ラウンドとも言える日でした。
雌伏の時
治承5(1181)年正月、通親が仕えた高倉院は21歳の若さで崩御します。
そして、寿永2(1183)年7月、いわゆる平家の都落ちで、これまで親交を結んできた平家一門も京を去ります。
後ろ盾を失った通親は後白河院に仕えつつ、雌伏の時を過ごすこととなります。
元暦2(1185)年、後白河院が源義経に追討の院宣を与えたことに怒った源頼朝は朝廷の改革を要求し、九条兼実が後鳥羽天皇の摂政に就任します。
以後、兼実が鎌倉の頼朝と強調しつつ、朝廷の政治を主導します。
藤原摂関家を絶対視する兼実の下では、藤原氏ではない通親の出世は抑えられました。
通親はいつか自分が政治の中心に立つ日が来るのを待ちます。
後鳥羽天皇の乳母・高倉範子を妻に迎えたのはこの頃とされます。
かつては平教盛の娘を妻として平家に接近しました。
通親は再び婚姻から出世の道を探ります。
源博陸
待ち続けた通親にチャンスを与えたのは後白河院でした。

後白河法皇
文治5(1189)年、後白河院は通親を自身の第六皇女・宣陽門院覲子内親王の別当(後見人)に指名します。
後白河院は自身の最後の子である覲子内親王を大変可愛がり、建久3(1192)年の崩御を前に最大の荘園群である長講堂領を覲子内親王に譲ります。
この長講堂領を別当として実質的に管理することになった通親は朝廷で大きな力を持つこととなりました。
その後の通親の生涯についてはこれまでの本編で書いてきましたので、リンクを貼りつつ簡略に書きます。
源頼朝が娘・大姫を入内させるべく通親に接近しますが、のらりくらりと交わす通親によって入内工作は失敗に終わりました。
養女・在子が後鳥羽天皇の第一皇子・為仁親王(土御門天皇)を出産。
建久七年の政変で九条兼実を政界から葬りました。
これにより実質的に京の政界の頂点に立ちます。
その後、後鳥羽天皇が譲位し、養女・在子が産んだ土御門天皇が即位します。
通親は「源博陸」(源氏の関白)と称され、栄華を極めました。
しかしその絶大な影響力は、成長する後鳥羽天皇にとって少しずつ煙たい存在となっていきます。
九条家が復権し、ライバルであった九条兼実の息子・九条良経が左大臣に就任。
後鳥羽院による通親をけん制する人事でした。
そして通親が外祖父として支える土御門天皇の皇太弟として守成親王が立てられたことで、朝廷への影響力に陰りが見えます。
ただ、後鳥羽院との関係は表面上最後まで良好で、後鳥羽院による『新古今和歌集』編纂を支える中で病となり他界しました。
享年54歳。
村上源氏中興の祖
政治的地位を落としつつあった村上源氏は通親の活躍により。その地位を向上させました。
その嫡流は、久我家として貴族社会において五摂家に次ぐ家格である清華家の一つとして列しました。
久我家以外にも中院家、東久世家、北畠家、岩倉家などその後の歴史にも登場する村上源氏の名家は全て通親の子孫が興した家門です。
道元禅師との関係
鎌倉時代について書いていて源通親の子孫の話をする以上、絶対に触れなければいけない人物がいます。
曹洞宗の宗祖・道元です。
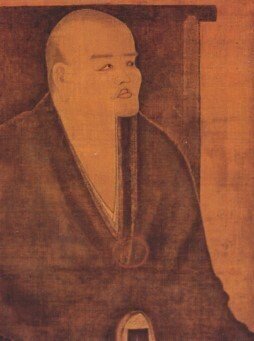
宋(中国)に留学経験もあり、ひたすらに坐禅を行う「只管打座」の思想を広めました。
道元は、村上源氏の出身と言われており、源通親の息子という説があります。
「育父源亜相」
という表現が道元の著書『永平広録』の中にあります。
「亜相」は大納言の唐名、中国風に言い表したものです。
なので源亜相は「源大納言」となります。
では、通親は大納言なのかというと、確かに大納言にも就任していますが、それより上の内大臣に昇っていますので、「源亜相」と表現することは普通ありえない。
安倍晋三氏について「安倍元官房長官」と言わないですよね。
「安倍前首相」が普通です。
よって「源亜相」は生前の最高官職が大納言である通親の次男・源(堀川)通具という説が有力です。
ちなみに先にも述べた「源博陸」の「博陸」は関白の唐名。
でも、通親は実際には関白になったわけではないので、本来の官職である内大臣の唐名を用いれば「源内府」でしょうか。
大河ドラマなどで徳川家康や徳川慶喜が「内府」と呼ばれているのを聞いたことがある人もいることでしょうから、これはそこそこ馴染みがありますね。
さて話を道元に戻します。
「源亜相」が通親の次男・源通具を意味するとすれば、道元は通親の孫になるのか、というとこれがまたそう簡単な話ではなく、「育父源亜相」の「育父」は育ての親のことであり、実の親はやはり源通親ではないかという見解もあります。
子か孫かいずれにしろ、道元は通親の子孫であることはほぼ間違いないと考えられます。
なお、曹洞宗の大本山である永平寺は寺紋として村上源氏嫡流・久我家の家紋でもある「五つ竜胆車(久我竜胆)」を使用しています。
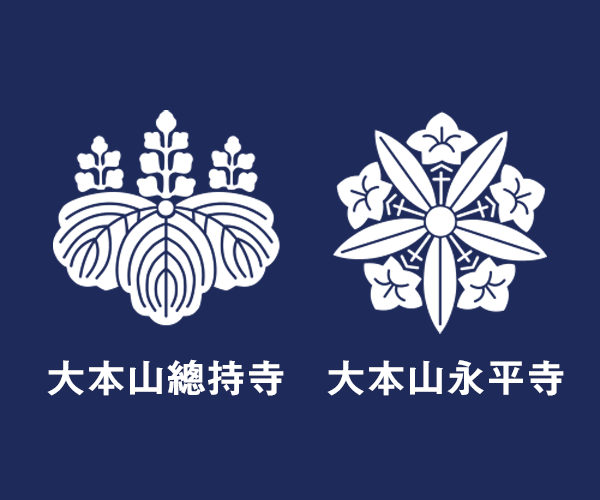
次回予告
次回は年内最後の更新です。
源頼家政権の終焉まで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
