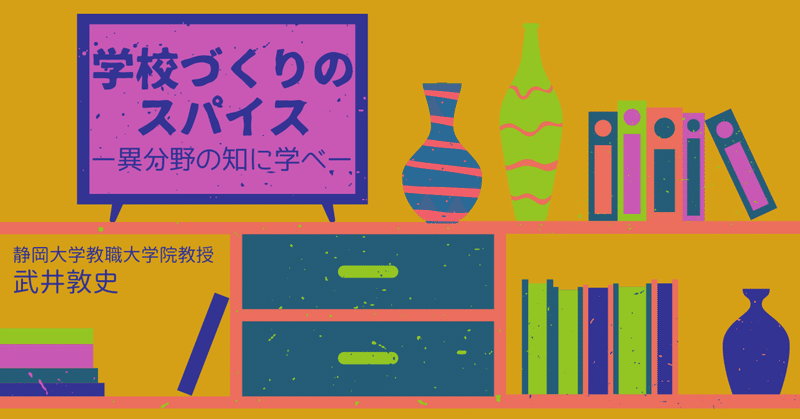
#36「おせっかい」のすすめ~渡辺一史『なぜ人と人は支え合うのか』より~|学校づくりのスパイス
コロナ禍にせよ、自然災害にせよ、紛争にせよ、人の生活を脅かすような事態が突然生じると、しばらくの間は目の前の問題解決に注目が集まりますが、徐々に人は慣れてきます。
ところが、一段落するとその背後で進んでいるさまざまな潜在的な課題が徐々に表面化してくることがあります。
そして現在まさに表面化しつつあることの一つに、「人の孤立化」という問題があるのではないだろうかと筆者は考えています。
今回はノンフィクションライターの渡辺一史『なぜ人と人は支え合うのか――「障害」から考える』(筑摩書房、2018年)を手がかりに、人間同士の支え合いについて考えてみたいと思います。渡辺氏は、2018年に公開されて話題となった、大泉洋さん主演の映画『こんな夜更けにバナナかよ――愛しき実話』の原作者でもあります。

身勝手な障害者
本書では、2016年に相模原市で起きた障害者殺傷事件から、上記映画のモデルとなった、進行性筋ジストロフィーの鹿野靖明さんとの交流、「障害」の表記問題などを通して、「障害者」とそれを支える人々との関係について考えたものです。
この本のなかで繰り返し問い直されている社会のあり方の問題は、障害者と支援者との関係を「困難に負けずけなげに努力する障害者」とそれを支える「善意のボランティア」という関係で描く「あわれみの福祉観」です。
たとえば、上述の鹿野さんの死後に編纂された追悼文集のなかで記された次のような社会人ボランティアの言葉が紹介されています。
「別に立派な人だったとは思わない。むしろダメなところが目立つ人だった」
「私が彼の元を離れなかったのは、欠点も弱さも隠さず、ずるかったり、繕ったり、人にあたったり、自分を実態以上に大きく見せようとしたり、そんな誰もが持っていながら、誰もが隠したがる面を、彼は全てさらして、丸裸で生きていたからだ。本人としてはさらすつもりはないのにバレバレ、ということもあるが、まぁ、それも含めてだ」(132~133頁)。
さて、鹿野さん以外にも介助を必要としていた人はたくさんいるにもかかわらず、鹿野さんにボランティアが集まったのは、身勝手であった「のに」ではなく、身勝手であった「から」こそであったようです。ボランティアに参加する人の背景にある意識について、渡辺氏は次のように説明しています。
「どんな人でも、多かれ少なかれ、誰かを支えたり、誰かの役に立っているという実感なしには生きていけないところがあります。それは、ボランティアにかぎらず、多くの人が『職業』というかたちで、誰かの役に立ち、社会に貢献し、そこから生きがいや収入を得て生活していることを考えて見ても分かることです」(125頁)。
では、支援を求めることの価値とは何か。それは「『支える人』と『支えられる人』の双方がいてこそ、初めて社会や経済というものが成立し、自分の日々の生活も営めているのだということ」(127頁)であるというのが渡辺氏の問題提起です。
社会には助けを必要としている人はたくさんいます。そして機会があれば人の助けになりたいと考えている人も少なからずいます。けれども両者のマッチングがうまくいかないばかりに相互扶助のはたらく関係が築かれず、本当に必要な人に支援が届かないとすればそれは残念なことです。
……と、このようには書いたものの、実は筆者も人にお願いをするのが苦手です。この本に出てくる鹿野さんのように率直に助けを求められたらとは思っても、そして困っていることは山ほどあっても、「助けて」とはなかなか口に出せないのです。このように支援を求めにくい社会の弊害は、学校教育の現場とも無関係ではありません。
「合理的な愚か者」
ここ数年、全国の不登校は増加傾向にありますが、大学生であっても入学して少し経つと授業に出てこられない状態になってしまうことは少なくありません。
そんな危惧もあって筆者は、大学生向けの授業で入学間もない時期に、こんな質問をしてみることがあります。
「自分がもし何かの理由で大学に出てこられなくなったときに、他の友人に声をかけてほしいですか? それともそっとしておいてほしいですか?」
このような質問を投げかけてみると、大体7~8割くらいの学生は「声をかけてほしい」と手をあげます。けれども全員ではありません。毎回1割くらいですが、「そっとしておいてほしい」と応える学生もいます(残りの学生は判断に迷って手を上げません)。
しかし、友人の姿を大学で見かけなくなったときに、無理にでも電話をかけて会話をしようとしてみたり、アパートに出かけていったり、といった行動に出られる学生は昨今多くはありません。友人が心配な気持ち以上に「自分が余計なことをしてかえって本人を傷つけてしまったら……」という懸念が先に立つのです。確かにその気持ちも分かります。
けれども、(筆者がそうだから分かるのですが)「助けて」とは言えない人でも、困っている人に「大丈夫?」とか「手伝おうか?」とか声をかけてみることは、まだハードルが低いのではないでしょうか。
1998年にノーベル経済学賞をとったアマルティア・センは、個々の人間が合理的な行動をとる結果、集団の利益が阻害される現象について「合理的な愚か者」(rational fool)と揶揄しました。
友人をそっとしておくという選択は個々人から見たならば合理的な行動かもしれませんが、誰もがそうすると人々は孤立して社会は閉塞化し、皆が不幸になっていってしまいます。現代では「おせっかい」が人の支え合いの潤滑油になるはずです。
現在の日本社会は、まさにこうした孤立社会に近づきつつあり、昨年来のコロナ禍はその傾向に追い打ちをかけたはずです。となれば多少「うざい」と思われることがあったとしても、少しおせっかいなくらいでちょうどいいのではないでしょうか?
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)
【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
