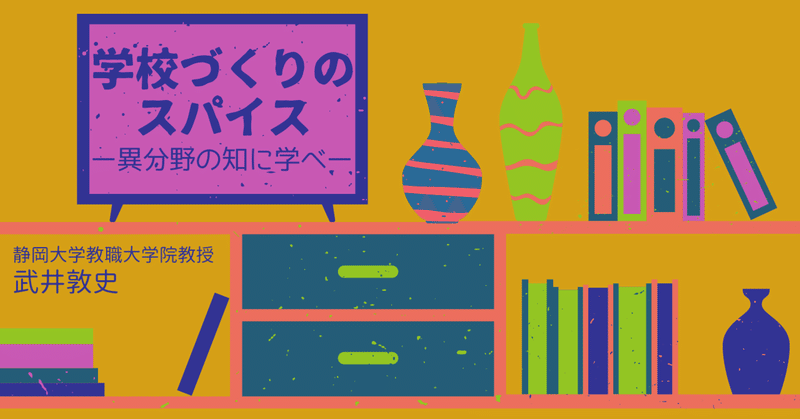
#66「欠乏」という資源~森恒二『自殺島』より~|学校づくりのスパイス
今回は森恒二氏のコミック『自殺島』(白泉社、1~17巻、2009~2016年)を足がかりに、若者の生への意思やその否定としての自殺について考えてみようと思います。この作品はタイトルも過激で場面の描写には生々しいところもありますが、そのストーリーからは人の命という問題に真摯に向き合ったことが伝わってくる作品です。未熟な青年たちが苦悩しながらも成長していく群像劇であり、再生の物語でもあります。

命の再発見
この作品の物語の舞台は「自殺未遂常習者隔離目的特別自治区」、通称“自殺島”です。自殺未遂常習者の医療や福祉が国の負担になり、国で死んだことにされて自殺島に送り込まれることに……。島とその半径1キロ以内の海から出ることは許されませんが、その範囲内では法律もなく、死ぬも生きるも、また人を殺めるのもすべてが自由という設定です。
自ら命を絶ったつもりの自殺未遂者たちは、目が覚めると自殺島にいることに気づきます。この島には、家屋や学校などかつて人が住んでいた形跡はあるものの、電気や水道などのインフラは何もありません。この島でどうやって生きていくのか? 多くの人はすぐにその場でも自殺をしようとしますが、他人の死を目にして死ねなくなる者もいます。
死ねなければ生きるしかありません。生きることを選んだ者たちはほかの生き残りの人たちと協力して、なんとか命をつなぎます。水の調達にはじまり、バナナや野草の採集、塩の精製、魚の捕獲や鹿やイノシシなどの狩猟、野菜の栽培、ニワトリや山羊の飼育、米の耕作にまで食料調達の術も拡大していきます。
もちろん島では仲間同士互いに協力するばかりではなく、人間間の軋轢も生じます。再三生じる自殺、食料の略奪、仲間への裏切り、売春、レイプ、集落間の諍いが抗争に発展し、時に加害者と被害者が入れ替わりながら怨恨による殺人も発生します。おおよそ社会で生じている問題が小さな島の中でもその縮図のようにくり返し起こり、徐々に明かされていくそれぞれの過去……。
この物語の主人公のセイも、こうした仲間との摩擦を経験しつつ徐々に生への意欲を取り戻していきます。そのきっかけは、自然の中に入っていくことでした。森で出合った鹿の美しさに感動して、本で読んだ知識の記憶を頼りに弓矢をつくって鹿を追います。
そして「僕にその資格はあるんだろうか……? あの美しく無垢な存在を殺す 命を放棄した事のある僕が命を奪う」(2巻、141~142頁)と自問しつつも、鹿に矢を放ちます。矢は命中して鹿は命を落とし、セイは鹿を食べることで命をつなぎます。そのときにセイの心に沸いてきた言葉は次のものです。「ありがとう……? ふいに――胸の奥から熱い感情があふれ その言葉の意味を理解した 命をくれた鹿に 鹿を育てた森に この島に温かい気持ちが湧いてきた 感謝の気持ち… 僕は生まれて初めて感謝をした」(2巻、180~181頁)。
欠乏という資源
若年層の自殺が近年急増しています。日本全体の自殺率を見るとバブル経済崩壊後の平成10年から平成22年までがとくに高くその後落ち着きを見せましたが、令和に入り、ふたたび上昇に転じました。
とくに気になるのは、10〜19歳の若年層の自殺率の増加です。若年層の自殺は凸凹はあるものの上昇基調を続けており、令和4年度には796人(人口10万人あたり7.4人)の若者が自殺により命を落としました。自殺率としては過去最高、過去5年間に約1.5倍の増加を示しています(「令和4年中における自殺の状況』2023年3月 厚生労働省自殺対策推進室ほか)。ざっくりと見積もると、人口10万人程度の市の中で毎年一人の若者が自ら命を断っている計算になります。自殺未遂者はそれよりはるかに多いでしょう。
筆者は自殺を「悪」と断罪するつもりはありません。自殺増加の背景にはさまざまな要素が複合的に関係していると考えられます。
けれども学校という社会で生きた結果、若者が自ら死を選んでしまうとしたら、学校などない方がマシです。本の中には、ストーリーとは切り離されて森氏自身の自殺に対する考えが表現されている部分があります。
「なるべく勝ち なるべく得で なるべく上に行くよう私達は教育されてきた……(中略)……具体的な大きな理由(ひどいいじめや生活苦 健康問題など)がなくても 自殺者は増えている 仕事があり 飢えていなく 家族がいても気うつになり 自殺する人がいる 他人がわからなくてもその人にとっては 自ら命を絶つ程 苦痛な暮らしなのだ それは何故だろう 私は“喜びを感じる能力”が重要だと思う。そして 今の社会は その重要なスキルを あまりに無視してはいないか」(10巻、158頁)。
さて、「喜びを感じる」ということが今日むずかしくなってしまっているのはなぜでしょうか? 筆者はその原因の一つに「欠乏の欠乏」があるのではないかと考えています。
衣食住のような物理的な課題であれ、安心のような心理的な課題であれ、「自身に何かが欠けている」という対象がはっきりしていれば、そこから他者や事物を求める気持ちが芽生え、またそれをきっかけに社会とのつながりを回復させていくこともできるはずです。ジクソーパズルの凹みのようなものです。
ただしかつてと異なり、現代社会では明確な輪郭をもった欠乏を自動的には与えてくれません。「漠とした不安」はあってもその正体である具体的な欠乏に気づけず、自分の存在価値が自他双方に対して不透明になっています。
主人公セイが食を求めて鹿を追ったように、欠乏から求める心は「生きる意欲」の一つの原初的なかたちにほかなりません。上述の鹿を殺めて食した場面の後、セイは心の中でつぶやきます。「生きよう この島に 寄り添い 環る命の 輪の中で」(2巻、184頁)。
こんな現代だからこそ、欠乏を資源と考える逆転の発想が必要なのではないかと考えるのですが、どうでしょうか?
【Tips】
▼10~39歳までの年代の死因の第1位は自殺です(令和2年)。
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)

【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
