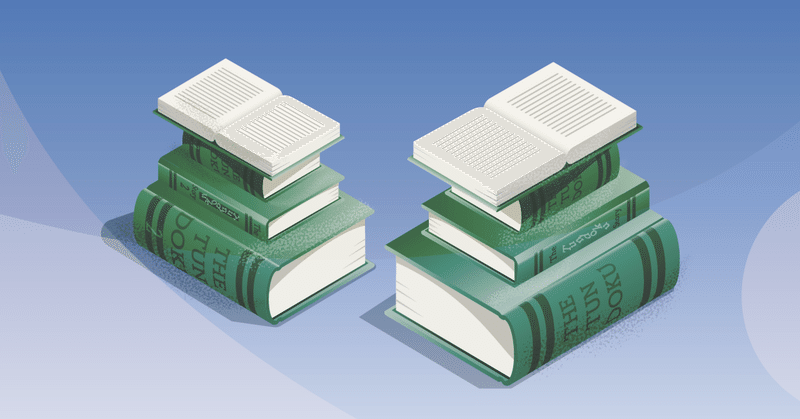
雑感記録(82)
【プロレタリア文学再読】
先週から突如の係替えがあり、日々忙殺されながら過ごしている。本当に急に決まったことで引継ぎもままならず、本当に0からのスタートで非常に苦しい時期である。幸いにも周囲の人が助けて下さるので何とかここまで来られている状況である。しかし、精神と身体がどうもうまく嚙み合わず体調も中々優れない。そこで急遽、木曜日と金曜日お休みを取ってリフレッシュを試みた。ところが、不幸なことにお休み初日で職場から連絡が入る。リフレッシュもクソもない。
最近、本当に文字を読むのが辛くなった。過去に何度も書いているけれど、忙しさを理由に本を読まないのは僕の中で怠慢だと思っている。しかし、人間極限まで行くとそんなことを考える余裕すらなく、帰宅後はご飯を食べて風呂入って寝るという必要最低限のことしか出来なくなってしまった。この状態がすぐに終わればいいのだけれども…。
人は慣れる生き物だ。いずれ慣れてしまえば精神的にも物理的にも余裕が出来てきっと文字を読めるようになるだろう。しかし、僕は今の仕事に慣れたいとは思わない。自分で選択したものでは決してなく、ある種"エサ"の如く与えられたものに僕は自身の意思を感じない。それをしないという選択肢もあるだろうが、それを選択してしまえば会社が困るのではなく自分自身が困るということを知っているからこそ厄介なのだ。ん、待てよ…。そしたら僕は一生文字が読めなくなるのか…?
こういった状況を打破すべく、昨日神保町へ行ってきた。久々に実店舗に赴き本を購入するのは3ヶ月ぶりとなる。いや、実に感慨深いものがある。

本を買うと不思議と「よし、読もう!」というスイッチが入る。これは本好きには分かって頂けることかと思う。新しい本を買うとそれを読みたくなるというようなものだ。本当はもっと買いたかったのだけれども、体力的に余裕がなくて結局8冊程度しか購入できなかった。いつもならリュックにパンパンに詰めて、それでも足りなくて手提げカバンもパンパンにするところなのだが、そんな余裕すらなかった。いやはや、労働とは恐ろしいものだ。
神保町から帰宅して本を読み耽る。この中の2冊、『小林多喜二日記』と『プロレタリア文学論』を読む。これが結構面白い。というよりも僕が興味関心がある分野ということもあるからだ。
僕は大学3年生の頃からプロレタリア文学にご執心であった。自分でもなんでかなと思い返してみるのだが、具体的にどうだというのはあまり思い出せない。ただ唯一覚えているのは、大学3年生の時に横光利一の『機械』を論じた時に浅ましくも"マルクス主義"に関連付けて論じたことが端緒だったように思われて仕方がない。
加えて、他の授業で中野重治の『雨の降る品川駅』を読んだこともあるだろう。検閲で随分と削除されてしまった作品であったが、全集版で削除された部分も読んだ時に、その描写に心打たれたということもあるだろう。
何と言うか、僕はこの当時ある種の文学理論的なところに非常に興味を持っていた。色んな授業へ出る中で蓄積されていく訳だ。そういうのを学んでいくと大抵ぶつかるのがマルクス主義だ。デリダもマルクスの亡霊とか何とか言ってるけれども、本当に至る所にそいつは現れてくる。大学生当時、それを感じた僕は「じゃあ、手っ取り早くマルクス主義勉強しちゃえば良くね?」と何とも短絡的に考えてしまった訳だ。
しかし、そうは言ったって「じゃあ、マルクス主義を勉強するか!」と言ったところで何から始めればいいのか分かる訳もない。況してや、いきなりマルクス読むかとは当時の僕にはなれなかった。そこで、日本文学を勉強していた僕はプロレタリア文学を学べば自ずと近づけるんではないか?とこれまた短絡的に考えた訳なのだ。そうして大学3年生の後半からはずっとプロレタリア文学にご執心であった。
しかし、日本のプロレタリア文学は非常にややこしい。というのも派閥というか、所謂〇〇派みたいなものが多くあるからだ。例えばだけれども、文藝戰線とかナップとか沢山のグループが解体されては、新しく作られたりというのが絶えず繰り返されるのでそれを逐一追っていくのは非常に骨が折れる。
加えて、その各グループがどういったマルクスの解釈をするかでも分かれてくる。専門的な話をするなら、所謂、福本イズムか山川イズムのどちらを採択するかでも変わってくる。もうこれが非常にややこしい。僕は正直ここで挫折してしまった人間の1人である訳なのだが…。
僕はマルクス主義云々も勿論重要であると考えていたが、何より重要であると考えていたのは転向後の姿勢である。プロレタリア文学にとって「転向」という問題は切っても切り離せないことである。詳細については吉本隆明の『転向論』など読んでもらえればよいだろう。投獄される中でみなが転向していき、左翼文学から足を洗っていく作家が続出する訳だ。そんな中、中野重治は転向後も書き続けたというところに僕は面白さを覚えた。
また、色々な人が「プロレタリア文学論」などと様々な方法論を論じているのも面白い。どれが良いか良くないかとかという問題は置いておくとして、結構面白いことを書いている。これは作品の技術的なところでも非常に有用な姿勢を示してくれているという点で面白い。
小説などはそもそものスタートがブルジョアジーに属する文化であり、そういったものを愉しむという文化はブルジョアジーのものである。言いかたは非常に悪いが、「貴族の高貴なお遊び」みたいなものだと思われる。今では大衆に親しまれているということもあり、そういったことは意識されずに来ているが僕はこの感覚は忘れてはいけないと思うのだ。
むしろ、大衆に親しまれるという点に於いて意識的に貢献したのはプロレタリア文学であると考えている。そもそもプロレタリア文学は労働者のための文学であり、それは我々働くものに向けた文学である。今では当時と社会情勢が異なり、明確な差というものが見えにくくなっている状況であるからあまり意識されないことなのだと思う。僕は個人的に大衆文学の原点的な部分、つまり広く読まれるべきという姿勢だけ見るのであればプロレタリア文学が開いた道は大きいと思わざるを得ない。
ただ1つ言えるのは、現在の大衆小説と比べてしまうと申し訳ないがレベル感は大分異なる。現在の大衆小説は本当にただの娯楽として屹立し、愉しませるということに主眼が置かれている。ぶっちゃけ、楽しめれば内容なんてのは何だっていい訳だ。
ところが、プロレタリア文学の場合はそうはいかない。常に労働者の立場に立ちそのありのままの生活を描くこと。これに尽きる。愉しませる以前の問題として、考えさせるというのが大前提としてある訳だ。ある意味でこちらの方が思想性はどうであれ、我々の生活に密着して描かれているという点に於いては同じ地平に立った文学であり、これこそ大衆的であると言えるのではないだろうか。
僕は以前の記録で「生活感の溢れる作品が好きだ」という話を書き、最後に中野重治を引用した。
これは中野重治が戦後まもなくして書いた『文学論』ではあるのだが、これ以前から一貫している姿勢である。我々の生活にじかに接触していくことから始まる文学。これは非常に大事な姿勢であるように思われて仕方がない。
僕が今もなおプロレタリア文学を読み続けるのはこういったことを感じたいが為なのである。生々しい現実と生活がそこに描かれており、時代を経て勿論現在と事情は異なっているかもしれないが、通底しているものは同じような気がしてならない。
労働というのは現在の我々にとっては切っても切り離せない関係である。生きていく術としての手段として、我々は選択しなければならないからだ。労働をしないことも選択できるだろうが、そうすると世間の風当たりは厳しいし生きていくことが出来なくなってしまう。逃げたくても逃げられない関係性なのである。
しかし、労働と一言で言ってもそれに対しての思いは人それぞれである。労働が愉しいと思える人も居れば、労働などクソだと思う人も当然いる訳だ。あるいは、労働なんてしたくはないけれど、生きるために仕方なくしているという人も居る。僕はどちらかと言えばこれだ。仕方なく働いているという部類だ。多分、僕だけではないと信じたいところだが。
そんな時にプロレタリア文学を読むと、何だか自分自身がちっぽけだとも思えるし、「時代は隔てていても感じることや考えることは同じなんだな」となることが多い。これこそプロレタリア文学が徹頭徹尾、我々の生活を起点に成り立っているからこそであると思われて仕方がない。注意したいのはただの共感ではなく、各々のシミュラークルのアウフヘーベンによるところの共感である。
プロレタリア文学は何より「生きること=労働=死」という連結が常に存在している。僕はこの連結が現在も通底しているものだと思われる。この「死」というものをどう捉えるかにもよるが、僕は物理的な「死」と社会的な「死」の2つを想定している。
現在では物理的な「死」という観点からすると、あまり見られないように思われる。どちらかと言えば社会的な「死」の方が現在に於いては見られるものであろう。これは簡単に想像が付くだろう。仕事で何かやらかして、SNSに晒上げられ、職場に居られなくなり、職場を辞め、将来を奪われる。勿論、自業自得である場合もあるだろうが、一概に自分だけが悪いことも無きにしも非ずである。
僕がプロレタリア文学を好んで読むのはこの点にもある。つまり、作中の彼らは必死に生きようとするのだけれども、それは結局労働というものに絡めとられて生きているか死んでいるか分からない状態であるというところだ。僕らは労働によって麻痺させられていることをまざまざと見せつけられる。自然にやられるとはまた異なるが、プロレタリア文学にやられたいのである。
プロレタリア文学、オススメなのでぜひ。よしなに。
人生に對して何者も要求しなかつたら、その作者は眞の藝術家であり得ない、人生をありのまゝ描く、といふ事しかその作者に、作的要求がなかつたら、その人は冩眞家よりもおとる。(中略)
けれども日本には、小説とはたゞ單に、この世の事實を「無意識」にたゞ「克明に」如何にも「如實」に、描かうとしかしてゐない作家が實に多いこと。作者は夢想家でなければならない、と言はれる程、作者は人生に對して、絶えず「要求」をしてゐなければならない。(中略)
然し、彼等が如何程、人生に對して、やつきとなつて、要求を續けても、人生はついに循環小數である。だから、「いかなる」要求も「夢想」でしかなくなる。循環小數の事實を知つてゐるものは、その要求を、だから、何時も「夢想に過ぎない」「何になる、フン」「あゝあいつも馬鹿だ!」と言ふ。
P.13,14
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
