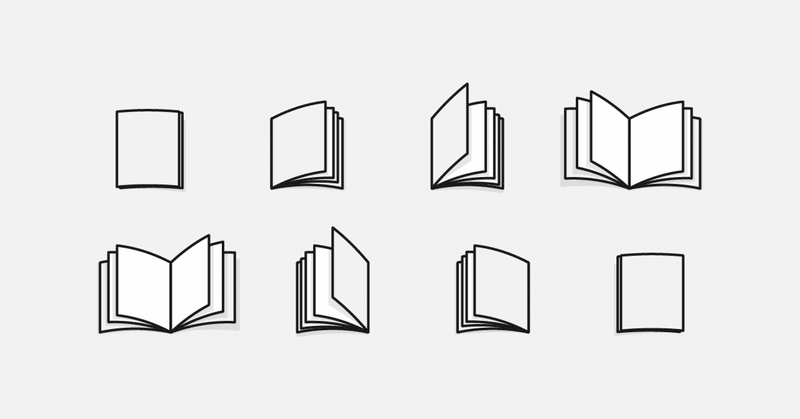
雑感記録(182)
【芥川賞雑感】
先日、芥川賞の発表があったらしい。
僕はテレビを不所持なのでニュースなど滅多に見ない。本当につい昨日にこのことを知った。それでネットにある、今回の受賞者の記事を手探りしながら読み進める。しかし、この手の記事は作品内容について云々というのはあまり書かれず、その作者の背景やある種の生き様みたいなところを深堀しているに過ぎない。もうほとほと呆れてしまう。
そんな中で、たまたまこんなサイトを見つけた。
このサイトには歴代の芥川賞の選評などが掲載されており、今回の受賞者とか実際どうでもよくなってしまった。それで自分が好きな作家が芥川賞を取った当時は誰が選出して、どのような選評を書いているかが気になった。サイトをどんどんスクロールさせて見ていく。これが結構面白いのである。僕は2時間ぐらいずっとモニターにかじりつきだった。
個人的に選評の内容も当然に面白かったのだが、歴代の受賞者と併せて候補作も紹介されており、またその年の選評者も掲載されているのが良かった。古井由吉や黒井千次が選考委員をやっていることに驚いたが、その古井由吉にしても黒井千次にしても芥川賞を受賞、あるいは候補作となっている訳である。後藤明生も候補作に選出されていたが結局受賞することは無かったようだ。好きなんだけどな…後藤明生の作品。
この歴代の芥川賞の受賞作と候補作を見ていると凄く不思議な感覚がした。というのも、芥川賞受賞者は片手で数えられるぐらいしか知らないのに、候補となった人はさすがに片手で数えるには厳しい。しかも、その人の作品が結構好きだったりもする。先にも少し触れたが後藤明生や黒井千次、あとは鷺沢萠なんかが該当する。これは完全に僕個人の好みではあるのだが。
芥川龍之介賞規定
一、芥川龍之介賞は個人賞にして廣く各新聞雜誌(同人雜誌を含む)に發表されたる無名若しくは新進作家の創作中最も優秀なるものに呈す。
二、芥川龍之介賞は賞牌(時計)を以てし別に副賞として金五百圓也を贈呈す。
三、芥川龍之介賞受賞者の審査は「芥川賞委員」之を行ふ。委員は故人と交誼あり且つ本社と關係深き左の人々を以て組織す。
菊池寛・久米正雄・山本有三・佐藤春夫・谷崎潤一郎・室生犀星・小島政二郎・佐佐木茂索・瀧井孝作・横光利一・川端康成(順序不同)
四、芥川龍之介賞は六ケ月毎に審査を行ふ。適當なるものなき時は授賞を行はず。
五、芥川龍之介賞受賞者には「文藝春秋」の誌面を提供し創作一篇を發表せしむ。
「芥川龍之介賞規定」『文藝春秋』
(文藝春秋社 1935年1月発行)P.110,111
芥川賞規定については設立当時にはこんなような宣言がなされた。「無名若しくは新進作家」とあるので、知らなくて当然ちゃ当然かもしれないが…いやいや待てよ。僕が生まれていない時に受賞した作品は、既に僕にとっては「古典」なのである。ところが、僕は過去の受賞作を知るどころか、「え、この人誰ですか?」という人あるいは作品が多いのである。芥川賞を取っても忘却の彼方へ行く作家や作品も当然にある。そういえば以前「古典」を読むことの大切さなんか書いてみた。
しかし、どうも手にしようという気がしない。自分から進んで例えば「じゃあ、菊村到(1957年上半期受賞)を読むか!」とはどうしてもなれない。小説は人の名前で読むものではないが、あまりにも知らないのは恐怖というものである。実際僕は今本当に適当に「菊村到」という人の名前を書いたが、僕からすると「誰?」という感じである。調べれば多くの著作を残しているらしいが1冊も知らない。
僕が偉そうに言えたことでは決してないのだけれども、これは詰まるところ小説的な強度が足りなかったという事なのではないだろうか。それが「古典」として成立するには強度的な部分が足りなかったのではないかと思われて仕方がないのである。と書いたが、僕は常々「小説的強度」という言葉を使用することがある。この際だから僕の想定する「小説的強度」というものを書いてみたい。
僕が使用する「小説的強度」という言葉は本当に単純な話で、「外部に耐えうる力の強弱」「小説の自立」ということを指している。僕は予てより「テクストはそれ自体では自立しない」という風に考える人間の1人である。つまりは、大勢の人の読みにより築き上げられる類のものであると考えている。それは例えば読者個々人の感想や口コミ、あるいは批評家による新たな読みの提示など。そういったものが小説を支える強度だと僕は思っている。
これは過去の記録で示した通り、読みのプロ(これは小説家でも、批評家でも)に正当に「批評されること」が重要であるはずだ。そこに作者自身も気づけ得ない新しさを常に発見し、そして後進の人たちがそれを読み、どんどん更新させていくというその一連の中で小説は強度を増していく。「小説的強度」と言うのは詰まるところ、「小説の魅力」と言い換えても良いのかもしれない。
その「小説的強度」が強い作品が結局残り、僕らの世代になって「古典」として輝かしく眼前に現れるのである。それこそ古井由吉の『杳子』あるいは『妻隠』、その前で行くと『男たちの円居』とか。そのような作品はまず以て選評され、その後に柄谷行人を始めとした批評家に批評されて行き、どんどん「小説的強度」を増している。その後、後進の人たちにより更なる批評がなされて行き、その小説の強度は増していく。
大江健三郎なんかも最初は『死者の奢り』が候補作となり、その年1958年7月に『飼育』で芥川賞を取る。無論、大江健三郎の技術による作品そのものの強度もあるが、あらゆる小説家や批評家がその強度に引き付けられて、触発され、彼らの手によりさらにその「小説的強度」を増し、小説は小説として初めて自立する。そしてそれらは語られ続け、常に更新され続けるのではないのだろうか。
そういう「小説的強度」を持った作品がきっと「古典」として読まれるのかもしれないのではないか。芥川賞を取ってもこうして忘れ去られてしまうということは、僕には詰まるところその「小説的強度」が足りなかったということなのではないかと考えているのである。
しかし、これは僕が「よし、過去の芥川賞作家の作品を読もう!」とならないことの説明にはなっていない。あくまで、芥川賞を取っても忘れ去られてしまうということは、詰まるところその「小説的強度」が足りなかったということを言いたかったのである。
では、なぜ僕が過去の芥川賞作家の作品を読むことをしないのかについて改めて考えてみたい。と書いてみたが、実は既に答えを書いている。
ズバリ、「名前を知らない」からである。
「名前を知らない」というのはつまり、知名度の無さである。それこそ僕は近代文学を専攻しており、プロレタリア文学を専門にしていたとはいえ、現代文学にもそれなりに興味がある。自分で言うのもおかしな話だが、それなりにその当時の批評家や小説家の小説やエッセーは読んできた…はずだ。だけれども、その中で名前が出ていた記憶は個人的にはない。強いて言えば、車谷長吉は知っていた。金井美恵子の『目白雑録(ひびのあれこれ)』で出てきたので覚えている。
非常に雑で尚且つ物凄く酷い書き方をしよう。
同時代の小説家にも書いてもらえず、批評家にも何も触れられずに無関心を貫かれている。ということは「眼にも止められない」ということで、そこら辺の石ころと同じである。きっと賞を取って満足してしまったのだろうと僕には思われて仕方がないのである。
あるいはこうも考えられる。僕と同様に、別に文章を生業にして食べていこうという気概はなくて、趣味の延長線上として書いていたらたまたま文章がうまくて、皆に(といってもこれはせいぜい本当に近くの人)ちやほやされて、何だかトントン拍子にうまく進んでしまって、別になりたくはないのにそうならざるを得なくなってしまった。こういったパターンだって十分に可能性としてはあり得る。
そういった作品に果たして「小説的強度」は存在しうるのか?
ということを考えると、今の作家の人たちは断然いい。と言うよりも、昔に比べてある種「そこまでの小説的強度を持つ作家が増加する」可能性を多く孕んでいるのである。ある種、うらやましい状況ではある。ここについては詳しく述べることにしよう。
僕は先に「あらゆる人に読まれ批評されることで小説的強度を増し、作品として自立する」というように書いた。昔の場合はメディアもあまり発達していたとは言えず、今の僕の状況のように、個人が何かを書いて発信する場というのが無かった。今こうして簡単に自分自身の思いや考えを大多数の人間に伝えることは容易になったし、当然、逆も然りである。あらゆる情報が気軽に入るようになった。
最近はSNSなどで僕みたいな所謂エセ批評家も存在するわけだが、こういうような作品の感想だったり、読み方などを懇切丁寧に書いてくれる人もちらほら存在する。単純にその母体数が多いので、幾ら僕のようにクソみたいなことを書く人が大勢いいても、素晴らしい読みを提供してくれる人は存在する。正当な批評をしてくれる人もいる。中にはネトウヨみたいなクソみたいな奴もいるけど、そんなのは無視しておけばよい。
つまり、単純に作品が眼に晒される機会が非常に多いことに加え、批評を書く者、感想を書く者、書評を書く者…様々な人たちが様々な視点から作品を作品たらしめようとしている訳なのだ。そういった意味では、今の作家はかなり恵まれているのではないだろうかと思われる。だが、実はここに1つの落とし穴が存在する。
それは以前の記録でも書いているが、「書く側も読む側も、読解するレヴェルが低下している」ということである。これは事実僕も含めてそうだし、広く全般に言えるのではないかと感じている。だって、僕なんか延々とくだらないこと書き続けているんだよ。これのどこに読解力があるのさ?だからと言って僕は開き直りはしないが、少なくとも最低限の水準の読解力は保てるように日々研鑽を重ねているつもりである。
これも過去の記録に書いたが、要はSNSが発達して便利「過ぎて」しまうが故に僕らの読解力なるものは低下したのかなとも思う。これは書評について書いたときに詳細は書いているので、そちらを参照されたい。
つまり、このSNSで多くの人にあらゆる形で作品が読まれるということでその「小説的強度」を高めはするが、しかしその実は厚みが増しただけで、構造はスポンジのようにスカスカになりかねない危険性を孕んでいるということである。偽りの「小説的強度」である。見てくれの「小説的強度」である。数が物を言い、その書かれた中身ではなく、その小説について語る「数」が多ければ多いほど、どんどん「小説的強度」が増していくと思ったら大間違いである。
ある意味で僕が昨今の芥川賞や、最近の小説に興味関心がないのはここにあるといっても過言ではない。
結局、選評する人たちはその作品がどうであれ、唯一公の場で正当に批評してくれる存在である。しかし、それでは不十分であると僕は考える。結局彼らは言ってしまえば「小説のプロ」な訳である。そうすると当然に小説の観点から物事を語り、勿論ウィットに富んでいる(という書き方は失礼すぎるな…)選評をする。しかし、そこにはある種の限界があるようにも思う。
そこで批評家の出番である。……ところが……。どうだろう。今の時代に批評を書いてくれる人は居るのか。いや、そもそもその人のお眼鏡にかなわなければならないのだから、その前提条件をクリアする必要がある。そこで興味関心も持たれなければ「正当な」評価が受けられない。いや、むしろそれよりももっと大きな問題。「批評家って今、存在しているの?」
では、SNSを頼ることにするか。自分の都合のいい記事が溢れに溢れ、そして中身は僕のように大したこと書いていない作品ばかり。でも、数だけはいっちょ前にあるから、そこを一括りにしてしまえばそれは「その作品が良い」ということの証明になる!しめしめ…。と悦に浸り、結局「賞を取ること」がゴールになってしまって作家生命は終了するのである。本当の意味で。
だから僕が今の小説やそういった賞が嫌いなのは、「中身の無い数」に頼らざるを得ない状況がそこに在るからだ。不可避なんだ。それは作家が良い悪いとかの問題ではなくて、選評者が良い悪いとかの問題ではなくて、社会的な部分でそういう考え、つまり「中身の無い数」が無意識のうちに僕らに根付いているということそのものが何か嫌なのだ。そして、それをまざまざと、そして作家は分かっているか、あるいは分かっていないかは別としても、堂々と利用しているから嫌いなんだ。
その背後に僕は常に付きまとう「中身の無い数」かっこよく「空虚な数」とでも言っておこうか?それが気に食わない。それに抵抗するのが作家なんじゃないのかとも思ってみたりするが、もう今更言ったところで感があるので極力関わらない方がいいかなと思って実は距離を置いているのだ。
だからね、別に最近の小説を読もうと思えば読める。だけれども、最近の小説に手が伸びないのは、僕がその「空虚な数」によって支配されていることを自分自身で自覚していても、それをまざまざと見せつけられるのには辛いものがある。格好つけている訳じゃないけど、僕は今の小説とは距離を置きたいと思っているのである。
これが僕が「最近の小説を読まない」ということの真意である。
自分自身への記録へのアンサー的な記録である。
よしなに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
