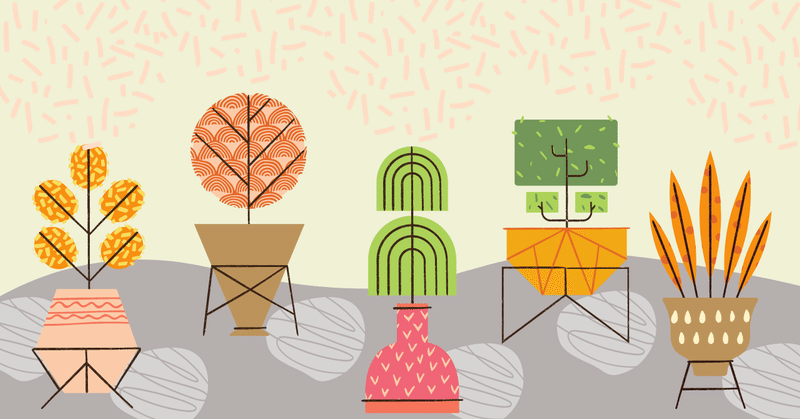
2050年のお庭
「都丸さん、おはようございます。今日は、2050年12月14日。天気は快晴、日中の気温は12度。」
朝起きると、ロボットが元気に話しかけてくる。
もう12月14日か...
彼女がいなくなって、ちょうど1ヵ月が経った。
真っ暗な窓から少しずつ、心地のよい「太陽光」が入ってくる。最新のテクノロジーが搭載されているこの窓は、夜は光を遮断し、朝は自然の太陽光と相違ない光が入るように設計されている。
実家が日当たりがよかったこともあって、人工的な太陽光なんて冗談だと思っていた。でも友人のマンションにある最新型の窓から海に沈む夕日を見て、すっかり心変わりしてしまった。もちろん本物の太陽光が入るマンションの家賃は、自分の収入と比べると不釣り合いだということもある。
今のマンションの間取りは2LDK、55平米。マンションの2階になるが、毎日富士山を拝むことができる。平成時代に建てられたマンションをリノベーションしているので、外観は結構古い。かれこれここに住んで3年半が経つ。
窓を開けると、現実世界が広がる。北東向きで、日当たりはあまりよくない。ということで、僕はめったにベランダには出ないのだけれど、ベランダはそれなりに広く、テーブルに椅子を2脚、植物を7個ほど置いている。そのうちの2個は彼女と一緒に買ったものだ。
彼女はこのスペースを「お庭」と呼んで、植物を育てるの好きだった。モンステラの鉢の中に、彼女が持ってきた亀の置物が置いたままになっている。
彼女が出て行った理由は分からない。
ある土曜の昼過ぎに、表参道のカフェで待ち合わせていた。すると突然彼女から、急用で今日は行けないとメッセージが来た。「OK、また来週会おう」と返事をしたが、彼女の文面がどことなくいつもと違う気がして、何か問題あった?と聞いた。
夜になっても返事がなくて、既読にもならない。電話をしてみたが繋がることはなかった。
翌朝になってもずっと未読のままで、電話をしたけれど繋がらない。
居た堪れない気持ちになって、滅多に使わないAIのカウンセラーに相談をした。自分の毎日の体調管理アプリと連動していて、医療・遺伝子データ、性格分析も入っているから、その辺の人間のカウンセラーより的確なアドバイスがもらえると評判のやつだ。
一連の出来事をAIの「町田さん」に話したところ、結局自分は彼女に振られた可能性が高いということが分かった。AIのカウンセラーは、個人情報に配慮する必要があるから断定はしないけれども、「総合的にデータを分析」したところ、彼女がなんらかの事件に巻き込まれている可能性は非常に低い、ということだった。つまり、このアプリのデータか、それと連携している何かのデータが、彼女がいつも通りの生活をしていると示しているのだ。
最後に話したってよいじゃないか、そう思い、日曜の昼に彼女の家のある駅まで出かけてみた。彼女は実家暮らしで、一度も家には行ったことがないから、住所までは知らない。
駅前のカフェでコーヒーを飲みながら、外に通る人を眺めていた。彼女のシルエットに似ている人が通るたびに、全身がビクッと硬直するのが分かった。次の瞬間違う人だと分かると、自分は一体何をしているんだという気持ちになって、コーヒーが飲み終わらないうちに家に戻ることにした。
そうやって今週はモヤモヤしながら仕事をした。VRのマッチングサイトで何人かとデートもしたけれど、なんだか虚しくなって、やけくそになって、彼女と一緒にやったゲームのアイテムを全部売りに出した。ゲームのアイテムは、NFT(ノン・ファンジブル・トークン)というもので、マーケットプレイスで自由に売買することができる。
そして、缶ビールを開けて、窓をマイアミの夜景に設定した。
「プスッ、プスッ」
どこからともなく、おかしな音が聞こえてきた。
風のせいかと思ったが、何度か聞こえてくる。意識を集中して、音の方向を探ってみると、どうもベランダの方から音がしているようだった。
サッシを開けてベランダに出みると、ものすごい勢いの風が吹き出した。かなりの衝撃に息が止まりそうになる。砂がものすごい勢いで舞い上がって、視界が完全に遮られる。思わず目を思つぶったが、不思議とその砂を顔で感じることはない。
恐る恐る目を開けて足元を見ると、自分は浮いているということが分かった。いったい何が起きているというのだ...。
足元に、何か緑の影がちらっと見えた。目を凝らしてみると、彼女が残していった亀の置物だった。
その亀から足がにょきにょきと伸びて出てきた。そしてそのつま先、と言っていいのか分からないが、その部分をすっと伸ばして僕の手を取った。そして、下へと下がっていった。砂のせいでどれぐらい下がったのかは分からないけれど、気がつくと足が地面に触れているのを感じた。
そこに足を付けて立ってみると、もう突風は収まっていて、真っ暗なところにいた。淡い光がところどころに、ぼんやりと射している。地面は、生暖かい砂のようなものがあって、さらさらしていて気持ちよい感触がする。しばらくいると目が慣れてきて、上を見上げると天井がかなり高いということが分かった。
「おい、一体何なんだ!」
亀がもそっと動いたが、何も返事がない。しかたなく、僕もその砂の上で寝転がってみる。砂は足で感じていたよりも暖かくて、体がじわじわ温まっていくように感じた。どうしてこんなところに来てしまったのだろう。そんなことを考えていると、急に空腹に襲われて何かを食べずにはいられない気持ちになった。
食べ物を探しに行こう。そう思い立って、歩いてみることにした。亀は寝ているのか、少し突いてみたけれど、ビクともしないので、そのまま置いていくことにした。
少し歩くと目の前に小さい丸い光が見えて、その方向に歩いていくと、それがだんだんと大きくなっていく。そこが出口になっているようだ。
出口を出ると、そこには、ガラス張りの大きな建物があった。その入り口には、CHECK INと書かれたコーナーがあって、スクリーンが5つ並んでいる。その先にはカフェがあって、奥には公園が見える。少し歩いて見ると、公園というよりきれいに整備された広大な森という感じだ。老若男女が集まっていて、一人で過ごしている人もいれば、グループで集まってスポーツをしていたり、子供を連れた家族がピクニックをしていたり、人種もバラバラだ。
カフェにはカウンター席があって一人で座っている男が一人いた。カウンターに座っているのは、30代後半ぐらいに見える男性だった。鼻が高く、肌は黒めで、カールした黒い髪の毛。Tシャツにジーンズで、分厚い本を読んでいる。スペイン出身の友達を思い出させる雰囲気を持っていた。
かなり集中しているようだったので、声をかけるのに戸惑いつつ、少し目線を送ると相手こちらを向いて、「ヘイ! 」と声をかけてきた。手首に付けていたバンドが即座に通訳をしてくれるが、簡単な会話なら自分でできる。
「ハイ!」と返した後で、なんて切り出すべきかと思ったが、とりあえず、「元気?」と聞いてみる。
「元気、あなたは?」僕も元気、ありがとう、などと定型的な挨拶をした。アレックスという名前の男だ。
「一つ聞きたいことがあって、変な質問かもしれないけれど、ここはいったいどういう場所なんだい?」
「僕も全て分かっているわけではないけれど、言えることは、ここはとても安全で気楽な場所であるということだね。そして十分な食料があって、安全に眠るところがある。あっちの世界のものはなんでも買うことができるし、働く必要がない。毎日気楽に暮らしている。ただ、ある程度の額で売れた場合だけれどね。」
「あっちの世界って...?」
「分かるだろう、君が来た世界のことだよ」
アレックスは、そう答えると、本に目線を戻し、もう質問には十分に答えたから、自分の時間に戻るんだというそぶりを見せた。
ある程度の額で売れるというのはどういうことなんだろうか...。
カフェは、いつも行く無人カフェのように、コーヒーやお酒のボトルがずらりと並んでいて、そこでロボットが動き回り、飲み物を作ってくれる。ただ、いつもと違うのは、なんというかロボットの動きが滑らかだということだ。人間の動きのようにスムーズに動いていて、なんだかダンスを見ているような気分になってくる。
手元にあるタブレットでメニューから、モヒートとパニーニをオーダーする。自動で運ばれてきたモヒートをすすり、パニーニをひとかじりすると、ようやく頭が動いてきた感じがした。
ふと気がつくと、いつの間にかカウンターに座っていた男はいなくなっていた。他のお客も少しずついなくなっている。自分はこの後どこに行けばよいのだろう。CHECK INと書いてあったから、ここはホテルなのだろう。泊まれるのだろうか。
カウンターに行って、CHECK INのボタンを押してみる。僕の「アドレス」を聞かれたのの、名前を入力して、「.sat」を選択する。「.sat」は僕が使っているブロックチェーンのネットワークのアドレスだ。これで、いつも給与の受け取り、買い物、資産の運用など色々使っている。
入力が終わると、メッセージが出てきた。
CHECK INしますか?
一度CHECK INをすると、あなたが来た場所には戻ることができなくなります。また、いかなる理由であっても、CHECK INを取り消すことはできません。
僕がきた世界に戻れない...?それはありえない。
しかし、さっき会ったスペイン人が言う通り、この世界も住みやすいかもしれない。だが得体の知れないこの世界から出られないのは嫌だ。
カウントダウンが始める。
あと30秒、20秒、10秒、5秒前...
僕はキャンセルボタンを押した。
その瞬間、砂が舞い上がり、また完全に視界が遮られる。
その砂が少しずつなくなり、やがて落ち着くと、僕はベランダに戻っていた。一体何が起きたのか、頭が混乱したまま、とりあえず部屋に入ろうとサッシに手をかける。すると、部屋には知らない人たちがいた。
男性と女性、そして彼らの子供と思われる男の子2人が食事をしている。自分が持っていた家具や植物はなくなっている。ただ部屋の隅に自分のスマグラ(スマートグラス)だけ置かれていた。
「一体どういうことなんだ。僕は実は死んだのか、または彼らが...」
僕の存在に、家族は誰一人として僕に気づかない。さらに試しにサッシをノックしてみたけれど、誰も気づかない。思い切って部屋に入ってみたけれど、僕のことが見えていないようだった。とりあえずスマグラだけもって家の外に出ることにした。
家の近くのいつもの小さな公園に来てみる。スマグラをかけると、売り払った自分のアバターが売れたと通知が出た。
「まさか...」
自分のアバターは、購入者から再び売り出されていた。思い切って、それを買い直してみる。
その途端、公園中に砂が舞い上がった。公園全体なのか自分の周りなのかはわからない。ものすごい勢いで、痛くてもう目を開けていられない。涙が出て、目を瞑る。呼吸もできない。
「もう無理だ...」
このまま意識が飛びそう...というところで、急に収まった。公園は何事もなかったかのようで、ベンチに座っている僕がいた。
僕の家、少なくとも数日前までは家だった場所に帰って、恐る恐る家のドアを開けると、さっきまでいた家族はいなくなっていた。
自分のものが置いてある殺風景な2LDK。何も変わっているところはなかった。ソファ、テーブルと椅子、ベッド、観葉植物のある「お庭」。
ソファに座ってスマグラをかける。僕のアドレスに、ミステリーボックスが届いているという通知があった。送信元のアドレスを見ると、彼女のアドレスだった。
「Open」のボタンをクリックする。
すると、僕のアバターは鶴に変わり、同時に亀のアバターが出てきた。レトロなドット絵で、データを見ると、28年前のアンティークNFTだった。
-- THE END --
本ストーリーに出てくるNFTのリンクです:
https://opensea.io/collection/the-garden-in-2050
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
