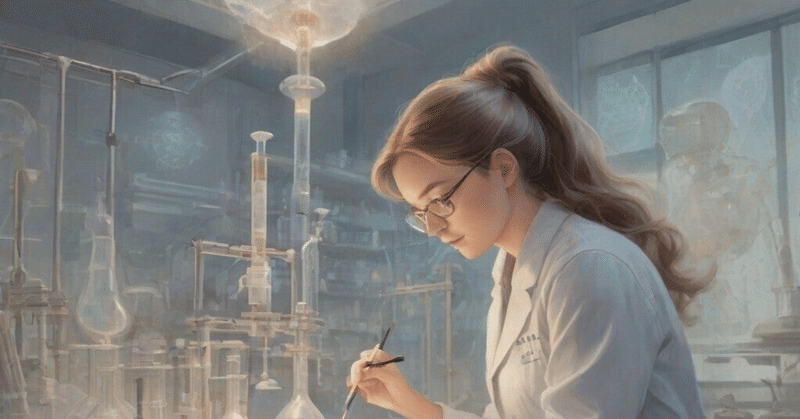
学校だけが「現場」ではない
これまで当たり前だと思ってきたことを違った視点で見るというのは、とても大切なことだと思います。
学校の「当たり前」を冷静に見つめるためには、「学校から離れる」という経験が大いに役に立ちます。
実際に学校を離れることはできなくても、視点だけでも学校の外に向け、学校を「遠くから見る」ことならすぐにできます。
その視点は、学校や教師としての在り方を客観的に見ることにつながります。
方法は意外と簡単です。学校現場以外の人が書いた学校や中学生に関する調査や研究に触れることです。
今、学校が変わらなければいけないという論調の本は実に多く出版されています。
それらの本が必ずしも学校現場の実態を正確に理解しているとは限りませんし、学校や教師を批判的に述べているものも多くあります。
けれども、だからこそ、あえて学校や教師に否定的な本や論文を手にすることには意味があります。
自分たちとまったく違った視点に出会うからこそ、新しい発見がそこに生まれるのです。
また、「大学の先生や研究者が書いた本なんて、どうせできもしない理想論に過ぎない」と思って、読まないのはとてももったいない話です。
1冊の本を読んで、その中のわずか一行でも「いいな」とか「使える」と思えることがあれば、読んだ価値はあります。
そして、学校の外から学校を分析している本を読むことは、私たちに「学校から離れた」視点を与えてくれます。
それが、今自分のやっていることを、いい意味で相対化させてくれることがあります。
信念をもって教育にあたるというのは大切なことですが、それ以上に重要なのは、その信念が本当に正しいのかを確認し続ける姿勢です。
特に、今の中学生や若者がどういう意識を持っているかをきちんと分析してくれている本は貴重な存在となります。
時間をかけて精密な調査や分析をするような時間は私たちにはありません。それをやってくれている人がいるのですから利用しない手はないと思うのです。
最近読んだ本の中にこんな一文がありました。
「……大事なことは、さまざまな「現場」(教育行政の現場、教育研究の現場、子育ての現場、社会教育の現場など)の知見を、お互いに持ち寄り、交換し、活かし合うことだとわたしは思います。
「現場を知らずに……」という言い方は、その機会を自ら捨て去ってしまうことだと思います。
もうちょっと言うと、「現場を知らずに」と言う先生にわたしが密かに思うのは、その先生の言う「現場」というのは、あくまでもその先生が経験してきた、ほんの何校か、何クラスかの「現場」にすぎないんじゃないか、ということです。
その限られた経験をもって「現場」一般を語ってしまうのは、ちょっと乱暴なんじゃないかとわたしは思います。」
( 引用文中( )内は引用者が著者の主張の他の部分から抜粋し、付け足したものです。ちなみに、苫野氏は熊本大学准教授、専門は哲学、教育学です)
私はこの文の内容をすべて受け入れているわけではありません。
限られた現場を詳細に記述することも大いに意義あることだと思います。
でも、私はこれを自戒をこめて読みました。
自分たちの「学校現場」や「経験」に支えられた「信念」が「独善」に変わってしまったら、見えるはずのものが見えなくなるだろうし、見なければいけないという視点そのものを失うことになります。
私は、可能な限り、学校現場のことを「現場」と言わないように努めてきました。
教育の世界のなかだけでも、学校現場以外に、教育委員会も「現場」であるし、研究機関もそこにいる人からすれば、まさに「現場」なのです。
学校だけが「現場」だと考えた時点で、私たちの視野狭窄は始まっているのです。
「私は一日中、学校のあり方を考えている。目の前の業務に追われている教員よりも、よほどじっくりと学校の課題に向き合っているとさえ主張しうる。それでも、「あなたは学校の現場を知らない」と非難され、一方で「研究の現場」のことには見向きもされない。学校とは、議論のアリーナにおいてあらかじめ優位性の高い現場だということなのだろうか」
これをどう受けとめるか、私たちの姿勢が問われています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
