
絵画と音楽
古い本を開いてみた。
いつか読み直すつもりで、本棚の隅に追いやられていた本。
絵画と音楽、という一番興味がある繋がり。
共感覚についてにも書かれていたはずで、面白いけれど読みにくかったような印象だった。
家にいることが長くなったので、読み返してみようと思ったのだ。
この本から、大学に提出する論文を書いたはずで、劣化した付箋がおどろおどろしくなって貼られままだ。
学生時代の私は、何に着目していたのか。
本につけた付箋というのは、後から見ると面白いものだ。
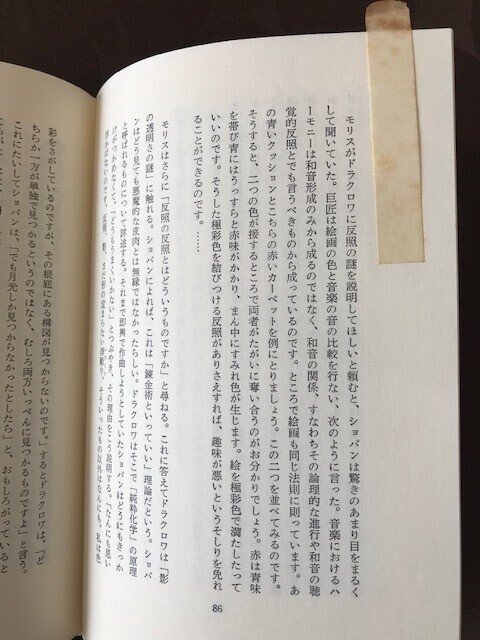
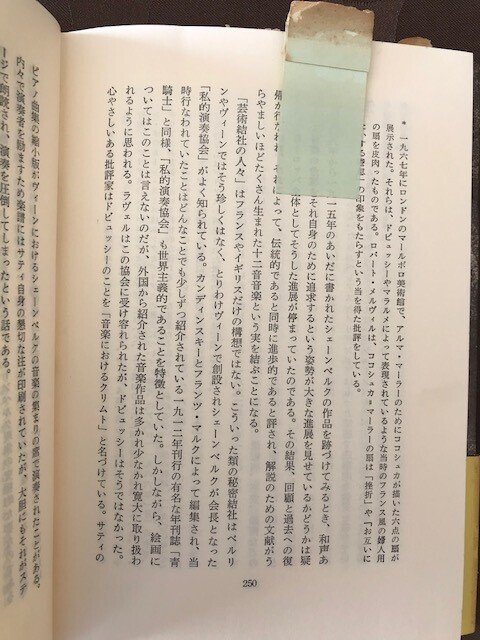
ここだけ読んでみても、今でも、「何?」と心に触れるものがある。
「芸術結社の人々」って?
秘密結社などというと、当時、周りの友人も私も読んでいた澁澤龍彦を思い出す。
心やさしいある批評家はドビュッシーのことを「音楽のクリムト」と名づけているって・・・気になる文章だ。
序文には、このように書かれている。
私のねらいは第一に、十九世紀の音楽の観念と絵画の観念の相互作用を解釈することであった。観念はどんなに発展していても胚というべき発端を持っているはずだという原理を根拠に置く私は、音楽を生み出す想像力と絵画を生み出す想像力の接する部分に、われわれの音楽の問題を解く手がかりが隠されているのではないかという予感をもった。
『絵画と音楽』
ターナーからシェーンベルクに至る
絵画と音楽の比較美学
というのがこの本の題名である。
そして、ボードレールの批評についての章がある。
美術批評、文芸批評など、芸術批評の筆を執っていたボードレール。
この中に、
ボードレールの中で引き起こされるあの色彩が、音楽によって導かれる状態にもなぞられられる「幸福感」の状態であることを歴史家が承認したとしても、壮大な音楽的、視覚的態度でなされたボードレールの批評を定義するという困難な問題がやはり残る。この困難さは最初は、その反応の強烈さにもかかわらずボードレール自身画家でも音楽家でもなかったという事実によって倍加されるように見える。が、実際はこのことはボードレールにとって幸いだった。ボードレールはたわごと的批評の言いのがれや複雑さに巻き込まれることがなかったので、ヴァーグナーの音楽やドラクロワの絵画の中にこたえられない新鮮さと暖かさを自由に感じ取ることができたのである。
批評家としてのボードレールは自分で気が付いている以上のものを構築している、という。
例えば、ドラクロワの色は、「自分で思考して」おり、この色彩画家の微妙な濃淡法からは「数学と音楽」が感じられる、と。
他の芸術を持ち出してそれと同一であることを示したりすることによって、ボードレールの批評は変わらぬ豊かさを持ち続けている。こうした諸芸術の融合においては、画家と音楽家は周囲の状況に応じて色を変えるカメレオンとなる。が、それだけではない。作家と詩人は・・・ボードレール自身その代表的人物なのだが・・・こうした融合においては姿を消してしまう。
このような「批評」についての文章を、今、見つけたのには意味があるように思える。
批評によって、芸術家(に限らず表現者とも言える)は鼓舞されたり、落胆したりして成長するのだろう。
一番大きいのは、自分では気が付けなかった自分自身の弱点や魅力に、気がつく機会を与えてもらえることだ。
道筋が見えない中で、どちらに進んでいくのかの、一つの指針をもらえることは、とても大きな財産だと、私は思う。
自らを批評の対象にしてもらえる公募は、成長の糧になると私は思う。
そればかりか、自分と違うものとの結びつきまで発見してもらえたなら。
そして、それをフィードバックしてもらえたりしたら。
美術批評、広告批評、文芸についての批評・・・この世には、わざわざその専門誌があるほどだ。
そして、それを読むことで、そのものと関係のない自分の「傍観者としての視点」も高めてもらえる。
そして、批評の着眼点、文章そのものも、一つの作品であるのだと思う。
この本は、「象徴」の問題を扱っている。
象徴の問題が美学において重要な意味をもつことを、絵画と音楽の比較美学を通して語ろうとしたものだ。
「象徴」とは。
概念では言い表せない場合に用いられる表現形式のこと。
「象徴」によってしか表現できない領域、つまり視覚や聴覚といった個々の感覚を超えた共感覚の世界であり、実は、これこそが想像力(イマジネーション)の世界であるという。
訳された中村正明さんは、美学の方である。
美学とはどのような学問ですかという質問に対しての答えをこう書かれている。
美学は哲学の一分派であり、真・善・美のうちの美を扱うものですとか、知性と対比された意味での感性を扱うものですとか答えてきた。特に最近は、後者の答えの言い換えになるが、感情についての学、感覚についての学という言い方をすることが多い。が、いずれの場合にも、われながら漠然とした答えだなあと隔靴掻痒の感がぬぐいがたかった。しかし、本書に出会った今、迷うことなくこう言える。この本をおすすめします、これが美学というものです、と。
この本は、誰かに紹介されたものでもないし、なぜ、出会うことができたのか、今となってはわからない。
しかし、私にとって大切な本だった。
ところで、当時書いたはずの文章はどこへ行ってしまったのか。
すっかり忘れてしまっている。
この本をおすすめします、これが美学というものです。
この言葉の深さを感じる本である。
書くこと、描くことを続けていきたいと思います。
