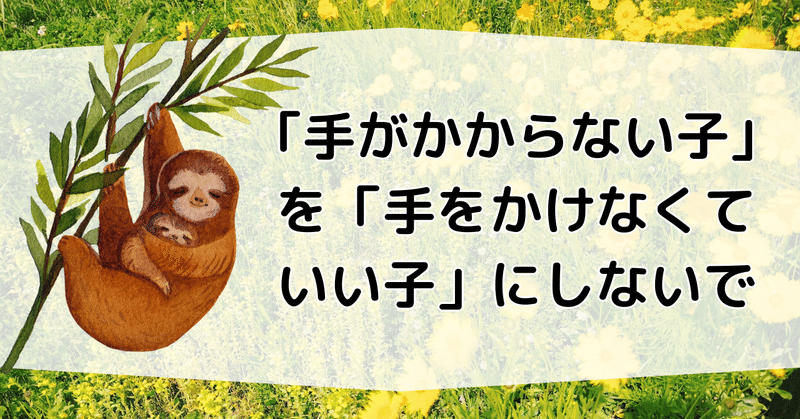
正しく褒めることの重要性〜褒められずに育った大人たちにも届けたいメッセージ〜
◎「手がかからない子」とは
「手がかからない子」について、ここでは、
真面目(頑張り屋さん)、優しい、ものわかりが良い、
主張が少ない(口数が少ない)、甘えることが少ない、
器用(勉強などにも困らない)、
などの側面を持つ子について話したい。
ただ、上記の特徴に当てはまらなくても、
「手がかからない」と感じているのであれば、
ぜひ、このこのまま読み進めてほしい。
◎「手がかからない子」が陥りやすいこと
器用なところがあると、それなりに何でもできてしまう。
それなりに何でもできることが本人にとって通常であり、日常であれば、
そのことに周りの大人も慣れてくる。
その結果、褒められる機会や誰かに頼る機会が、
少なくなってしまう場合がある。
それなりに何でもできる子は、
自分で考えて、自分で解決できる子でもあるといえる。
しかしそれは、相談しないこと、相談の仕方を学ばないことにも繋がる。
他人を頼らず、自分の考えだけで完結してしまう傾向がないか、
注意してあげたい。
ある程度何でもできることが日常になり、
それによって褒められることが減っていくと、
ある程度何でもできることは、褒められることではない
という認識に変わってしまったりする。
そして、「ある程度当たり前にできる人間=私」が構築され、
その私を維持しなければならないと感じ始めたりする。
大人になれば、環境が変われば、難しく感じる物事にも出会う。
そんな時、うまくできない自分を認められなかったり、
そんな自分を、周りの人に見せれなかったりする。
器用にできることが当たり前になり、それが自分になり、
相談をして、自分とは異なる他人の視点に触れる機会も少なかったために、
自分だけの世界で、自分で決めつけてしまった自分と向き合う状態になる。
何かできないことがあると、そのことが、
自分の価値を下げてしまっているような感覚になる。
「器用にこなせる=私」を維持できないことに、不安になったりする。
「ある程度できる=私」が通常で、それ以上でないと褒められる自分ではないから、うまくできない自分が嫌になる。
「ある程度できる=私」という基準を下回ることは、
良くないことだと認識してしまって。
成長とともに、環境は変わっていく。
新しいこと、初めてのことに、たくさん出会う。
その中で、うまくいかないことがあるのは自然なことなのに、
「できないことがあってもいい」という見方を持っていないために、
できない自分を恥ずかしく感じ、周りの人に打ち明けられなかったりする。
今まで自分だけで解決してきたために、
誰かに相談することや、甘えることが選択肢に用意されていない。
また、どう相談すればいいのか、どう甘えていいのかも
分からずに一人で抱え込んでしまう。
そして抱え込むことが重なれば、心はその重さに耐えれなくなってしまう。
手がかからないために、
褒められることがあまりなかったために、
いつの間にか、独りで生きる道を歩いていたりする。
◎褒められて育った子と褒められずに育った子の違い
褒められないという状況は、自分の良さや頑張りに気づけないことに繋がる。
褒められることで、自分の頑張りが何かのかたちになることを
しっかりと認識でき、自分の頑張りに注目することができる。
自分の良さや頑張りに気づけない状態では、常に不安を感じてしまう。
「頑張りが足りない」「良さが足りない」と、常に気を張ってしまう。
すでに頑張っているのに、そのことに気付けず、
今の自分を労われず、頑張りすぎてしまう。
大人になり、自立していく中で、
そのような生き方をするのは大変なことである。
褒められることは、自分が何か行ったことで
誰かと繋がることができるという経験になる。
自分の行いや頑張りが、
誰かのためになることをしっかりと認識できる。
自分の頑張りが、自分や誰かの喜びに変わる。
それを嬉しく感じ、次もまた何か挑戦しようと前向きになれる。
そのような経験が土台となっていれば、
苦い経験をしたとしても、また立ち上がることができる。
自分の良さや頑張りを知り、
自分の喜びだけでなく、誰かの喜びも土台にあるから。
しかし、褒められてこなかったことで、自分の良さや頑張りを認識できず、
頑張った先に誰かと繋がる喜びも知らない孤独な土台では、
苦い経験を支えることはできない。
頑張ることを、繰り返すことも難しくなる。
また、何か喜ばしいことがあったとしても、褒められ慣れていないことで、
素直にそのことを喜べなかったり、自分の成果として受け取れなかったりする。
◎褒めることで教えてあげられること
褒めることを忘れることは、コミュニケーションを忘れることだともいえる。
お互いに、相手の気持ちに触れる機会が減れば、
相手の気持ちに気づきにくくなる。
その子に対して、手がかからないと感じていても、
その認識をそのまま放っておくのではなく、
積極的に心を配り、コミュニケーションをとってほしい。
真面目な子は、自分の頑張りを、
自分でもそれは当たり前のことだと考えがちだ。
自分は、頑張り屋さんであることを、認識していない場合がある。
でも、「当たり前」などというものは何もない。
何事も自分で真面目に取り組むことができて、
そのことを主張することも少ないのであれば、
その子に関わる周りの大人が、積極的にその子の頑張りと良さに気づき、
その子自身も、そのことをきちんと認識できるように、
褒めて、教えてあげてほしい。
◎未来の孤独から救うコミュニケーション
おすすめのコミュニケーションの取り方は、一緒に何かに取り組むことである。
誰かとコミュニケーションをとりながら、相談し合いながら行う経験は、
視野を広げることに繋がる。
自分が考えていることや気持ちを言葉にする練習にもなり、
困ったときに、自分の考えだけで完結させなくてもいいことを学べる。
誰かに相談をする、甘える練習にもなり、
誰かに頼れる機会がたくさんあること、
そんな環境の中にいることを、認識させてあげられる。
離れても、その子を支えられる愛情である。
自ら主張することが少ない子には、
そのような愛情に触れられる機会を多くつくってほしい。
そのような環境の中で育つことで、困ったことがあったときに、
誰かを頼るということも自然と選択できるようになる。
◎子供に気を遣わせないコミュニケーションを
話を聞くときには、
できるだけしっかり聞いていることが分かるようにしてほしい。
「あなたの話をしっかり受け止めているよ」ということが伝わるように。
何か違う作業をしながら会話をしていると、真面目で優しい子は相手の忙しさなどを感じ取って、身を引いたり、主張することをより控えてしまう場合がある。
少しの時間でも、ちゃんと向き合ってコミュニケーションをとる機会を設けることで、愛情もストレートに伝わりやすい。
◎相手を苦しめてしまう褒め言葉もある
褒める内容はとても重要である。
相手を縛ったり押さえつけるような褒め言葉ではなく、
相手が伸び伸びと羽を広げられる褒め言葉をかけてあげたい。
例えば、
手がかからないことや、何でもできることをそのまま褒めてしまえば、
手がかからないことや、何でもできることが良いことになってしまう。
それでは、手をかけさせてはいけない、できないことがあるのは良くないことだと伝えているのと同じである。
真面目で何でも頑張ってやれる子ほど、
できないことがあっていいのだと伝えたい。
それは、自分にも他人にも優しくなれる方法である。
◎褒められずに育った大人たちへ
褒められずに大人になってしまった人、
失敗を恐れがちな人にも伝えたい。
「できる=良いこと」ではない。
「何でもそつなくこなせる自分=良い自分」ではない。
これはできて、これはできない、
そのような組み分けの結果があなたなのではない。
一つ一つ違うことを体験していくのがあなたである。
体験そのものが、経験そのものが、
あなたなのである。
だから、
自分の手に負えないことがあっていい。
できないことがたくさんあっていい。
できないことを経験する、
それがあなたなのだから。
そして、できないときには周りの人を頼ること。
1人に断られても、他の人たちにたくさん声をかけること。
電話相談や、ネットに書き込んでみるのもいい。
そして、そんな経験ができた自分を褒めてあげること。
できたり、できなかったり、困ったり、喜んだり、
色んな日々を体験することを、自分に許してあげること。
できないことも、失敗も、後悔も、
本当は人生のプレゼントの一つなのだから。
大切なあなたに、届きますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
