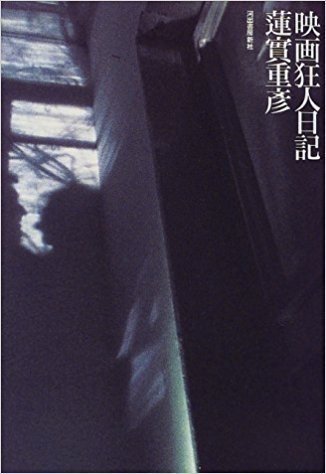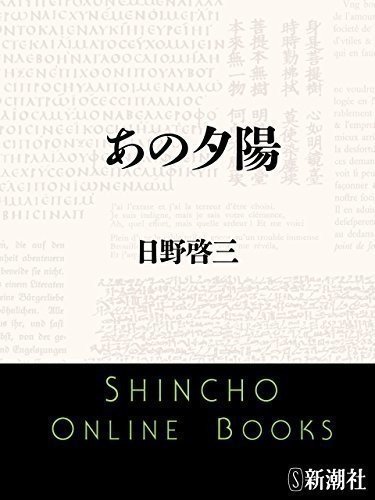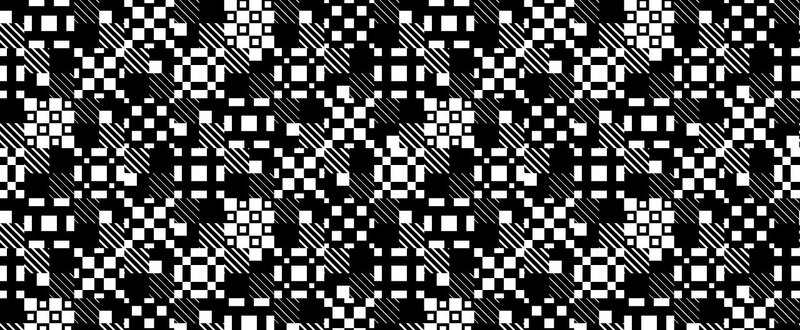
わかりやすい物語からの逃避行 小説と世界と物語
雑食でとにかく何でも読むタイプなので、小説も国内、海外問わず読んできた。読んでは忘れる。どんな話だったかきれいさっぱり、忘れ去ってたりする。音楽も、映画も、絵画も、様々な作品に触れることが好きで、美術史やら評論やらも読んではいたのだけど、ある時期から距離を置き始めた。評論にしても、文学史、美術史のような歴史にしても、個々の作品をひとつのわかりやすい物語に収束させていくものだから。
曰く、この頃の作者は●●との別れに悲嘆にくれていたから云々。古典的な作品研究は作者研究に近いところがあって、作者の人生と作品の関係性を詳らかにしていくものが多い。その根底にあるのは作者が作品についての最高権威であるとする考え方だ。でもその一方で、作者と作品を切り離して考えても良いでしょう、と言う考え方もあるわけだ。
フランスの哲学者、批評家であるロラン・バルトはそれを「作者の死」*1 と言い、ある作品がどのような意図で作られ何を意味するのか、それをこうだと断定し支配する権限は作者にはない。意図や意味は作者が決めるものではなく、受け手が積極的に作品から引き出すものなんだ、と宣言した。これは作品の鑑賞をめぐるひとつのパラダイムシフトだったわけだ。
だから、何にせよ、作品を鑑賞すると言う行為は自由だ。自由なのにいざ、自由になると人は戸惑って、どうしたら良いかわからなくなる。実は無意識のうちに鑑賞の仕方って制限されていたりする。何で読んだのかは思い出せないのだけど、東大の元学長であり映画評論家でもある蓮實重彦*2の講演をまとめたもので、彼は映画の見方が抑圧されている、と言っていた。ストーリーの良し悪し、みたいな話が支配的だけど、それはあくまでも一要素、一観点でしかない。何カットあったか数えるような見方もあれば、フェイドイン、フェイドアウトの数に注目する見方があっても良いでしょう、とかいうことを話しながら、小津安二郎の映画について語る内容だったと記憶しているのだけど、当時浪人生だった僕はなるほどねー、そんなこと考えたこともなかったよ、と目から鱗だったことを思い出す。
作品の鑑賞の末に何か算数の問題のような答えがあるわけではなく、そこを求めてもなぁ、と思うのだけど、やっぱり人はわかりやすい物語には引きづられてしまう。こう言う作品なんだ、作者の●●が表現されているのだ、雑学としての面白さとかわかった気がする気持ちよさがそこにはある。それは僕のような素人鑑賞者にバイアスをかけるには十分すぎるし、気がつくと思考停止に陥るわけ。それ、本当に自分が感じて、考えたことなの?って。他人の言葉を借りているだけなんじゃないの? わかりやすい物語でわかった気になっているだけなんじゃないの?
だから、もともと好きなんだけど、いわゆる文学史、美術史、的なものとか、解説っぽい評論とかから距離を置いて、そこに時間かけるよりは作品自体を鑑賞することを優先してきたんだけど、久しぶりに文学史的な、評論を読んでみた。自身も作家である池澤夏樹が語る世界文学に関する講義をまとめたもの、だ。
この本では、小説を下記のように捉えている。
小説はその時代、その国、その言葉の人々の世界観の一つの表明である
小説は人と世界を描いてきていて、世界の変化は小説にも変化として現れる、と。それを1838年の作品であるスタンダールの『パルムの僧院』*3 から、1967年のガルシア=マルケス『百年の孤独』*4 まで、10の作品を語りながら明らかにしていく試み。
具体的には、世界観には大きく二つあって、一つは樹木上の分類項目に従う、つまりディレクトリのある形。大きなカテゴリーがあって、その下にまたいくつものカテゴリーがあって、その下にさらに小さなカテゴリーがあって、と言う統制のとれたロジカルな構造の世界。もう一つは、単に物がひたすら並んでいるだけの羅列的な秩序なき世界。そして世界は秩序あるディレクトリー型から秩序なき羅列的な世界へ変化しているのではないか、と。
で、人は元来、なんとか脈絡をつけて、こっちにあるものと、あっちにあるものを繋いでみたいと言う欲望や、繋いでいくうちに世界の基本構造が見えてくるのではないかと言う期待を持っている。そうやってわかりやすい物語を作り、見えざる秩序を顕在化して世界を一つの大きな図柄に織り上げようとしてきた。でも、一方でそんなにうまく物語は作れるのか、と言う考え方もあるわけです。
日野啓三*5という作家の言葉を紹介しながら語るくだりが僕にとってはそのものズバリな話だったので、丸っと引用してみる。
「よく思い出してくれよ。映画でも文学でも、本当に君の心に焼きついているのは、それが世界と自分について本当に新しい発見と喜びをもたらしてくれたものは、ストーリーだったか? いくつかの部分だったか。ストーリーと無関係な部分の描写はありえないなどという一般論は抜きにして、君自身の過去でもいい、本当にきらめいて残っているのは、互いに無縁の切れ切れの偶然の場面ではないだろうか。その場面と場面との間は忘却の暗黒。少なくとも私の場合はそうだよ。誕生から現在までを繋げるひと繋がりの何かなどは、無理にこじつける以外に存在しない」
つまり彼は、脈絡はない、と言いたいんです。
でも、その一方、人間には騙されたいという気持ちがあるものだとぼくは思います。そしてその気持ちの背後には、われわれ人間の抜き去り難い強固な一つの性癖が隠されている。すなわち、混沌とした事象の中に何かストーリー性を見出したい、無意味なパターンの中に何か脈絡を見つけたいという、強烈な本能的な欲求です。
P.394
そう、自分にとって脈絡のない断片を集めて、断片を断片としてそのまま大切にしていけば良いと思うんだけど、その断片はなかなか人に伝えづらいものだったりもする。
今これ書きながら自分なりにわかったんだけど、だからどの作品が好きなの?って言われてもパッと答えられないのはこれも原因の一つなんだろうな。物語としての面白い、面白くないはあまりストックされていなくて、全て脈絡のない断片となって自分の中に存在しているから。
だって、断片だから。断片自身には物語がないから。でもそれを人に伝えようとすると、そこには何かしらの物語性が発生してしまって、その時点で断片は断片として伝えられないのかもしれない。断片のきらめきを伝えようとして語り出した途端、それはわかりやすい物語に回収されて本来伝えたかったものが逃げていく。それなのに人は物語が好きだから、物語として理解した気になってしまう、みたいな。
わかりやすい物語にはそれが物語になった時点で失われているものがあると思うのだけど、そこに気をつけないとわかりやすい物語に囚われ続けてしまう。わかった気になっている全てのことは、たまたま知ってるわかりやすい物語の一つに過ぎないのかもしれない。
連想文献
「作者の死」*1
Wikipediaってとっても便利ね。
ここで紹介されている「森田 亜紀 作者であることの事後性をめぐって 倉敷芸術科学大学紀要,(12),25-36 (2007-03-01)」をこれ書くついでにちょっと見てみたのだけど、論文の冒頭に「作者の死」の概要が綺麗にまとまっていてとてもわかりやすかった。
東大の元学長であり映画評論家でもある蓮實重彦*2
浪人時代、池袋のジュンク堂で東大の学長が映画の本出したって平積みされていて、何とは無しに手に取ったのが出会いだったのだけど、それはそれは衝撃的な出会いだったな。だって、この本に出てくる映画、ほとんど聞いたこともないような監督と作品だらけだったから。全然、わからない!ていうか、自分が今まで映画だと思ってきたものは一体なんだったんだ!?と思ったのでした。
そして同じく蓮實重彦の『映画に目が眩んで』を手に取ったものの、こちらもなんだかさっぱり見たことない作品ばかり。浪人から大学卒業まで、渋谷ツタヤとユーロスペースとシアターイメージフォーラムと、といった映画三昧時代を迎えるのでした。懐かしい。
スタンダールの『パルムの僧院』*3
ちなみに『赤と黒』も『パルムの僧院』も読んだことあるはずなんだけど、忘却の彼方。本当に覚えてないもんだな。この本読んだのも何かの縁だから、再読しようかな、という気持ちになってきている。
ガルシア=マルケス『百年の孤独』*4
魔術的リアリズムという手法を代表する作品なんだけど、現実をベースにした作品世界の中で幻想的な事象が起きていく。美しく印象に残る断片の宝庫、みたいな作品。ファンタジーと何が違うのかということに関して池澤夏樹の定義がわかりやすい。
ファンタジーというのは、ここにこういう現実があることを前提にしたうえで、今ここでない場所の話をしますよ、という約束の下に展開されます。ファンタジーの場合はその外側に現実がある。だからしばしばファンタジーには移動が伴うのです。
P.325
確かにファンタジーは別の世界の話なんだよね、でも『百年の孤独』は異世界の話ではない。ファンタジーがしばしば移動を伴うというのも確かにね。ピーターパンも、ナルニア国物語も、オズの魔法使いも、違う世界に移動して戻ってくる物語。
日野啓三*5
今まで知らず、読んだことなかったので、ひとまず芥川賞受賞の『あの夕陽』と泉鏡花文学賞の『抱擁』を読んでみようかな。
自分の好きなことを表明すると、気の合う仲間が集まってくるらしい。とりあえず、読んでくれた人に感謝、スキ押してくれた人に大感謝、あなたのスキが次を書くモチベーションです。サポートはいわゆる投げ銭。noteの会員じゃなくてもできるらしい。そんな奇特な人には超大感謝&幸せを祈ります。