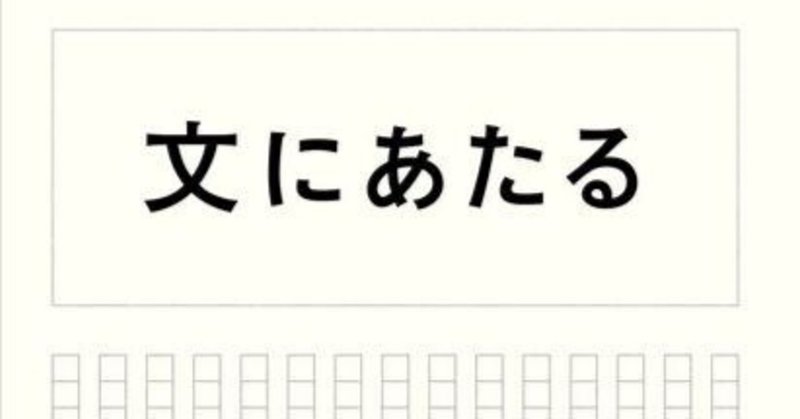
牟田都子『文にあたる』から得た知見
同業者が職業について書いた本の記述は生々しすぎて、読むのがつらい箇所もたくさんあった。だからこそ感想を書いておかねばならない。
まずは校正という仕事、校正者という職業について。本書では「校正・校閲」をまとめて「校正」と呼んでいるので、この記事もそれに倣って「校正」とする。
校正は常に完璧である(誤植をひとつも出さない)ことを求められていながら、完璧な仕事をすることはほぼ不可能である、といっていい。
絶対に落とさない人は絶対にいない。
どんなに注意深い人でも、ミスをする確率が低くはなってもゼロにはなり得ない。
そう、「ミスを拾い損ねることは滅多にない」人はいても、「絶対にすべてのミスを拾える」神様のような人はいない。そこがこの仕事の難しさである。それなのに、校正というプロセスをなぜ入れるのか。
校正を入れることの意義は目に見えにくい。なぜなら何も問題がないと言えるのが校正が十全に機能した結果だからです。
校正は「防災」だというたとえがあります。防災グッズを用意し訓練をして、実際には役立つことのないまま月日が過ぎていくのならそれに越したことはありません。災害が怒ってから慌てても遅いように、ひとたび印刷され製本されて本という形になり、世に出てしまった言葉は取り返しがつきません。あとから書き直したり訂正したりはできないから、あらかじめ備えておきたい。
具体的にいうなら、「あとから関係者の誰が読んでも間違いがない」のに加えて「読者から何も指摘がこない」のが校正の目標ということは言えるだろう。それを初刷りで実現するのは不可能に近いかもしれないが。
そして、校正には大きく分けて出版校正以外と商業印刷校正がある。校正とひとことで言うが、分野や用途によって、求められる技術は若干異なる。商業印刷というのはカタログやパンフレット等を指すが、本書には次の例が載っている。
たった一文字の誤植のために、膨大な印刷物が紙くずと化すことがある。特に鬼門なのがダイヤモンドをはじめとする宝飾類のカタログで、商品の金額が高いから誤植がすぐに致命傷となる。
カタログというのは、企業情報・商品情報そのものである。製品スペックや価格のほか、製品番号、店舗の所在地や電話番号、さらには会社名が違っていると肝が冷える。自分の所属する社名を間違える人はいないと思うかもしれないが、社員や関係者は記憶だけに頼って書くので、意外と間違えていることが多い。「株式会社AA」なのか「AA株式会社」なのか、通称と正式名称が違ったり、店名と社名が一文字だけ違っていたり、最近、社名が変わったがうっかり前の社名を書いてしまったということもある。
ここを落としては校正者が入った意味がないので、公式資料を見ながら、一文字一文字、心を落ち着けてゆっくり照合する。入れるべきクレジット(著作権者等の表示)が入っていてロゴは合っているかどうかも重要だ。ひとつ間違えば「刷り直し」が待っている。
対して出版校正はどうかというと、その中にもいろいろジャンルが分かれている。
「本」が小説なのかエッセイなのか、実用書なのか子ども向けなのかで、校正の勘所は違います。詩や小説、エッセイにおいては句読点ひとつとっても著者の表現なのだから、軽々しく踏み込むべきではない、という考えかたが染みついていますが、料理の本で「菠薐草」「ほんれんそう」「ホウレンソウ」が混在していたら読者は混乱するだけです。求められる技術がまるで異なるのに、同じ「校正」といっていいものだろうか。
わたしは実用書から校正の世界に入ったのでよくわかる。ムックなどで多いが、製品紹介のページには格段の注意が必要だ。スペックの数字や単位、製造会社名が違っていることはよくある。これをひとつひとつ調べていくのが校正者の重要な役割のひとつ。実用書を校正する勘所は、商業印刷校正とよく似ている。
さらに、わたしは英語教材を校正することが多いのだが、これがまたおそろしい。特に、英語そのもののミスは許されない。英文にはもちろんネイティブチェックをかけるが、ネイティブスピーカーにも「100%」拾える人はいない。「ネイティブが見たから英語はもう安心」ということはなく、ネイティブチェックの後に「3単現のsが抜けている」といった単純ミスが残っていることは日常茶飯事である。これが学校で配布されてしまうと、生徒たちは間違った英語を暗唱することになるのだ。
最後に小説だ。わたしは最近小説が回ってくるようになったばかりなので、じつは薹の立った新人だが、小説はまた別の技術が要る。
どんな表記を選ぶかは著者の語感、文章のトーンにもよりますし、そのつど使い分けたい著者もいて、それこそが「表現」ではないでしょうか。
そう、小説の場合には、明らかな誤りと思えない限り表現にはコメントしない。きちんと検証しなければならないのは、ロジックがとおっているかという点だ。さっきは右手で銃を構えていたのに2ページ後での記述では左手としか読めない。両手利きだったとはどこにも書いていないけど、伏線としてこの後で重要な情報となるのだろうか。メモしておこう、となる。架空の場所であっても地図を書き、登場人物が通った道を蛍光ペンで辿ってみると、行きはひとつしかない扉を開けて通ったとあるのに、帰りはそれが2つあったり、扉がないことになっていたりする。これも、間違いなのか伏線なのかは最後までゲラを読んでみなければわからない。この辺が小説の勘所と言えるかもしれない。
とまぁ、校正とひとことで言ってもいろんな校正があるのだ。本書では、校正の技術をひとことでいうならどこに行き着くかという、著者の「答え」も記されている。ここは、ことばや印刷物(商業印刷ももちろん含む)に携わるすべての人に読んでほしい。
校正の技術とは、突き詰めていくと思い込みや先入観をいかに排するかというところに収斂するのではないでしょうか。
調べることには段階があります。ゲラを読んでいて疑問が生まれ、何を使って調べるか考える。しかし「調べる」始まりはそこではなくて、まず「疑う」ことなのです。「パンダの尻尾は白い」という典拠を示すことは、これまで書いてきたようにそれほど難しくありません。でも、尻尾の黒いパンダを見た時に「パンダの尻尾の色は黒でよかった?」と思えなければ、そもそも調べることもできない。校正の技術として「調べる力」があるならば、更に求められるのは「疑う力」であるとも言え
ます。
深くうなずくばかりだ。思い込みや先入観が入っていて「疑う」ことをしなければ、調べるという工程に到達しない。
校正者は「○○はどこを見れば調べられる」という知識は教えてもらうこともできるし、経験と共に増えていく。だが、それ以前にもっとも必要とされる資質は、クリーンな脳、まっさらな気持ちでその都度ゲラと向き合うことなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
