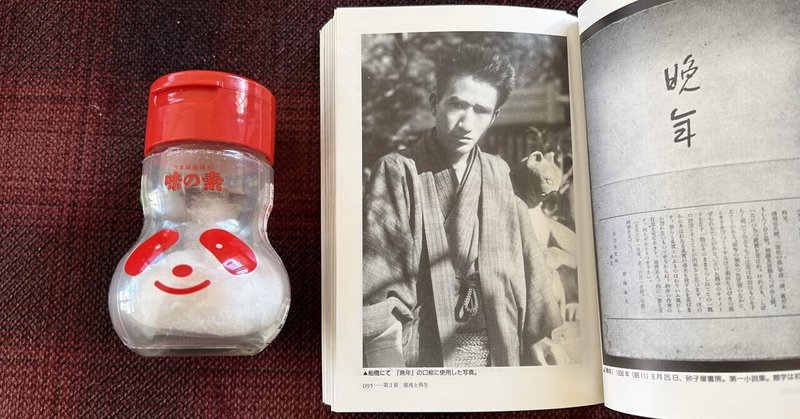
太宰治と味の素について
太宰治のエピソードでよく語られるのことのひとつに、味の素が好きだったというものがあります。
太宰の作品では、パビナール依存症の治療のために東京武蔵野病院の閉鎖病棟に入院「させられた」時の日記という形式で書かれた「HUMAN LOST」や、最後の発表作となった新聞連載小説「グッド・バイ」に登場します。
私は、筋子に味の素の雪きらきら降らせ、納豆に、青のり、と、からし、添えて在れば、他には何も不足なかった。
キヌ子は惜しげも無くその一ハラのカラスミを全部、あっと思うまもなくざくざく切ってしまって汚いドンブリに山盛りにして、それに代用味の素をどっさり振りかけ、
「召し上れ。味の素は、サーヴィスよ、気にしなくたっていいわよ。」
カラスミ、こんなにたくさん、とても食べられるものでない。それにまた、味の素を振りかけるとは滅茶苦茶だ。
青年時代の太宰と親交が深く、山岸外史と共に三馬鹿と呼ばれた檀一雄が太宰の死の一年後に発表した「小説 太宰治」の中にも、当時太宰夫婦が住んでいた飛島定城邸に初めて訪ねて来た檀一雄をもてなすために、丼に開けた鮭缶に味の素を振りかける場面があります。
鮭缶が丼の中にあけられた。太宰はその上に無闇と味の素を振りかけている。
「僕がね、絶対、確信を持てるのは味の素だけなんだ」
クスリと笑い声が波立った。笑うと眉毛の尻がはげしく下る。
その他にも、井上ひさし『太宰治に聞く』には、甘味にも味の素をかけて食べていたという記述があります。
先生には、食べものといういう食べものに片っぱしから味の素をふりかける癖があったらしい。証人が大勢いて、たとえば、檀一雄は、先生が羊羹にも饅頭にもお汁粉にもパッパッと味の素をふって食べるのを目撃しているが、どういうわけか、わたしは先生のこの癖が大好きで、味の素の小瓶を見るたびに太宰治の作品をあれこれとなく思い出すのである。
このように太宰治の味の素好きは広く知られていますが、2011年には当の味の素社が「偉人の食卓」という新聞広告のシリーズを始めるにあたり、第1回目に太宰のエピソードを紹介しています。そしてこの広告シリーズを振り返った「活動レポート」では、味の素が発売されたのは明治42年(1909年)、太宰の生まれた年と同じということで「奇遇とはいえ、何か縁のようなものを感じます」と書かれています。
ところで、太宰治はいつから味の素を愛用するようになったのでしょうか。
太宰が生まれた年に味の素の発売が始まったとはいえ、「兄たち」などの太宰の作品や美知子夫人の回想を読む限りでは、太宰が少年の頃の津島家(太宰の実家)ではめいめいの前にお膳を置いて食事をしていたようですし、食べるものも昔ながらの調理法を堅持しているような保守的な家だったらしいので、新興の調味料を子供が愛用するような環境とは思えないんですよね。おそらく金木の実家を出て東京で最初の妻初代と住むようになってから覚えたのではないかと思います。その前に弘前高校に通うために遠縁にあたる豊田家に住んでいた時期もありましたが、やはり調味料などを自分で買い揃えるようになってから愛用するようになったと考えた方が自然だと思います。
そう考えていくと、どうやら昭和6年(1931年)2月に初代夫人と東京で生活を始めてから昭和8年(1933年)7月に檀一雄が訪ねてくるまでの間に太宰は味の素を愛用するようになったと思われますが、この間の太宰について書かれた文章に興味深いものがあります。
それは初代の母の弟にあたる図案師の吉沢祐(祐五郎)が昭和31年6月30日に発刊した小山清編『太宰治研究』に寄せた「太宰治と初代」です。これは姉の娘である初代とその夫となった太宰と自分との交流を書いたもので、これによると太宰が吉沢と初めて会ったのは昭和6年(1931年)で、のちに檀一雄や山岸外史も加わるようですがよく一緒に飲み歩いていたらしいんですね。この文章は時期が前後していると思われる箇所もあって、檀一雄と知り合ったあとのエピソードのようにも読めるのですが、太宰が吉沢の下宿で食事をする場面があります。少し長いですが引用します。
酒屋へよって洋酒の瓶を二本位ぶら下げて帰り、缶詰など開けて夜更かしをし、昼めしどきに握りめしの朝めしを済ましたり、“横のものを縦にもしない”太宰が部屋を掃き、さも大掃除でも終えたように腰をのばして満足し、私がテーブルなど引っぱり出して晩めしにすることもある。懐具合ではテーブルの上はだいたい茶碗二つだ。炊きたての飯に生の玉子を二つ割り、これを掻きまわすと玉子の泡が茶碗一杯にもり上る。それに醤油をタラッと落し、味の素と焼海苔をもんで振りかける。いい色をしてとろろめしの味だ。太宰はうまいうまいと云ったが、一番めんどうでなく、私は得意にして一つ覚えに繰り返したから太宰はそのうちに褒めなくなった。然し、フライパンで、牛肉(出来ればしもふり)を一枚ずつ両面をほどよくいため、焼け次第味の素を角砂糖ほども入れた生醤油をつけ、唐がらしなどの薬味で食う。これはジンギスカン焼に勝り何遍くり返しても倦ることはなく、此方法は、太宰は自分の家へももちこんだ。
いずれも味の素を使用した料理ですが、この卵かけご飯のように「海苔を揉んで振りかける」太宰の姿を檀一雄が書いています。昭和42年(1967年)5月に芸術座のパンフレット『太宰治の生涯』に寄せた「友人としての太宰治」という文章で、のちに昭和43年(1968年)7月25日に虎見書房から刊行した『太宰と安吾』に収録されています。
そこで太宰は食卓の前に座りこんで、妹が並べてくれる品々を眺めまわしながら、やれ、塗箸は赤くなくっちゃいけないだとか、やれ、シジミは汁だけを吸うのだとか、やれ、海苔はこうやって、揉んでゴハンの上にフワリと振りかけるのが一番だとか、何よりも味の素だとか、地上で信じていいものは味の素だけだとか……、とりとめない出まかせを口走った挙句、
「じゃ、檀君、出かけようか? 出かけるなら、早い程、いい」
と、まったく巧みな頃合を見はからって、家の中から滑り出してしまうのが常でありました。
このエピソードの相似から太宰の味の素好きの由来を吉沢祐だとするのは早計に過ぎるかもしれませんが、こんな風に想像してみることは楽しいことです。このように同じエピソードを別の人の文章の中から探して集めていくことで、そのエピソードをより立体的に味わうことができるというのが近代文学の楽しみのひとつだと思います。
参考文献
檀一雄『小説 太宰治』岩波現代文庫
檀一雄『太宰と安吾』角川ソフィア文庫
小山清編『太宰治研究』筑摩書房
井上ひさし・こまつ座編著『太宰治に聞く』文春文庫
津島美知子『回想の太宰治』講談社文芸文庫
山内祥史『太宰治の年譜』大修館書店
石川弘編『人物書誌大系2 檀一雄』日外アソシエーツ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
