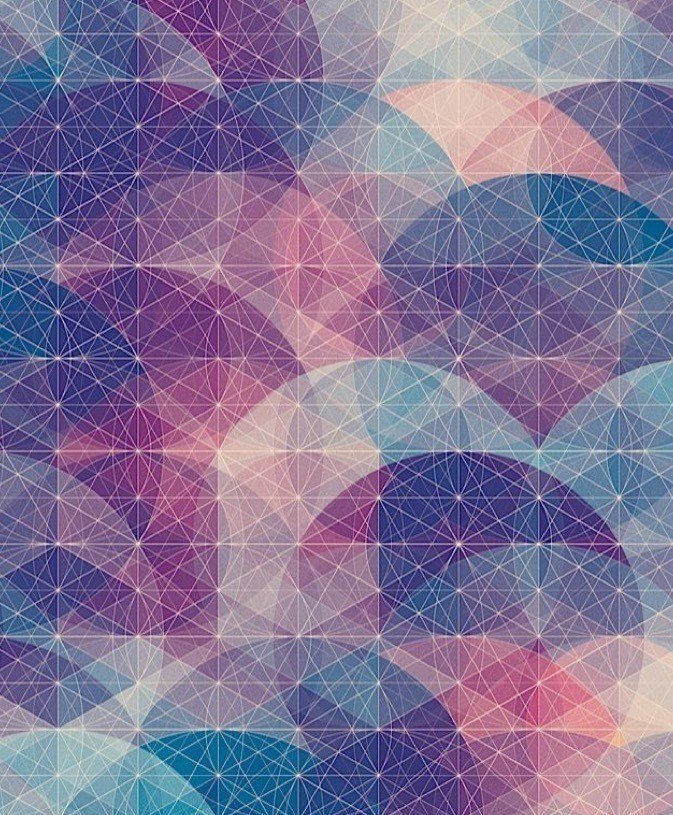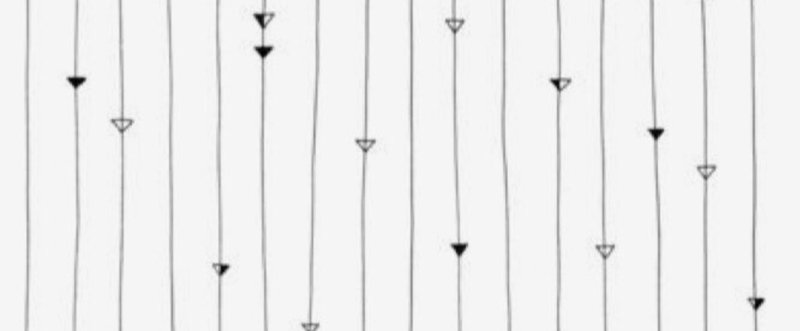記事一覧
もう人形は踊らない 2
団長が彼女のことをどこで知ったのかはわからない。
私は拾われ子で、気づいた時にはこの劇団で働いていた。団長の言うことは絶対で、ほかの団員達は最年少の私を可愛がってくれていた。でも私には演者としての才がなかった。多少の芸はこなせるものの、人を引き付けるようなものがどうしてか足りないのだ。そうそうに見切りをつけられた。裏方に回るように言われ、それに徹した。
ここでは、いらない人間は簡単に切り
もう人形は踊らない 1
パントマイムは黙劇とも呼ばれている。
言葉ではなく、動きだけで人を魅了するそのさまは、少しの違和感と子気味悪さを兼ね備えている。喜劇を演じるのが最近の主流だけれど、彼女の踊りはどちらかというと悲劇に近いのかもしれない。はっきりと言い切れないのは、「操り人形」という演目の内容のせいではない。彼女のまとう雰囲気がそうさせるのだ。
舞台に立つ彼女はいつだって人の心をとらえ、そして逃しはしない。
待ち焦がれながら真夜中に。
閉じていた瞳をゆっくりと開く。まつげの間をすり抜けて、街灯の光が入り込んできた。夏の夜の重苦しい熱風が、少し伸びた私の髪の毛と戯れている。手で髪を撫で付けながら、また時間をかけて瞳を閉じる。
ゆっくりと瞬きをする癖が付いたのは、この歩道橋で彼を待つようになってから。
歩道橋の手すりに頬付をついて、不安になるほどに薄い瞼の開閉を繰り返す。瞼を開いている時に彼が現れるのか、はたまた閉じている