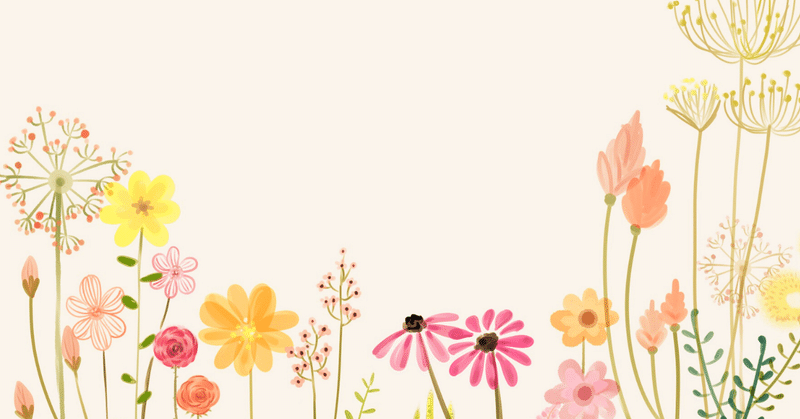
通院終了後も、転職後も続けていること
適応障害での休職・退職を経て、昨年春から再び働きはじめました。もう少ししたら転職からも1年。
比較的元気に過ごしているものの、細かくみればアップダウンもたくさんあったし、新しい職場でのいろんな出来事もありました。
バタバタしていたこと、そして、ありがたいことに充実していたこともあって、noteにはすぐに書けなかったけれど、再び動き/働きはじめてからもやっていてよかったなと思うことを2つ書きます。
1:月1くらいのカウンセリング
病院に行く前から通っていたこともあり、通院と同時に終了という感じにならなかったカウンセリング。
むしろ、通院で医療的なアプローチが必要な状態を抜け出していたからこそ、カウンセリングで日常的な部分をフォローしていくために継続している感じです。
月1といっても、固定でこの日というわけではないし、たまたま自分が行こうかなというペースがきれいに月1というのもありますが、診断を受ける直前からの担当カウンセラーとのセッションなので変化の感じ方も実感がわいてて良い感じです。
と、いいながら、実は職場の福利厚生で受けられるカウンセリングも併用しています。頻度は多くなくて、本当に、どうしようもなく誰かに話をしたいけど、家族や友人・職場の人ではNGとか、いつものカウンセラーさんとのやりとり以外の視点がほしいときに使う形。タイミング重視なので、カウンセラーさんの選択肢はないし、当たり外れもないわけじゃないけど、ちょっと思考を整理するのには助かっています。
(月1のカウンセラーにも、福利厚生のカウンセラーにも、なんなら上司にも併用していることは伝えています。)
2:日記とは別の振り返りノート
これは、ノートを使い分けていた話とつながってます。
日記として出来事を書くのではなくて、分析視点も持ちながら書く振り返りノートは、自分でペースを決めているとはいえ仕事ですぐに予約が取れるわけじゃなかったカウンセリングの合間に自分で状況を整理していくのに役立ちました。
最低限のラインでは、何事もなかったかのように社会復帰している一方で、それなりにトラウマになっていたものもがあった。それも、意識していないもので。
直面している状況や人が本当の原因ではなくて、フラッシュバックのように過去のことが原因でしんどくなって場面が何度かありました。
そんなとき、自分でノートに状況を書き出したり、なぜそう感じるのかを書いていくことで、現状はトリガーだけど、メインのしんどさは過去だと気づいて、それも伝えながら解決に向けて動くことができました。
こればっかりは、地雷のようにフラッシュバックのトリガーがあって、タイミングが重なると作動しちゃうみたいなところがあるので、これからも対処しないといけないことなんだろうなと思ってます。
ありがたいことに、私は自分にとって合う職場にめぐりあうことができたので、フラッシュバック起こしたり、勝手にしんどくなったり、他の転職者や新卒メンバーとは違う壁にぶつかりながらですが、どうにか現職をつづけてこれてます。
「何かあったら必ず相談する。そして、その相談ができる人の数を増やす。」というのを徹底できていたことも大きいかもしれません。
なかなか実践は難しいことも多いけど、また誰かのヒントになったらいいな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
