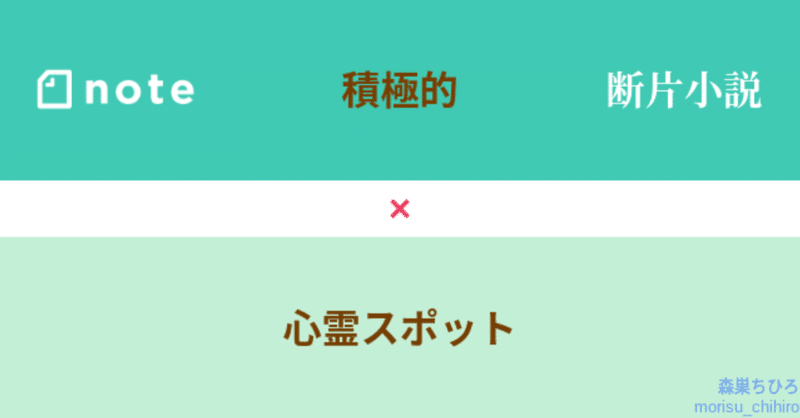
久米院長のリフォーム計画
保護ゴーグルをかけていても、マスクをしていても、ずだ袋の中に入れていても、蛍光灯を割るのは気が進まない。
「こんなことしていいんかね」
「いいんじゃないか。医院だし」
がははと、園田が笑う。前野はずだ袋の口を押さえ、中の蛍光灯を斜めに踏み折った。
「けども、ガラスの粉が舞うし、なんかほら、身体に悪いんでないの。水銀とか」
言いながらも前野は、少し胸のすくような気分を味わった。行儀よく真面目にしか生きられなかった前野は、夜の校舎で窓ガラスを割ったこともない。
まさか四十の盛りも過ぎて、廃病院の蛍光灯を割ることになろうとは。まだ昼間ではあるが、電気の消えた院内は薄暗い。
「蛍光灯の水銀は無機水銀だし、多少吸い込んでも吸収されることなく排出されます。飛散する蛍光体も、人体に影響はありません」
「んなら、もう一本」
前野はまだまだ床に転がっている蛍光灯を、ずだ袋の口の隙間から差し入れて蹴り折った。
「いいね、前野選手。ナイスキック」
園田がペンキのバケツから、刷毛で赤い塗料を散布する。血糊だ。全員汚れてもいいツナギを着ているとはいえ、まるで遠慮がない。さっきゴーグルに一滴ペンキがついてしまって、視界の左下が気になって仕方がない。
久米医院が廃業したのは一年ほど前だ。つい最近、久米院長の一周忌があった。狭い村だから村人はみんな顔を揃えたが、よそからの訪問はほとんどなかった。
「きゃあっ」
黄色い声が廊下に響く。
ついに出たか、と前野と園田は元診察室から身を乗り出した。
「く、く、蜘蛛」
「なんだ、まだ残ってやがったか」
福本が指さす床を園田が踏み潰す。福本女史はさらに甲高い悲鳴を上げた。
「おばさんがきゃーきゃー言うな」
「なによ、お化けより蜘蛛のが怖いじゃない」
蜘蛛は村人が放ったものだ。各自、納屋や菜園や林からつかまえてきた蜘蛛を持ち寄り、院内に解き放った。廃業してからほとんど手入れをしていないため、院内には餌となる虫はたくさんいた。窓を開けて一晩明かりを点けておけば、嫌でも蛾が飛び込んでくる。おかげで蜘蛛たちはせっせと蜘蛛の巣をこしらえてくれた。
作業をしていると、よく顔や髪に糸が引っかかる。用済みになった蜘蛛たちはバルサンを焚いて皆殺しにした。
「ナース連中がもうちょい若けりゃ、この病院も繁盛したかもしれんのに」
軽口を叩いた園田が、福本女史に肩を叩かれている。圧縮したクリームパンのような手で、思い切り。前野の肩なら砕かれてしまうだろう。
「日本の蜘蛛には強い毒性のあるやつはほとんどいません。噛まれたらムヒを塗れば腫れもおさまります。デキサメタゾン酢酸エステルが含まれている市販の薬なら、どれでも大丈夫です」
「ふうん。蜘蛛も蚊もおんなじか」
前野は足もとを横切った蜘蛛を踏もうとして、寸前で避けた。毒がないとはいえ、潰すのは気持ち悪い。軽トラに常備してあるウナコーワクールに、そのデキサなんとかが入ってるかもわからない。
久米医院を心霊スポットに仕立て上げ、村興しをしようと提案したのは、他ならぬ久米院長の父親だった。高齢で、息子を亡くしてから酒浸りのため、会うたびに身体の震えが酷くなっていく。湿度の高い村のまとわりつく暑さの中で、院長の親父さんだけが、極寒の地にいるみたいに震えていた。気の毒なほどに青白い顔をして。
そりゃ、医療ミスの隠蔽が発覚して息子が首を括ったとなれば、お酒に逃げるのも無理はない。村人たちは久米の爺さんは気が狂ったんだと陰口を叩いたが、誰もその提案には逆らわなかった。
久米爺さんは耄碌としているが、それでも古い代からの大家だ。それに村興しが成功すれば、前野の純喫茶にも地元の常連以外の顔が増える。園田の酒屋だって儲かるだろう。
「前野店長のコーヒーは最高でした」
くすぐったい褒め言葉に、前野は耳を払って笑った。その指先に蜘蛛の巣が絡まる。
作業は滞りなく進んだ。割った蛍光灯は適当に、お客さん方が踏まないように部屋の隅に転がし、かろうじて形を保っているものは天井につけ直し、梱包用の透明テープで補強した。
「だいぶお化け屋敷然としてきたでないの」
待合室のベンチに腰掛け、タオルを巻いたペッドボトルのお茶を飲みながら、感慨深げに園田がつぶやく。点々と血糊のついたツナギ姿の村人たちが、おにぎりを頬張ったりラジオを聴いたり、思い思いに休憩している。
「そこが先生が亡くならはった部屋かね」
「だな。なんも病院で首吊らんくてもなあ」
「まあ、おかげで心霊スポットとしての箔がつくってもんだ」
談笑する声が、蒸し暑いロビーに響く。
例の部屋は、受付の割れたガラスから中が丸見えだ。ガラスというガラスは村人たちが壊して回った。破片が飛び散らないように、フィルムテープを貼ってから、バールで慎重に割っていた。
「院長が使ったロープでも残ってれば、目玉になったのになあ」
不謹慎なことを園田がぼやいたが、確かに惜しいことをしたと前野もうなずきかけた。
「惜しい人を亡くしたもんだ」
前野はつぶやいたが、特に同意は得られなかった。常連がひとり減るのは、前野珈琲にとっては死活問題だというのに。
重機で外観をえぐり、窓を割り、蜘蛛の巣を張り巡らせ、血糊を撒き、蛍光灯を粉々にした。ポスターは濡らしたあと天日干しにし、充分に色褪せたのを、少し破いて貼り直した。注射器や薬品は観光客がいたずらをすると危ないから、中身や針は捨てて、元の戸棚に転がしておいた。
ふと見ると、割れた受付の奥の部屋で、男が一人まだ作業をしていた。ツナギを持っていないのか、元は白かったであろう外套が、ひどく血糊で汚れている。
横顔は見えるが、歳のせいか視界がぼやけて誰だかわからない。もちろんゴーグルには度は入っていない。やけに首の長い男だ。
男は天井にロープを結ぼうとしていた。先ほどの会話を聞いていたのか。気の利く男だ。
「頸部の圧迫により死に至るまでの時間は、やり方によってことなります。落下エネルギーを用いて頚椎損傷を招けば、即意識を失います。運良く脛骨を骨折すれば、ぼぼ即死です」
その静かな声は男が発しているようだが、部屋を隔てているわりにははっきりと聞こえた。
「臆せば長引きますが、意識喪失までの平均はほんの七秒。その間、頸動脈洞反射により急激に血圧が低下するので、もとより痛みも苦しみもありません。医学的に言って、縊死、つまり首吊り自殺が最も合理的な自殺法です」
「はは、医師が縊死かい」
前野の軽口に、園田が怪訝な顔をした。くだらない駄洒落は園田の十八番だろうに。
「前さん、さっきから誰と話してるんだい」
園田に言われて気がつくと、受付の割れた窓の向こうに、男の姿はすでになかった。ただ、宙ぶらりんになったロープの輪の中で、蜘蛛の巣が陽光を浴びてきらめいていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
